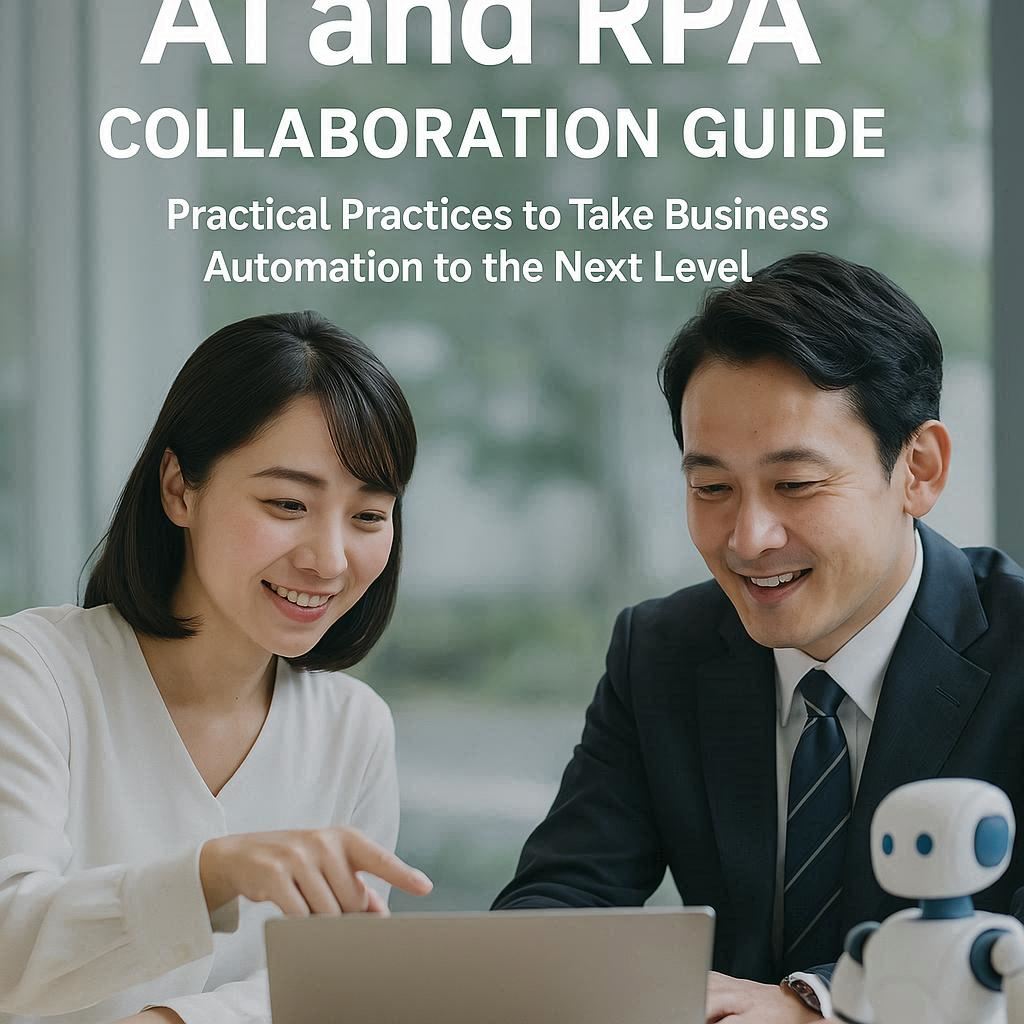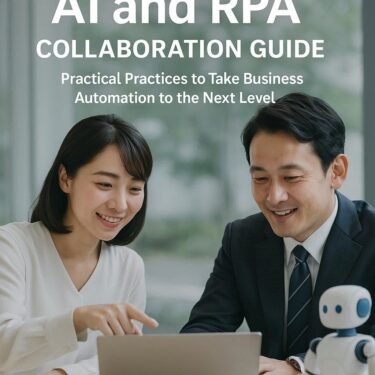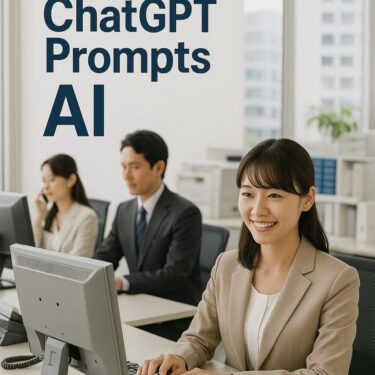AIとRPA連携ガイド|業務自動化を次のレベルへ導く実践法
「RPAを導入して定型業務は自動化できたが、紙の書類やイレギュラーな対応が残ってしまい、結局人手が介在している…」
「自動化の範囲をさらに広げたいが、RPAだけでは限界を感じている」
多くの企業でRPA活用が進む一方、このような課題に直面するケースが増えています。ルール通りに作業をこなすRPAは、指示が明確な業務では絶大な効果を発揮します。しかし、手書きの帳票を読み取ったり、状況に応じて判断したりすることは苦手です。
この「RPAの壁」を突破する鍵こそが、AI(人工知能)との連携です。
AIが持つ「学習・認識・判断」の能力と、RPAの「正確な業務実行」能力を組み合わせることで、これまで自動化を諦めていた非定型業務や、人の判断が必要だったプロセスまでを自動化の対象に広げることが可能になります。
この記事では、AIとRPAの連携に関心を持つ企業の担当者様に向けて、以下の点を網羅的かつ具体的に解説します。
- RPAとAIの根本的な違いと、なぜ連携が必要なのか
- AI連携で実現できる代表的な3つの自動化パターンと具体例
- 業界・業務別の詳細な活用事例
- 自動化の最終形「インテリジェントオートメーション(IA)」とは何か
- 失敗しないための導入ロードマップと注意点
最後までお読みいただければ、自社の業務にAIとRPAの連携をどう活かせるか、そして何から始めるべきかの明確な道筋が見えるはずです。
この記事のポイント
- RPAは「手」、AIは「脳」。両者の連携で、認識・判断を含む業務まで自動化できる。
- 代表的な連携パターンは「AI-OCRでのデータ入力」「特化型AIによる判断」「AIによる業務分析」の3つ。
- 金融・製造・物流・行政など、幅広い業界で申請業務や検品、需要予測の自動化に成功事例がある。
- 最終目標は、プロセス全体を最適化する「インテリジェントオートメーション(IA)」。
- 成功の鍵は「RPAから小さく始め、段階的にAI連携へ拡張する」アプローチ。
そもそもRPAとAIの違いとは?「手」と「脳」で理解する補完関係
AIとRPAの連携を理解する上で、まず両者の役割の違いを正確に把握することが重要です。一言でいえば、RPAは「人間の手」、AIは「人間の脳」の役割を代替します。
| 項目 | RPA (Robotic Process Automation) | AI (Artificial Intelligence) |
|---|---|---|
| 役割 | 実行(手) | 学習・判断(脳) |
| 得意なこと | ルールベースの定型的な反復作業(データ入力、転記、クリック、アプリ操作など) | データからの学習、パターン認識、自然言語処理、画像認識、予測、最適化 |
| 苦手なこと | ルール外の例外処理、非構造化データの認識、状況に応じた判断 | 物理的なPC操作やシステムへの入力・実行 |
| キーワード | 効率化、正確性、スピード、定型業務 | 認識、予測、判断、最適化、非定型業務 |
| 具体例 | 請求書データを会計システムに転記する | 手書きの請求書を読み取り、テキストデータに変換する |
このように、RPAは「決められた手順を高速かつ正確に実行する」プロフェッショナルですが、手順書にないことはできません。一方、AIはデータから学び、「これは請求書だ」「この申請は承認すべきだ」といった判断はできますが、その結果をシステムに入力するような物理的な作業はできません。
両者は得意・不得意が真逆であり、だからこそお互いを補完し合う最高のパートナーとなり得るのです。
なぜ今、AIとRPAの連携が注目されるのか?
国内では、年商50億円以上の企業の約4割がRPAを導入済みという調査結果もあるなど、RPAの活用は一定の普及を見せています。しかし、その多くが直面するのが「自動化範囲の限界」という課題です。
RPA単体では自動化が難しい業務領域
- 非構造化データの処理: PDFや画像で送られてくる請求書、手書きの申込書、メール本文、音声など、形式が定まっていないデータの処理。
- 人の判断が必要な業務: 問い合わせ内容に応じた回答の分岐、与信審査、需要予測、異常検知など、過去の経験や複雑なルールに基づく判断。
- プロセスの最適化: 業務プロセスそのものに潜む非効率な部分を発見し、改善すること。
これらの業務は、多くの企業で依然として人手に頼らざるを得ず、業務効率化のボトルネックとなっています。AIとRPAを連携させることで、AIがこれらの「認識」や「判断」を担い、その結果をRPAが「実行」するという一連の流れを自動化できるようになるため、注目が集まっているのです。
AI連携で実現する3つの代表的な自動化パターン
AIとRPAを連携させることで、具体的にどのような業務が自動化できるのでしょうか。ここでは、代表的な3つの連携パターンを解説します。
パターン1:AI-OCRで非構造化データをRPAが扱える形に変換
これは最も普及しており、効果を実感しやすい連携パターンです。
- AIの役割: AI-OCR(光学的文字認識)や音声認識AIが、紙の書類、PDF、画像、音声といった「非構造化データ」を読み取り、RPAが処理できる「構造化データ(テキストデータ)」に変換します。
- RPAの役割: AIによってテキスト化されたデータを、基幹システムや業務アプリケーションへ入力・登録・照合します。
【具体例:請求書処理業務】
- AI-OCR: 取引先から届く様々なフォーマットの請求書(PDFや紙)をスキャンし、支払先、請求金額、品目などの必要項目を高い精度で読み取り、テキストデータ化する。
- RPA: テキスト化されたデータを会計システムに自動で入力し、購買データと突合して内容をチェック。承認ワークフローを起票する。
この連携により、これまで担当者が一件ずつ手入力していた作業が自動化され、月初の繁忙期の残業削減や、入力ミスの撲滅に繋がります。同様の仕組みは、申込書処理、アンケート集計、名刺管理などにも応用可能です。
パターン2:特化型AIの「判断」をRPAが「実行」に移す
専門的な分析や予測を行うAIの「判断結果」をトリガーとして、RPAが後続の業務を「実行」するパターンです。
- AIの役割: 過去の膨大なデータを学習し、需要予測、与信審査、異常検知、顧客セグメンテーションなどの「判断」や「予測」を行います。
- RPAの役割: AIの判断結果に基づき、発注処理、アラート通知、審査結果のシステム登録、ターゲット顧客へのメール配信など、具体的なアクションを実行します。
【具体例:製造ラインでの異常検知】
- AI: センサーデータやカメラ映像をリアルタイムで解析し、製品の傷や設備の異常など、通常とは異なるパターンを検知する。
- RPA: AIからの異常検知シグナルを受け取り、即座に管理者のPCやスマートフォンにアラートを送信。同時に、生産管理システムに記録を残し、ラインを一時停止するコマンドを実行する。
これにより、これまで熟練者の勘に頼っていた異常の早期発見が可能になり、不良品の流出防止や設備の安定稼働に貢献します。
パターン3:AIが業務分析を行い、RPA開発・運用を高度化
これは、RPAの適用業務そのものを見つけ出したり、開発を効率化したりするためにAIを活用する、より高度な連携パターンです。
- AIの役割: プロセスマイニングやタスクマイニングと呼ばれる技術を使い、PCの操作ログなどを分析。業務プロセス全体を可視化し、どこにボトルネックがあるか、どの業務が自動化に適しているかを分析・提案します。
- RPAの役割: AIの分析結果に基づき、RPA開発者が効果の高い業務から自動化に着手します。将来的には、AIがRPAの設計図(シナリオ)を自動生成することも期待されています。
この連携は、自動化の取り組みを場当たり的に進めるのではなく、データに基づいて最も投資対効果の高い業務から着手することを可能にし、全社的な生産性向上を加速させます。
【業界・業務別】AI×RPAの具体的な活用事例
AIとRPAの連携は、すでに多くの業界で成果を上げています。ここでは、具体的な活用シーンをいくつかご紹介します。
金融・保険業界:
- 業務内容: 住宅ローン審査、保険金支払い査定、口座開設手続き
- 活用例: AI-OCRで申込書や本人確認書類をデータ化し、RPAが情報を基幹システムに登録。AIが過去のデータから貸し倒れリスクや不正請求をスコアリングし、RPAが審査結果に応じて担当者へ通知・システム登録を行う。これにより、審査期間の大幅な短縮と精度の向上を実現。
製造・物流業界:
- 業務内容: 需要予測に基づく生産・在庫調整、外観検査、倉庫内のピッキング指示
- 活用例: AIが販売実績や天候データから将来の需要を予測。RPAがその予測に基づき、生産管理システムや発注システムに生産指示・発注データを入力する。また、物流倉庫では、AIが走行動画を解析して危険挙動を検知し、RPAが管理レポートを作成することで、年間1,900時間もの工数削減を達成した事例も。
行政・自治体:
- 業務内容: 各種申請書(住民票、税、給付金など)の受付・処理
- 活用例: コロナ禍の特別定額給付金申請では、AI-OCRとRPAの連携ソリューションが無償提供され、膨大な量の紙の申請書を効率的に処理。申請書の読み取りから、システムへの入力、既存データとの突合チェック、振込データ作成までの一連のプロセスを自動化し、迅速な給付に貢献。
コンタクトセンター:
- 業務内容: 問い合わせ対応、応対記録の入力
- 活用例: AIチャットボットや音声認識AIが顧客からの問い合わせ内容を理解し、一次対応を行う。複雑な問い合わせやオペレーター対応が必要な場合、RPAが顧客情報や問い合わせ内容をCRMシステムに自動で入力し、オペレーターに引き継ぐ。これにより、顧客の待ち時間を短縮し、オペレーターはより高度な対応に集中できる。
RPAの進化とAI連携の位置づけ|Class 1からインテリジェントオートメーション(IA)へ
RPAの技術は、その自動化レベルに応じて3つのクラスに分類されることがあります。AIとの連携は、この進化の過程で極めて重要な役割を果たします。
- Class 1:RPA (Robotic Process Automation)
- PC上の定型的な作業を自動化する段階。現在、多くの企業がこのクラスに該当します。
- Class 2:EPA (Enhanced Process Automation)
- AI-OCRなど一部のAI技術と連携し、非構造化データを扱えるようにするなど、RPAを拡張する段階。プロセス全体の最適化を目指します。
- Class 3:CA (Cognitive Automation)
- 機械学習や自然言語処理などの高度なAIと連携し、自律的な判断を伴う業務まで自動化する段階。
そして、この進化の先にあるのが「インテリジェントオートメーション(IA)」という概念です。
IAは、単にRPAとAIを組み合わせるだけでなく、プロセスマイニング、BPM(ビジネスプロセスマネジメント)など複数の技術を統合し、個々のタスクの自動化(点)から、業務プロセス全体の自動化と最適化(線・面)を目指すものです。
例えば、ある申請業務において、RPAが止まってしまった場合、IAの仕組みでは、ルールベースのAIが状況を判断し、「担当者にメールで通知する」「別のRPAに処理を依頼する」「一旦保留にして後で再実行する」といった最適な次のアクションを自動で選択・実行します。
このように、IAは例外処理も含めたエンドツーエンドの業務フローを自律的に管理・実行することで、人の介在を極小化し、ビジネスプロセス全体の生産性を劇的に向上させることを目的としています。AIとRPAの連携は、このIAを実現するための核心的なステップなのです。
AI連携を成功させるための実践的ロードマップ
では、実際にAIとRPAの連携を導入するには、何から手をつければよいのでしょうか。ここでは、成功確率を高めるための段階的なアプローチをご紹介します。
ステップ1:RPAによる定型業務の自動化と業務可視化
まずはAI連携を急がず、既存のRPAでルールが明確な定型業務の自動化から着手します。これにより、現場に自動化の成功体験を積んでもらうと同時に、RPA化の過程で既存の業務プロセスが可視化され、どこに非効率な点や判断業務が残っているかが明確になります。
ステップ2:AI連携の候補業務を特定
ステップ1で洗い出された「RPAだけでは自動化できない業務」の中から、AI連携の候補を洗い出します。特に、以下のような業務は有力な候補です。
- 紙やPDFの帳票を手入力している業務 → AI-OCR連携
- 担当者が目視で確認・判断している業務 → 画像認識AIや特化型AIとの連携
- 問い合わせメールの内容に応じて対応を振り分けている業務 → 自然言語処理AIとの連携
ステップ3:スモールスタートでPoC(概念実証)を実施
いきなり大規模な導入を目指すのではなく、最も費用対効果が高そうな業務を1つ選び、小規模なPoCを実施します。例えば、「特定の1種類の請求書処理をAI-OCRとRPAで自動化してみる」などです。ここで技術的な実現可能性や具体的な導入効果を検証し、課題を洗い出します。
ステップ4:横展開と効果測定
PoCで成功モデルが確立できたら、同様の課題を抱える他の部署や業務へ横展開していきます。この際、単に「削減できた時間」だけでなく、「処理精度の向上率」「リードタイムの短縮日数」「エラー発生率の低下」など、多角的なKPIを設定して効果を測定し、経営層や関連部署に成果をアピールすることが重要です。
ステップ5:全社的な自動化基盤(IA)を目指す
個別のAI連携事例が増えてきたら、それらを統合的に管理・運用し、プロセス全体を最適化するインテリジェントオートメーション(IA)の実現を視野に入れます。CoE(Center of Excellence)のような専門組織を立ち上げ、全社的なガバナンスを効かせながら、自動化を推進していくフェーズです。
導入前に押さえるべき3つの注意点と解決策
AIとRPAの連携は強力なソリューションですが、導入を成功させるためにはいくつかの障壁を乗り越える必要があります。
1. 専門人材の不足
AIやRPAを使いこなせる人材が社内にいない、という課題は多くの企業が抱えています。
- 解決策:
- ノーコード/ローコードツールの活用: 近年は、プログラミング知識がなくても直感的な操作でAIモデルの構築やRPAシナリオの作成ができるツールが増えています。
- ベンダーの伴走支援を活用: 導入から運用、人材育成までをトータルでサポートしてくれるベンダーを選定し、パートナーとして協業する。
2. 費用対効果(ROI)の不明確さ
AI導入には一定のコストがかかるため、「本当に投資に見合う効果が出るのか」という懸念から、導入に踏み切れないケースも少なくありません。
- 解決策:
- スモールスタートで効果を実証: 前述のロードマップの通り、まずはPoCで小さな成功事例を作り、具体的なROIを算出します。その実績を基に、本格導入の社内承認を得ます。
- 定性的な効果も評価する: 時間短縮のような定量的な効果だけでなく、「従業員の創造的な業務へのシフト」「顧客満足度の向上」「ミスの削減による信用の維持」といった定性的な効果も合わせて評価し、多角的にメリットを訴求します。
3. 現場の理解と協力体制
IT部門主導で導入を進めた結果、「現場の業務実態と合わない」「自分の仕事が奪われるのでは」といった反発を招き、活用が進まないことがあります。
- 解決策:
- 企画段階から現場を巻き込む: 自動化の対象業務を選定する段階から、実際にその業務を行っている部門の担当者に参加してもらい、一緒に課題やゴールを設定します。
- 目的の共有: 「自動化は、単純作業から皆さんを解放し、より付加価値の高い仕事に集中してもらうためのツールである」というポジティブなメッセージを経営層から継続的に発信し、社内の意識改革を図ります。
よくある質問(FAQ)
Q1. AIとRPA、どちらから始めるべきですか?
A1. 多くの場合、RPAから始めることをお勧めします。まずはルールベースの定型業務をRPAで自動化し、社内に成功体験と自動化のノウハウを蓄積します。その上で、RPAだけでは対応できない非定型業務や判断業務に対して、AI連携を検討するのが着実な進め方です。
Q2. プログラミングの知識は必要ですか?
A2. 必ずしも必要ではありません。最近のRPAツールやAIプラットフォームは、専門家でなくても使えるノーコード/ローコードのものが主流です。ドラッグ&ドロップなどの直感的な操作で開発できるため、現場の業務担当者が主体となって自動化を進めることも可能です。
Q3. 導入費用はどのくらいかかりますか?
A3. 費用は、RPAツールの種類(デスクトップ型、サーバー型、クラウド型)、連携するAIソリューションの種類、自動化する業務の規模や複雑さによって大きく異なります。月額数万円から始められるクラウド型サービスもあれば、大規模なシステム構築で数千万円以上かかる場合もあります。まずは複数のベンダーから情報収集し、自社の規模や目的に合ったプランを検討することが重要です。
Q4. AI-OCRの文字認識率は100%ですか?
A4. 100%ではありません。特に手書き文字や印字品質の低い帳票の場合、誤認識が起こる可能性があります。しかし、近年のAI-OCRは95%以上の高い認識精度を誇る製品も多く、誤認識の可能性がある箇所を担当者が確認・修正するプロセスを組み込むことで、業務全体としては大幅な効率化が可能です。
まとめ:RPAの限界を突破し、真の業務改革へ
本記事では、AIとRPAの連携による業務自動化について、その基本概念から具体的なパターン、導入の進め方までを網羅的に解説しました。
RPAは定型業務の効率化に大きな力を発揮しますが、それだけでは「部分最適」に留まってしまいます。そこにAIの「認識・判断」能力を掛け合わせることで、これまで人手に頼らざるを得なかった業務領域にまで自動化のメスを入れ、プロセス全体の最適化、すなわちインテリジェントオートメーション(IA)への道が拓けます。
AIとRPAの連携は、単なるコスト削減や工数削減のためのツールではありません。従業員を単純作業から解放し、より創造的で付加価値の高い業務へシフトさせることで、企業の競争力を根本から高めるための戦略的な一手です。
まずは自社の業務プロセスを見渡し、「紙の情報を手入力している」「担当者が目視で判断している」といった、AI連携が活かせそうな業務がないか探すところから始めてみてはいかがでしょうか。小さな一歩が、企業の未来を大きく変えるきっかけとなるはずです。