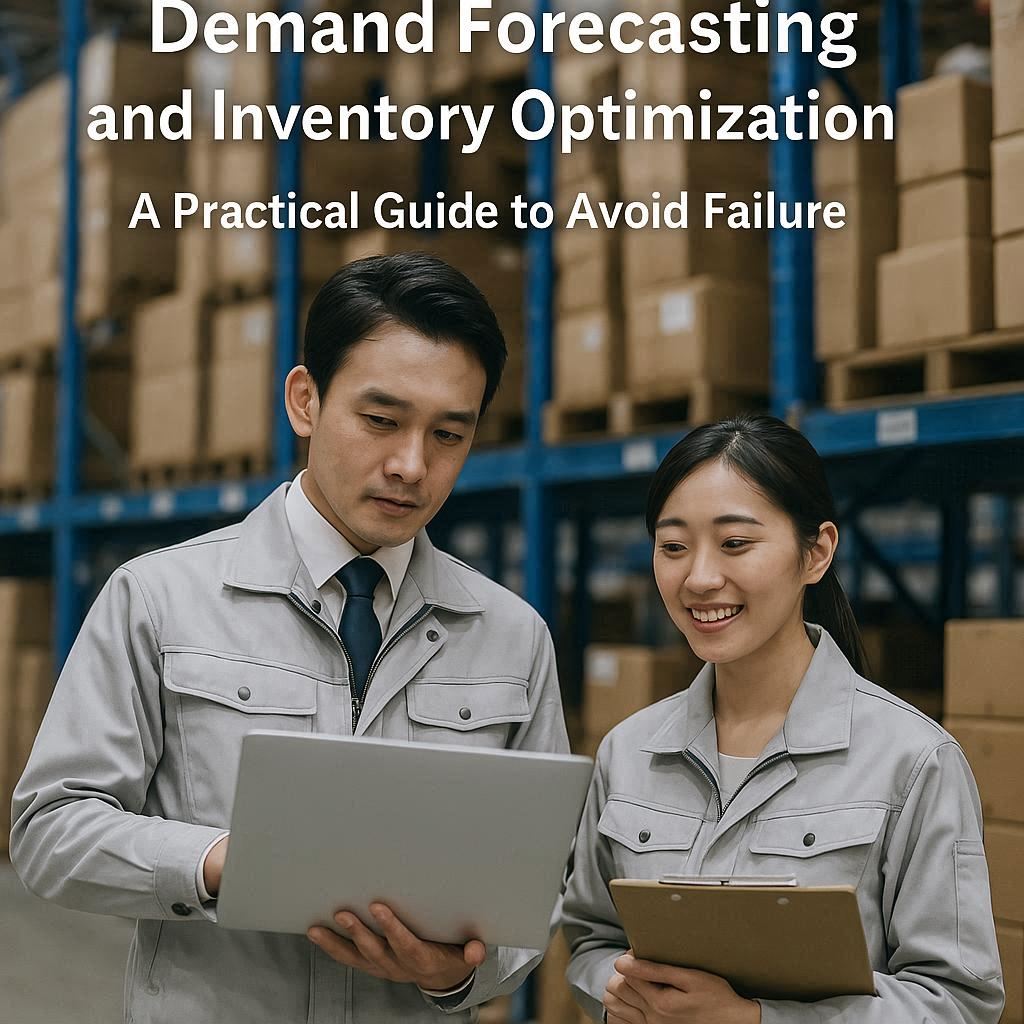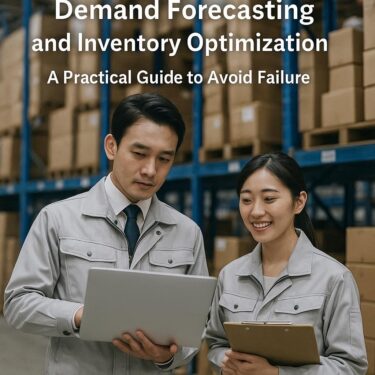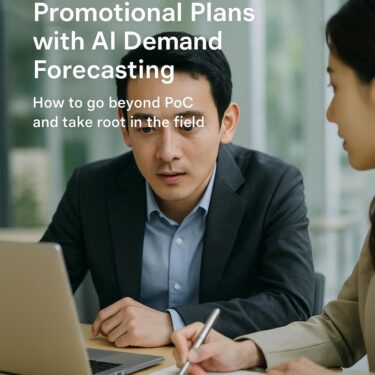AI需要予測導入の理想と現実:予測精度より大事だった、現場の「違和感」と「お茶会」
「AIによる需要予測と在庫最適化」。なんとスマートで、未来的な響きでしょうか。ウェブサイトや提案書には、ピカピカのグラフと輝かしい成功事例が並びます。しかし、あの華やかな舞台の裏側では、もっとずっと人間臭くて、泥臭いドラマが繰り広げられていることを、皆さんはご存知でしょうか。
AIによる需要予測と在庫最適化:失敗しないための実践ガイド はじめに:その在庫の悩み、「勘と経験」から「データとAI」で卒業しませんか? 「在庫が多すぎて、倉庫の保管コストや商品の廃棄ロスが経営を圧迫している…」「欠品[…]
私はこれまで、物造りや物流の現場で数々の改革をお手伝いしてきました。AI導入もその一つです。そして断言できるのは、プロジェクトの成否を分けるのは、最新のアルゴリズムや潤沢な予算だけではない、ということです。むしろ、本当の戦場は会議室のPC画面の中ではなく、現場の担当者やベテラン社員の「心の中」にあります。
今回は、私が関わったある食品卸売企業でのAI導入プロジェクトを例に、綺麗な計画書の行間からこぼれ落ちる、マネジメントとコミュニケーションのリアルな裏話をお届けしたいと思います。この記事を読めば、「なるほど、AI導入って技術の話だけじゃないんだな」と、プロジェクトを成功に導くための生々しいヒントが得られるはずです。
データの大掃除は「人間関係の大掃除」から始まる
プロジェクトが始まると、まずぶつかるのが「データ収集」の壁です。元記事の第2章「データの大掃除」には、「社内に散在するデータを集め、使える状態に『掃除』する、地味ですが最も重要なステップです」と書かれています。全くその通り。しかし、この「散在」の裏には、根深い「部署の壁」と「縄張り意識」が隠れていることがほとんどです。
今回のプロジェクトで実務担当者に任命されたのは、入社8年目の佐藤さんという30代の女性でした。非常に真面目で優秀、データ分析のスキルも高い。しかし、彼女は大きな壁にぶつかっていました。
「すみません…。営業部がなかなか販売実績の元データを共有してくれなくて。情報システム部も、『仕様が固まらないとデータ抽出の工数は割けない』の一点張りで…」
初回の打ち合わせで、彼女は疲れ切った顔でそう言いました。これは典型的なパターンです。データは、ただの数字の羅列ではありません。それぞれの部署が長年かけて蓄積してきた「汗の結晶」であり、ある種の「資産」なのです。
特に手強かったのが、営業一筋30年のベテラン、高橋部長でした。御年58歳、典型的な現場主義者です。
「高橋部長にAIの話をしたら、『そんな数字遊びで俺たちの経験がわかるもんか!長年の勘だぞ、勘!』って、聞く耳を持ってもらえなくて…」
私は佐藤さんにこうアドバイスしました。
「佐藤さん、いきなり『AIのためにデータをください』って正面から行くのはやめましょう。それは相手からすれば『あなたの仕事のやり方を否定します』って言っているように聞こえかねない。まずは、高橋部長の『武勇伝』と『苦労話』を、敬意をもって聞きに行くんです。僕たちは武器を持って戦うんじゃない。丸腰で懐に飛び込むんですよ」
半信半疑の佐藤さんでしたが、翌日、営業部へ向かいました。
「高橋部長、お時間少しよろしいですか。去年の夏、猛暑で急遽アイスの特売を組んだ時、すごい売上でしたよね。あの時の在庫調整、どうやって乗り切ったんですか?ぜひ、教えていただきたくて」
最初はいぶかしげだった高橋部長ですが、自分の功績を認められると、少しずつ表情が和らいでいきました。
「んだ。あの時は大変だったんだぞぉ。メーカーの担当者に夜中の2時まで電話して、なんとか在庫ば確保したんだ。倉庫の連中ど何度もやりあってな。おかげで欠品させねで済んだんだ。」
存分に苦労話を語ってもらった後、佐藤さんは切り出しました。
「本当にすごいご経験ですね…。そのご苦労を、少しでも減らせないかと考えているんです。もしAIが、『来週は猛暑でアイスがこれくらい売れそうだ』って事前にそっと教えてくれたら、部長がもっと大きな商談に集中できる時間が増えるかな、なんて…」
高橋部長は、腕を組んでしばらく黙っていましたが、ポツリと言いました。
「…まぁ、少しは楽になるかもしれねな。…んだば、俺が個人的に持ってる過去の特売記録、見てみるか?Excelだが、何かの役に立つかもしれね。」
この瞬間、プロジェクトの空気が変わりました。データクレンジングとは、単なる技術的な作業ではありません。それは、各部署が守ってきた「仕事の歴史」と「プライド」を一つひとつ丁寧に紐解き、共感を得るための対話から始まる、極めてウェットな「人間関係のクレンジング」なのです。
AIが見逃す「パートさんの井戸端会議」に宝がある
元記事の第5章には、「現場の知見を切り離してしまう」という失敗の落とし穴が紹介されています。これもまた、多くのプロジェクトが陥る罠です。
私たちのプロジェクトでも、PoC(概念実証)が始まり、AIが推奨発注数を算出するようになりました。データサイエンティストが作ったモデルは、過去のデータから見れば非常に高い精度を誇っていました。しかし、その画面を見て、現場のパートリーダーである鈴木さん(50代)が首をかしげたのです。
「うーん、AIは来週、このお弁当を50個って言ってるけど、絶対足りないわよ。発注、80個にしておかないと」
「え、鈴木さん、どうしてですか?過去のデータだと、来週の火曜日は平均50個くらいなんですが…」
佐藤さんが尋ねると、鈴木さんはこう答えました。
「あら、知らないの?すぐ近くの工場、来週から新しい製造ラインが動くって噂じゃない。作業員の人がどっと増えるはずよ。そうなると、ガッツリ系のお弁当が売れるのよ」
AIは、過去の販売データや気象データは分析できます。しかし、「近所の工場の噂」というデータは持っていません。これこそが、AIが逆立ちしても敵わない「現場の暗黙知」です。
この一件で、私たちはAIに対するアプローチを根本から見直しました。AIは完璧な答えを出す「神様」ではない。むしろ、少し経験の浅い、でもものすごく計算が速い「新人」のようなものだ、と。新人が成長するためには、ベテランからのフィードバックが不可欠です。
そこで佐藤さんが企画したのが、週に一度の「AIのここが変だよ!お茶会」でした。パートさんたちに休憩時間に集まってもらい、お菓子を食べながら、AIが出した来週の予測値についてワイワイガヤガヤと意見を言ってもらうのです。
最初は「私たちなんかが言ってもねぇ…」と遠慮していたパートさんたちも、リラックスした雰囲気の中では本音が出てきます。
「そういえば、駅前の道路工事、来月で終わるらしいから、作業員さん向けのお茶は減らした方がいいかもね」
「来月の地域のお祭りの日は、この唐揚げ惣菜が鉄板なのよ。AIはわかってるかしら?」
「向かいに新しいマンションが建ったから、ファミリー向けの冷凍食品が最近よく動くのよねぇ」
私たちは、これらの貴重な「生きた情報」を、システムに簡単なメモとして入力できる機能を追加しました。「鈴木さんの工場情報」「お祭りフラグ」「近隣工事情報」といったタグを付け、AIに再学習させるサイクルを構築したのです。
結果、AIの予測精度は飛躍的に向上しました。「AI vs 人」という対立構造ではなく、「AI with 人」という協業関係が生まれた瞬間でした。「現場の知見」とは、会議室で出てくるような小難しい意見だけではありません。現場で働く人々の日常会話や、ふとした気づきにこそ、プロジェクトを成功に導く宝が眠っているのです。
「仕事が楽になる」という言葉がもたらす、思わぬ抵抗
プロジェクトが軌道に乗り、実際に発注業務が効率化され始めると、新たな問題が浮上しました。元記事の第3章で触れられている「発注作業時間の削減」というKPIが、思わぬ心理的抵抗を生んだのです。
ある日、佐藤さんの表情がどこか晴れないことに気づきました。
「どうしたんですか?順調じゃないですか」
「はい、そうなんですけど…。今まで一日中かかっていた発注作業が、午前中で終わるようになって。時間ができたのは嬉しいんですが、なんだか手持ち無沙汰で…。これまで発注業務が私のメインの仕事だったので、自分の価値がなくなったような気がして、少し不安なんです」
これにはハッとさせられました。私たちは「業務効率化」という言葉を安易に使いがちですが、当事者にとっては「自分の存在価値の喪失」という恐怖に直結しかねないのです。どんなに優れたシステムも、使う人が「自分の仕事が奪われる」と感じてしまえば、無意識の抵抗に遭い、形骸化してしまいます。
私は、この会社の創業期から商品開発を支えてきた、商品部の木村部長(62歳)のもとへ佐藤さんと一緒に向かいました。
「木村部長、ちょっと面白い話があるんですよ。AIのおかげで、佐藤さんの時間に余裕ができたんです。彼女、すごく真面目でデータを見る目もある。部長がこれから仕掛ける新商品の企画に、彼女の分析力を活かせませんか?」
木村部長は、白髪混じりの眉をピクリと動かしました。
「ほう、そりゃ面白いごどだ。わしは長年の勘で仕事してきたが、最近の若い人の好みはわがんねぐなってきたからの。…んだば佐藤さん、今度、新しいスイーツの展示会さ一緒に行くべ。おめさんの若い感性で、データば見ながら、面白い商品見つけてみでけろ。」
この一言が、佐藤さんのキャリアを大きく変えました。私たちは彼女の新しいミッションを定義しました。「あなたはもう、単なる『発注担当者』じゃない。AIを使いこなし、データに基づいて次のヒット商品を生み出す『データ活用プランナー』なんだ」と。
業務効率化を推進する際は、必ず「創出された時間で、どんな新しい価値を生み出すのか」というポジティブな未来をセットで提示しなければなりません。それは、担当者の不安を解消し、新たな成長の機会を提供することに他ならず、変革を組織に根付かせるための最も重要な鍵となるのです。
結論:AIは「人」と「人」を繋ぐための道具である
AI導入プロジェクトの裏側には、こうした無数の人間ドラマがあります。華やかな導入事例の裏では、誰かが頭を下げ、誰かが誰かの苦労話に耳を傾け、そして誰かが新しい自分の役割を見つけているのです。
最新の技術や完璧な計画書はもちろん重要です。しかし、それ以上に大切なのは、現場で働く一人ひとりの感情に寄り添い、彼らの不安を期待に変える泥臭いコミュニケーションです。データとAIは、あくまで人と人とを繋ぎ、組織が同じ未来を向くための強力な「道具」に過ぎません。
もし、あなたがこれからAI導入を検討するなら、ぜひ思い出してください。あなたの会社の「高橋部長」や「鈴木さん」の顔を。プロジェクトの成功は、彼らとの対話から始まるのです。