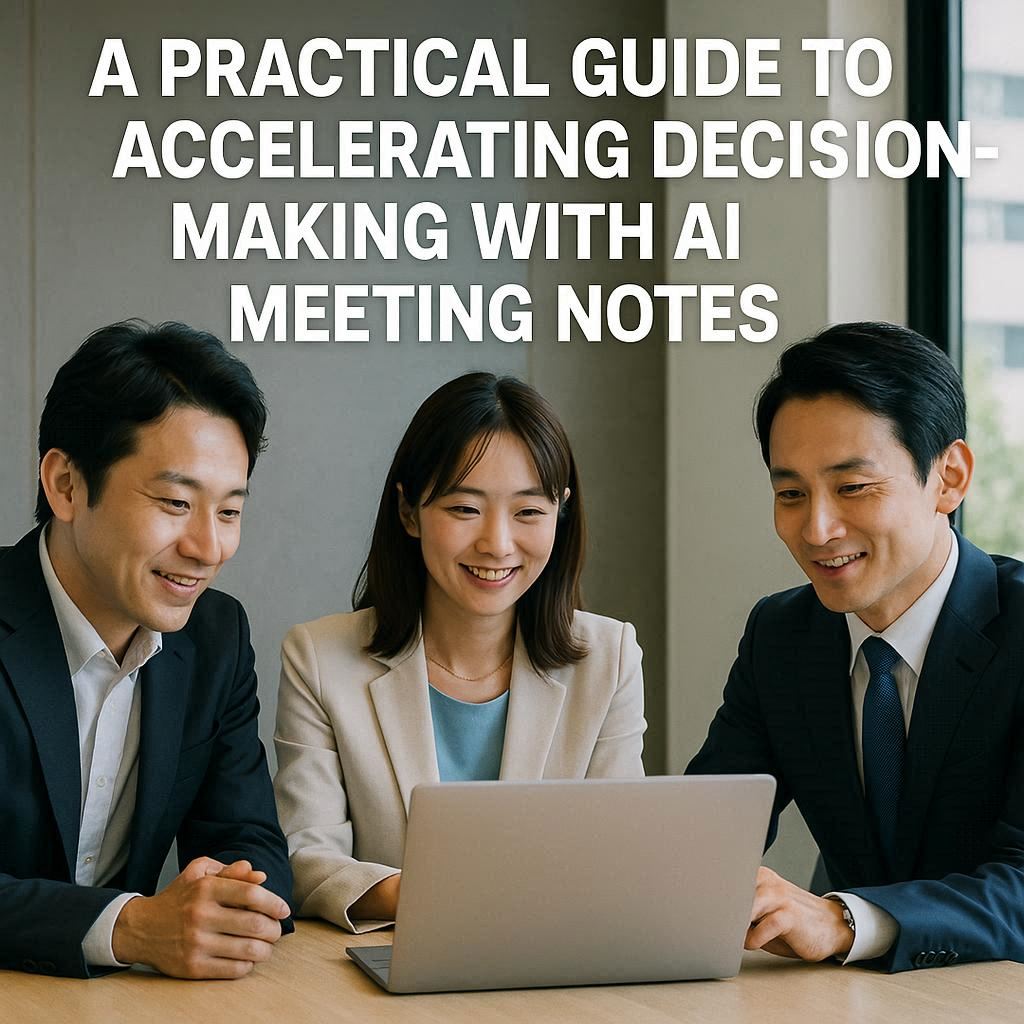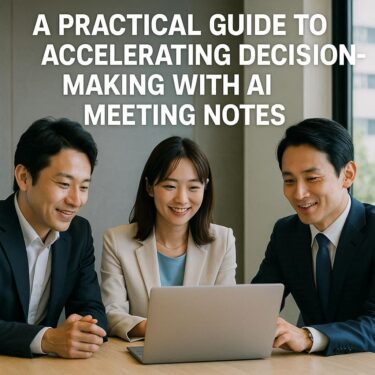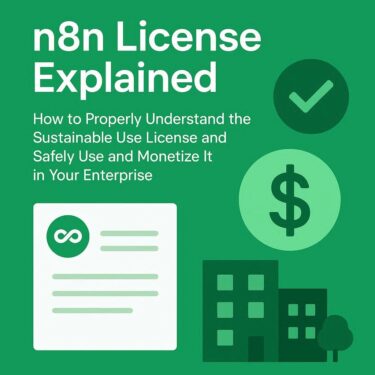AI議事録導入の裏側:「ツール」がなぜ現場で使われないのか?抵抗勢力を味方に変えた話
先日公開した『AI議事録で意思決定を加速する実践ガイド』。ありがたいことに多くの方にお読みいただき、「早速試してみた」「プロンプトが参考になった」といった嬉しい声をいただいています。
AI議事録で意思決定を加速する実践ガイド|選び方・プロンプト・運用設計のすべて 会議は終わったのに、仕事は進まない…その悩みをAIで解決しませんか? 「会議はしたけれど、結局何が決まったんだっけ?」「議事録が送られてく[…]
しかし、今日は少し違う話をさせてください。
あの記事に書かれているような理想的なステップで、すんなりと事が進む現場がどれだけあるでしょうか?私の経験上、残念ながらほとんどありません。どんなに優れたツールや完璧な運用設計図を描いても、現場には分厚い「壁」が立ちはだかるのです。
その壁の正体は、技術ではありません。それは、人の「心理」と「習慣」という、もっと厄介で、人間臭いもの。
今回は、あの華やかな成功ガイドの裏側で、私たちが実際に体験した、ある地方の製造業での泥臭い奮闘記をお話ししようと思います。これは、ツール導入のハウツー話ではありません。変化を恐れる人々の心をどう動かし、単なる「ツール導入プロジェクト」を「チームの行動変容プロジェクト」へと昇華させていったのか、そのマネージメントとコミュニケーションの裏話です。
第1章:静かなる抵抗勢力 – 「そんなもん、いらねぇ」
そのプロジェクトは、ある中堅製造業の工場で始まりました。課題は明確。「会議は多いが、次のアクションが遅い。言った言わないが頻発し、部署間の連携が滞っている」。まさに、AI議事録が特効薬になり得る典型的なケースでした。
私は自信を持って、最新のAI議事録ツールと、あの記事で紹介したような完璧な運用フローを提案しました。しかし、プロジェクト担当に任命された、入社8年目の佐藤さん(30代女性)の表情は、最初から曇っていました。
「理屈はわかります。でも…うちの現場は、たぶん受け入れてくれないと思います」
彼女の言う「現場」の中心人物は、この道40年の大ベテラン、斎藤さん(60代男性)でした。最初の説明会で、斎藤さんは腕を組み、終始苦虫を噛み潰したような顔で私の話を聞いていました。そして、質疑応答で最初に口を開いたのです。
「あのさ、ミズさん。こんだな機械さ頼らんでも、今までちゃんとやってきたんだでの。議事録だば、おれらが頭で覚えで、ちゃんと若いもんに伝えでる。だいたい、会議でだれが何しゃべったがなんて、全部文字に残して、どうすんだなや」
庄内地方の朴訥(ぼくとつ)とした、しかし有無を言わせぬ迫力のある言葉でした。彼の周りに座るベテラン社員たちも、深く頷いています。これは、単なる懐古主義ではありません。彼らにとっては、自分たちの仕事のやり方、ひいては存在価値そのものを否定されたように感じたのでしょう。
さらに厄介だったのは、彼らの上司である鈴木部長(50代男性)の態度でした。
「いやぁ、ミズさんの言うごどはよぐわがんだげんと…。斎藤さなんかの言うごども一理あんだよのぉ。長年の経験でやってきたごどだすけ、無理強いはでぎねべなぁ」
改革には前向きな姿勢を見せつつも、現場の重鎮との衝突を恐れ、完全に腰が引けている。典型的な「板挟み管理職」の姿がそこにありました。
完璧なツール、完璧なロジック。しかし、それだけでは人の心は1ミリも動かない。私はプロジェクトの初日で、いきなり厚い壁にぶち当たったのです。
第2章:担当者の涙 – 「理想だけ言われても、現場は動かないんです」
説明会から数日後、佐藤さんと二人で打ち合わせをしていると、彼女は俯いたまま、ぽつりぽつりと本音を漏らし始めました。
「すみません、うまく進められなくて…。斎藤さんたちには、会議後に私がヒアリングして、手書きで要点をまとめて回覧しているんです。でも、私のまとめ方が悪いって言われたり、そもそも『そんなこと言ってない』って後から言われたり…」
彼女の声は、だんだんと震えていました。
「AIで楽になるって言われても、そのAIを動かすために、また斎藤さんたちを説得して、使い方を覚えてもらって…その手間を考えたら、私が今まで通りやった方が早いんじゃないかって…。もう、どうしたらいいか…」
ついに彼女の目から涙がこぼれ落ちました。上からは「改革を進めろ」、現場からは「余計なことをするな」。その間で彼女はたった一人、孤独に戦っていたのです。
この時、私は自分のアプローチが根本的に間違っていたことに気づかされました。私は「AI議事録ツールを導入する」という手段の正しさばかりを説いていました。しかし、彼女や現場のメンバーが本当に解決したかったのは、「ツールを導入すること」ではありません。
佐藤さんは、「言った言わない」の責任を押し付けられる精神的な負担から解放されたかった。
斎藤さんたちは、自分たちの経験や知識が軽んじられることへの不安を払拭したかった。
鈴木部長は、現場との無用な軋轢を避けたかった。
彼らの課題は「議事録作成の非効率」という表面的なものではなく、もっと根深く、感情的なものだったのです。
私は佐藤さんに言いました。「ごめんなさい。僕の進め方が悪かった。もう一度、ゼロから考え直しましょう。これはツールを入れるプロジェクトじゃない。佐藤さんと、斎藤さんたちが、もっと気持ちよく仕事ができるようになるためのプロジェクトなんです。主役はAIじゃなくて、皆さんですよ」
その言葉に、佐藤さんは少しだけ顔を上げてくれました。私たちの本当の挑戦は、ここから始まったのです。
第3章:突破口は「AIの先生」- プライドの高いベテランを巻き込む逆転の発想
正攻法がダメなら、やり方を変えるしかない。私は一つの賭けに出ることにしました。それは、最大の抵抗勢力である斎藤さんを、「敵」ではなく「味方」、それもプロジェクトの「主役」に据えるという作戦です。
数日後、私は佐藤さんと共に、再び斎藤さんの元を訪れました。
「斎藤さん、先日は失礼しました。少し考え直しまして、ご相談があるんです」
「んだ、まだ何かあんのが」と、訝しげな顔の斎藤さん。
私は一枚の紙を差し出しました。それは、前回の説明会の音声をAIで文字起こししたものでした。案の定、専門用語や固有名詞は誤変換だらけ。「旋盤」が「全般」に、「焼き入れ」が「焼き鮭」になっている有様です。
「斎藤さん、これを見てください。今のAIって、こんなもんなんですよ。現場の言葉が、全然わかってない。正直、このままじゃ全く使い物になりません」
斎藤さんはその紙を覗き込み、「んだべ?おれが言った通りだ。こんだなもんは、わがね(ダメだ)」と、少し得意げな表情を浮かべました。
ここだ。私は続けました。
「そこで、お願いがあるんです。このダメなAIに、斎藤さんが先生になって、正しい言葉を教えてやってもらえませんか?斎藤さんが長年培ってきた、この工場の『言葉』を、財産としてAIに覚えさせてほしいんです。これは、斎藤さんにしかできない仕事です」
斎藤さんの目の色が変わりました。「おれが…先生?」
「はい。例えば、この『焼き鮭』は『焼き入れ』だってAIに教える。そういう用語集を、斎藤さんに監修していただきたい。そうすれば、AIが少しずつ賢くなって、斎藤さんたちの言葉を正確に記録できるようになる。若手も、それを見れば正しい用語を学べます。斎藤さんの技術と言葉が、未来に残るんですよ」
「AIに仕事を奪われる」という恐怖を、「AIを育てる」というプライドへと転換させる。これが私の狙いでした。しばらく沈黙が続いた後、斎藤さんはぼそっと言いました。
「…まぁ、そんだなごどだば、やってやってもいいげどな」
横にいた佐藤さんが、信じられないという顔で私を見ていました。この瞬間、プロジェクトの潮目が大きく変わったのです。
第4章:「作業」から「価値創造」へ – チームの意識が変わった瞬間
斎藤さんを「AIの先生」に任命してから、事態は面白いように好転しました。彼は、水を得た魚のように専門用語リストを作り始め、他のベテラン社員にも「おめえの部署の言葉も教えろ」と声をかけ始めました。今まで面倒な雑用だと思われていた議事録が、「自分たちの技術を伝承するツール」へと意味合いを変えたのです。
私たちは、いきなり全社会議で導入するのではなく、斎藤さんたちが参加する週一の製造定例会だけで、実験的にAI議事録を使い始めました。
最初のうちは、AIが生成した要約を見て、「こごは、こーでねぇ!ニュアンスが違う!」と斎藤さんが赤入れする光景が日常でした。しかし、そのプロセスこそが重要だったのです。
ある日の会議で、設備Aの不具合について議論が紛糾しました。いつもなら、「じゃあ、各自で検討して」で終わるところです。しかし、その日のAI議事録には、こう記されていました。
【アクションアイテム】
| タスク内容 | 担当者 | 期限 |
|---|---|---|
| 設備Aの過去トラブル事例を調査し、原因を特定する | 田中 | 翌水曜まで |
| 設備メーカーに見積もりを依頼する | 鈴木部長 | 翌金曜まで |
これを見た斎藤さんが、「お、これなら誰が何やんのが、すぐわがんなや」と呟きました。
佐藤さんも、「はい。私が後で皆さんに聞いて回らなくても、これを見れば進捗がわかります」と笑顔で答えます。
彼らは、身をもって体験したのです。AI議事録は、単に会話を記録するツールではない。曖昧な会話を、具体的な「次の行動」に変えるためのツールなのだと。
議事録作成という「作業」に忙殺されていた佐藤さんは、抽出されたアクションアイテムの進捗を管理し、次の会議のアジェンダを準備するという、より付加価値の高い「マネージメント」業務に時間を使えるようになりました。
「誰かがやらなければいけない、でも誰もやりたがらない作業」から解放されたことで、チームの会話は「誰が責任を取るか」という後ろ向きなものから、「次に何をすべきか」という前向きなものへと変わっていったのです。
結論:新しい技術とは、人の「感情」と向き合う旅である
あの工場でAI議事録が定着するまで、約半年かかりました。今では斎藤さんが「このAIは、まだだまだわらすこだな(まだ未熟だな)。おれが教えでやんねば」と笑いながら、若手に使い方を教えています。
この経験から私が学んだ、どんなDXプロジェクトにも通じる教訓は、極めてシンプルなものです。
- 「正しさ」だけでは人は動かない。
どんなに優れたツールも、それを使う人の感情を無視すればただの箱だ。「効率化」「生産性向上」という言葉の前に、相手が何に不安を感じ、何を大切にしているのかを理解することが全ての始まりになる。 - 抵抗勢力を「主役」にする。
変化に最も抵抗する人は、現状のやり方に最もプライドを持っている人だ。彼らを否定するのではなく、そのプライドと経験を「新しいやり方」の中で活かす役割を与えることで、最強の協力者に変わることがある。 - 「意味」を再定義する。
「議事録作成の効率化」という作業レベルの目的から、「自分たちの技術を未来に残す」「次の行動を明確にする」といった、より上位の「意味」へと目的を再定義することで、メンバーの当事者意識を引き出すことができる。
もしあなたが今、新しいツールの導入や業務改革で、現場の抵抗に悩んでいるのなら、少しだけ立ち止まってみてください。あなたが説いているのは、ツールの「機能」や「正しさ」だけになっていませんか?
その壁の向こう側にいる人々の、言葉にならない不安や、守りたいプライドに、少しだけ耳を傾けてみてください。本当の突破口は、最新の技術仕様書の中ではなく、そんな人間臭い対話の中にこそ隠されているのですから。