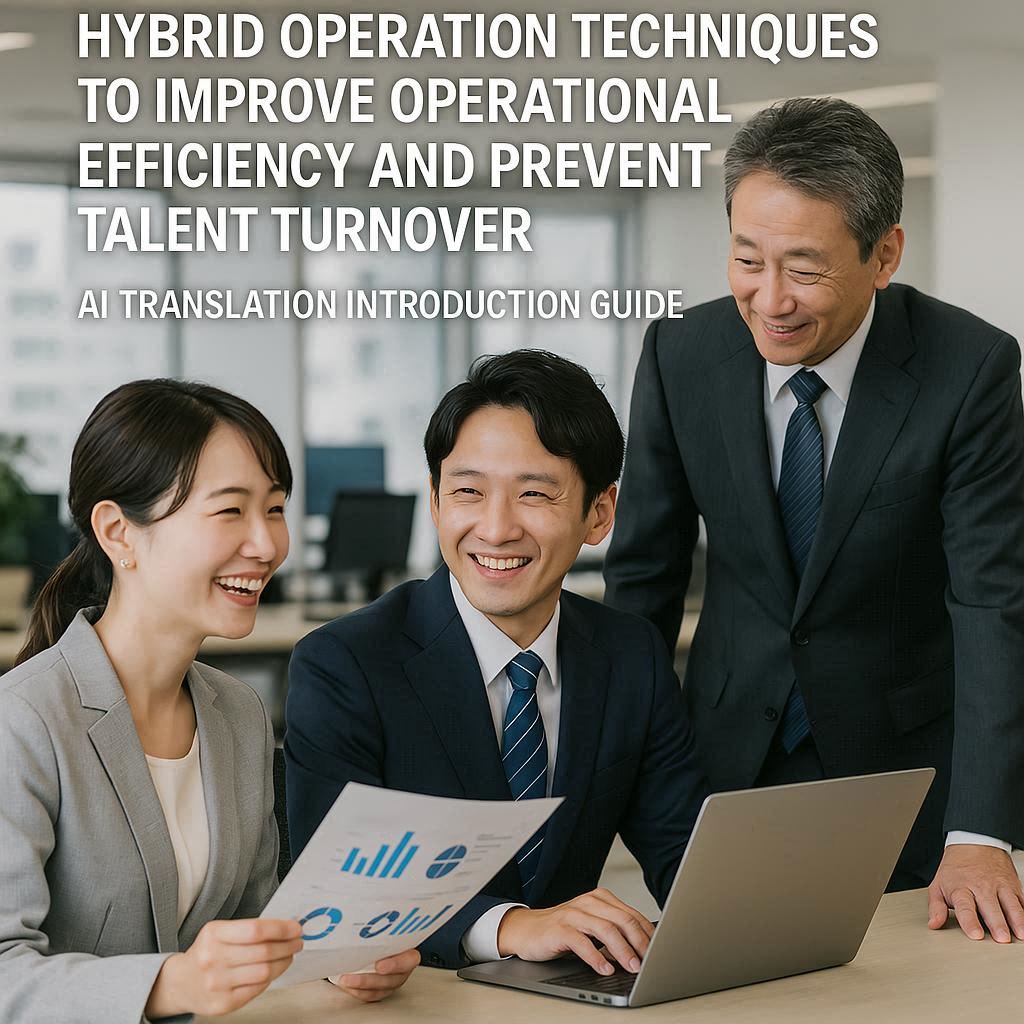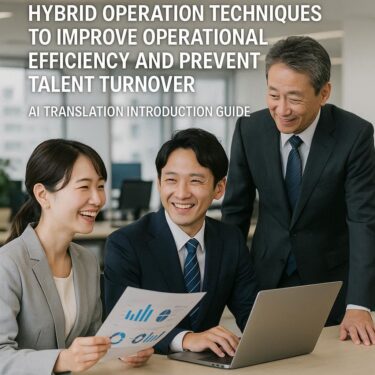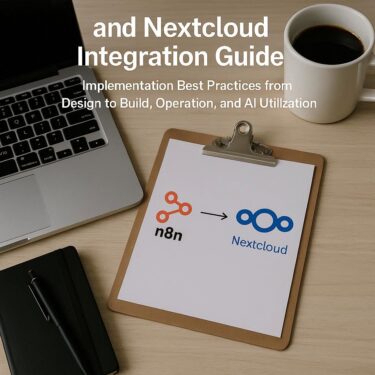AI翻訳導入の現実―「正論」だけでは動かない、人を動かすコミュニケーション術の裏側
「AIを導入すれば、業務効率が上がって、優秀な人材の離職も防げますよ」
もしあなたが、こんなキラキラした提案書を鵜呑みにしているなら、少しだけ立ち止まってこの話を聞いてほしい。これは、先日公開した「AI翻訳導入ガイド」の記事の、どこにも書けなかった裏話だ。
AI翻訳導入ガイド|業務効率化と人材離職を防ぐハイブリッド運用術 はじめに:その翻訳業務、貴重な人材を疲弊させていませんか? 海外拠点との連携、グローバル市場への進出、多国籍チームでの協業。事業の成長に伴い、翻訳はもは[…]
机上の空論は美しい。ステップ1から7まで、手順通りに進めれば誰でも成功できるように書いてある。だが現実は、そんな綺麗なチャート通りには進まない。そこには、変化を恐れる人の「心理」があり、長年培われた部門間の「壁」があり、そして善意が引き起こす「停滞」がある。
これは、私が関わったある製造業のクライアントでの、泥臭くも愛おしい、改革の記録だ。あのプロジェクトは、最新のAIツールとの戦いなんかじゃなかった。間違いなく、「人」と向き合う戦いだった。
第一章:最初の壁―「AIなんて信用できるか!」という巨大な感情論
プロジェクトが始まって早々、私たちは最初の、そして最も分厚い壁にぶち当たった。例のガイドで言うところの「ステップ1:業務の棚卸しと翻訳物の分類」の会議でのことだ。
プロジェクトリーダーに任命されたのは、海外営業部で活躍する佐藤さん(30代)。非常に優秀で真面目な女性だ。彼女が作った綺麗な資料に基づき、私が「まずは社内の翻訳業務を洗い出し、重要度で分類して、AIに任せる領域とプロに任せる領域を切り分けましょう」と説明した、その時だった。
会議室の空気が、一瞬で凍った。
口火を切ったのは、技術部の鈴木部長。この道40年の、叩き上げのベテランだ。白髪混じりの頭を掻きながら、私と佐藤さんを交互に見て、重々しく口を開いた。
「んだってなぁ、あんたたち。あの機械っちゅーのは、魂がねぇんだ。魂が」
場の空気が、さらに重くなる。鈴木部長は続けた。
「俺らが血反吐吐いで作った製品の仕様書を、ポチッとなで訳せるもんだど思ってんならか?ネジ一本の締めるトルクが、コンマ1違うだけで全部ダメになる世界だ。そんげな機微が、AIなんぞに分かるもんだべか?昔、機械翻訳で痛い目見たごどあっでのぉ。信用できん」
鈴木部長の言葉は、他の部署のベテラン社員たちの心を代弁していた。「そうなんだよ」「うちの製品のブランドイメージが…」「法務的なリスクはどうするんだ」と、堰を切ったように不安や不満が噴出する。
正論を並べただけの資料は、彼らの「感情」の前で無力だった。佐藤さんの顔は青ざめ、どう対応していいか分からず固まっている。
ここで私が「いえ、今のAIは昔と違って…」と反論しても火に油を注ぐだけだ。こういう時、必要なのは「正しさ」の証明じゃない。「共感」と「仲間になる」ことだ。
私は一歩前に出て、深く頷いた。
「鈴木部長、おっしゃる通りです。魂のこもった製品の仕様書を、魂のない機械に任せるなんて、とんでもない話ですよね。私も、もし自分が技術者だったら絶対に同じことを思います」
まず、すべてを受け止める。彼らのプライドと歴史に、敬意を払う。
「だからこそ、皆さんにお願いしたいんです。今回のプロジェクトは、AIに仕事を奪われる話ではありません。皆さん自身が『AIにどこまで任せられるか』を見極める鑑定人になっていただくためのプロジェクトです。AIが訳したものが、皆さんの厳しい目に耐えられるのか。ダメならダメでいいんです。その『ダメ』というデータこそが、会社にとって一番の財産になりますから」
私は続けた。
「この『業務の分類』という作業は、言い換えれば『AIには絶対に触らせてはいけない聖域を決める作業』です。その聖域を決めることができるのは、長年この会社を支えてこられた、皆さんしかいないんです」
「敵」から「鑑定人」へ。役割を変えるだけで、人の心理は大きく動く。さっきまで険しい顔をしていた鈴木部長が、「…ほう、俺らが鑑定人か」と少し口元を緩めた。
「そこまで言うなら、手伝ってやんねごどもねぇ。ただし、中途半端な翻訳見せたら、ちゃぶ台ひっくり返すからな」
分厚い氷が、少しだけ溶けた瞬間だった。計画書通りに進めることだけがマネジメントじゃない。相手の感情を読み、プライドを尊重し、役割を与えて巻き込んでいく。改革の第一歩は、いつだって地道な心理戦なのだ。
第二章:見えない抵抗―「用語集作り」という名の部門間サイロ戦争
最初の壁をなんとか乗り越え、次に着手したのが「ステップ4:言語資産の整備」、つまり用語集作りだ。これもまた、一筋縄ではいかなかった。
「用語集?ああ、作ればいいんでしょ」
誰もが最初は軽く考えていた。だが、これが部門間に深く根差した「サイロ(縦割り組織)」の存在を浮き彫りにする。
佐藤さんが各部署から集めた用語リストを見て、私たちは頭を抱えた。同じ部品を指すのに、技術部は「締結用金具A」、営業部は顧客向けに「ワンタッチ・リリーサー」、マーケティング部に至っては「スマート・ロック・システム」と呼んでいる。どれも間違いではない。だが、これをAIにどう教えるのか。
案の定、用語を統一するための会議は紛糾した。
「うちでは昔からこの呼び方だ。現場が混乱する」
「お客様には『スマート・ロック』のほうが響きますよ。今さら『金具』なんて言えません」
「そもそも、マーケの連中のキラキラした言葉は、仕様書の文脈に合わん!」
佐藤さんは板挟みになり、必死に調整しようとするが、話は一向に進まない。会議が終わるたびに、彼女は私のところにやってきて、疲れ切った顔でため息をついた。
「もう、何が正しくて、誰の言うことを聞けばいいのか…分かりません。みんな、自分の部署のことしか考えてないみたいで…」
彼女の目には、うっすらと涙が浮かんでいた。無理もない。これは単なる言葉の定義の問題ではない。各部署が守ってきた歴史とプライド、そして縄張り意識のぶつかり合いなのだ。
私は次の会議で、ファシリテーター役を買って出た。そしてホワイトボードに、大きくこう書いた。
「この用語集は、『誰を』幸せにするためのものですか?」
シーンと静まり返る会議室。
「技術部の皆さんのためのものでしょうか?マーケ部の皆さんのため?…違いますよね。最終的に、私たちの製品を使ってくださるお客様が、混乱しないため。そして、バラバラだった会社の知識を一つの『資産』として、未来に残していくため。目的は、そこにあるはずです」
原点に立ち返らせる。そして、具体的な解決策を示す。
「一つの言葉に、一つの訳しか認めないから、戦争になるんです。それなら、利用シーン(TPO)で使い分けるルールを作りませんか?」
私は、検討していたAI翻訳ツールの管理画面をプロジェクターに映し出した。
「例えば、このツールなら『社内文書用』『技術マニュアル用』『マーケティング用』と、文脈に応じた訳語を登録できます。AIは、翻訳する文書の種類を認識して、自動で最適な言葉を選んでくれる。これなら、皆さんの文化を壊すことなく、全社で一貫性を保てます」
「唯一の正解」を押し付けるのではなく、多様性を許容する「仕組み」を提示する。技術的な解決策が、人間関係の潤滑油になることは多い。
各部署の担当者たちが、画面を食い入るように見つめている。「へぇ、そんなことができるのか」「それなら、うちの部署の用語も残せるな」。ようやく、建設的な議論が始まった。
この一件で、佐藤さんは大きく成長した。ただ調整するだけでなく、プロジェクトの「目的」を常に問い続け、技術的な選択肢を提示することで議論を導く。彼女が、本当の意味でプロジェクトリーダーになった瞬間だったのかもしれない。
第三章:「私が全部見ます」という善意が招く、最悪のボトルネック
パイロット導入が始まり、AIが吐き出す翻訳結果を人間がレビューする「ポストエディット」の段階に入った。ここで、またしても予期せぬ問題が発生した。「善意」という名の、最も厄介なボトルネックだ。
品質を重視するあまり、各部署のエース級や、あの鈴木部長までもが「中途半端なものは出せん。俺が全部レビューする」とレビュアーに名乗りを上げてくれたのだ。これは心強い。そう思ったのは、最初の数日だけだった。
彼らは、当然ながら本業がめちゃくちゃ忙しい。レビュー依頼のメールは、彼らの受信トレイの底に沈んでいく。
「佐藤さん、例のレビュー、まだですか?」
「すみません!今週は急なトラブル対応で…来週には必ず!」
AIが数分で終わらせた翻訳作業のあと、人間によるレビューで3日も4日も滞留する。AI導入でスピードアップを図ったはずが、結果的に導入前よりリードタイムが悪化するという、笑えない事態に陥ってしまった。
佐藤さんは、優秀な人たちに「早くしてください」と催促もできず、一人で焦りを募らせていた。
「皆さん、善意で協力してくれているのに…。私がマネジメントできていないせいです…」
私は彼女を会議室に呼び、一つのデータを見せた。翻訳依頼から完了までのリードタイムをグラフ化したものだ。AI導入後、グラフの線は明らかに右肩上がりになっていた。
「佐藤さん、これはあなたのせいじゃありません。完璧を目指しすぎた結果です。いいですか、ビジネスにおける翻訳は、すべてが100点満点である必要はないんです」
私は、最初のステップで作成した「翻訳資産マップ」をもう一度広げた。
「思い出してください。この『社内共有の議事録』は、70点でいい文書でしたよね?意味が通じれば十分。一方、この『公式サイトのプレスリリース』は、120点じゃないとダメな文書です。今、私たちは70点でいいはずの文書にまで、120点を目指すエース級のリソースを投入してしまっている。これが、ボトルネックの正体です」
私たちは、レビュー体制を根本から見直した。
- 品質レベルの再定義: 文書ごとに「70点(スピード優先)」「90点(正確性重視)」「120点(プロ品質必須)」の3段階の品質目標を明確に設定した。
- 役割分担の変更: 「70点文書」のレビューは、若手担当者に一任。スピードを最優先する。
- ベテランの役割変更: エース級や鈴木部長には、日常的なレビュー業務から外れてもらった。その代わり、「90点以上の文書の最終承認者」および「若手が判断に迷った時の相談役(メンター)」という、より付加価値の高い役割をお願いした。
鈴木部長は最初、「若ぇのに任せて大丈夫なんか?」と心配していたが、「部長にしか判断できない、本当に重要な文書だけを見ていただくための体制です。若手の育成も兼ねて、ぜひご指導をお願いします」と頼むと、まんざらでもない顔で頷いてくれた。
彼らのプライドと専門性を尊重しつつ、ボトルネックにならない場所へと動かす。これもまた、重要なマネジメント術だ。この改革後、滞留していたレビューは一気に解消され、プロジェクトは再びスピードを取り戻した。
まとめ:AI導入とは、「人」のOSをアップデートする旅である
今、振り返れば、AI翻訳導入プロジェクトは、テクノロジーを導入するプロセスではなかった。それは、古い常識や固定観念という「人のOS」を、少しずつアップデートしていく旅だったのだと思う。
綺麗な計画書や正論だけでは、人は動かない。変化への不安、仕事への誇り、縄張り意識。そうしたドロドロとした感情と向き合い、受け止め、敬意を払い、そして一緒に新しい未来を描いていく。その地道なコミュニケーションの先にしか、本当の改革はない。
あのプロジェクトが終わる頃、すっかり自信をつけた佐藤さんの顔は、リーダーそのものだった。そして鈴木部長は、今ではすっかりAI翻訳を使いこなし、「おう、佐藤さん。このAIっちゅーのも、なかなか賢い部下だのぉ。俺がしっかり教育してやっから」と笑っている。
もし、あなたの会社で改革の壁にぶつかったら、この話を思い出してほしい。目の前の抵抗勢力は、敵ではない。彼らは、会社を愛し、自分の仕事に誇りを持っている、一番の功労者なのだ。その心を理解しようと努めた時、きっと分厚い氷を溶かす突破口が見つかるはずだ。