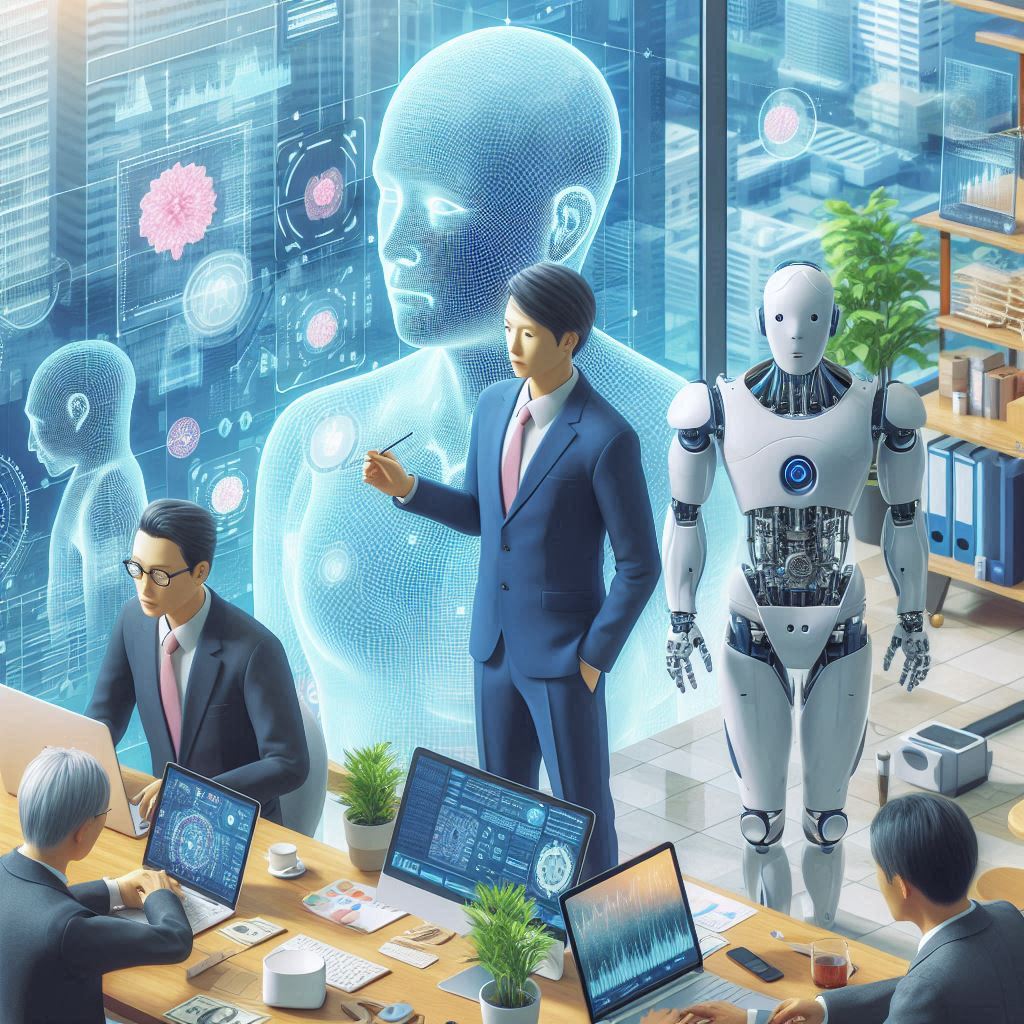AI経営の裏側で、社長の「心」をハックした静かな戦いの話
先日、「社長のAI活用は新常識へ」という記事を書いた。主要企業の社長の4割がAIを毎日使い、もはやAIは経営者の「戦略的参謀」である、と。そして、AIネイティブ経営者になるための3つの思考法と3つの実践ステップを、華々しい事例と共に紹介した。
あの記事は、これからの経営者が目指すべき「北極星」だ。そこに書かれていることに、嘘偽りはない。
しかし、だ。北極星がどれだけ輝いていても、そこへ至る航路は、嵐あり、凪あり、時に座礁しかけることだってある。今日は、あの輝かしい北極星だけを見ていては見えてこない、泥臭い航海の記録を話そうと思う。
これは、ある叩き上げの社長が、AIという得体の知れないテクノロジーを前に、どう戸惑い、どう反発し、そして最後にはどう向き合ったのか。その心の変容を、すぐ側で支え続けた、あるプロジェクトの裏物語だ。この記事は、AI導入の「正論」に疲れたあなた、トップの心を動かせずに悩むあなたのための、生々しい処方箋である。
「AIやらねば時代遅れだ!」社長の“焦り”がすべてを空回りさせる
すべての始まりは、五十嵐社長(仮名)が、まさに私が書いたような記事を読んだ、その日の午後だった。彼は一代で会社を築き上げたカリスマ。決断が早く、行動力に満ち溢れている。その強烈なリーダーシップが、会社を成長させてきた原動力だ。しかし、時にそのエネルギーは、組織をあらぬ方向へと暴走させる。
「ミズさん、見たか、この記事!社長の4割が毎日AI使ってるんだど!ウチは完全に乗り遅れてる!けしからん!明日から全役員、AI使うのを義務化するぞ!使わねぇやつは役員辞めてもらう!DX推進室は、すぐに全社研修の準備をしろ!」
緊急招集された役員会で、彼はそうまくし立てた。その目には「乗り遅れてはならない」という強烈な焦りの色が浮かんでいた。これが、AI導入プロジェクトにおける最初の、そして最大の難関だ。経営者の「焦り」と「恐怖心」に端を発した、トップダウンの号令。
この号令は、一見すると力強いリーダーシップに見える。しかし、その実態は、具体的な目的も戦略もない、ただの精神論だ。このままでは、現場は「AIを使うこと」自体が目的となり、誰もがアリバイ作りのような使い方に終始し、結果として「AIなんてやっぱり使えない」という最悪の烙印を押すことになるだろう。
私は、彼のプライドと熱意を傷つけないよう、しかし、そのエネルギーの矛先を変えるために、静かに口を挟んだ。
「社長、素晴らしい決断力ですね。そのスピード感こそが、この会社の強みです。ただ、一つだけお聞きしてもよろしいでしょうか。社長ご自身は、AIを『参謀』として、どんな相談をしてみたいですか?」
彼は一瞬、虚を突かれた顔をした。
「おれが…相談?そりゃ、あれだ、市場分析とか、競合の動向とか、そういうのだべ」
彼の答えは、まだどこか他人事だ。AIを、自分が使う「道具」ではなく、部下に「使わせる」ものだと考えている証拠だ。
私は、さらに踏み込んだ。
「では、もっと個人的なことではどうでしょう。例えば、来週に控えた、あの難しいA社との価格交渉。あるいは、なかなか言い出せずにいる、B事業部長の人事について。そんな、夜も眠れないほど頭を悩ませるような、本当に『孤独な決断』の壁打ち相手として、AIを使ってみるというのは、いかがでしょうか?」
具体的な、彼にしかわからない「痛み」に触れる。AIを「全社導入すべき流行りのツール」から、「社長、あなた自身の孤独な闘いを支える、たった一人のパートナー」へと、その意味合いを書き換えるのだ。
彼は、私の目をじっと見つめたまま、しばらく黙り込んだ。そして、「…考えておく」とだけ呟いた。暴走列車は、まだ止まってはいない。しかし、運転士が初めて、前方に別の線路があることに気づいた瞬間だった。
「おれは忙しいんだ!」“触らない社長”という名の分厚い壁
社長の号令一下、DX推進室長の田中さん(仮名)を中心に、全社的なAI研修の準備が始まった。しかし、プロジェクトは早々に暗礁に乗り上げる。肝心の五十嵐社長自身が、一向にAIに触ろうとしないのだ。
「ミズさん、困りました…。社長にアカウントをお渡しして、使い方を説明しようとしても、『そんな細かいことはいい。お前らがしっかりやれ。おれはもっと大事なことがあるんだ』の一点張りで…」
田中さんは、ほとほと困り果てていた。トップが使わないものを、部下が本気で使うはずがない。社長の「AIを使え」という号令と、「おれは使わない」という行動の矛盾。この「ダブルバインド」が、現場の士気を静かに、しかし確実に蝕んでいく。
多くの経営者は、プライドが高い。そして、自分ができないことを認めたがらない。「わからない」「できない」と言うくらいなら、「興味がない」「必要ない」という鎧をまとう。五十嵐社長も、例外ではなかった。彼は、内心ではAIに興味がある。しかし、今さら若手社員に使い方を教わったり、初歩的な質問をして恥をかいたりすることを、無意識に恐れていたのだ。
私の仕事は、彼からその「鎧」を、そっと脱がせてあげることだった。
私は、誰にも告げず、社長室のドアをノックした。そして、ノートPCを開きながら、こう切り出した。
「社長、少しだけ、二人だけの秘密の作戦会議をしませんか?誰にも言いませんから」
「なんだ、改まって」
「先日お話しした、A社との価格交渉の件です。もし私がA社の社長なら、こんなカウンターオファーを出すだろうな、というのをAIにいくつかシミュレーションさせてみました。ちょっと、ご覧になりますか?」
私は、「AIの使い方を教える」という体裁を一切取らなかった。代わりに、彼が今まさに頭を悩ませているであろう「現実の課題」を解決するための、「AIを使った分析結果」を、お土産として持参したのだ。
彼は、黙って画面を覗き込んだ。そこには、彼が予想だにしなかったであろう、A社の取りうるであろう複数の交渉パターンと、それに対する反論のロジックが、箇条書きで整理されていた。
「…なんだこれ。面白いな。…この3つ目のパターンは、あり得るかもしれん。だとしたら、ウチの準備は甘かったな…」
彼の目が、初めて「評論家」から「当事者」の目に変わった。私は、すかさず畳み掛けた。
「ちなみに社長、このAIは、私が『あなたは長年の経験を持つ、百戦錬磨の交渉人です』という“役割”を与えてから質問しています。もし、社長が『おれは創業者の五十嵐だ』と名乗ってからAIに命令したら、もっとすごい答えが返ってくるかもしれませんよ。試してみませんか?」
「教わる」のではなく、「自分の力を試す」。彼のプライドを最大限に尊重しながら、彼が自らハンドルを握りたくなるような状況をデザインする。その小さな仕掛けが、分厚い壁に、最初の亀裂を入れたのだ。
AIが暴いた、会社の“不都合な真実”
社長が少しずつAIを使い始めると、事態は思わぬ方向へと転がり始めた。彼は、市場分析や競合調査といった「外向き」のテーマだけでなく、社内の様々な「内向き」のデータについても、AIに分析させるようになったのだ。
ある日の役員会。彼は、重々しい口調で切り出した。
「…先日、過去5年間の営業日報と失注データを、AIに分析させてみた。その結果がこれだ」
スクリーンに映し出されたのは、衝撃的な内容だった。特定の営業部長が率いるチームの失注率が、他のチームに比べて突出して高いこと。そして、その原因が、彼の成功体験に基づいた古い営業スタイルに固執し、若手の新しい提案をことごとく却下していたことにある、というAIの冷徹な分析結果だった。
会議室は、水を打ったように静まり返った。その営業部長は、社長の右腕として長年会社を支えてきた功労者だ。誰もが気づいていた、しかし、誰も口にできなかった「不都合な真実」。それを、AIが何の忖度もなく、データに基づいて突きつけてきたのだ。
これは、私が予測していなかった副作用だった。AIは、経営者の「参謀」になるだけでなく、時に組織が隠してきた「病巣」を白日の下に晒す、「優秀すぎる外科医」にもなり得るのだ。
社長は、苦悩していた。データを信じるなら、長年の功労者である右腕を更迭しなければならない。しかし、情を重んじれば、会社の未来を危険に晒すことになる。
その夜、私は社長と二人で酒を飲んだ。
「ミズさん、おれはどうすりゃいいんだ…。AIは正しい。だが、AIには血も涙もねぇ」
私は、静かに答えた。
「社長、AIが出したのは、あくまで『診断結果』です。どう『手術』するかを決めるのは、医者である社長、あなた自身です。彼を罰するのではなく、彼の長年の経験を、別の形で会社に活かす道はないでしょうか。例えば、彼の経験を若手に伝える『営業顧問』という新しい役割を創設し、現場の第一線は、AIが示したデータに基づいて新しい戦略を立てられる若手に任せる。AIが出した冷たいデータに、人の心の通った『処方箋』を書くこと。それこそが、人間にしかできない、経営者の最も重要な仕事ではないでしょうか」
AIは、「What(何が問題か)」と「Why(なぜ問題か)」は教えてくれる。しかし、「So What(だからどうするのか)」という、最も重要で、最も人間的な判断は、人間にしかできない。AIという鏡に映し出された自社の姿と向き合い、時に痛みを伴う決断を下し、それでもなお、人の心を救う道を探し続ける。それこそが、「AIネイティブ経営者」に求められる、本当の覚悟なのだ。
終わりに:AIは、経営者の“人間力”を試すリトマス試験紙
あの日から一年。五十嵐社長の会社は、大きく変わった。
彼は、もはや「AIを使え」とは言わない。代わりに、会議でこう問いかけるようになった。「この課題について、AI君ならどんな意見を出すと思う?」「そのAIの分析に、我々人間の知恵として、何を付け加えられる?」。
AIは、彼の「命令」の対象から、「対話」の相手へと変わった。そして、その変化は、組織全体に伝播した。トップダウンの号令は消え、データに基づいた建設的な議論が、あらゆる部署で生まれるようになったのだ。
元の記事で、私は「AIは経営者の戦略的参謀だ」と書いた。今、それをこう補足したい。
AIは、経営者の“人間力”そのものを試す、一枚のリトマス試験紙である、と。
AIが示す冷徹なデータや合理的な判断を前に、あなたはどんな物語を紡ぎ、どんな決断を下し、どう人の心を動かすのか。AIが進化すればするほど、皮肉なことに、私たち人間の「人間らしさ」が、より一層問われることになる。
あなたの会社にAIを導入するということは、単に新しいツールを手に入れることではない。それは、社長であるあなた自身が、自らのリーダーシップ、決断力、そして人間力と、真正面から向き合う、長く、しかし、この上なく刺激的な旅の始まりなのである。