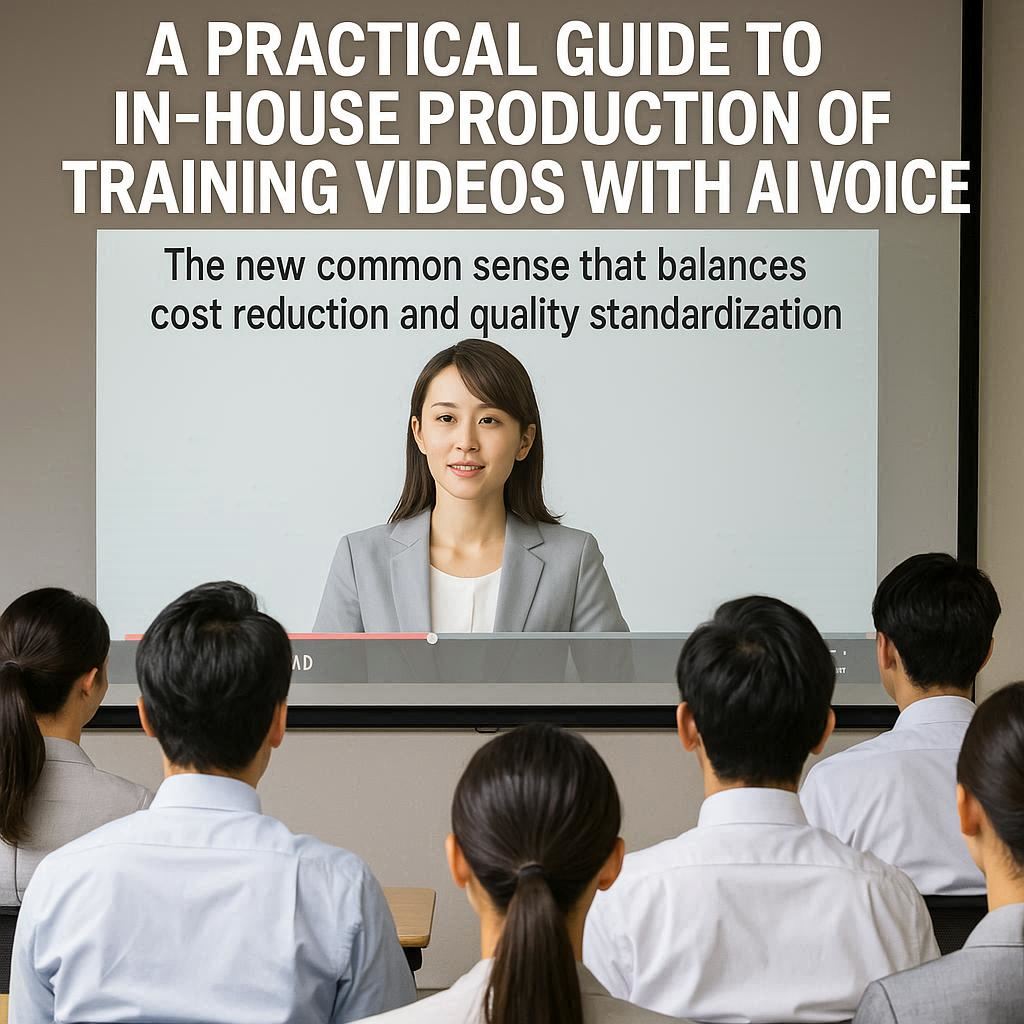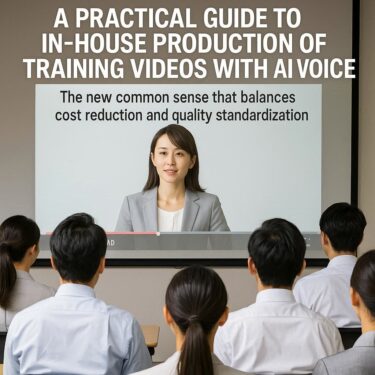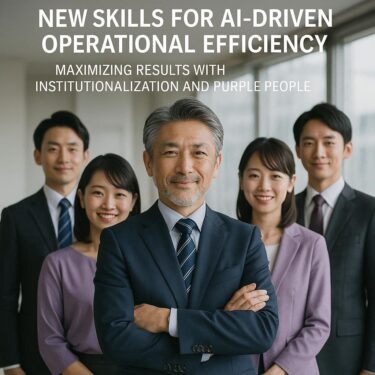AI研修動画内製化の裏側 ~現場担当者の「やらされ仕事」を「小さな成功体験」に変えた話~
「AI音声で研修動画を内製化する実践ガイド」――。
AI音声で研修動画を内製化する実践ガイド:コスト削減と品質標準化を両立する新常識 「研修動画の更新に手間と時間がかかりすぎる…」「講師によって教え方にバラつきが出て、品質が安定しない」「拠点や言語が増えるたびに、動画制作のコストが膨[…]
この記事を読み返しながら、私は少しばかり苦笑いを浮かべていました。もちろん、書かれている内容は嘘偽りのない事実ですし、この通りに進めればプロジェクトの成功確率は格段に上がるはずです。ですが、この記事には書かれていない、いや、書けなかった「もう一つの物語」があります。
それは、ツールの選定や台本設計といった華やかな表舞台の裏側で繰り広げられる、もっと泥臭くて、人間臭い物語。きれいな計画書の行間から滲み出る、現場の担当者のため息、ベテラン社員のプライド、そして部署間にそびえ立つ見えない壁…。
今日は、私が実際に経験した、ある中堅製造業での「研修動画内製化プロジェクト」の裏話を、少しだけお話ししようと思います。これは、単なるAI導入の成功譚ではありません。新しい変化の波に戸惑う人々の心を、いかにして解きほぐし、同じ船に乗せるかという、コミュニケーションとマネージメントの格闘の記録です。
もし、あなたの会社でも「新しいツールを入れるぞ!」という号令はかかるものの、なぜか現場が動かない、むしろ反発すら感じる…そんな経験があるなら、きっと共感していただける部分があるはずです。
第一幕:冷めた瞳の担当者と「正論」という名の鈍器
そのプロジェクトは、ある地方都市に本社を構える、中規模の機械部品メーカーで始まりました。私に与えられたミッションは「AI音声と動画の活用による、製造現場向け研修のDX化」。聞こえは良いですが、要は「古くなった紙マニュアルを動画に置き換えて、コスト削減と品質標準化を図りましょう」という話です。
プロジェクトの担当者としてアサインされたのは、人事部の佐藤さん(33歳・仮名)。入社8年目で、採用から労務まで幅広くこなし、周囲からの信頼も厚い、いわゆる「エース」でした。
しかし、最初の打ち合わせで私を迎えた彼女の目は、明らかに歓迎の色を浮かべていませんでした。
「はじめまして、佐藤です。それで、AI音声でしたっけ? 結局、ロボットみたいな無機質な声で読み上げるだけでしょう? そんな動画で、あの複雑な機械の操作が本当に頭に入るとお思いですか?」
立て板に水とはこのこと。彼女は続けます。
「そもそも、そんな新しいことを始める前にやることがあるんじゃないでしょうか。今のマニュアルだって、現場の仕様変更に追いついていなくて誤字だらけです。まずは、そっちを直す時間を確保する方が、よっぽど有益だと思うんですけど」
完璧な正論です。ここで私が「いや、最新のAI音声は非常に自然でして…」「長期的に見ればこちらのほうがコストメリットが…」などと、いわゆる「正論」で返していたら、このプロジェクトは初日にして詰んでいたでしょう。
新しい提案に対し、現場から「現状の課題」を盾に反論される。これは、変革プロジェクトにおける「あるある」の第一関門です。彼女の言葉の裏には、こんな本音が隠されていました。
「ただでさえ日々の業務で手一杯なのに、また上からよくわからない仕事が降ってきた…」
「過去にも似たようなITツールを入れたけど、結局使われずに埃をかぶったじゃない…」
「どうせ私たち現場の苦労も知らずに、コンサルがきれいごとを並べてるだけでしょ…」
私はPCを閉じ、彼女の目をまっすぐ見て言いました。
「佐藤さん、おっしゃる通りです。めちゃくちゃよく分かります。今の業務だけでも大変なのに、また新しいことをやれって言われても、正直『またか』って感じですよね」
一瞬、彼女の眉がピクリと動きました。反論されると思っていたのでしょう。
「もし、ですよ。もし、これから導入するこの仕組みが、佐藤さんが今一番時間を取られている『マニュアルの修正と、現場への問い合わせ対応』という仕事を、劇的に『減らす』ためのものだとしたら…少しだけ、興味わきませんか?」
私は「新しい仕事を増やす」のではなく「今の仕事を楽にする」という文脈で話を切り出しました。そして、「導入を決定する」のではなく、「佐藤さんの仕事が楽になるか、一緒に『実験』しませんか?」と持ち掛けたのです。
ポイントは、「やらされ仕事」から「自分ごと」へ、意識のスイッチを切り替えること。正論という鈍器で相手を黙らせるのではなく、相手の懐に飛び込み、同じ目線で「どうやったら私たちが楽できるか」という共通のゴールを設定する。この小さな一歩が、固く閉ざされていた彼女の心の扉を、ほんの少しだけ開けてくれたのです。
第二幕:「ウチのやり方は特別だ」という名の聖域
次の壁は、さらに手強いものでした。研修の元となるマニュアルを作成し、現場の技術指導を一手に担っている、製造二課の五十嵐課長(58歳・仮名)です。筋金入りの現場主義者で、その道35年の大ベテラン。彼の言葉は、工場の「憲法」にも等しい重みを持っていました。
事務所の隅にある、油の匂いが染みついた彼の城(デスク)で、私はAI音声のデモを聞かせました。
「ミズさん(私のこと)、AIだかなんだが知らねぇけども」
五十嵐課長は、腕を組み、ゆっくりと庄内弁で語り始めました。
「ウチの仕事はな、そだなモニターで見るもんど違う。この紙のマニュアルば見て、俺らが横で『ここのバルブの締め方はな、”クッ”じゃねぇ、”グッ”だ!』って、手ぇ取って教えで、初めて覚えられんだ。そだなパソコンから出る冷てぇ声で、何が伝わるっていうんだがな」
これもまた、強烈な正論です。そして、彼の言葉には、自らの仕事と経験に対する揺るぎない誇りが満ち溢れていました。ここで彼のやり方を否定することは、彼の35年間を否定することに等しい。絶対にやってはいけない禁じ手です。
「課長、おっしゃる通りです。課長が直接指導されるOJTに勝る研修なんて、絶対にありません。今回ご相談しているのは、そのOJTを、もっと価値あるものにするためのお手伝いなんです」
「…どういうことだ?」
「今、課長やベテランの方々は、新人に『ネジは右に回すと締まる』というレベルの、本当に基本的なことから教えていらっしゃいますよね。その時間を、AIの動画に任せるんです。そうすれば、課長はもっと大事な『言葉では説明しにくい”グッ”という力加減』とか、『機械の異音を聞き分ける勘所』といった、本当にベテランにしか教えられないことに時間を使えるようになる。そうは思いませんか?」
私は、AIを彼の仕事を「奪う敵」ではなく、彼のノウハウを「増幅させる相棒」として位置づけました。彼の聖域である「OJT」を侵すのではなく、その前段階の「知識学習」を肩代わりする存在だと定義し直したのです。
そして、もう一押し。私は、彼が何年もかけて作り上げた、手垢のついたマニュアルの一部を、その場でテキストに起こし、AIに読み上げさせてみました。少しトーンを落とした、落ち着いた男性の声です。
「…ほう、思ったより聞きやすいもんだな。んだども…ここの『危険箇所を確認』っていうところは、もっとこう…切羽詰まった感じで言わねど、新人はボケーっと見過ごすな」
チャンスです。
「ありがとうございます! まさに、その『切羽詰まった感じ』の調整が、このツールの面白いところでして。課長の、その『魂』を、このAIの台本に吹き込んでいただくことはできませんでしょうか? この言い回しは、課長にしか作れません」
その瞬間、五十嵐課長の顔が、ただの「評論家」から「当事者」のそれに変わりました。彼は「AIなんて」と言いながらも、赤ペンを手に取り、AIが生成した台本に、現場の魂を込めた言葉を書き込み始めたのです。
第三幕:「誰がやるの?」という永遠の課題
佐藤さんと五十嵐課長という二人のキーパーソンを巻き込み、最初のパイロット版研修動画(新人向けの安全衛生教育)は、驚くほどスムーズに形になりました。しかし、本当の戦いはここからでした。
「さて、これを本格運用するとなると…」
私が切り出すと、途端に場の空気が重くなります。そうです。「誰が、どの作業を、責任を持ってやるのか」問題です。
佐藤さん(人事部):「動画で使うマニュアルの内容の正確性を担保するのは、私たち人事では不可能です。これは現場の製造部さんでチェックしていただくしか…」
五十嵐課長(製造部):「馬鹿言え。こっちは日々の生産で手一杯だ。動画の見栄えだの、ナレーションの言い回しだの、そだな細かいごどまで見でられっか。そごは人事部の仕事でねぇのが」
典型的なセクショナリズムのぶつかり合い。ボールの押し付け合いが始まり、プロジェクトは完全に停滞しました。
この種の対立を解決するのに、精神論は無意味です。「皆さん、協力し合いましょう」なんて言っても、誰も動きません。必要なのは、感情論を排した、具体的な「協業フロー」という名の仕組みです。
私はホワイトボードの前に立ち、一枚の図を描きました。
- 【起点:製造部】 現場でマニュアルが更新されたら、その電子ファイル(WordやPDF)を、指定された共有フォルダに放り込むだけ。作業時間は1分。
- 【自動化:AI】 Notebook LMのようなツールが、共有フォルダを定期的に巡回。新しいファイルを見つけたら、自動で内容を読み取り、研修動画の台本の「たたき台」を生成します。
- 【監修:製造部】 五十嵐課長には、週に一度、火曜の朝10時から30分だけ時間を確保してもらいます。その場で、AIが作った台本に目を通し、現場でないと分からない表現の間違いや、ニュアンスの修正(赤入れ)だけを行う。「ゼロから作る」のではなく「出来上がったものをチェックする」だけなので、負担は最小限です。
- 【品質保証:人事部】 佐藤さんには、製造部が「赤入れ」した最終稿の台本を受け取り、AI音声の生成と動画の最終組み立てをお願いします。彼女の役割は、内容の正しさではなく、「研修コンテンツとしての分かりやすさ・聞きやすさ」という品質に責任を持つことです。
このフローのポイントは、各部署の専門性と責任範囲を明確に切り分けたことです。製造部は「内容の正確性」に、人事部は「教材としての品質」に、それぞれが責任を持つ。そして、最も面倒な「たたき台作成」という作業をAIに任せることで、両者の心理的・時間的負担を大幅に軽減しました。
「これなら…やれるかもしんねぇな」
「…そうですね。これなら、役割が明確でやりやすいです」
責任の押し付け合いで止まっていた歯車が、仕組みの力によって、ゆっくりと、しかし確実に回り始めた瞬間でした。
最終幕:担当者の涙と、ボトムアップの波
数ヶ月後。完成した研修動画シリーズは、新入社員研修や中途採用者向けのオンボーディングに正式導入されました。
ある日の夕方、私の携帯に佐藤さんから電話がかかってきました。少し弾んだ声です。
「ご報告したいことがありまして! LMSのデータを見たんですが、新人研修後の現場OJTの時間が、前年比で平均15%も短縮されてたんです! 五十嵐課長からも、『今年は新人の覚えが早い』って初めて褒められました」
それだけではありませんでした。
「何より嬉しかったのが…今まで、研修が終わると現場のリーダーから『なんであんな基本的なことも教えでないんだ!』って、よく人事部にクレームの電話があったんですけど…それが、この3ヶ月、一件もなくなったんです」
電話の向こうで、彼女が少し声を詰まらせるのが分かりました。
「…正直、最初は本当に面倒な仕事だと思ってました。でも、自分のやったことが、こうやって数字になって、現場の負担を減らして、新人の成長にもつながってるんだって実感できて…。本当に、やってよかったです」
エースと呼ばれ、常に完璧に仕事をこなしてきた彼女が初めて見せた、感情の揺らぎ。それは、「やらされ仕事」が「自分の価値を実感できる仕事」に変わった瞬間の、何よりも尊い涙でした。
この小さな成功体験は、強力な伝播力を持っていました。「製造二課が導入した新しい動画マニュアル、すごく良いらしい」という噂は、あっという間に社内に広がります。トップダウンで「やれ」と言っても動かなかった他部署から、「ウチの部署でも、あの仕組みを使えないか?」という問い合わせが、人事部に舞い込むようになったのです。
「AI音声の実践ガイド」のような記事は、いわば綺麗な航海図です。しかし、実際の航海には、必ず予期せぬ嵐や、船員たちの衝突がつきものです。
ツールを導入するだけでは、変革は起きません。大切なのは、そのツールの先にいる「人」の心をどう動かすか。相手の立場に立って共感し、プライドを尊重し、対立が起きない仕組みを設計し、そして何より、小さな成功体験を分かち合うこと。
もしあなたが今、新しい挑戦の前に立ちはだかる「人」という壁に悩んでいるのなら、思い出してください。その壁の向こう側には、あなたと同じように、日々の仕事に奮闘し、自分の価値を信じたいと願っている仲間がいることを。その心の琴線に触れることさえできれば、最も強固な抵抗勢力は、最も頼もしい推進力へと変わるのですから。