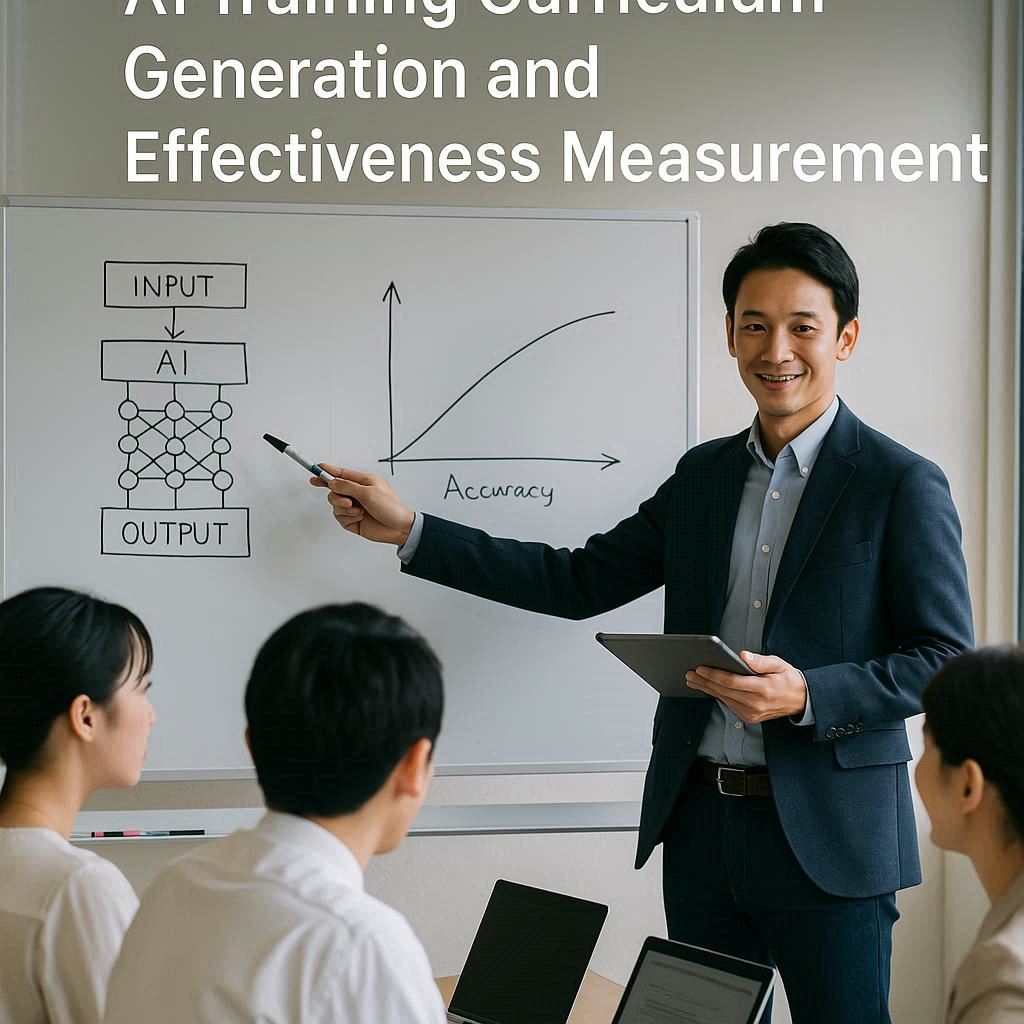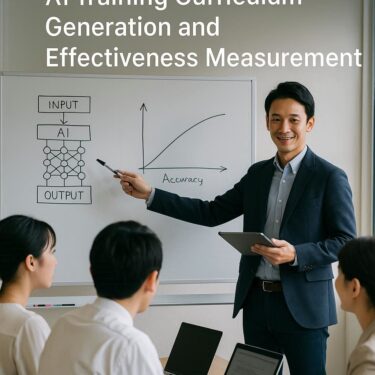AI研修のきれいな計画書の裏側で起きていたこと
「明日から使える、AIを活用した研修カリキュラムの自動生成プロセス」「ROIで成果を可視化する」…先日公開した記事では、いかにAIを使って戦略的に研修を設計し、成果を出すかという、いわば「理想の姿」を描きました。フレームワークを提示し、ステップを踏めば誰でもできるように解説したつもりです。
AI研修カリキュラム自動生成と効果測定の実践ガイド|目的設計からROI可視化まで いま、多くの企業で研修のあり方が根本から問われています。生成AIの登場により、個々の従業員が必要とするスキルは急速に変化し、従来の画一的な研修では現場[…]
しかし、正直に告白します。
あの美しいプロセスの裏側では、もっと泥臭く、人間味あふれる、一筋縄ではいかない現実が繰り広げられていました。計画書通りに進むプロジェクトなど、この世には存在しないのです。
今日は、あの記事には書けなかった「裏話」を少しだけお話ししようと思います。これは、AI導入や業務改革のプロジェクトで、あなたが直面するかもしれない壁を乗り越えるための、ささやかなヒントになるかもしれません。これは、ある製造業のクライアントで起きた、マネジメントとコミュニケーションを巡る奮闘の記録です。
第一幕:会議室の凍りついた空気と「フワッとした目的」の正体
プロジェクトのキックオフ。私の目の前には、人事部で研修担当を務める佐藤さん(30代)が座っていました。彼女は非常に真面目で、なんとかこのプロジェクトを成功させたいという熱意が伝わってきます。しかし、彼女が持ってきた企画書の「研修目的」の欄には、こう書かれていました。
「全社員のAIリテラシーを向上させ、DXを推進する」
私は内心で(うわ、一番困るやつだ…)と思いましたが、顔には出しません。この手の「フワッとした目的」の裏には、必ず現場の複雑な事情が隠れているからです。
私:「佐藤さん、素晴らしい目的ですね。ちなみに、具体的にどの部署の、どんな業務から変えていきたい、というイメージはありますか?」
佐藤さん:「えっと…それは、これから皆さんと一緒に考えていければと…」
彼女の目が泳いでいます。これは彼女一人の問題ではありません。私は彼女を問い詰める代わりに、プロジェクトの主要メンバーである現場のキーパーソンたちとの個別ヒアリングを提案しました。
まず訪れたのは、製造ラインを管理する生産管理課。鈴木課長(40代後半)は、PCの画面から目を離さずに言いました。
鈴木課長:「AI研修? ああ、上からなんか来てたな。悪いけど、こっちは毎日トラブル対応と納期調整で手一杯なんだ。研修で半日も人を抜かれる余裕なんてないよ。そもそも、そんな横文字の研修やって、明日の生産量が上がるのか?」
…痛いところを突いてきます。彼の言うことはもっともです。次に話を聞いたのは、設計部を長年束ねてきた高橋部長(60代前半)。彼は鶴岡市出身で、腕利きのベテラン技術者です。
高橋部長:「AIだぁ? ミズさん、わがんねぇごど言うなやの。うぢの仕事は図面一枚に魂込めでの仕事だ。ポッと出の機械に何が分がるって言うんだ。そんなもんに頼ってたら、若ぇのが育たねぐなるべ」
会議室に戻ると、佐藤さんはすっかり落ち込んでいました。
佐藤さん:「やっぱり、無理なんでしょうか…。鈴木課長には『どうせ上が言ってるからやってるだけだろ』って言われましたし、高橋部長は聞く耳を持ってくれませんでした…」
私:「佐藤さん、これが現実です。そして、ここが私たちの本当のスタート地点ですよ」
私は彼女に言いました。「フワッとした目的」は、彼女の怠慢ではなく、現場の強固な抵抗に対する「鎧」だったのです。具体的な業務に踏み込めば、鈴木課長や高橋部長のような人々から総攻撃を受けるのが目に見えている。だから、誰からも文句の出ない、最大公約数的な言葉に逃げるしかなかった。
【コンサル術①:『なぜ』を責めるな、状況を読め】
担当者が具体的でない目的を掲げた時、「もっと具体的に考えろ」と突き放すのは簡単です。しかし、多くの場合、その背景には板挟みになった担当者の苦悩や、組織内の見えない力学が存在します。まずやるべきは、その担当者を取り巻く環境を理解し、「なぜ、そう言わざるを得ないのか」という状況に共感すること。そして、彼女(彼)を孤独な戦士にせず、「一緒に壁を突破する共犯者」になることです。
私:「佐藤さん、作戦を立てましょう。鈴木課長と高橋部長、二人を敵に回したらこのプロジェクトは進みません。彼らを『なるほど』と言わせるための、小さなワナを仕掛けに行きませんか?」
第二幕:正論は通じない。懐に入り込むための「貢ぎ物」
元記事には「自社データを使ったワークショップが効果的」と書きました。しかし、その「自社データ」を入手するのが、プロジェクトで最も高いハードルの一つです。
案の定、鈴木課長は「機密情報だらけの生産データなんか、絶対に出せん」の一点張り。高橋部長も「会社の宝である設計図面を、どこの馬の骨ともわからんAIに食わせるだと? とんでもねぇ」と取り付く島もありません。
正論では勝てません。「AIは安全です」「NDAを結びますから」なんて言っても、彼らの長年の経験で培われた警戒心は解けません。こういう時、必要なのは「理屈」ではなく「実利」、それも相手が個人的にメリットを感じる「貢ぎ物」です。
私はまず、鈴木課長の元へ一人で向かいました。
私:「課長、お忙しいところすみません。先日の件、研修でご迷惑はおかけしません。ただ一つ、もしよろしければ、課長が毎週月曜の午前中を丸々使って作っている『週次生産報告書』、あれをAIで30分で終わらせるデモを、お見せするだけ見てもらえませんか?」
私は事前に佐藤さんから、鈴木課長がその報告書作成に膨大な時間を費やし、いつもイライラしているという情報を得ていました。ダミーデータと、報告書のフォーマットだけ借りて、彼の目の前でプロンプトを打ち込みます。あっという間に、グラフ付きの報告書の骨子が生成されました。
鈴木課長:「…ほう。これは…なんだ?」
私:「まだ完璧じゃありません。でも、この面倒な集計とグラフ作成の部分だけでもAIにやらせれば、課長はもっと重要な『なぜ生産性が落ちたのか』の分析に時間を使えると思いませんか?」
次に高橋部長の元へ。彼には、技術者としてのプライドをくすぐるアプローチを取りました。
私:「部長、先日は失礼しました。AIが部長の技術を超えるなんて、私も思いません。ただ、思ったんです。部長が若手の頃、ベテランの先輩の図面を見て技術を盗んだように、AIに部長の過去の傑作図面の『考え方』を学ばせることができたら、若手が育つスピードが格段に上がるんじゃないかと」
高橋部長:「…うぢの図面の考え方、だと?」
私:「はい。例えば、あの伝説的な製品『ZX-5』の設計思想です。あのときの、部品Aと部品Bの絶妙なクリアランスの決め方。ああいう『勘どころ』を言語化してAIに教えれば、若手が凡ミスをすることも減る。部長が毎回同じことを教える手間も省けます。言わば、部長の『デジタルな弟子』を作るようなものです」
高橋部長:「…んだな。あいつら、何度言ってもわがんねぇがらな…。まあ、その『弟子』とやらが、どれほどのモンか、見でみねぇごどには始まらねぇな」
【コンサル術②:相手の『土俵』でメリットを語れ】
「全社的な生産性向上」といった大きな話は、現場の人間には響きません。彼らが興味があるのは「自分の仕事がどう楽になるか」「自分の部署の問題がどう解決するか」です。相手の課題を徹底的にリサーチし、相手の言葉(土俵)で、個人的なメリットを具体的に示すこと。それが、頑なな心の扉を開く鍵になります。それは時に、相手の承認欲求やプライドをくすぐる言葉かもしれません。
第三幕:「効果測定」という名の最終プレゼン
小さなワナは功を奏し、鈴木課長と高橋部長は「まあ、お試しでやってみるだけだ」という条件付きで、限定的なデータ提供とパイロット研修の実施を許可してくれました。
研修は、生産管理課と設計部の若手それぞれに特化した内容で実施。元記事で紹介した通り、彼らの実務データ(を加工したもの)を使った演習は、非常に効果的でした。研修後のアンケートでは、「大変満足」「業務に役立つと思う」といったポジティブな回答が並びます。
佐藤さんはその結果を見て、ホッと胸をなでおろしていました。
佐藤さん:「良かったです! 皆さん、満足してくれたみたいで…!」
私:「ええ、素晴らしい第一歩です。でも、本当の勝負はここからですよ、佐藤さん。このアンケート結果を鈴木課長に見せても、『ふーん、楽しかったみたいで良かったな』で終わります。彼が知りたいのは、ただ一つ。『で、仕事は早くなったのか?』です」
「効果測定」とは、単なるデータ収集ではありません。それは、懐疑的なステークホルダーを納得させるための、最も重要な「最終プレゼン」なのです。
私たちは、カークパトリックモデルのレベル3(行動変容)とレベル4(結果)を証明するための証拠集めに奔走しました。
設計部の若手、田中君に協力してもらい、研修で学んだプロンプト術を使って、ある部品の設計図面のたたき台を作成する時間を計測。結果、従来の手法に比べて、作業時間が40%も短縮されたのです。
生産管理課では、研修を受けたメンバーがAIで報告書を作成したことで、鈴木課長のレビューと修正指示の時間が、以前の半分以下になりました。
そして、私たちは鈴木課長と高橋部長を会議室に呼びました。しかし、プレゼンしたのは私や佐藤さんではありません。実際に成果を出した、若手の田中君です。
田中君:「…というわけで、AIに条件を細かく指示することで、この図面のドラフトが約1時間でできました。以前なら半日はかかっていた作業です。高橋部長に教わった『ZX-5』の設計思想をプロンプトに組み込んだのが、特に効果的でした」
高橋部長は、腕を組んで黙って聞いていましたが、口元が少し緩んだのを私は見逃しませんでした。
次に、佐藤さんが口を開きました。
佐藤さん:「鈴木課長、こちらのデータをご覧ください。研修後、課の週次報告書の初回提出時の修正依頼件数が、平均で60%減少しました。これにより、課長のレビュー時間が週あたり約2時間削減された計算になります」
鈴木課長は、しばらく黙ってデータを見ていましたが、やがて顔を上げ、私を見てニヤリと笑いました。
鈴木課長:「…なるほどな。俺の時間を2時間も奪ってた犯人は、お前(AI)だったってわけか。まあ、悪くない」
【コンサル術③:本人に語らせろ、第三者が数字で裏付けろ】
改革の成果は、推進者が語るよりも、実際に変化を体験した現場の当事者が語る方が何倍も説得力があります。「こんなに楽になりました」「こんなに早くできました」という生の声は、どんな綺麗なグラフよりも人の心を動かします。そして、その「個人の感想」を、研修担当者や我々のような外部の人間が「客観的な数字」で裏付ける。このコンビネーションが、組織の空気を変えるのです。
終幕:小さな成功が、大きなうねりになる
この小さな成功事例は、佐藤さんの手によって、すぐに社内報の記事になりました。「あの懐疑的だった鈴木課長が認めた! 生産管理課の報告書作成時間が半減した秘密」という、少し煽り気味のタイトルで。
すると、どうでしょう。今まで遠巻きに見ていた他部署の課長たちから、「うちでも話を聞かせてくれないか」という問い合わせが、佐藤さんの元に次々と舞い込むようになったのです。高橋部長は、設計部の若手に「あのAIの弟子、もっと賢くできねぇのが?」と自分から言い出すようになりました。
AI研修のフレームワークや効果測定モデルは、確かに重要です。しかし、それはあくまで地図のようなもの。実際に荒野を進むためには、そこにいる人々の心を動かすコミュニケーションが不可欠です。
もしあなたが今、社内の抵抗や無関心に悩んでいるのなら。
まずは、たった一人でいい。あなたの目の前にいる、懐疑的で、忙しくて、でも本当は自分の仕事を良くしたいと願っているはずのキーパーソンを見つけてください。
そして、正論で打ち負かそうとせず、彼(彼女)の個人的な悩みに寄り添い、小さな「貢ぎ物」を差し出してみてください。その小さな成功体験が、やがて組織全体を動かす、大きなうねりの第一波になるはずですから。