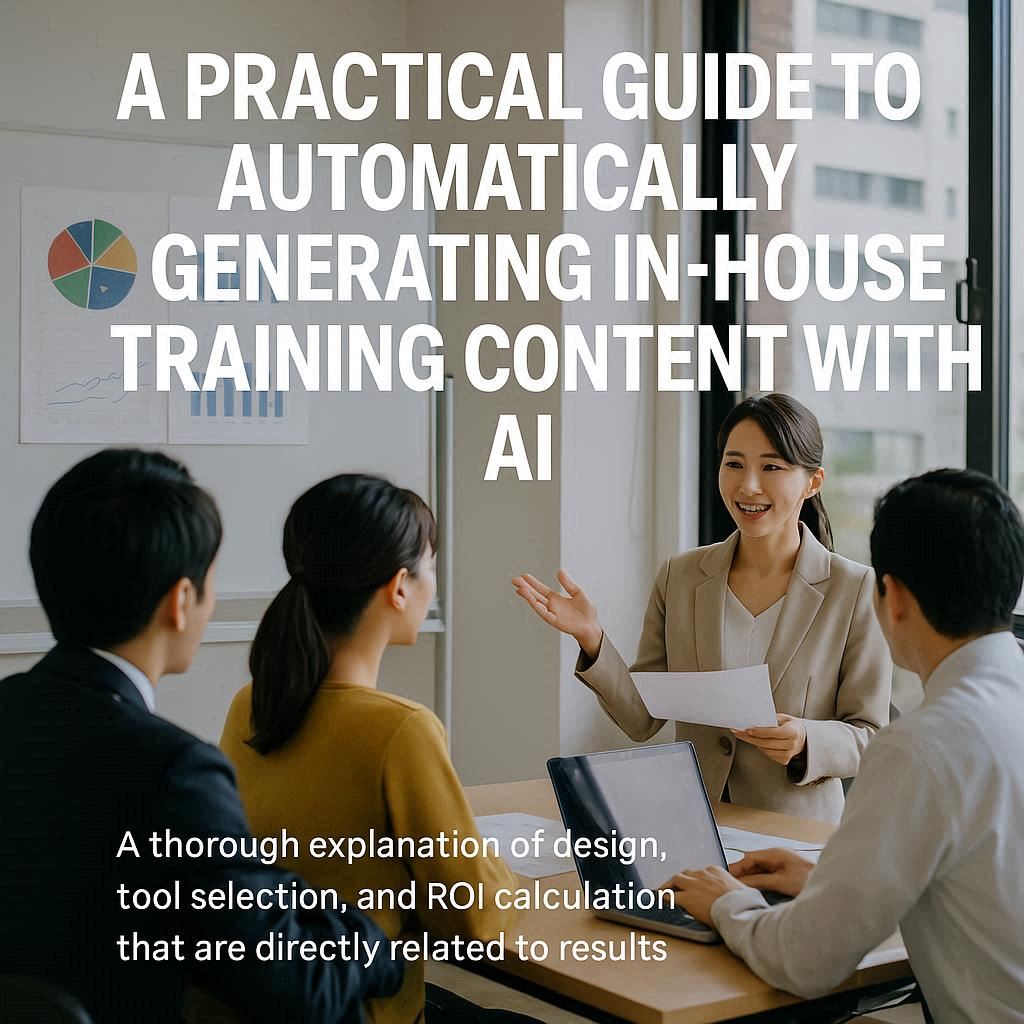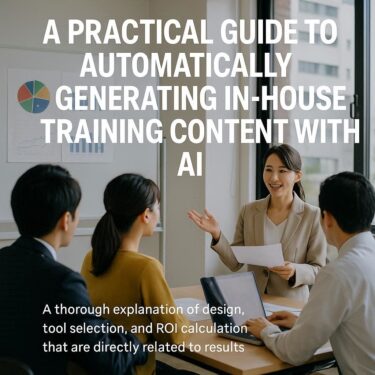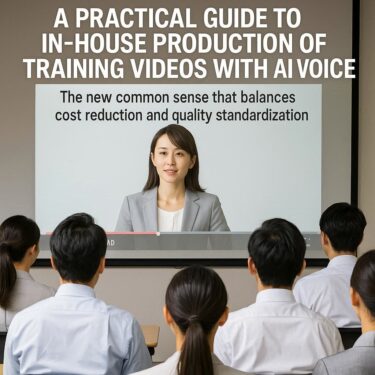AIで社内研修、裏側で起きていたこと ― 「AIでよろしく」丸投げ案件を現場主導に変えた話
先日、私は「AIで社内研修コンテンツを自動生成する実践ガイド」という、いささか教科書的な記事を執筆しました。目的設定からROIの算出まで、フレームワークに沿って進めれば誰でも成果を出せる、そんな風に見えるかもしれません。
AIで社内研修コンテンツを自動生成する実践ガイド:成果に直結する設計、ツール選定、ROI算出まで徹底解説 はじめに:研修は「作る速さ」から「成果を出す仕組み」へ 「生成AIを導入したものの、一部の社員しか使っておらず、[…]
しかし、あの記事には書けなかった、というより、書かなかった「裏側」があります。
企業改革の現場とは、きれいなパワポの資料通りには進まない、もっと人間臭くて泥臭い場所です。最新のAIツールを導入する話なのに、結局は人の「感情」とどう向き合うかが成功の9割を占める。今日は、あの華やかな成功事例の裏で繰り広げられた、マネジメントとコミュニケーションを巡る、ちょっとした苦労話にお付き合いください。
これは、ある中堅製造業のクライアントで、私が体験した物語です。
第一幕:会議室に漂う「とりあえずAI」という名の思考停止
最初のキックオフミーティングの空気は、今でもはっきりと覚えています。広々とした会議室に集まったのは、経営層から「特命」を受けた情報システム部の課長と、人事部から引っ張られてきた研修担当の佐藤さん(仮名・30代女性)。
「ミズさん、よろしくお願いします!トップダウンで『AIで研修を抜本的に改革しろ』と。ついては、ChatGPTを使って研修資料を自動生成するシステムをですね…」
意気揚々と語る課長(40代)の横で、佐藤さんは不安そうな顔で分厚いファイルを手にしていました。その目は明らかに「どこから手をつけていいか分からない」と訴えています。
こういう時、私は技術の話は一切しません。AIの性能やツールの比較を語っても、彼らの本当の課題には届かないからです。
「課長、ありがとうございます。その話の前に、佐藤さんにお聞きしたいのですが」
私は、あえて佐藤さんに視線を向けました。
「今の研修業務で、一番『もう、やってられない!』って思うことは何ですか?」
一瞬、戸惑った表情を見せた佐藤さんでしたが、ぽつり、ぽつりと本音を話し始めました。
「…毎月、新製品が出るたびに、技術部門から送られてくる膨大な資料を読み込んで、営業向けの研修スライドを作るんです。でも、完成する頃にはもう次の製品情報が来ていて…。結局、資料作りに追われて、一番大事な若手へのロールプレイング指導や、現場でつまずいている子のフォローに全く時間が割けないんです。作った資料も、ちゃんと読まれているか分からなくて…」
これです。これこそが、AI導入プロジェクトの本当の出発点になるべき「痛み」です。
私は頷きながら、ホワイトボードにこう書きました。
「目的:研修資料を『作ること』→ 新人が『早く独り立ちできること』」
「課長の言う『AIで資料を自動生成する』のは、あくまで手段です。私たちの本当のゴールは、佐藤さんの時間を確保して、若手のフォローに集中できるようにすること。そして、その結果として、例えば『新製品の単独提案が可能になるまでの期間を3ヶ月から2ヶ月に短縮する』といった、具体的な業務成果に繋げることですよね?」
課長はハッとした顔で頷きました。
「なるほど…手段が目的化していました」
「ええ。AIは魔法の杖ではありません。私が物造りの現場でよく言うんですが、『ゴミを入れたらゴミしか出てこない』んです。質の悪い材料(データ)からは、不良品(役に立たないコンテンツ)しか生まれない。だからこそ、最初に『どんな製品(成果)を作りたいのか』という設計図(KPI)を、現場の皆さんと一緒に描く必要があるんです」
この日を境に、会議の議題は「どのAIツールを使うか」から「新人が一番つまずくのはどの部分か」に変わりました。佐藤さんの表情から不安が消え、当事者としての強い意志が宿り始めたのは、言うまでもありません。
第二幕:抵抗勢力という名の「最後の砦」をどう巻き込むか
プロジェクトの目的が定まり、次に私たちが着手したのは、AIの「教科書」となる社内ナレッジの収集でした。業務マニュアル、過去の成功事例、トップセールスのトーク集…。しかし、ここで私たちは大きな壁にぶつかります。
製造部のベテラン、木村部長(仮名・62歳)。この道40年の生き字引のような人で、社内の誰もが彼に一目置いています。彼の協力なくして、リアルな現場の知見をAIに学習させることは不可能でした。
私が製造部のフロアを訪ねると、木村部長は腕を組み、いかにも不機嫌そうな顔で私を迎えました。
「ミズさん、なんかAIだかなんだか知らねぇけどよ。俺たちの仕事は、そんなマニュアル通りにやってるわけじゃねぇんだ。勘と経験、それに状況判断。全部、この頭の中さ入ってるんだ。それをいちいち文章にしろって言われても、無理な話だべ」
庄内弁の朴訥とした語り口には、自分の仕事への誇りと、得体の知れない新しい技術への警戒心が滲み出ていました。これが典型的な「抵抗勢力」の姿です。しかし、私は彼らを抵抗勢力とは呼びません。彼らは、会社の品質を守ってきた「最後の砦」なのです。
正面から「AIの重要性」を説いても、彼のプライドを傷つけるだけでしょう。私は戦略を変えました。
「部長、おっしゃる通りです。部長のそのご経験をマニュアル化なんて、到底無理な話だと思います」
「んだろ?」
「ただ、一つだけ教えていただきたいんです。3年前に起きたクレーム、あの時、誰もが匙を投げた案件を部長が一発で収めたと聞いています。あの時、どうやって原因を突き止めたんですか?あの神業を、少しでも若手が学べたら、会社にとってすごい財産になると思うんですよね…」
私は、彼の功績を具体的に挙げて、心からの敬意を示しました。木村部長の眉間のシワが、少しだけ和らぎます。
「…ああ、あの時のごどが。あれはな、異音の周波数がいつもと違うだっけんだ。長年の勘だ」
「その『勘』の正体を、部長の言葉でAIに教えてやることはできませんかね?もちろん、最終的にAIが作ったコンテンツが、部長の意図とズレていないか、最後にチェックしていただくのは部長、あなたしかいません。部長がOKを出さない限り、絶対に社内には公開しません。品質保証の責任者は、あくまで部長です」
この一言が決定打でした。「AIに仕事を奪われる」という恐怖が、「AIは自分の知識を継承する弟子であり、自分はその師匠であり最終監査役である」という認識に変わった瞬間です。
「…んだば、しゃーねぇな。ミズさん、こっちさ来て座れ。まず、あの時の図面、見せでやるさかい」
木村部長は、埃をかぶった棚から古いファイルを取り出してきました。彼の「暗黙知」が、初めて「形式知」へと変わろうとしていました。
あの記事で書いた「SME(Subject Matter Expert)レビュー」という横文字の工程。その裏側では、こうした現場の職人たちのプライドと、彼らへの深い敬意に基づいたコミュニケーションが、常に繰り広げられているのです。
第三幕:期待の暴走と「できた!」の小さな火種
木村部長の協力も得られ、プロジェクトは一気に加速しました。ChatGPTを使い、リアルな事例に基づいたQ&Aやロールプレイの台本が次々と生み出されていきます。その成果を目の当たりにした課長と佐藤さんは、興奮を隠せない様子でした。
しかし、ここで新たな問題が生まれます。「AI万能論」という、甘い罠です。
「ミズさん、すごいですね!これなら営業だけじゃなく、経理の問い合わせ対応も、総務の社内規程案内も、全部AIチャットボットに置き換えられますよ!全社展開しましょう!」
課長の期待は膨らむ一方。しかし、物造りの現場を知る人間なら分かります。試作品(プロトタイプ)が一つ上手くいったからといって、いきなり量産ラインをフル稼働させれば、必ずどこかで歪みが生じ、大規模なリコールに繋がる。
「課長、落ち着いてください。今、僕らが作っているのは、あくまで『営業部門の新製品研修』という、たった一つの部品です。この部品の品質を徹底的に高め、小さな成功を確実に掴むことが先決です。ここで焦って全社展開すれば、必ず失敗します」
私は、あの記事のステップ4で紹介したワークフローを、あえて彼ら自身の手で体験させることにしました。
「じゃあ、この前木村部長から聞いたクレーム対応の事例で、ロールプレイ台本を作ってみましょう。佐藤さん、どんなプロンプトをAIに入力しますか?」
「ええと、『クレーム対応のロールプレイ台本を作成してください』…でしょうか?」
佐藤さんが入力すると、AIはそれらしい、しかし当たり障りのない、どこかの教科書から引用したような台本を出力しました。
「うーん、悪くはないですが、木村部長のあの時の緊迫感や、お客様の微妙な感情の揺れが全く表現されていませんね。これでは若手は学べない。じゃあ、プロンプトに『お客様は非常に感情的になっているが、本質的には製品への期待値が高いという設定で』という一文を加えてみましょう」
修正したプロンプトで、AIの回答は劇的に変わりました。リアルな顧客のセリフ、それに対する効果的な切り返し。まさに「生きた教材」です。
「すごい…!指示の仕方一つで、こんなに変わるんですね!」
佐藤さんの目が輝きました。この「あっ、できた!」という小さな成功体験こそが、人を動かす最大のエネルギー源です。私たちは完璧なシステムを一度に作ろうとするのをやめ、「新製品の競合比較に関するQ&Aボット」という最小構成のパイロット版を、まずは営業部の新人5人だけで試すことにしました。
一週間後、その新人たちから「いつでも気軽に質問できて、先輩に聞くより気が楽です」「お客様への提案に自信が持てるようになりました」という声が上がってきました。そのフィードバックを印刷して課長と佐藤さんに渡した時の、彼らの嬉しそうな顔を私は忘れません。
この小さな火種が、やがて全社を巻き込む大きな炎へと燃え広がっていくのです。
終幕:フレームワークの裏側にある、変わらない真実
AIによる研修コンテンツの自動生成。聞こえは華やかですが、その裏側にあるのは、どこまでも地道で、人間臭いやり取りの積み重ねです。
- 目の前の担当者の「痛み」に耳を傾けること。
- ベテランのプライドと経験に、最大限の敬意を払うこと。
- 完璧な計画より、小さな「できた!」を積み重ねること。
あの実践ガイドは、確かにプロジェクトを成功に導くための羅針盤にはなるでしょう。しかし、その羅針盤を手に、荒波を乗り越え、未知の大陸にたどり着くためには、技術の知識以上に、人の心を動かすマネジメントとコミュニケーションが不可欠なのです。
AI導入は、結局のところ「人」と「組織」の変革そのものです。もしあなたが今、同じような課題に直面しているなら、最新のAIツールを調べる前に、一度、現場で一番困っている人の席へ足を運んでみてください。そして、こう尋ねるのです。
「今、何が一番つらいですか?」と。
きっと、そこからすべてが始まるはずです。