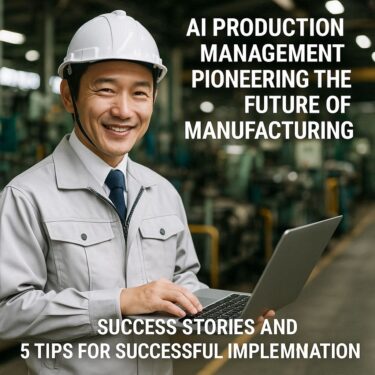AI生産管理導入の裏側:「なぁ、AIがうちの『神Excel』に勝てるのか?」
「AIで生産計画を最適化して、コストを3割削減したいんです!」
ある日、中小製造業の社長が目を輝かせながら、私にこう語りました。その手には、私が先日書いた「製造業の未来を拓くAI生産管理」の記事のプリントアウトが握られています。記事に書かれた成功事例や輝かしい未来像に、すっかり魅了されている様子でした。
もちろん、AIが製造業の未来を拓く力を持っていることは間違いありません。しかし、その輝かしい成果の裏には、データやシステムだけでは語れない、実に人間臭い、泥臭いドラマが必ず存在します。
今日は、AI導入プロジェクトの成功事例を語るだけでは見えてこない、その裏側で繰り広げられる経営者と現場の「心理戦」、そして、私がいつも心を砕いているマネージメントとコミュニケーションの、ちょっとした「裏話」を皆さんにお届けしたいと思います。
「鶴の一声」と「冷めた目」:AI導入、最初の壁
社長室での打ち合わせは、いつも熱気に満ちています。
「ミズさん、あの事例、すごいじゃないですか!計画立案が10分の1ですって。うちもすぐやりましょう!」
社長の熱意は本物です。人手不足、コスト高騰という目の前の課題を解決する「魔法の杖」として、AIに大きな期待を寄せているのがひしひしと伝わってきます。
しかし、一歩社長室を出て、生産管理を担当する事務の現場に足を運ぶと、その空気は一変します。
「…また、新しいシステムですか」
生産計画を長年一人で回してきた、ベテランの佐藤さん(仮名)は、私の顔を見るなり、そう言って静かにため息をつきました。彼女のデスクの上には、いくつものExcelファイルが開かれ、電話が鳴り、営業担当者がひっきりなしに駆け込んできます。
「社長、景気のいいこと言ってましたけど、私ら、そんなに暇じゃねぇんですよ。今のやり方で、なんとか回ってるんですから…」
これが、多くのAI導入プロジェクトが最初にぶつかる壁です。経営層の「トップダウンの熱意」と、現場の「ボトムアップの現実」との間にある、深くて冷たい溝。社長は「会社全体の未来」を見ていますが、佐藤さんは「今日の自分の仕事」と「明日の混乱」を見ています。どちらも間違ってはいません。だからこそ、この仕事は難しいのです。
「目的の明確化」の本当の難しさ:あなたの「困りごと」は何ですか?
AI導入を成功させる秘訣の第一歩は「目的の明確化」です。しかし、この「目的」が、それぞれの立場で全く違うから厄介なのです。
- 経営者: コスト削減、生産性向上、競合優位性
- IT部門: 最新技術の導入実績、システムの安定稼働
- 現場の担当者: 今の仕事を楽にしたい、残業を減らしたい、面倒な作業をなくしたい
ある部品メーカーでのこと。社長の目的は「AIによる生産計画の最適化で、在庫を20%削減すること」でした。私も当初はその線で話を進め、最新のAIツールをいくつか提案しました。しかし、事務担当の鈴木さん(仮名)の表情は、一向に晴れません。
何度か現場に通い、彼女の仕事ぶりを隣で見せてもらっているうちに、本当の問題が見えてきました。彼女が一番疲弊していたのは、生産計画を立てることそのものではなく、「営業からの急な仕様変更や納期変更の連絡に、都度、手作業で計画を修正し、関係各所に根回しすること」だったのです。
ある日の夕方、誰もいなくなった事務所で、鈴木さんがぽつりと呟きました。
「社長は在庫、在庫って言っけど、こっちは毎日、営業からの『ごめん、あれ、やっぱり変えて!』で振り回されて、昨日も夜10時までかかって計画やり直したんさ…」「ミズさん、AIがその電話、止めてくれるんですか?」
その言葉に、私はハッとしました。彼女が求めているのは、完璧な最適化計算をするAIではなく、この理不尽な「手戻り地獄」から解放してくれる存在だったのです。
そこで私は社長に提案しました。
「社長、在庫削減も大事だべ。でも、まずは鈴木さんの手戻り作業をゼロにすることを、このプロジェクトの最初の目的にしねぇか?彼女の残業がなくなって、定時で笑って帰れるようになったら、会社にとってそれ以上の財産はねぇと思うんさ」
プロジェクトの目的を「コスト削減」から「手戻り作業の撲滅と、鈴木さんの精神的負担の軽減」に切り替えた瞬間、彼女の目の色が変わりました。AIは、冷たい計算機から、自分を助けてくれる「相棒」へと変わったのです。
「現場との共創」という名の泥臭いコミュニケーション術
AI導入の秘訣に「現場との共創」とよく書かれていますが、それは決して綺麗な会議室で生まれるものではありません。本当の「共創」は、もっと泥臭い場所から始まります。
私が現場に入ってまずやることは、システムの話を一切しないことです。代わりに、現場の皆さんと一緒にコーヒーを飲み、お菓子を食べ、世間話をします。特に、事務の女性たちが集まる休憩時間は、宝の山です。
「ミズさん、これ見てくださいよ。うちの生産計画ファイル」
ある時、佐藤さんが見せてくれたのは、様々な色が複雑に塗り分けられ、謎の記号が飛び交う、まさに「神Excel」と呼ぶにふさわしい代物でした。
「これ、前の担当者から引き継いだもんだけど、もう何がなんだか…。でも、このピンク色が付いてるセルだけは、絶対に触っちゃダメっていうルールがあるんですよ。なんでかは、誰も知らねぇけど」
一見、非効率の塊に見えるこのExcel。しかし、私にとっては「宝の地図」です。この「誰も理由を知らない謎ルール」こそが、長年の経験の中で培われた、言葉にできないノウハウ、いわゆる「暗黙知」の塊なのです。
「ほぉ、これは面白いな。宝の地図みてぇだ。きっと、このピンクのセルには、過去に何か大きな失敗があったとか、特定の取引先との『暗黙の了解』が隠されているんだべ。この『謎』を解き明かすことこそが、AIに教えるべき一番大事なことかもしれねぇな」
私はITの専門家として、この「神Excel」を否定するのではなく、考古学者のように、そこに込められた歴史と意味を紐解いていくことから始めます。「なぜ、この作業が必要なんですか?」「この色分けには、どんな意味があるんですか?」と、一つひとつ丁寧に聞いていく。すると、最初は警戒していた佐藤さんも、次第に心を開き、「実は、このピンクのやつは、昔、〇〇社に納期遅れでめちゃくちゃ怒られた時の戒めで…」なんて、貴重な話を教えてくれるようになるのです。
AIシステムを設計する上で、この「ピンクのセルの物語」は、どんな最新のアルゴリズムよりも重要な情報になります。これこそが、現場に本当に寄り添ったシステムを作るための、唯一無二の設計図なのです。
「スモールスタート」の壁:社長の焦りを「最高の応援団」に変えるには
AI導入の鉄則は「スモールスタート」です。しかし、これがまた経営者を悩ませる。
「ミズさん、PoCだかなんだか知らねぇけど、そんなちまちまやってて、うちの会社、いつ変わるんか?ライバルはもっとすごいことやってるぞ!」
気持ちは痛いほどわかります。投資したからには、早く成果が見たい。その焦りをなだめ、説得するのも私の大事な仕事です。
そんな時、私はこう話します。
「社長、焦りは禁物だべ。大きな花火を一発打ち上げるのもいいけど、まずは、一番大変そうな現場で、小さな焚き火を一つ、灯してみませんか?」
そして、先ほどの鈴木さんのような、「一番困っている人」の、「一番面倒な作業」を一つだけ、AIで自動化するのです。例えば、彼女が毎週末、3時間かけて手作業で作成していた週報を、ボタン一つで出力できるようにする。
その結果、どうなるか。
鈴木さんは、金曜の午後に生まれた3時間で、溜まっていた他の仕事を片付け、定時で帰れるようになる。そして、会社の飲み会で、別の部署の同僚にこう話すのです。
「聞いてよ!うちの部署に入ったAI、すごくない?今まで週末潰してた週報、今じゃ5分で終わるんだよ!」
この「現場からの口コミ」こそが、どんな立派な導入事例よりも、社内にAI活用を広めるための最強のエンジンになります。鈴木さんは、もはやAI導入に懐疑的な担当者ではありません。プロジェクトの成功を誰よりも願う「最高の応援団」に変わっているのです。
社長には、その様子を報告します。
「社長、見てください。鈴木さん、最近楽しそうに仕事してるでしょう?彼女が灯した小さな火が、これから会社全体を温める大きな炎になるんさ。もう少しだけ、待ってやってくれませんか」
小さな成功体験は、人を動かします。そして、動いた人が、次の成功を生み出していく。このポジティブな連鎖を作ることこそが、スモールスタートの本当の目的なのです。
まとめ:AI導入は「人導入」。現場の物語にこそ、成功の鍵がある
AI生産管理の導入は、華やかな技術プロジェクトに見えるかもしれません。しかし、その本質は、どこまでも地味で、人間臭い「人導入」のプロセスです。
経営者の夢と、現場の現実。システム部門の理想と、製造部門の慣習。その間に立ち、それぞれの言葉を通訳し、時には緩衝材となり、同じ未来を見てもらうための橋渡しをすること。それが、私たちのような外部の人間に求められる、一番大切な役割なのかもしれません。
綺麗な成功事例の裏には、必ずと言っていいほど、佐藤さんの「神Excel」や、鈴木さんの「手戻り地獄」のような、現場の生々しい物語が隠されています。その物語に真摯に耳を傾け、一つひとつ丁寧に紐解いていくことなしに、本当に現場で使われるAIシステムを作ることはできません。
もし、あなたがこれからAI導入を推進する立場にあるのなら、ぜひ、最新の技術動向を追うのと同じくらい、あなたの会社の「現場の物語」に耳を澄ませてみてください。そこにこそ、プロジェクトを成功に導く、一番大切なヒントが隠されているはずですから。