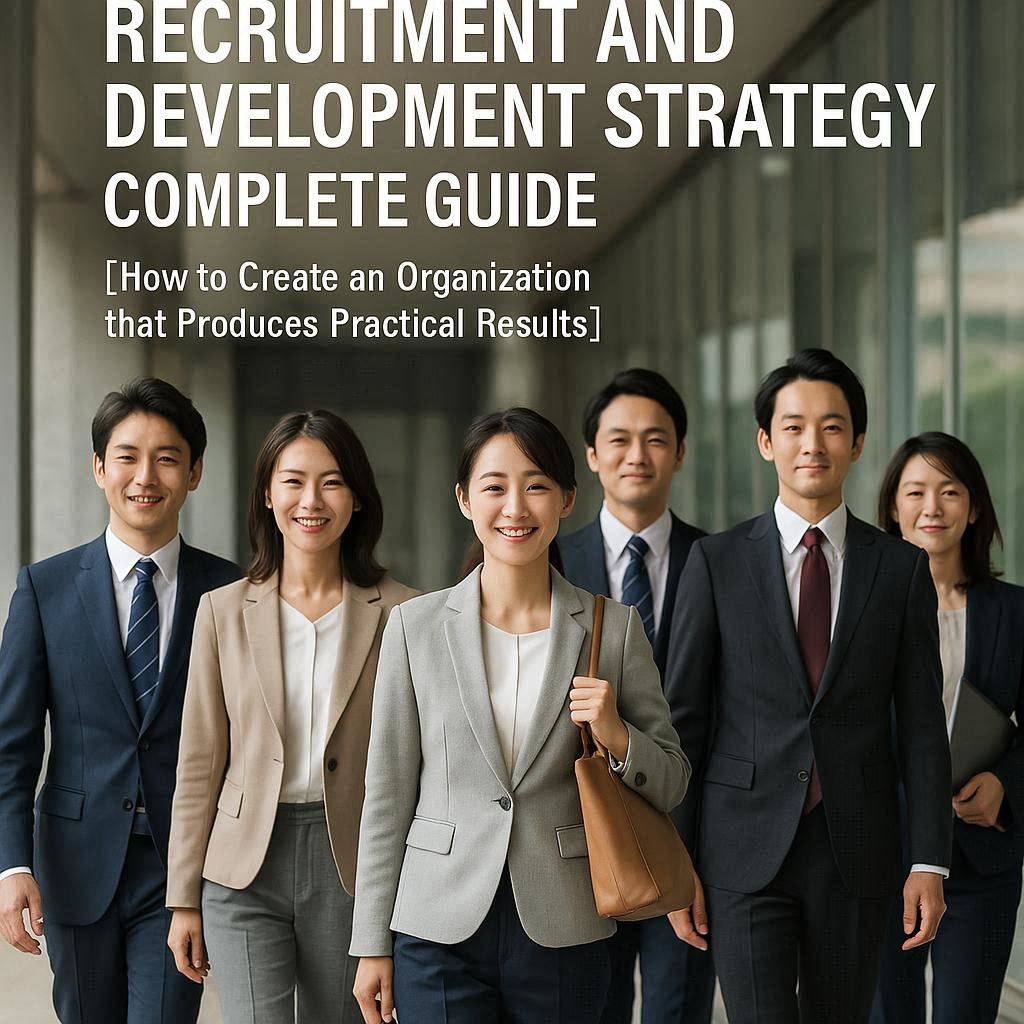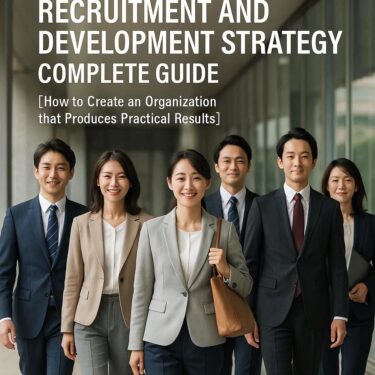AI人材育成の裏側で本当に起きていること【現場のリアル奮闘記】
どうも。企業の改革をお手伝いしている者です。物造りから物流、そして最近ではAI導入まで、色々な現場で経営者や社員の皆さんと汗を流してきました。
さて、先日「AI人材の採用・育成戦略」という、非常に理路整然とした記事を書きました。三層ポートフォリオ、KPI設定、ガバナンス…どれも正論ですし、目指すべき理想の姿であることは間違いありません。
しかし、です。
あのキラキラした戦略資料が会議室で承認された「後」に、現場で何が起きるのか。今日は、そんな教科書には載らない、泥臭くて人間臭い「裏話」を少しだけお話ししようと思います。AI導入のプロジェクトを成功させるヒントは、実はこういう生々しい現場の葛藤の中にこそ、隠されているんですよね。
「そんなスーパーマン、うちにはいません」― Bridge/Hub人材という理想と現実
あの記事で最も重要だと説かれているのが、ビジネスと技術の橋渡し役となる「Bridge/Hub層」の存在です。現場の課題を技術要件に「翻訳」し、プロジェクトを推進するキーパーソン。まさにその通り。この役割がなければ、どんなに高価なAIツールもただの箱になります。
ある製造業のクライアントでのこと。いつものように私が「このBridge/Hub層を、まずは各部門から一人ずつ立てましょう」と提案したところ、会議室がシン…と静まり返りました。その沈黙を破ったのは、企画部でエースと目されている30代のAさんでした。
「あの…おっしゃることは理解できます。でも、そんな『翻訳』ができるスーパーマンみたいな人、うちのどこにいるんでしょうか?業務も分かって、AIの技術も理解して、プロジェクトマネジメントもできるなんて…。私には、とても無理です」
彼女の声は、正直な不安と諦めが半分ずつ混じっているように聞こえました。周りのメンバーも、皆「そうそう、それが言いたかった」とでも言いたげに頷いています。
これが現実です。「理想の人材像」を提示された現場は、まず「うちにはいない」という壁にぶち当たります。そして、無理やり誰かが任命されれば、「なぜ私が…」というやらされ感とプレッシャーで潰れてしまう。
その時、Aさんの上司である佐藤部長(50代後半、現場一筋のベテラン)が、腕を組みながら重い口を開きました。
「んだのぉ…。いきなりホームラン打てるバッターなんて、どこにもいねぇでの。あんたが言う『翻訳』っちゅうのも、最初っから完璧な通訳になれって話ではねぇんだろ?」
佐藤部長は、私に鋭い視線を向けました。これは、私への「どうやって彼女たちを育てるつもりだ?」という問いかけです。
私は頷き、Aさんと皆にこう話しました。
「おっしゃる通りです。スーパーマンになれ、という話ではありません。『翻訳』という仕事を、もっと分解してみませんか?」
私はホワイトボードに書き出しました。
- まず「聞く」こと: 現場の人が「何に」「どれくらい」困っているか、ただひたすら聞く。技術のことは一切考えなくていい。「月初の請求書処理に3日もかかって残業になる」とか、そういう生の声を5つ集めるのが最初のミッション。
- 次に「伝える」こと: その声を、我々のような技術チームに「そのまま」伝える。「〇〇さんがこう困っているそうです」と。技術的な解決策はこちらで考えます。
- そして「持ち帰る」こと: 我々が提案した「こういうツールで、こう解決できるかもしれません」という話を、今度は現場に持ち帰って「こんな話があるんだけど、どう思う?」と意見を聞く。
「どうでしょう?これなら、できそうな気がしませんか?いきなり完璧な翻訳家になる必要はないんです。まずは『伝書鳩』から始めてみませんか、と。この『聞く・伝える・持ち帰る』を繰り返すうちに、だんだん言葉が分かってくる。それが、育成の第一歩です」
Aさんの顔から、少しだけ強張りが取れました。佐藤部長も「ほぉ、伝書鳩か。それならウチのAでもできっかもしんねな」と、冗談めかして笑いました。
ここでのポイントは、「役割」を「行動」にまで分解することです。 「Bridge/Hub」という抽象的な役割定義は、現場を萎縮させます。しかし、「まず5人の悩みを聞いてくる」という具体的な行動目標なら、誰でも一歩を踏み出せる。この小さな一歩を設計し、踏み出す勇気を持たせ、そしてその行動を「よくやった」と承認してあげること。改革のマネジメントとは、そういう地道な作業の繰り返しなのです。
「失敗したら評価が下がる」― KPIという”もろ刃の剣”との戦い
次にぶつかる壁が「育成と評価」の問題です。記事にもある通り、育成は「実務PoC × 数値KPI × ガバナンス」をセットで回すのが鉄則。これも大正解です。しかし、KPIの設定には細心の注意を払わないと、かえって組織の挑戦を妨げる”毒”になりかねません。
別のクライアントで、若手の育成のために「半年以内にAI活用PoCを1件成功させること」を人事評価のKPIに組み込んだことがありました。一見、合理的に見えますよね?ところが、数ヶ月経つと奇妙な現象が起きたのです。
技術部門の若手エンジニアたちが提案してくるPoCのテーマが、どれもこれも「絶対に失敗しない、手堅いもの」ばかりになったのです。例えば、すでに他社事例が豊富にあるような定型的なデータ分析や、既存業務のほんの少しの改善など。本来なら、もっと自社の競争力に繋がるような、挑戦的なテーマに取り組んでほしかったのですが…。
ある日、私が技術部門のフロアを歩いていると、一人の若手エンジニアが声を潜めて話しかけてきました。
「…実は、新しい画像認識の技術を使って、製品の微細な傷を検知するモデルを試してみたいんです。でも、成功確率が正直言って五分五分で…。もし失敗したら、今期の評価が…」
彼の言葉を聞いて、ハッとしました。良かれと思って設定した「成功させること」というKPIが、彼らから「挑戦する権利」を奪っていたのです。
この話を、彼の評価者であるベテランの管理職(これまた佐藤部長のような庄内弁のおっちゃんでした)にしたところ、彼は頭をガシガシ掻きながら言いました。
「んだのぉ…。そりゃそうだ。失敗したら評価下がるんだったら、誰だって安全な道ばり選ぶべ。わかっちゃいるけど、会社っちゅうのは『成果』で評価しねどなんねし…困ったもんだのぉ」
このジレンマをどう解消するか。私は経営層と人事部を巻き込んで、AI関連のPoCに対するKPIの考え方を根本から見直すことを提案しました。
変更後のKPI:
- 成功/失敗の二元論をやめる: PoCの評価は「成功したか」ではなく、「どれだけ価値ある『学び』を得られたか」を基準にする。
- 「挑戦数」を評価する: 半期で取り組んだPoCのテーマ数を評価項目に入れる。
- 「失敗報告会」を義務化し、賞賛する: PoCがうまくいかなかった場合、なぜ失敗したのか、そこから何が分かったのかを分析し、全社で共有する「ナレッジ共有会」を実施する。そして、その報告の質が高かったチームを表彰する制度を作ったのです。
この改革には時間がかかりましたが、徐々に組織の空気が変わっていきました。「失敗してもいいんだ」「むしろ、価値ある失敗は歓迎されるんだ」という雰囲気が醸成され、先ほどの若手エンジニアも、堂々と製品の傷検知モデルの開発に着手し、最終的には素晴らしい成果を上げてくれました。
KPIは、組織を動かす強力なエンジンです。しかし、アクセルとブレーキを間違えると、と思わぬ方向に暴走したり、エンストしたりする。特にAIのような未知の領域では、「成果KPI」と同時に「行動KPI」や「学習KPI」をバランス良く設計し、「心理的安全性」を担保することが不可欠なのです。
「それは規定で許可できません」― ガバナンスという名の”不落の城壁”
そして、最後にして最大の難関が「ガバナンス」です。記事では「安全な挑戦を支えるガバナンス」と美しく表現されていますが、現場での最初の姿は「新しいことを阻む鉄壁のルール」として現れることがほとんどです。
あるプロジェクトで、現場のデータを分析するために、最新のクラウドサービスを利用しようとした時のことです。事業部門の佐藤部長は「おぉ、そんげな便利なもんどごあるんだが!はよしぇ!」(おぉ、そんな便利なものがあるのか!早くやろう!)と乗り気でした。
しかし、その計画は情報システム部門の鈴木課長(40代、ルール遵守が信条)の一言で凍りつきます。
「佐藤部長、そのクラウドサービスは、当社のセキュリティ規定で許可されていない外部サービスです。機密情報である生産データを外部に出すなど、絶対に認められません」
案の定、です。佐藤部長は顔を真っ赤にして反論します。
「まだ使ってもいねぇうちから、なんでもダメダメって言うだけだが!ほだなごどで、どやって競争に勝てって言うんだ!」(まだ使ってもいないうちから、何でもダメダメと言うだけじゃないか!そんなことで、どうやって競争に勝てって言うんだ!)
「ですが、規定は規定です。万が一、情報漏洩でも起きたら誰が責任を取るんですか?」
会議室は一気に険悪なムードに。これが、多くの企業で繰り返される「アクセル部門 vs ブレーキ部門」の不毛な対立です。
ここで私の出番です。私は両者の間に立ち、まず鈴木課長に尋ねました。
「鈴木課長、ありがとうございます。リスクを指摘していただくことは非常に重要です。具体的にお伺いしたいのですが、『セキュリティ規定』で懸念されているのは、具体的にどのようなリスクでしょうか?例えば、通信経路の暗号化ですか?データの保管場所ですか?それともアクセス権限の管理ですか?」
私の質問の意図は、「ダメだ」という抽象的な言葉を、「〇〇というリスクがある」という具体的な課題に分解することです。
鈴木課長は少し戸惑いながらも、専門家として具体的に答えてくれました。「はい、主に3点あります。第一に…」
彼がリスクを全て挙げ終えた後、私は佐藤部長に向き直り、そして再び鈴木課長に視線を戻して言いました。
「なるほど、よく分かりました。つまり、鈴木課長が挙げてくださったこの3つのリスクを技術的にクリアできれば、このサービスを利用する道も開ける、と考えてよろしいでしょうか?」
鈴木課長は「…まぁ、理屈の上ではそうなりますが」と答えます。
空気が変わりました。先ほどまでの感情的な対立が、「じゃあ、この3つの課題をどうやって解決しようか?」という、前向きな議論に変わった瞬間です。
私たちはその場で、3つのリスクに対する対策案を技術チームと一緒に検討し、「この設定にすれば通信は暗号化できる」「データは国内のサーバーに限定できる」「アクセスログは全て監視できる」といった具体的な解決策を提示しました。
最終的に、情報システム部門の協力も得て、安全性を担保した形で新しいツールを導入することができたのです。
ガバナンス部門は、決して改革の敵ではありません。 彼らは彼らの職責として、会社をリスクから守ろうとしているだけです。彼らを「抵抗勢力」と見るのではなく、「一緒にリスクを乗り越えるパートナー」として巻き込むこと。そのためには、感情論ではなく、具体的な課題レベルで対話し、解決策を共に探すというコミュニケーションが不可欠なのです。
結論:戦略を血肉に変えるのは、いつだって現場の人間だ
AI人材戦略のフレームワークは、確かに強力な羅針盤です。しかし、その羅針盤が指し示す目的地まで船を動かすのは、エンジンや帆だけではありません。
不安に思いながらも「伝書鳩」から始めてみようと一歩を踏み出すAさんのような担当者。
部下の挑戦を信じ、古い慣習に疑問を投げかける佐藤部長のような管理者。
そして、杓子定規に見えても、会社の未来を真剣に考えてリスクと向き合う鈴木課長のような専門家。
こうした現場の一人ひとりの小さな「行動変容」の積み重ねこそが、立派な戦略を、本当に生きた組織の力へと変えていくのです。
私たちの仕事は、きれいな戦略資料を作ることではありません。現場の葛藤に寄り添い、彼らが抱える「できない理由」を一つひとつ、一緒に取り除いていくこと。対立を対話に変え、不安を自信に変えるための、ちょっとした「きっかけ」を作ること。
もしあなたが今、AI導入の壁にぶつかっているなら、ぜひ一度、戦略資料から顔を上げて、現場で奮闘している人たちの「生の声」に耳を傾けてみてください。答えはきっと、そこにあります。