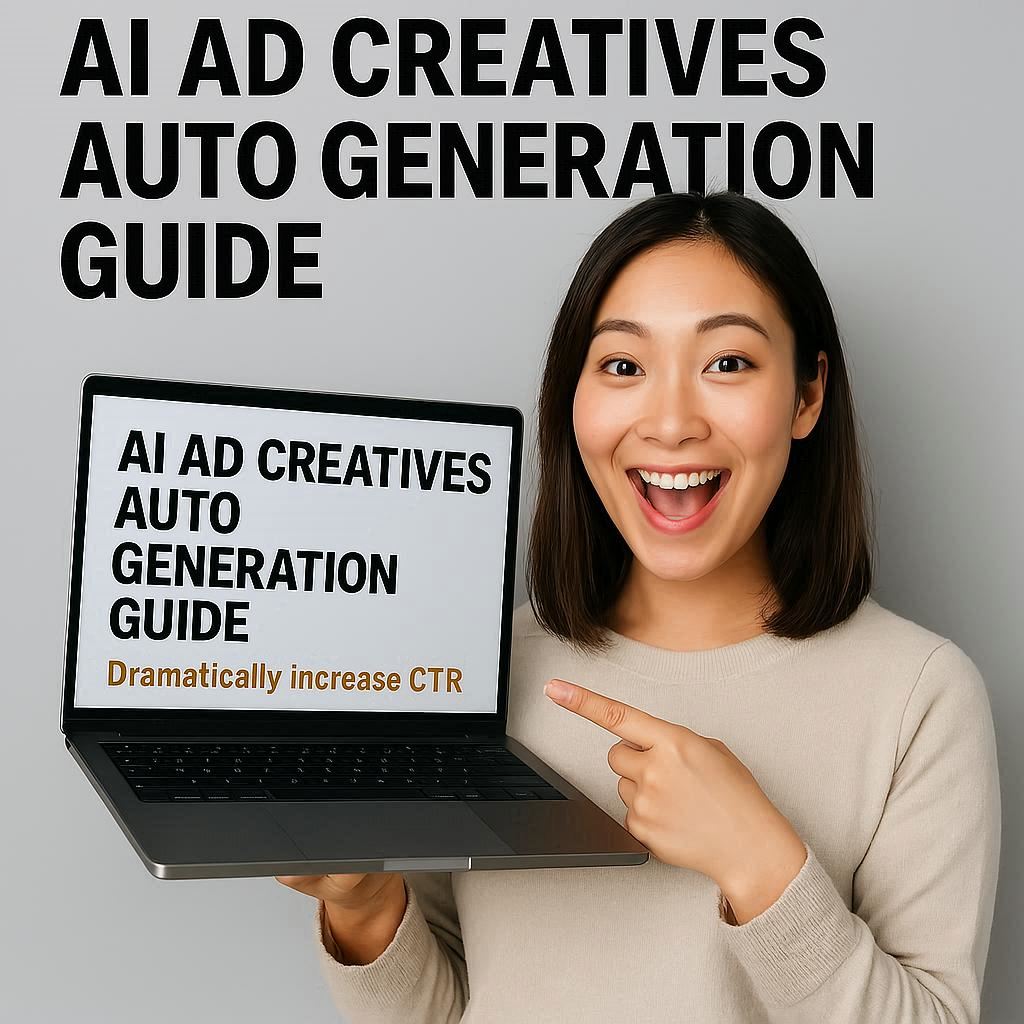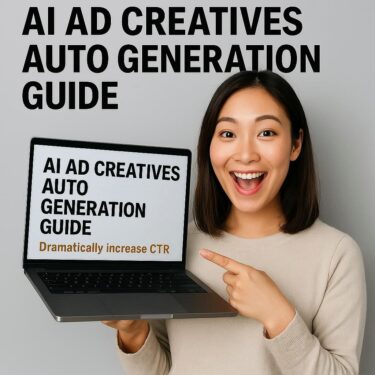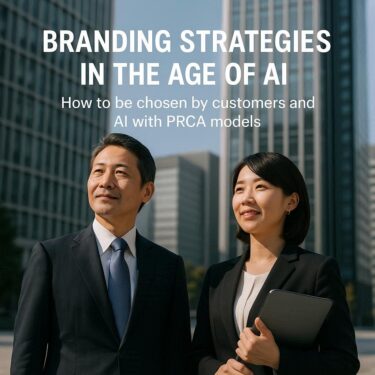AI広告クリエイティブのプロンプトに込める、「人と組織」の現実
先日、「AI広告クリエイティブ自動生成ガイド」という記事を寄稿しました。CTRを上げるための具体的なプロンプトや、AIと人間の協業ワークフローについて、これでもかというくらい体系的にまとめたものです。我ながら、かなり実践的な「教科書」が書けたと自負しています。
AI広告クリエイティブ自動生成ガイド|CTRを上げる実践プロンプトとワークフロー はじめに:Cookieレス時代、成果は「クリエイティブ」で決まる サードパーティCookieの段階的な廃止が進む今、これまでのような精緻[…]
しかし、今日はその教科書の「行間」に隠された、もっと人間臭くて、泥臭い話をしようと思います。
机上の空論や綺麗な成功事例だけでは、現場は1ミリも動きません。AI導入のプロジェクトは、最新技術の話をしているように見えて、その本質はいつだって「人と組織の変革」の話です。そこには必ず、感情のぶつかり合いがあり、立場の違いからくるすれ違いがあり、そして、それを乗り越えようとする人々の小さな奮闘があります。
これから語るのは、ある地方の中堅食品メーカーで、私が実際に体験した物語です。教科書に書かれた「制約付き発散」や「A/Bテストの高速化」といった美しい言葉の裏側で、一体何が起きていたのか。そのリアルな舞台裏を、少しだけ覗いてみてほしいと思います。
第一幕:AIは「魔法の杖」か、それとも「黒船」か
プロジェクトの始まりは、期待と警戒が入り混じった奇妙な空気感で始まりました。推進役は、マーケティング部の佐藤さん。30代半ばの、非常に勉強熱心で意欲的な女性担当者です。彼女の瞳は「これでウチも変われる!」という希望で輝いていました。
一方、その向かいに腕を組んで座っているのが、マーケティング部長の鈴木さん。勤続35年のベテランで、この会社の生き字引のような存在です。彼は、私の顔と佐藤さんの顔を交互に見ながら、重々しく口を開きました。
「先生よぉ、AIだかなんだか知らねぇけども、本当にそんなもんで、ウチの商品の良さがお客様に伝わるもんだべか? ワシらはな、この漬物一つ売るのに、何十年も汗水たらしてきたんだ。機械にポチッとな、で出てきた言葉で、人の心が動くとは思えねぇな」
これぞ、多くの現場で最初にぶつかる壁です。「AIへの不信感」。長年の経験と勘で培ってきた職人芸への自負が強いほど、この壁は高く、厚くなります。
対する佐藤さんは、前のめり気味に反論します。
「部長、違うんです! AIは魔法の杖じゃないですけど、私たちのアイデアを何百倍にも広げてくれる最高のパートナーになるはずなんです! 今まで1週間かかってたバナー案作成が、1日で100パターンも出せるんですよ!」
これもまた、よくある光景です。「AIへの過剰な期待」。まるでAIが全ての課題を解決してくれる銀の弾丸であるかのような、少し現実離れした理想像です。
不信感と過剰な期待。この両極端な感情が渦巻く中で、私が最初にやったことは、AIの「格下げ」でした。
「鈴木部長、佐藤さん、少しだけよろしいですか。今日から我々のチームに加わるAI君は、魔法使いでもなければ、部長の仕事を奪う黒船でもありません。彼は、『指示されたことは超高速でこなすけど、指示がないと何もできない、ちょっと気の利かない新入社員』だと思ってください。彼の能力を最大限に引き出すも殺すも、ここにいる我々、特に彼の先輩となる皆さん次第なんです」
この一言で、場の空気が少しだけ和らいだのを覚えています。敵でも救世主でもない。「手のかかる新人」。この絶妙なポジショニングが、現場の心理的ハードルを下げ、AIを「自分たちが育て、使いこなす対象」として認識させるための、重要な第一歩になるのです。
第二幕:「ウチのトンマナ」という名の魔物を言語化せよ
教科書にはこう書きました。「ステップ1:目的と制約を言語化する」。たった一行ですが、ここがプロジェクト全体の成否を分ける、最も険しい山だと言っても過言ではありません。
AIに広告クリエイティブを作らせるためには、「ブランドのトーン&マナー(トンマナ)」や「禁止表現」といった「制約」を明確に言語化して伝える必要があります。私は早速、チームメンバーに問いかけました。
「皆さんが考える、この会社の広告における『トンマナ』とは、具体的にどんな言葉で表現できますか?」
会議室は、水を打ったように静まり返りました。
沈黙を破ったのは、佐藤さんでした。
「えっと…温かみがあって、誠実で、少しだけ高級感がある…みたいな感じでしょうか…」
非常に曖昧です。これではAIは動けません。「温かみとは何か?」「誠実とは具体的にどういうことか?」を定義しなければなりません。私がさらに深掘りしようとすると、鈴木部長が助け舟(のつもり)を出します。
「先生、そんなもんは感覚だ! 言葉で説明できるような安っぽいものじゃねぇんだよ。長年やってれば、自然と身につくもんだ」
出ました。「感覚」「暗黙知」という名の魔物です。これが組織に蔓延している限り、AIの活用はおろか、業務の標準化すらままなりません。
ここで無理に言葉を引き出そうとしても、反発を招くだけです。私が取り出したのは、過去3年分の広告クリエイティブ(バナー広告)を印刷した大量の紙でした。それらを「すごく成果が良かったもの(勝ちパターン)」と「全然ダメだったもの(負けパターン)」に分けて、会議室の壁一面に貼り出しました。
「皆さん、これからワークショップを始めます。勝ちパターンを見て『なぜこれが良かったのか』、負けパターンを見て『なぜこれがダメだったのか』、その理由を思いつくだけ付箋に書き出して、この壁に貼っていってください。正解・不正解はありません。感じたままを書いてください」
最初は戸惑っていたメンバーも、一人、また一人とペンを走らせ始めました。
「こっちは、おばあちゃんの笑顔が優しい」
「こっちは文字が多すぎて読む気がしない」
「『期間限定』って言葉に弱いのかも」
「このキャッチコピーは、なんか上から目線で嫌だ」
30分後、壁は色とりどりの付箋で埋め尽くされました。それを私と佐藤さんでグルーピングしていくと、驚くべきことが見えてきました。
- 勝ちパターンに共通する言葉: 「笑顔」「手作り感」「安心」「家族」「旬の素材」「シズル感」
- 負けパターンに共通する言葉: 「専門用語」「機能説明」「情報過多」「安売り感」「カタカナ語」
鈴木部長が「感覚だ」と言っていたものの正体が、具体的なキーワード群として可視化された瞬間でした。
「鈴木部長、もしかして部長が仰っていた『感覚』というのは、この『家族の笑顔』や『手作り感』といった、お客様に『安心』を感じてもらうための表現のことではないでしょうか?」
鈴木部長は、腕を組んだまま壁の付箋をじっと見つめ、小さく「…んだな」と呟きました。
これが、AIに与える「制約」の原型です。教科書に書かれた綺麗な戦略ブリーフは、こうした泥臭いプロセスを経て、現場の「暗黙知」を「形式知」へと変換する作業の末に、ようやく生まれてくるのです。
第三幕:プロンプトは翻訳です。通訳なき部署間の断絶
ワークショップで言語化された「制約」を元に、いよいよプロンプトを設計していくフェーズに入ります。教科書には、コピペで使える立派なプロンプトのテンプレートをいくつも掲載しました。しかし、あのテンプレートが完成するまでには、もう一つの大きな壁がありました。それは「部署間の言語の壁」です。
ある日、新商品の「長期熟成・無添加味噌」の広告コピーをAIに作らせるため、マーケティング部の佐藤さんと、開発部の高橋さん(40代・技術一筋)を交えて打ち合わせをしていた時のことです。
佐藤さん:「このお味噌のベネフィットは、何と言っても『いつものお味噌汁が、まるで料亭の味になる』ことだと思うんです。忙しいお母さんが、手軽に家族を笑顔にできる。その点を訴求したいんです」
素晴らしい顧客視点です。しかし、高橋さんは少し不満げな顔で口を挟みます。
高橋さん:「いや、佐藤さん。この商品の本質はそこじゃない。国産大豆と天然塩だけを使い、杉樽で三年熟成させることで生まれる、豊富なアミノ酸と酵母菌の働きなんだ。アミノ酸含有量は従来品の1.5倍。この技術的な優位性を伝えないと」
佐藤さん:「高橋さん、お客様はアミノ酸の量なんて気にしません! 大事なのは、それを食べた結果、どんな良いことがあるか、なんです!」
高橋さん:「結果も大事だが、その結果を生み出す根拠、つまりファクトがなければ信頼されないだろう!」
議論は完全に平行線です。マーケティング部が話す「顧客言語(ベネフィット)」と、開発部が話す「技術言語(スペック)」。両者は同じ製品について話しているはずなのに、言葉が全く通じません。この状態では、AIに与える情報がチグハグになり、質の高いアウトプットは望めません。
ここで私の役割は「通訳者」になることでした。
「お二人とも、ありがとうございます。視点が違うだけで、どちらもこの商品の魅力を伝えたいという想いは同じですね。少し整理させてください」
私はホワイトボードに書き出しました。
「高橋さんの仰る『アミノ酸含有量1.5倍』というのは、技術言語ですね。これを顧客言語に翻訳すると、佐藤さんの仰る『いつものお味噌汁が料亭の味になる』ということ。つまり、『なぜ料亭の味になるの?』という問いへの答えが、『アミノ酸が1.5倍も豊富だからですよ』となる。この繋がりをAIに教えてあげればいいんです」
そして、私はプロンプトの一節をその場で書いて見せました。
これを見た二人は、ハッとした顔でお互いを見合わせました。自分たちの言葉が、一つの指示として繋がった瞬間でした。
優れたプロンプトとは、単にAIへの命令文ではありません。それは、組織内に散らばった異なる言語、異なる視点を繋ぎ合わせ、一つのゴールに向かわせるための「翻訳文」であり「共通言語」なのです。
第四幕:「勝ち」に酔いしれ、「なぜ」を忘れる人々
AIの導入から1ヶ月。佐藤さんたちのチームは、教科書通り「制約付き発散」のサイクルを回し、驚くべきスピードで広告クリエイティブを量産し始めていました。そして、ついにA/Bテストで目覚ましい成果が出ました。
「やりました! 先週リリースしたC案のバナー、CTRが従来の1.8倍です! 過去最高記録を更新しました!」
オフィスは歓声に包まれました。鈴木部長も「おお、たいしたもんだな! AIもやればできるんでねぇか!」と上機嫌です。プロジェクトは順風満帆に見えました。
しかし、私はこの「成功」にこそ、最大の落とし穴が潜んでいることを知っていました。
「素晴らしいですね、佐藤さん。ところで、なぜC案は勝ったんでしょうか? 逆に、同時にテストしたD案は、なぜ負けたんでしょう?」
私の問いに、佐藤さんはきょとんとした顔で答えました。
「え? なぜ、ですか…? うーん、デザインが良かったから…でしょうか?」
これです。多くのチームが「勝った(負けた)」という事実だけで満足してしまい、その「理由」を深く考察しません。これでは、せっかくの学びが次に繋がりません。成功体験が、単発の花火で終わってしまいます。
教科書に書いた「勝因・敗因の言語化」。これを実行させるのが、また一苦労なのです。
私は、再びメンバーを集めました。
「C案が勝ったのは事実です。では、その成功を『再現』するためには、勝因を言語化する必要があります。皆さんで『なぜ勝ち分析』をしましょう」
ホワイトボードに、勝ったC案と負けたD案を並べて表示します。
C案: 「いつもの食卓に、料亭のため息。」(背景は湯気の立つお味噌汁のアップ)
D案: 「アミノ酸1.5倍!杉樽三年熟成の味。」(背景はお味噌のパッケージ写真)
「さあ、この二つの違いは何でしょう? なぜお客様はC案を選んだのでしょう?」
最初は「なんとなくC案の方が美味しそう」といった感想レベルだった議論が、私の問いかけによって、徐々に深まっていきます。
「C案は『ため息』っていう言葉がいい。美味しさが伝わる」
「D案は、売り手の言いたいことって感じがする」
「写真も、C案は『食べるシーン』が想像できるけど、D案はただの『モノ』だ」
議論の末、チームは一つの結論にたどり着きました。
「我々の商品の広告で勝つパターンは、『スペック』ではなく『食卓の風景(コト)』を語り、お客様に『自分の生活が少し豊かになる未来』を想像させることだ」
この言語化された「勝ちパターン」こそが、チームにとっての本当の財産です。これを次回のプロンプトの制約条件に加えることで、AIが生み出すクリエイティブの平均点は、さらに向上していきます。単利ではなく、「複利」でチームは成長していくのです。
成功に浮かれるメンバーを少しだけ引き締め、結果の裏側にある「なぜ」を考えさせる。これもまた、教科書には書ききれなかった、現場における重要な役割の一つなのです。
終わりに:本当の変革は、人の心から始まります
AI広告クリエイティブの記事は、ツールや手法について語っています。しかし、その根底にあるのは、いつだって「人」と「組織」の物語です。
AIという「新人」をどう受け入れるか。
感覚という「魔物」をいかにして言葉に落とし込むか。
バラバラな部署の「言語」をどうやって繋ぎ合わせるか。
成功という「麻薬」に溺れず、学び続ける仕組みをどう作るか。
これらの課題は、どれも一筋縄ではいきません。しかし、一つ一つの壁を、チームで対話し、知恵を絞り、乗り越えていくプロセスそのものが、企業を変革する原動力になります。
AIは、その変革を加速させるための、強力な触媒にすぎません。本当の変革は、AIの導入をきっかけに、自分たちの仕事のやり方や、コミュニケーションのあり方を見つめ直し始めた、佐藤さんや鈴木部長のような人々の心の中から始まるのです。
もしあなたが今、AI導入の現場で孤軍奮闘しているのなら、思い出してほしいと思います。あなたのその苦労は、単なるツール導入の苦労ではありません。会社の未来を創るための、尊い「生みの苦しみ」なのだということを。