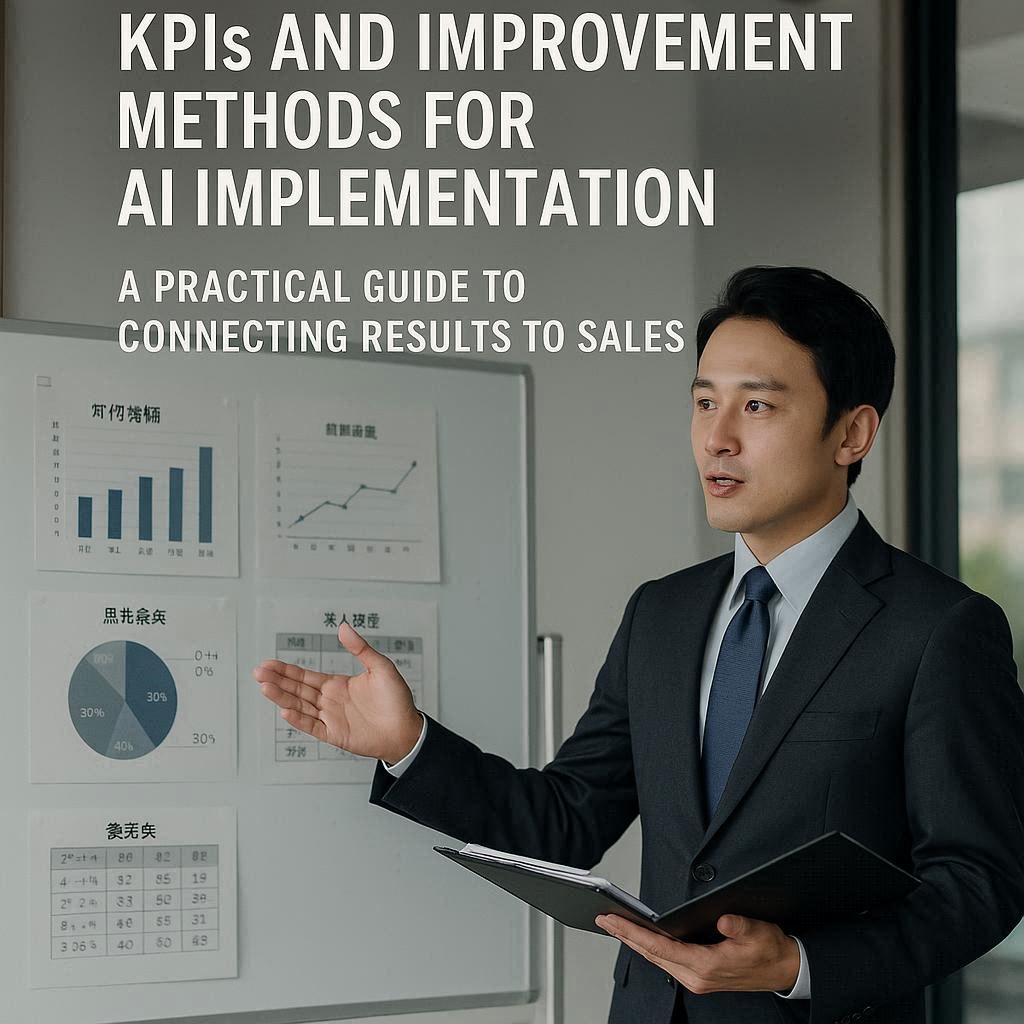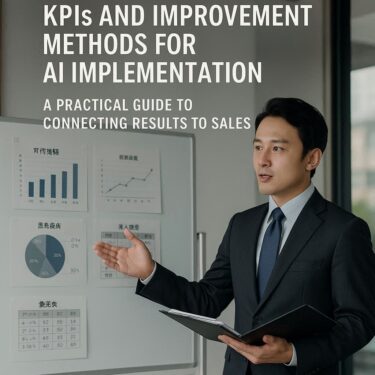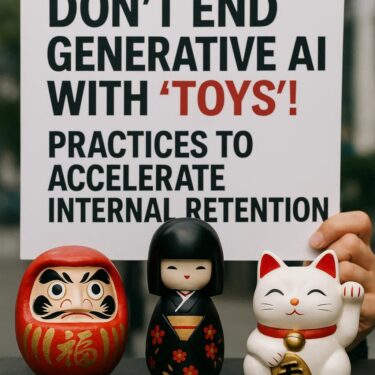AI導入の効果測定、「ほら見ろ、使えねぇじゃねぇか」と。裏側で起きていた泥臭い格闘の記録
先日公開した『AI導入の効果測定KPIと改善手法』という記事、ありがたいことに多くの方にお読みいただいているようです。KPIツリーを描き、PDCAを回し、削減した時間を再配分する…まさに王道であり、正解です。
しかし、今日はその裏側で、いつも本当に起きている「もう一つの物語」についてお話しさせてください。
あの綺麗なフレームワークやテンプレートは、いわば完成した料理のレシピです。ですが、実際のキッチンは、泥だらけの野菜、言うことを聞かない火加減、そして「そもそも、なんでこんな面倒な料理作らなきゃいけないの?」という料理人のボヤきで溢れかえっている。
この記事は、そんな現場のリアルな葛藤と、それを乗り越えるための泥臭いコミュニケーションの記録です。教科書通りの正論だけでは、決して人は動きません。AI導入の現場で本当に必要なのは、人の心を動かす「もう一歩先」の技術なのです。
第一の壁:「なぜ測るんですか?」ベースライン測定への静かなる抵抗
元記事にはこう書きました。「導入前の『ベースライン』を必ず採取する」。正論中の正論です。比較対象がなければ、効果など測れるはずもありませんからね。
ある中堅メーカーさんでのプロジェクト。AI導入の担当者に任命されたのは、入社8年目の真面目な佐藤さん(30代女性)でした。私は彼女とプロジェクトの第一歩として、この「ベースライン測定」をお願いしました。
「はい、分かりました。対象業務は営業事務のレポート作成ですね。今の作業時間を2週間、記録していきましょう」
そう言ってはくれたものの、1週間経ってもデータは全く上がってこない。どうしたのかと声をかけると、彼女は困り果てた顔でこう言いました。
「すみません…。皆さんに『今の作業時間を記録してください』ってお願いしたんですけど、『ただでさえ忙しいのに、なんでそんな手間をかけなきゃいけないんですか』って…。『AIで楽になるんですよね?だったら、なんとなく速くなったって分かればいいじゃないですか』って言われてしまって…」
これが現場の本音です。彼らにとって、日々の業務をこなすことが最優先。新しい取り組みは、たとえ将来のためであっても、今の自分たちの仕事を増やす「敵」に見えてしまう。
私は佐藤さんと、彼女の上司である鈴木課長(40代男性)を交えて、もう一度話をしました。鈴木課長も板挟みで疲れた顔をしています。
私:「鈴木課長、現場の皆さんの気持ちはよく分かります。これは決して、皆さんの仕事ぶりを監視したり、誰が遅いかを評価したりするためのものじゃないんです」
鈴木課長:「ええ、それは分かっているつもりなんですが…。どうも『犯人探し』をされているような、そんな空気になってしまっていて」
私:「では、伝え方を変えましょう。これは『健康診断』なんです。今の自分たちの体の状態(業務の現状)をちゃんと知らないと、どんな薬(AI)が効くのか、そもそも薬が必要なのかも分からない。そして、薬を飲んだ後、本当に健康になったのか(効果が出たのか)を知るためにも、最初の診断結果(ベースライン)が絶対に必要なんです。これは、皆さんの頑張りを『なんとなく』で終わらせず、『これだけ会社に貢献しました!』と胸を張って言うための『証拠集め』なんですよ、と」
さらに、私は具体的なアクションとして、測定のハードルを極限まで下げました。
「ストップウォッチでカチカチ測る必要はありません。作業を始める時にチームのチャットに『〇〇レポート作成開始』、終わったら『完了』と投稿するだけにしましょう。タイムスタンプが勝手に記録になりますから。これなら、1日数秒の手間ですよね?」
この「比喩による目的の翻訳」と「徹底的な負担の軽減」によって、現場の空気は少しずつ変わりました。佐藤さんが「健康診断なんですよ!証拠集めなんです!」と明るく言い続けたことも大きかった。
2週間後、無事にデータは集まりました。それは単なる数字の羅列ではありません。プロジェクトの第一歩を踏み出すために、現場の小さな「行動変容」を勝ち取った、最初の勝利の記録だったのです。
第二の壁:「ほら見ろ、使えねぇじゃねぇか」不都合な真実“最終調整工数”との向き合い方
次に立ちはだかったのが、元記事でも特に重要視したKPI、「最終調整工数」です。AIの生成物を人間が手直しする時間。これを測ることは、AI活用の成熟度を知る上で欠かせません。
このメーカーの工場にも、AIで日報のたたき台を作る仕組みを導入しようとしていました。しかし、そこにはこの道40年の斎藤工場長(60代男性)という大きな存在がいました。彼は、まさに職人の勘と経験で現場を仕切ってきた人物です。
AIが出力した日報のドラフトを彼に見せると、厳しい顔で一言。
斎藤工場長:「なんだこりゃ。現場の言葉で書がさんねば、意味ねぇべした。こんな出来の悪いもん、おらが直すだけで半日かかるぞ。時間の無駄だ」
(なんだこれは。現場の言葉で書かれていないと、意味がないだろう。こんな出来の悪いもの、私が直すだけで半日もかかるぞ。時間の無駄だ)
若手の技術者は反論します。「いや工場長、AIはまだ学習中なので…。でも、たたき台があるだけでも効率的じゃないですか!」
まさに、新旧の価値観のぶつかり合いです。担当者の佐藤さんは、斎聞工場長からの突き上げにすっかり疲弊していました。「AIは完璧じゃないって言ってるのに…粗探しばかりされても…」と。
この時、私が取ったアプローチは「敵対から協調へ」の転換です。私は斎藤工場長と二人で話す時間をもらいました。
私:「工場長、おっしゃる通りです。今のAIは、まだ新人の作業員と同じ。工場長の足元にも及びません」
斎藤工場長:「んだろ。こんなもんに頼ってたら、腕がなまるだけだ」
(そうだろう。こんなものに頼っていたら、腕がなまるだけだ)
私:「そこで、お願いがあるんです。この使えない新人に、工場長が先生になって、仕事を教えてやってもらえませんか?」
斎藤工場長:「はぁ?AIに教えるって、どういうごどだ?」
(はぁ?AIに教えるって、どういうことだ?)
私:「工場長が『ここはこう直すんだ』と手直しした内容、そのものが最高の教科書になるんです。例えば、『この表現は現場では使わない、こっちの言葉にしろ』とか、『この数字だけじゃなく、こっちのデータも入れろ』とか。その『手直しの記録』をデータとしてAIにフィードバックすると、AIはどんどん賢くなって、工場長の右腕に近づいていくんです。この『最終調整工数』という時間は、無駄な時間ではなく、AIを育てるための『教育時間』なんです」
私は、ただ「最終調整工数を記録しろ」と言うのではなく、その記録用紙に「なぜそう直したのか(理由)」というメモ欄を追加することを提案しました。
斎藤工場長の目が、少し変わりました。自分がただの批評家ではなく、「AIの教育係」という重要な役割を与えられたと感じた瞬間でした。
斎藤工場長:「…んだば、仕方ねぇな。おらが、いっちょ前に育てでみっか」
(…それなら、仕方ないな。俺が、一人前に育ててみるか)
そこから、彼は誰よりも熱心にAIの出力結果を赤ペンで修正し、びっしりと理由を書き込んでくれるようになりました。そのフィードバックを元に、我々はAIへの指示(プロンプト)を改善していく。まさに、人間とAIが協働するPDCAサイクルが回り始めたのです。
「最終調整工数」は、単なる測定指標ではありません。ベテランの暗黙知を形式知に変え、組織の資産に変えるための、極めて強力なコミュニケーションツールなのです。
第三の壁:「で、結局どうすんの?」削減時間の再配分という最大の迷宮
さて、いよいよ最大の難関です。元記事の核心でもある、「削減した時間を、売上に直結する高付加価値業務に再配分する」というテーマ。これが、言葉で言うほど簡単な話ではありません。
先の営業事務のレポート作成業務は、AI導入によって月間でチーム全体で40時間の工数削減に成功しました。素晴らしい成果です。しかし、2ヶ月経っても、売上という最終成果には何の変化も見られませんでした。
営業部長の高橋さん(50代男性)は、 predictably、渋い顔です。
高橋部長:「時間でぎだっつってもよ、それがすぐに売上になんかなんねべした。結局、空いた時間で他の雑用やったり、ちょっとだらだらしたりして終わるのが関の山だべ」
(時間ができたと言っても、それがすぐに売上になんかならないだろう。結局、空いた時間で他の雑用をやったり、少しだらだらしたりして終わるのが関の山だよ)
彼の言うことは、ある意味で真実です。心理学で言うところの「パーキンソンの法則(仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する)」が働いてしまう。担当者の佐藤さんも、「生まれた時間で高付加価値なことをやれ、と言われても、具体的に何をすればいいのか、皆ピンと来ていないみたいで…」と頭を抱えていました。
トップダウンで「空いた時間で新規顧客に電話しろ!」と命令するのは簡単です。しかし、それではやらされ仕事になり、長続きしない。
そこで私は、アプローチを180度変えました。営業チーム全員を集めて、小さなワークショップを開いたのです。
私:「皆さん、AIのおかげで、月に40時間、つまり一人あたり1日15分くらいの時間が生まれました。そこで、質問です。もし、魔法がかかって、皆さんの残業が一切なくなり、毎日定時で帰れるようになったとします。その上で、さらに『15分の自由な時間』が毎日手に入るとしたら、『本当はやりたかったけど、今まで時間がなくて出来ていなかったこと』って、何がありますか?」
最初は誰もが黙っていました。しかし、一人の若手が「…ずっと後回しにしてた、納品済みのお客様へのフォロー電話、ですかね」と呟くと、堰を切ったように意見が出始めました。
「競合の新製品の情報を、ちゃんと読み込む時間が欲しかった」
「普段あまり話さない設計部門と、次の製品について雑談する時間が欲しい」
「失注したお客様に、なぜダメだったのか、もう一度ヒアリングしてみたい」
これです。これこそが、現場が本当にやりたいと感じている「高付加価値業務」の種です。私たちはそれらをすべてリストアップし、「削減時間でやることリスト」を作りました。そして、「この中から、来月は一人一つ、何でもいいから試してみませんか?そして、その結果どうだったか、教えてください」とお願いしました。
これは「二次KPIの押し付け」ではなく、「二次KPIの共同設計」です。
翌月の報告会で、最初に発言した若手が嬉しそうに報告してくれました。
「フォロー電話をかけたお客様から、『ちょうど困ってたんだよ!』と言われて、追加の消耗品の注文をいただけました!」
この小さな成功体験が、チームの空気を一変させました。高橋部長も「ほう、やるじゃねぇか」と目を細めている。時間が生まれることの価値を、全員が初めて「自分ごと」として実感した瞬間でした。
結論:地図だけでは、旅はできない
元記事で示したKPIのフレームワークは、目的地までの「地図」です。どこに山があり、どこに川があるかを示してくれます。しかし、実際に山を登り、川を渡る旅をするのは、現場で働く生身の人間です。
彼らは不安を感じ、変化を恐れ、時には反発もします。私たちの仕事は、ただ綺麗な地図を渡すことではありません。彼らの隣に立ち、一緒に汗をかき、時には道なき道を行くための知恵を絞り、そして小さな成功を一緒に喜び合う「旅の仲間」になることです。
AI導入の成否を分けるのは、結局のところ、こうした人間臭いコミュニケーションの積み重ねです。KPIという数字の向こう側にある、人々の「心理」や「感情」に寄り添い、彼らが自ら一歩を踏み出すための「物語」をデザインできるかどうか。
もしあなたが今、AI導入の壁にぶつかっているのなら、一度立ち止まって、あなたのチームの「もう一つの物語」に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。きっと、そこにこそ、突破口のヒントが隠されているはずですから。