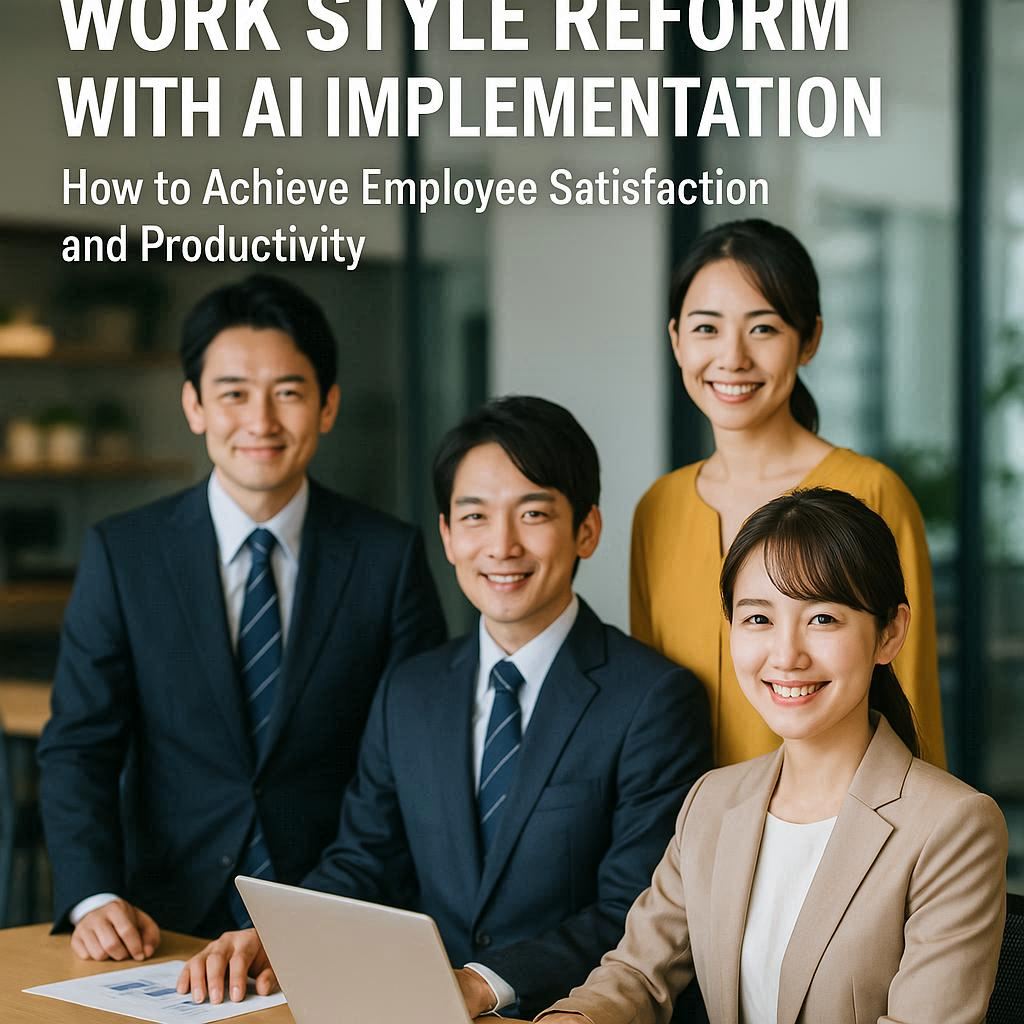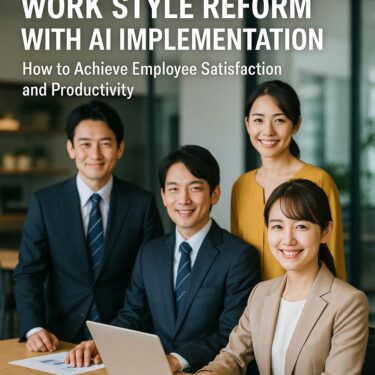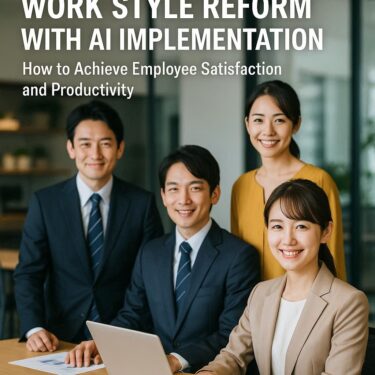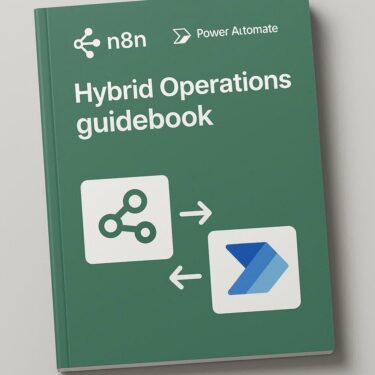AI導入の裏側で起きていた“静かな抵抗”と“小さな革命”の全貌
先日、有り難いことに多くの方に読んでいただいた「AIで働き方改革はここまで進む」という記事。そこでは、AIを導入し、働き方改革を成功に導くためのステップを、なるべく分かりやすく、体系立てて解説しました。
AIで働き方改革はここまで進む!生産性と満足度を両立する次世代の職場とは 「人手不足が深刻で、現場が疲弊している」「長時間労働を是正したいが、業務が終わらない」「働き方改革を進めたいが、何から手をつければいいかわからない」 […]
しかし、現実のプロジェクトは、図面通りにすんなり進むことなど万に一つもありません。むしろ、もっと泥臭く、人間臭い、数々のドラマの連続です。
机上の空論で終わらない、本当に現場で成果を出す改革とは何か。それは、最新のテクノロジーを導入することではありません。変化を恐れ、現状維持を望む「人の心」という見えない壁と、いかに向き合うか。これに尽きます。
この記事では、私たちが直面した生々しい現実――現場の“静かな抵抗”や、担当者の涙、そして、そんな状況をひっくり返した“小さな革命”の瞬間について、包み隠さずお話ししようと思います。AI導入を本気で考えるあなたが、同じ轍を踏まないために。
第一幕:「AIだかなんだか知らねぇ」。ベテラン部長の厚い壁
今回の舞台は、実直な物造りで地元に根付いてきた、とある中堅製造業。プロジェクトの担当者に任命されたのは、入社10年目、企画部の佐藤さん(38歳・女性)でした。彼女は非常に優秀で、改革への情熱も人一倍。しかし、彼女の前に最初に立ちはだかったのが、製造部門を半世紀近く支えてきた重鎮、五十嵐部長(68歳・男性)でした。
初めての部門長会議。私と佐藤さんがAI導入の概要を説明し終えた瞬間、どっしりと椅子に座っていた五十嵐部長が、重い口を開きました。
「佐藤さん、あんたの話はわがった。んだどもな、AIだかなんだか知らねぇけど、うぢの現場はそんな甘いもんでねぇぞ。職人の勘と経験で成り立ってんだ。パソコンポチポチやってる若い衆に、何がわがるんだや」
庄内地方独特の訛りで放たれる言葉は、穏やかながらも、決して心を開いていないことを物語っていました。会議室の空気は一気に凍りつき、他の部長たちも下を向くばかり。佐藤さんの顔から血の気が引いていくのが分かりました。
会議の後、彼女は私のところにやってきました。
「どうしましょう…。初日からこれじゃ、先が思いやられます。五十嵐部長は社内の誰からも一目置かれている方ですし、あの方が反対したら何も進みません…」
目にうっすらと涙を浮かべる彼女に、私はこう伝えました。
「佐藤さん、これはチャンスですよ。五十嵐部長は敵じゃありません。このプロジェクトが成功するかどうかを占う、一番大事な“お客様”です。彼を口説き落とせたら、このプロジェクトはもらったようなものです」
正論でぶつかっても、ベテランのプライドを傷つけるだけ。私たちがやったことは、ただ一つ。「徹底的に、相手の土俵で話を聞くこと」でした。
翌日、私と佐藤さんは作業着に着替え、五十嵐部長のいる工場へ向かいました。
「五十嵐部長、昨日は失礼いたしました。AIの話は一旦置いておいて、部長がこの工場で培ってこられた“技”を、私たちに教えていただけませんか?」
最初は訝しげな顔をしていた部長でしたが、私たちがメモを取りながら熱心に彼の“武勇伝”――機械の微妙な音の違いを聞き分ける話、油の匂いで故障を予知した話――を聞くうちに、少しずつ表情が和らいでいきました。
一通り話を聞いた後、私は切り出しました。
「部長、その素晴らしい技術、後継者の方にはどうやって教えてらっしゃるんですか?」
「んだなぁ…こればっかりは言葉で教えるのは難しいのぉ。見て、覚えてもらうしかねぇんだ」
「もし、部長のその“勘”や“経験”を、AIがデータとして記録して、若い技術者がいつでも学べるようになったら、どうでしょう?部長の分身が、24時間365日、みんなの先生になってくれるようなものです」
この言葉に、部長はハッとした顔をしました。「仕事を奪われる」という恐怖が、「自分の技術を遺せる」という期待に変わった瞬間でした。
あの記事で書いた「AIは人を代替するのではなく、人の能力を拡張するパートナー」という言葉は、綺麗事ではありません。現場のプライドと不安に寄り添い、彼らが守ってきたものを尊重し、その価値を未来に繋ぐための道具なのだと伝える。この地道な対話こそが、改革の第一歩なのです。
第二幕:「完璧な失敗」より「不完全な成功」を
現場の雪解けが見え始めた頃、次に私たちの前に現れたのは、まったく質の異なる壁でした。情報システム部のリーダー、鈴木さん(45歳・男性)です。彼は非常に優秀なエンジニアで、今回のプロジェクトの技術面を一手に引き受けてくれていました。しかし、その優秀さが、逆にプロジェクトの足かせとなり始めたのです。
「まず、全社のデータを統合管理するためのマスターデータベースを構築します。セキュリティを担保するために認証基盤も刷新し、将来的な拡張性を考えてクラウドネイティブなアーキテクチャを採用すべきです…」
彼が提示する計画書は、技術的に非の打ち所がない、完璧なものでした。しかし、その実現には少なくとも1年以上の歳月と、莫大な予算が必要でした。
「鈴木さん、計画は素晴らしい。でも、現場は今、日々の業務に追われて悲鳴を上げている。1年後じゃ遅いんです」と佐藤さんが訴えても、
「いや、ここで中途半端なシステムを入れると、後で必ず技術的負債になります。最初に完璧な土台を作ることが、結果的に一番の近道なんです」
と、彼は一歩も譲りません。
これが、多くのDXプロジェクトが陥る「完璧主義の罠」です。
あの記事で、私は「スモールスタートが成功への最短距離」だと書きました。その背景には、この鈴木さんのような“真面目な抵抗勢力”との戦いがあったのです。
膠着した事態を動かすため、私は関係者を集めた会議で、一枚の絵を見せました。それは、タイヤだけ、ハンドルだけが描かれた絵と、スケートボード、キックスケーター、自転車、そして最後に自動車が描かれた絵でした。
「皆さん、我々が目指すのは立派な自動車です。鈴木さんの計画は、その完璧な設計図でしょう。しかし、お客様(現場)は今すぐ移動手段が欲しい。私たちはまず、すぐに作れて動かせるスケートボードを提供すべきなんです。たとえ不格好でも、これがあれば前に進める。そして、現場からのフィードバックをもらいながら、キックスケーターへ、自転車へと進化させていけばいい。最初から完璧な自動車を作ろうとして、1年間何も提供できないことこそが、最大の失敗です」
そして、こう付け加えました。
「このパイロット導入の目的は、成功することじゃありません。安全に、小さく失敗するためです。今、スケートボードで転んでおくから、自動車に乗った時に大事故を起こさずに済むんです」
この言葉が、鈴木さんのような技術者のプライドを保ちつつ、方向転換を促すきっかけとなりました。完璧なシステムを追求するのではなく、「いかに早く学びを得るか」を共通のゴールに設定する。このマインドセットの転換が、プロジェクトを停滞から救い出したのです。
第三幕:「うちのデータは出せない」は、信頼関係のバロメーター
「スモールスタート」の方針が決まり、いよいよ具体的な準備に入りました。最初のターゲットは、記事でも紹介した「問い合わせ対応の自動化」。特に、各部署への社内問い合わせが総務部に集中し、パンク状態になっているのを解決しようと考えました。
AIチャットボットを賢くするには、学習データとなる各部署の業務マニュアルや過去のFAQが不可欠です。しかし、佐藤さんがデータ提供を依頼して回ると、各部署から返ってきたのは、予想以上に冷ややかな反応でした。
「うちの業務は特殊だから、マニュアル化できない」
「データは各担当者のPCに散らばっていて、どこにあるか分からない」
「そもそも、そんな面倒な作業、誰がやるんだ?」
記事では「独自データが競争優位を生む」とさらりと書きましたが、その「宝の山」は、組織の縦割りの壁、部門間のセクショナリズムという名の岩盤の下に、固く閉ざされていたのです。
特に手強かったのは、経理部のベテラン課長、高橋さん(58歳・女性)でした。
「経費精算のルールなんて、例外ばっかりよ。そんなものAIに学習させて、間違った回答をされたら誰が責任取るの?こっちは1円の間違いも許されないのよ」
彼女の言うことは、もっともです。この壁を突破するために、私たちは「ギブ&テイク」の原則に立ち返りました。
まず、佐藤さんは各部署にヒアリングして回り、「AIに学習させるためのデータ整備」という“お願い”をするのではなく、「皆さんが今、一番面倒だと感じている作業は何ですか?」という“質問”から始めました。
すると、面白いことが分かりました。経理部の高橋さんは、毎月末、各部署から集まってくるフォーマットのバラバラな経費精算書を、一つひとつ手作業でExcelに転記する作業に、膨大な時間を費やしていたのです。
そこで、私たちはこう提案しました。
「高橋さん、もし、AIが皆さんの質問に答える代わりに、あの面倒な転記作業を自動でやってくれるようになったら、どうですか?AI-OCRという技術を使えば、紙の精算書をスキャンするだけで、データ化できます」
高橋さんの目が、少しだけ輝きました。
「…そんなこと、本当にできるの?」
データ提供は、相手にとっての「手間」や「リスク」だけを伝えても動きません。そのデータを提供することで、自分たちの仕事がどう楽になるのか。その具体的な見返りを、相手の言葉で語ること。
私たちは、各部署のキーマンを集めた「データ整備ワーキンググループ」を立ち上げ、データ提供を「義務」から「自分たちの業務改善のための共同作業」へと位置づけました。佐藤さんがファシリテーターとなり、部署間の調整に奔走する中で、彼女はいつしかプロジェクトの「担当者」から、皆に頼られる「リーダー」へと成長していきました。
最終幕:一人のベテランの変化が、組織を動かした日
小さなパイロットが始まり、数週間が経ったある日のことです。
製造現場で、数十年前の古い機械に特殊なエラーが発生しました。誰も原因が分からず、メーカーに問い合わせても「古すぎて資料がない」と匙を投げられ、生産ラインが止まりかけていました。
万策尽きたその時、一人の若手社員が、ダメ元で試験導入していたAIチャットボットに「(機械の型番) エラーコードXXX 原因」と打ち込みました。すると、AIはこう回答したのです。
『15年前に五十嵐部長が作成した引継ぎ資料(PDF)の7ページに、類似事象の記載があります。原因は特定部品の経年劣化で、代替部品は倉庫Bの棚3に保管されている可能性があります』
若手社員が半信半疑で倉庫へ走ると、ホコリを被った箱の中に、まさにその代替部品があったのです。ラインは無事に復旧。この一件は、あっという間に工場中に広まりました。
翌朝、五十嵐部長が私のところにやってきて、少し照れくさそうに頭をかきました。
「…いやぁ、まいった。わしが書いたことなんか、とっくに忘れとった。こいづ(AI)、わしより物覚えがいいなや。なかなか、たいしたもんだのぉ」
この、たった一つの成功体験。
無機質な「工数40%削減」といったデータよりも、五十嵐部長のこの一言の方が、よほど雄弁にAIの価値を物語っていました。佐藤さんはこのエピソードを丁寧にまとめ、写真付きで社内報に掲載しました。数字だけの成果報告ではなく、誰が、どのように助かったのかという「物語」を添えて共有したのです。
そこから、組織の空気は劇的に変わりました。
「うちの部署でも試したい」という声が、これまで抵抗勢力だった部署から次々と上がり始めました。あれだけ否定的だった経理部の高橋さんまでもが、「うちの複雑な規定、あの子(AI)なら覚えられるかしら?」と相談に来るようになったのです。
あの記事に書いた、AIによる働き方改革のロードマップは、決して嘘ではありません。しかし、そのステップを一つひとつ進めるためには、テクノロジーの知識以上に、人の心に寄り添う力が不可欠です。
抵抗は、悪意ではありません。変化への不安、自分の仕事を失うことへの恐怖、守ってきたものへの誇り。そうした感情の自然な現れです。その声に耳を傾け、彼らの言葉を理解し、不安を期待へと変えていく地道なコミュニケーションの積み重ねこそが、改革の本当のエンジンになります。
もしあなたが今、AI導入の壁にぶつかっているのなら。どうか、思い出してください。あなたの目の前にいる“抵抗勢力”は、かつての五十嵐部長かもしれません。彼らを論破するのではなく、彼らの最高のパートナーになることから、すべては始まるのです。