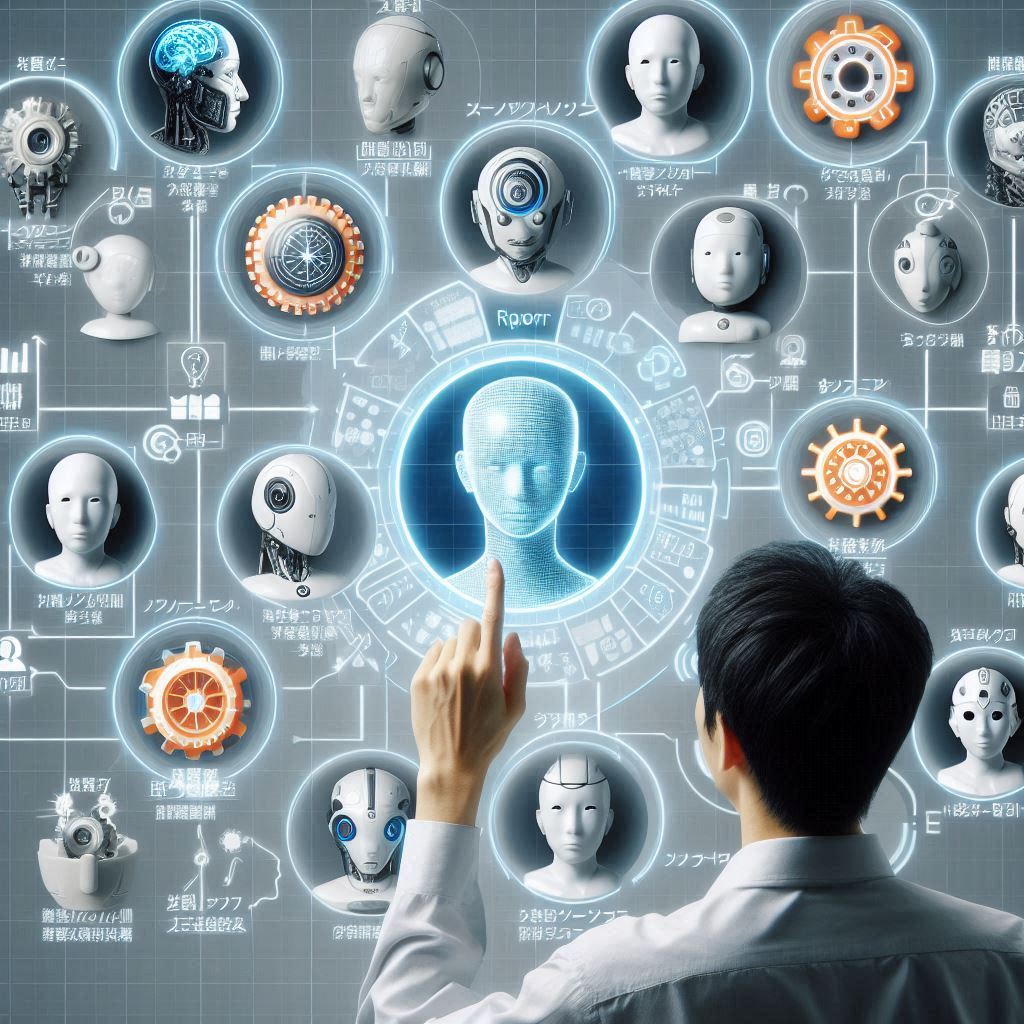AI導入の落とし穴。「やってるフリ」の社員たちと、たった一人の事務員から始まった静かな革命
AIツールの活用法について私が書いた記事を読んで、「よし、うちも導入しよう!」と意気込んでくださった経営者の方々、本当にありがとうございます。記事に書いた通り、AIは間違いなく、あなたの会社の生産性を劇的に向上させるポテンシャルを秘めています。
…しかし、もしあなたが「ツールさえ導入すれば、社員が勝手に使ってくれて、魔法のように成果が上がる」と思っているとしたら、少しだけ立ち止まってこの話を聞いてください。
これは、華々しいAI活用事例の裏側で、私が何度も目撃してきた「最も厄介な失敗」の物語です。それは、社員が声高に反発するわけではない、しかし静かに、そして確実にプロジェクトを蝕んでいく「無関心の壁」と「やってるフリ文化」との戦いの記録です。
前回、前々回では「個人の抵抗」や「部門間の壁」という分かりやすい障壁についてお話ししました。しかし今回向き合ったのは、それよりもっと根深く、見えにくい敵でした。もしあなたの会社で、「新しいシステムを入れたのに、誰も使っていない」「DXと騒いでいるが、何も変わっていない」と感じることがあるなら、この話はあなたのためのものです。
「全員に武器を配った」社長と、誰一人戦わない兵士たち
その会社は、地元で人気の惣菜や弁当を製造・販売する食品加工メーカーでした。二代目の加藤社長(60代)は、アイデアマンで決断が早く、新しいテクノロジーへの投資も積極的。ある日、彼は満面の笑みで私にこう言いました。
「ミズさん、ついにうちもAI時代さ突入だ!全社員にMicrosoft Copilotのアカウントば配布したぞ。これで明日がら、みんなの仕事も劇的に速ぐなるはずだ!」
社長の期待とは裏腹に、プロジェクトの推進役を任された企画部の田中さん(30代女性)の表情は曇っていました。彼女は私の元へ相談に来ると、小さな声で打ち明けてくれました。
「アカウントを配布して、社内研修も開いて、マニュアルも作ったんです。でも…導入から3ヶ月経っても、ほとんど誰も使ってくれていないんです…」
詳しく話を聞くと、事態は深刻でした。利用ログを見ると、ログインした形跡はある。しかし、実際の業務で活用されている様子はまったくない。田中さんが各部署を回ってヒアリングしても、返ってくるのは歯切れの悪い言葉ばかり。
「あ、使ってますよ。メールの返信を考える時にちょっとだけ…」
「便利ですよね(と言いつつ、一度も開いていない)」
「今までのやり方で特に困っていないので…」
誰も反対はしない。しかし、誰も本気で使おうとしない。まるで、全員に最新鋭のライフルを配ったのに、誰一人として使い方を覚えようとせず、塹壕の中で今まで通り竹槍を振り回しているような光景です。
田中さんは「私の研修が悪かったんでしょうか」「マニュアルが分かりにくかったのかもしれません」と自分を責めていましたが、問題の根っこはもっと深いところにありました。
なぜ人は「変わらない」ことを選ぶのか?行動経済学が示す不都合な真実
私は田中さんに、こう問いかけました。
「田中さん、社員の皆さんは、AIを使うことで『自分にどんないいことがあるか』を具体的にイメージできているでしょうか?」
人は、本質的に変化を嫌う生き物です。行動経済学でいうところの「現状維持バイアス」が強く働くため、たとえ新しい方法が合理的で優れていたとしても、慣れ親しんだ古いやり方を手放すことには強い心理的抵抗を感じます。
この抵抗を乗り越えるには、「変化によって得られるメリット」が、「変化に伴うコスト(学習の手間、失敗のリスクなど)」を明らかに上回っていると、本人が確信する必要があります。
今回のケースでは、加藤社長が「生産性向上」という会社全体の大きなメリットを提示しましたが、それは現場で働く一人ひとりの社員にとって、あまりにも漠然としていました。「会社の生産性が上がること」と「今日の私の面倒な作業が楽になること」の間には、天と地ほどの隔たりがあるのです。
さらに、「全社一斉導入」というトップダウンが、問題をより複雑にしていました。業務内容も、ITスキルも、日々の悩みも全く違う社員全員に、同じツールを「はい、どうぞ」と渡しても、「自分ごと」として捉えられるはずがありません。
彼らは「使わない」と反抗しているのではなく、単純に「自分に関係ないもの」として無視しているだけ。これが、「やってるフリ」という静かな抵抗の正体でした。
攻略の鍵は「お局様」?一点突破・全面展開という逆転の発想
この膠着状態を打破するために、私は田中さんに一つの戦略を提案しました。
「田中さん、全員に10%ずつ使わせようとするのは、もうやめましょう。たった一人でいい。その人に120%使いこなしてもらうんです。その一人の『小さな成功』を、燎原の火のように全社に広げていくんです」
いわゆる「一点突破・全面展開」戦略です。そして、その突破口として白羽の矢を立てたのが、営業事務を20年以上務めるベテラン、佐藤さん(50代女性)でした。
彼女は、社内の誰よりもアナログな作業に苦しめられている人物でした。毎月末になると、全国の営業担当者からメールで送られてくる、フォーマットもバラバラなExcelの売上報告書を、手作業で一つのファイルに転記し、集計し、役員会議用のグラフを作成する。この作業に、毎月丸々3日間を費やし、月末は決まって残業していました。
一方で、彼女は社内のインフルエンサーでもありました。おしゃべりで面倒見が良く、他の事務員や若手社員からの人望も厚い。彼女が「これ、すごくいいわよ!」と言えば、多くの社員が耳を傾ける。彼女こそ、このプロジェクトの鍵を握る人物だと私は確信しました。
田中さんと二人で、月末の作業でてんてこ舞いの佐藤さんの元を訪れました。
「佐藤さん、毎月大変だねぇ。目がしょぼしょぼしてらべ」
「んだんだ、ミズさん!毎月毎月、肩は凝るし目は疲れるし、もうじぇんじぇんする!若い子らは好き勝手なファイルば送ってくんだもの、まいねぐなる!」
不満をたらふく吐き出してもらった後、私は切り出しました。
「もし、その3日かかる作業が、たった30分で終わる魔法があったら、使ってみたいと思わねが?」
「はぁ?何寝ぼげだごと喋ってらんだ。そんげなのあるわけねぇべ!」
私たちは、佐藤さんの隣にノートパソコンを置き、実際に彼女が格闘しているExcelファイルを使って、AI(Copilot in Excel)のデモンストレーションを行いました。バラバラのデータを瞬時に整形し、ボタン一つで集計表とグラフが生成される様子を、彼女は食い入るように見つめていました。
デモが終わった時、彼女は唖然とした表情で呟きました。
「…うそだべ。わだしが3日かげでやってだごどが、なんで…」
そこで、私は最後のひと押しをしました。
「佐藤さん、これは魔法じゃなくて、社長がみんなに配った新しい道具なんです。田中さんが使い方をマンツーマンで教えるから、覚えてみませんか?そしたら、月末に2日半も時間が浮きますよ。その時間があったら、前から行きたがっていた温泉旅行にも行けるし、可愛いお孫さんと遊ぶ時間もたっぷり取れますよ」
ここでのポイントは、「会社の生産性が上がるから」とは一言も言わないことです。あくまで、彼女個人のメリット、「残業がなくなって、プライベートが充実する」という、具体的で魅力的な未来を提示することに徹しました。
佐藤さんの目に、好奇心と期待の光が灯りました。彼女が、重い腰を上げた瞬間でした。
一人の「楽になった!」が、組織を動かす最強の口コミになる
それからの1ヶ月、田中さんは付きっきりで佐藤さんをサポートしました。そして翌月の末締め。佐藤さんは、本当に半日で全ての作業を終えてしまったのです。
定時きっかりに「お先に失礼します!」と晴れやかな顔で帰っていく佐藤さんを見て、他の事務員たちは目を丸くしていました。
「え、佐藤さん、もう終わりなんですか?」
「あら、当たり前じゃない。私はもうAIっていう便利な秘書がいるんだから。あんたたちみたいに、いつまでも手作業でちまちまやってないわよ。ほっほっほ」
彼女のこの一言が、最高の口コミになりました。
翌日から、田中さんの元には「佐藤さんが使っている“魔法”を教えてほしい」という問い合わせが、他の部署の事務員から殺到するようになったのです。
そこで私たちは、佐藤さんを「AI活用マイスター」に任命し、彼女自身に講師役をお願いして、小さな勉強会を開きました。専門家の私や田中さんが説明するよりも、同じ立場で、同じ悩みを抱えていた佐藤さんが、自分の言葉で「いかに自分が楽になったか」を語る方が、何百倍も説得力がありました。
「やってるフリ」だった社員たちが、初めて「自分もそうなりたい!」と本気で思った瞬間でした。
改革とは、壮大な計画書ではなく、一人の笑顔から始まる
この一連の出来事を、私は加藤社長に報告しました。
「社長、号令をかけるだけでは、兵士は戦いません。兵士が戦うのは、この戦いに勝てば故郷に帰って家族と幸せに暮らせる、という個人的な希望がある時です」
「…なるほどな」
「AI導入も同じです。まず、誰か一人の『困りごと』を徹底的に解決し、『こんなに楽になった!』という成功体験を間近で見せること。その“幸せのおすそ分け”が、自然と周りに伝播していくんです。改革とは、分厚い計画書からではなく、現場の一人の社員の笑顔から始まるんですよ」
私の話を聞いた社長は、深く頷きました。そして次の役員会で、AIを活用して業務改善を行った社員を積極的に評価する新しい制度の導入を決定しました。
あの「AIツールの賢い使い分け」の記事に書かれていることは、すべて事実であり、理想の姿です。しかし、その理想にたどり着くまでの道のりは、決して平坦ではありません。そこには、変化を恐れ、面倒くさがり、見て見ぬフリをする、私たち人間のどうしようもない愛すべき弱さが横たわっています。
その壁を突破するのは、最新のテクノロジーではありません。それは、相手の立場に立ち、その人の「個人的な幸せ」に繋がる道筋を一緒に見つけてあげる、という極めて地道で、人間的なコミュニケーションです。
もし今、あなたの会社で改革が停滞しているなら、一度、全社展開という大きな視点を手放してみてください。そして、たった一人でいい、目の前で本当に困っている人を探し、その人のためだけに、テクノロジーという武器を使ってみてください。
その一人の満面の笑みこそが、やがて組織全体を動かす、最もパワフルなエンジンになるのですから。