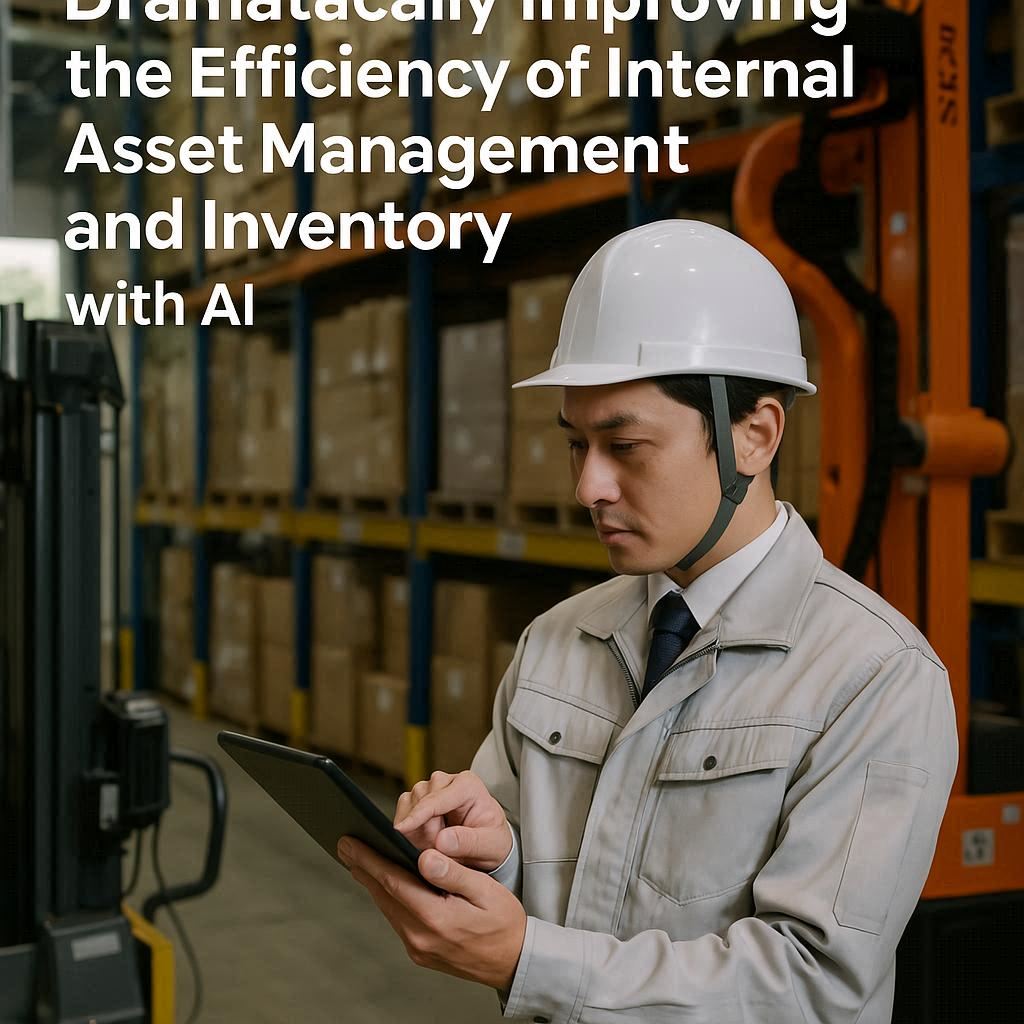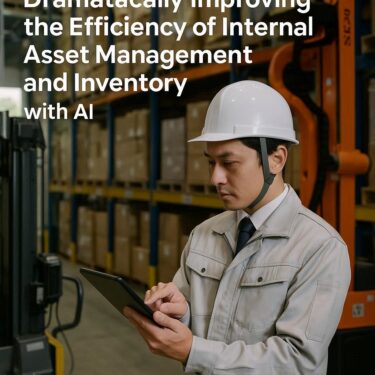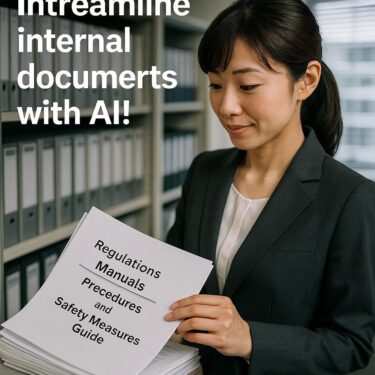AI導入の理想と現実。「AIを信じられますか?」担当者の不安へのコミュニケーション術
先日、私が監修した『AIで社内資産管理・棚卸を劇的に効率化する実践ガイド』という記事を公開しました。おかげさまで多くの方に読んでいただき、嬉しいお言葉をいただいています。
AIで社内資産管理・棚卸を効率化する実践ガイド——需要予測からRAG活用まで 「また棚卸の季節か…丸一日潰れるな」「この在庫、本当に適正?欠品も過剰在庫も怖い」「あの備品、今どこにあるんだろう?」 もし、あなたがこのよ[…]
しかし、今日は少しだけ、あの記事の裏側をお話しさせてください。
あの記事に書かれている「7つのステップ」や「チェックリスト」は、いわば美しい航海図のようなものです。しかし、実際の航海は、凪の時ばかりではありません。突然の嵐、見えない岩礁、そして何より、船員たちの不安や反発という、図上では決してわからない荒波が待ち構えています。
私がこれまで企業改革やシステム導入の現場で見てきたのは、最新のAI技術や完璧なプロジェクト計画が成功を約束するのではない、という厳然たる事実です。成功の核心は、いつだって「人」にあります。今日は、あの綺麗な記事には書ききれなかった、泥臭くて人間臭い、汗と涙のコミュニケーションの物語をいくつかご紹介したいと思います。
第1章:『データは資産です』と言った瞬間に凍り付いた会議室
あれは、創業70年を超える、実直な物造りを続けてきたある地方の製造業でのことでした。AI導入による業務改革プロジェクトのキックオフ会議。関係者が集まる中、私は意気揚々と切り出しました。
「今回のプロジェクト成功の鍵は、何と言っても『データ資産化』です。皆さんの日々の業務データを、会社の貴重な資産として磨き上げていくことから始めましょう!」
その瞬間、会議室の空気がスッと冷たくなったのを感じました。視線の先にいたのは、今回のプロジェクトで現場側のキーパーソンとなる、入社10年目の佐藤さん(30代)。彼女は真面目で責任感が強く、誰からも信頼されるエースです。しかし、その彼女の顔はみるみるうちに曇っていきました。
会議後、私は彼女にそっと声をかけました。
「佐藤さん、さっきの話、何か気になるところがありましたか?」
彼女は少し躊躇した後、堰を切ったように話し始めました。
「データが大事なのは、頭ではわかります。でも、『資産化』って言われても…。誰がやるんですか?私たちは、日々の出荷と、いつ鳴るかわからないクレームの電話に対応するだけで一日が終わるんです。その上、過去のバラバラなデータを綺麗にしろと言われても、正直、無理です…」
彼女の目には、疲労と諦めが滲んでいました。これこそが、多くの改革プロジェクトが最初にぶつかる「正論の壁」です。「データは宝だ」「DXが重要だ」という言葉は、日々の業務に追われる現場にとっては、遠い国のお経のようにしか聞こえないのです。
私は、プレゼン資料を閉じ、彼女の目を見て言いました。
「佐藤さん、ごめんなさい。言い方が悪かったですね。AIは魔法使いじゃないんです。私がやりたいのは、佐藤さんたちが毎月末、帳簿と現物が合わなくて、結局、暗い倉庫で現物を数え直している、あの時間を無くすことなんです」
彼女が、ハッとした顔で私を見ました。
「あの作業を無くすための『道具』がAIなんです。だから、まず全社のデータを全部きれいにしようなんて、そんな無茶は言いません。最初に、佐藤さんたちが一番『数が合わなくて面倒だ!』って思ってる、あの金型の管理から楽にしませんか?あの金型が、今どこにあって、何回使ったか、ピッてやるだけでわかるようになったら、少しは楽になりますよね?」
「全社的なデータ資産化」という壮大で他人事なテーマを、「目の前の、あの忌々しい月末の残業をなくす」という、リアルで切実な「自分ごと」に翻訳する。彼女の表情が、諦めから「それなら…」という微かな希望に変わった瞬間でした。
行動変容の第一歩は、いつだって共感と「自分ごと化」から始まるのです。あの綺麗な記事の「ステップ2:データ整備」という短い言葉の裏には、こうした一人ひとりとの地道な対話が隠されています。
第2章:「わしらのやり方ば変えろってのが!」ベテランの壁と信頼の証
さて、佐藤さんたちの協力も得られ、データの整備に光が見えてきました。次のステップは、いよいよ「棚卸のデジタル化」です。今回のプロジェクトでは、作業効率を劇的に改善するため、RFID(電波で一括読み取りできるICタグ)の導入を提案しました。
しかし、ここに分厚い壁が立ちはだかりました。現場のリーダー、鈴木さん(65歳)です。この道45年の大ベテランで、倉庫のどこに何があるか、頭の中に完璧に入っている「生き字引」のような方でした。
説明会でRFIDのデモを見せた後、鈴木さんは腕を組んだまま、低い声で言いました。
「んだ、よぐわがんね面倒なもんどごつけで、何になんのだ!わしらはずっとこयन(この)やり方でやってきたんだ。今まで、それで何の問題も無がったべ!」
周りの若い社員たちは、彼の気迫に押されて黙り込んでいます。典型的な「現場の抵抗」です。しかし、私は彼の言葉を、単なる変化への拒絶とは捉えませんでした。そこには、自分の仕事への誇りと、新しいものに自分の聖域を侵されることへの不安が入り混じっていたのです。
ここで彼のプライドを否定しては、絶対に前に進めません。私は、鈴木さんの隣に歩み寄り、尊敬の念を込めて話しかけました。
「鈴木さん、おっしゃる通りです。鈴木さんの頭の中にある在庫マップは、誰にも真似できない、この会社の最高の財産です。本当にすごいことだと思います」
彼の表情が、少しだけ和らぎました。
「ただ、私が心配なのは、その最高の財産を、どうやって若い人たちに引き継いでいくか、なんです。鈴木さんがいないと現場が回らないのは素晴らしいことですが、逆に言えば、鈴木さんが安心して休むこともできない、ということじゃないですか?」
「このピッてやるやつは、鈴木さんのやり方を変えるものじゃありません。鈴木さんのそのすごい記憶と経験を、誰でもわかる『形』にして、若い人たちが一日も早く一人前になるのを手助けするための道具なんです」
さらに、私は彼に質問を投げかけました。これは、彼の懸念を聞き出すための、重要なコミュニケーションです。
「だども、お父さん(おどさ)。こयनタグ、水さ濡れだら大丈夫なが?うちの現場は油で汚れっけど、それでもちゃんと読めっのが?」
彼の口から出てきたのは、現場を知り尽くした者ならではの、リアルで的確な懸念事項でした。カタログスペックだけではわからない、生きた情報です。
そこで私は、彼にある提案をしました。
「鈴木さん、ありがとうございます。その視点は私にはありませんでした。でしたら、一つお願いがあります。この新しい道具が、本当にこの現場で使えるものなのか、お父さんの厳しい目でテストしてみてけねが(もらえませんか)?もし『こんげなもんは使えね』ってなったら、私は社長に正直にそう報告します。鈴木さんに、このプロジェクトの品質評価リーダーをお願いしたいんです」
彼を「変化に抵抗する人」から、「変化を評価し、導く人」へと役割転換させたのです。彼の顔に、頑なさが消え、職人としての誇りが戻ってきました。
結果ですか?言うまでもありません。PoC(概念実証)が始まると、鈴木さんは誰よりも熱心にRFIDリーダーを手に取り、「こっつさ当てだ方が反応いいぞ」「この棚は電波が通り悪いな」と、改善点を次々と見つけてくれる、最高の推進役になってくれたのです。
あの記事の「ステップ3:棚卸のデジタル化」の裏には、ベテランのプライドを尊重し、敵かもしれない相手を最強の味方へと変える、こんなドラマがあったのです。
第3章:「AIを信じられますか?」担当者の不安と『AI教育係』という名の信頼
紆余曲折を経て、システムは稼働を開始しました。AIが過去のデータや天候などの外部要因を分析し、最適な発注量を提案する。まさに、記事に書いた通りの理想的な仕組みです。
しかし、新たな問題が起きました。誰も、AIが出した数字を使おうとしないのです。
ある日、担当の佐藤さんが私のところにやってきました。PCの画面を指さしながら、不安そうな顔で言います。
「見てください。この部品、AIは『来週までに100個発注』と提案してきています。でも、私たちの経験だと、この時期はせいぜい50個なんです。もしAIの言う通りに発注して、大量に売れ残ったら…。その責任は、誰が取るんですか?」
これこそが、「AIのブラックボックス問題」の核心です。なぜその数字が出てきたのか、根拠がわからないものに対する人間の根源的な不信感。そして、失敗した時の「責任」という現実的な恐怖。これは、いくら「AIの精度は95%です」と説明しても解決しません。
私は彼女にこう話しました。
「佐藤さん、その『肌感覚』、ものすごく大事です。AIには絶対に真似できない、佐藤さんの経験と知識の結晶なんですから。それを無視してAIを鵜呑みにするのは、一番やっちゃいけないことです」
まず、彼女の経験を肯定し、尊重する。その上で、新しい関係性を提案しました。
「こうしませんか?これから、AIの提案と佐藤さんの最終的な判断が違った時、その理由を簡単でいいので、システムにメモしておいてもらえませんか。『今週は近隣の競合がセールをやるから、うちは控えめにした』とか、そんな一言でいいんです」
「そのメモが、このAIを、ただの計算機から、ウチの会社の事情をよく理解した『賢い新入社員』に育てるための、最高の教科書になるんです。佐藤さんには、このAIの『教育係』になってほしいんです」
この提案は、彼女の役割を劇的に変えました。AIに「使われる」オペレーターではなく、AIを「育てる」トレーナーへ。AIの提案が外れたら、それは自分の責任ではなく、「まだまだ教え方が足りない新人のミス」と捉えられる。彼女の肩から、責任という重荷が少し降りたように見えました。
それからというもの、彼女は積極的にAIの提案を吟味し、判断理由を記録してくれるようになりました。そのデータは、AIモデルを再学習させる際の、何物にも代えがたい貴重な教師データとなります。AIと人間が、互いの長所を活かし、短所を補い合いながら成長していく。理想的な関係が、そこに生まれ始めたのです。
結論:改革のエンジンは、技術ではなく『人』の心だ
あの綺麗な記事に書かれている7つのステップは、いわば設計図にすぎません。しかし、実際に家を建てるのは、現場で汗を流す大工や左官といった職人たちの知恵と情熱です。
企業改革という名の家造りも、全く同じです。プロジェクトの成否を分けるのは、最新のAIモデルやクラウド技術ではありません。現場で働く一人ひとりの不安に寄り添い、プライドを尊重し、変化への恐怖を新しい役割への期待へと変えていく。そんな、地味で、時間のかかるコミュニケーションこそが、AIという強力なエンジンを動かすための、唯一無二の燃料なのだと、私は信じています。
もしあなたが今、何かの改革の壁にぶつかっているのなら、一度PCの画面から顔を上げてみてください。そして、現場で働く人々の声に、真摯に耳を傾けてみてください。答えは、最新の技術書の中ではなく、きっと、そこにあるはずですから。