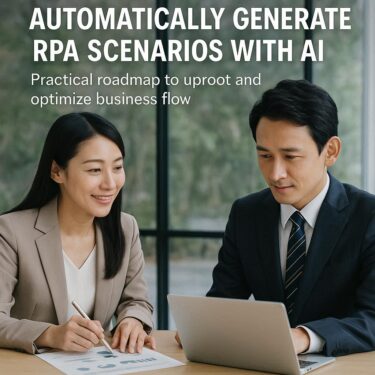AI導入の理想と現実、その裏側で起きていたこと ―「AIなんて使えません!」から始まったSNS改革の舞台裏
先日、ある企業様と進めた「AIを活用したSNS運用効率化」の取り組みについて、ノウハウをまとめた実践ガイドを公開しました。そこには、課題設定から仕組み化、そして成功に至るまでの綺麗な道筋が描かれています。
AIでSNS運用を効率化!投稿文・画像生成を仕組み化し属人化から解放される実践ガイド 「今日の投稿、何にしよう…」「キャプションの下書きだけで午前中が終わってしまった」「担当者が休むとSNSが完全に止まってしまう」。 もしあな[…]
しかし、物事には必ず表と裏があるものです。
あの整然としたガイド記事の裏側では、実に人間臭い、泥臭いドラマがありました。最新のテクノロジーを前にした人々の戸惑い、プライド、見えない抵抗、そして、それらが少しずつ氷解していく過程。それは、ツールを導入するだけでは決して語れない、リアルな物語です。
この記事は、あのガイド記事の「行間」を埋めるための裏話です。私が現場で目の当たりにした、マネジメントとコミュニケーションの苦労話、そしてそこから得た生々しい学びを、少しだけ皆さんにお話ししようと思います。これは、AI導入を検討している、あるいはすでに壁にぶつかっているすべての担当者、そして管理職の方々にお届けしたい、もう一つの実践ガイドです。
第1章:最初の壁 – 「私の仕事、AIに奪われるんですよね?」
プロジェクトのキックオフミーティング。会議室には、期待に満ちた経営陣と、少し緊張気味のSNS運用担当部署の鈴木部長(40代後半)、そして、その部下で現場担当者の佐藤さん(30代女性)が座っていました。
私がAI導入のメリット――効率化、品質の安定化、属人化の解消――を意気揚々と説明し終えたとき、ずっと黙って俯いていた佐藤さんが、おそるおそる顔を上げました。
「あの…、すごく初歩的な質問で申し訳ないんですが…」
彼女の声は、少し震えていました。
「これって、つまり、私の仕事がAIに奪われるっていうこと、ですよね?」
その一言で、会議室の空気が凍りついたのを今でも覚えています。経営陣は「いやいや、そんなことは…」と口ごもり、鈴木部長は少しバツの悪そうな顔で彼女を見ています。
これこそが、あらゆる現場で最初にぶつかる、最も本質的で、最も高い壁です。人は、正論だけでは動きません。特に、自分の存在価値が脅かされると感じたとき、心に分厚いシャッターを下ろしてしまいます。
私はプレゼン資料を閉じ、佐藤さんにまっすぐ向き直りました。
「佐藤さん、逆です。私たちは、佐藤さんがやらなくてもいい仕事をAIに押し付けて、佐藤さんにしかできない仕事にもっと時間を使ってもらうために、このプロジェクトをやるんです」
「…私にしか、できない仕事?」
「はい。例えば、投稿に付いたコメントに、お客様一人ひとりの気持ちを汲み取って返信すること。これはAIにはできません。AIが生成した投稿案を見て、『こっちの表現の方が、うちのブランドらしい』と最終判断を下すこと。これも、ブランドを一番理解している佐藤さんにしかできない。AIはあくまで、最高に優秀なアシスタントです。佐藤さんは、編集長であり、戦略家になるんです」
この対話が、あのガイド記事にある「AIは『思考停止』の道具ではない。『思考の壁打ち相手』である」という一文の、本当の出発点でした。ツールを導入する前に、まず人の「不安」という感情に寄り添い、新しい役割を一緒に見つけてあげる。この地道なコミュニケーションこそが、改革の成否を分ける最初の分水嶺なのです。
第2章:見えない抵抗 – 「秘伝のタレ」を守りたい担当者の本音
佐藤さんの不安は少し和らいだものの、プロジェクトはすぐには進みませんでした。AIツールを導入し、使い方をレクチャーしても、彼女が作る投稿は、以前と変わらずゼロから手作業で作られたものがほとんど。AIが生成した下書きは、参考程度にしか使われていないようでした。
鈴木部長は少し苛立っていました。「せっかくツールを入れたのに、どうして使わないんだ?」と。しかし、これもまた、現場でよく起こる「見えない抵抗」の一つです。
私は佐藤さんと二人で、お昼休憩にランチへ行きました。仕事の話はせず、趣味や最近見たドラマの話で盛り上がった後、帰り道にポツリと聞いてみました。
「佐藤さんって、SNSの投稿文作るの、すごく上手ですよね。いつもどんなことを意識してるんですか?」
すると彼女は、待ってましたとばかりに、目を輝かせて語り始めました。
「最初のフックで、いかに『自分ごと』だと思ってもらえるかが勝負なんです。だから、冒頭の15文字には一番時間をかけます。あと、専門用語は絶対に使わないようにしていて…。箇条書きを入れると、保存率が上がるんですよ」
次から次へと出てくる、彼女だけのノウハウ。それは、長年の試行錯誤の末に生み出された、まさに「秘伝のタレ」でした。その時、私はハッとしました。彼女がAIを使わない理由は、「AIが信用できない」からではない。「自分の価値そのものである『秘伝のタレ』を、AIに明け渡したくない」という、無意識のプライドと抵抗感だったのです。
翌日、私は彼女にこう提案しました。
「佐藤さん、その『秘伝のタレ』の作り方を、AIに教えてくれませんか? 佐藤さんのノウハウをプロンプトという命令文に落とし込んで、佐藤さん専用の『分身ロボット』を作るんです。そうすれば、面倒な下書きは全部そいつにやらせて、佐藤さんはもっと面白い企画を考える時間に集中できる」
彼女の顔が、パッと明るくなりました。
「私のノウハウを、AIに教える…?」
「そうです。AIを『使う』んじゃなくて、『育てる』んです。育ての親は、佐藤さんです」
この日から、私たちの「万能プロンプト作り」が始まりました。あのガイド記事に載っているコピペ可能なプロンプトは、実は彼女の「秘伝のタレ」を言語化し、体系化したものなのです。彼女が大切にしてきたスキルを否定するのではなく、「あなたのスキルは素晴らしい。だからこそ、それを仕組み化してチームの財産にしましょう」とアプローチを変えた瞬間、彼女はプロジェクトの強力な推進力へと変わりました。
第3章:承認フローという名の巨大な壁と、上司のプライド
担当者が前向きになっても、次なる壁が待ち受けていました。上長である鈴木部長の「承認フロー」です。
AIのおかげで、投稿の下書きは1週間分がわずか30分で完成するようになりました。しかし、それが鈴木部長に提出されると、返ってくるまでに2、3日かかるのです。しかも、返ってきたドキュメントは、細かな「てにをは」や言い回しまで真っ赤に修正されていました。
これでは、せっかく短縮した時間が水の泡です。
ある日の夕方、私は鈴木部長の席へ向かいました。
「部長、少しよろしいですか。AIが作った下書き、読みにくいですか?」
すると部長は、少しバツが悪そうにこう言いました。
「いや、そんなことはないんだが…。なんだろうな、AIが作った文章って聞くと、どこか人間味が足りない気がして、つい細かく見てしまうんだ。それに、万が一、変な表現で炎上でもしたら、責任を取るのは私だからね」
彼の言葉には、二つの本音が隠れていました。一つは、AIに対する漠然とした不信感。もう一つは、管理職としての強い責任感、言い換えれば「俺がチェックしないとダメだ」というプライドです。
これを頭ごなしに「非効率だ」と指摘しても、反発を招くだけです。私は、彼のプライドを尊重しつつ、役割を再定義するアプローチを取りました。
「部長のおっしゃる通りです。最終的な責任は部長にあります。だからこそ、部長にはもっと重要な、部長にしかできないチェックをお願いしたいんです」
「私にしかできないチェック?」
「はい。具体的には3つだけです。一つ、会社のブランドイメージを損なう表現はないか。二つ、法律やコンプライアンス的に問題はないか。三つ、伝えたいメッセージの核がズレていないか。この『砦』さえ守っていただければ、細かい表現は佐藤さんとAIに任せてみませんか? 彼女の編集能力を信じて、少し権限を委譲してみる、という考え方です」
ガイド記事に書いた「承認フローを3つのチェックポイントで軽量化する」というノウハウは、この鈴木部長との対話から生まれました。彼の役割を「修正者」から「最終的なリスクを判断する砦」へと変えることで、彼の責任感とプライドを傷つけることなく、承認プロセスを劇的にスピードアップさせることができたのです。マネジメントとは、時に人の役割をデザインし直すことなのだと、改めて実感した出来事でした。
第4章:「そんな横文字、わがらねぇ」が教えてくれた本質
プロジェクトがようやく軌道に乗り始めた頃、思わぬ人物から声をかけられました。品質管理一筋40年、定年後も嘱託で会社に残る大ベテランの高橋さん(60代後半)です。
ある日、私が廊下を歩いていると、高橋さんに呼び止められました。
「あんたが、えーあい?とかいうのをやっでる先生が?」
「は、はい。まあ、そんなところです」
「なんだが知らねぇけども、最近の若いのは、プロンプトだの、ガバナンスだの、横文字ばっかりでわがらねぇな。俺らの頃はなぁ、こごさ気持ち込めで、お客さんの顔ば思い浮かべで、一字一句考えだもんだぞ」
一瞬、旧世代からの“横槍”かと身構えましたが、彼の言葉には不思議な説得力がありました。そして、それはプロジェクトの核心を突く一言でもあったのです。
私たちは、AIというツールに目を奪われるあまり、「誰に、何を伝えたいか」という最も大切なことを見失いかけていたのかもしれない。高橋さんの言葉は、私たちに冷や水を浴びせ、本質に立ち返らせてくれました。
この出来事がヒントとなり、「画像テキストとキャプションの同時生成術」のアイデアが生まれました。高橋さんが言っていた「お客さんの顔を思い浮かべる」とは、つまり、スマホをスクロールしているユーザーの指を一瞬でも止めさせることではないか。そのためには、キャプションの前に、まず画像内の短い言葉で心を掴む必要がある。
「高橋さん、一言で伝わらねぇど、誰も見ねぇぞ」
彼の庄内弁の力強い言葉が、私の頭の中でリフレインしました。AIに「画像で注意を引く短い言葉」と「キャプションで詳しく説明する文章」という役割分担を明確に指示するプロンプトを考案し、試してみたところ、投稿のエンゲージメントは目に見えて向上したのです。
懐疑的な意見や、一見プロジェクトの邪魔に思えるような言葉の中にこそ、物事の本質を突くヒントが隠されている。組織で何かを変えようとするとき、あらゆる声に耳を傾けることの重要性を、高橋さんは教えてくれました。
終わりに:ツールが変えるのは作業、人が変えるのは未来
あのガイド記事に書かれている洗練されたノウハウの一つひとつは、実はこうした人間同士のぶつかり合い、対話、そして小さな気づきの積み重ねから生まれています。
AI導入の成功は、どのツールを選ぶか、どんなプロンプトを書くかといった技術的な話だけでは決してありません。それ以上に、関わる人々の「不安」や「プライド」といった心理的な壁をいかに乗り越え、彼ら自身を改革の「主役」にしていくかにかかっています。
AIは作業を変えることはできますが、会社の文化や人の心を動かし、未来を変えるのは、いつだって「人」の仕事です。
この記事を読んでいるあなたの職場にも、変化を恐れる佐藤さんや、責任感の強い鈴木部長、そして本質を突く高橋さんのような人がいるかもしれません。もしあなたがAI導入で壁にぶつかっているなら、一度ツールのことや効率化のことは忘れて、彼らの「心の声」に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。
きっとそこに、あなたのプロジェクトを前進させる、一番のヒントが隠されているはずです。