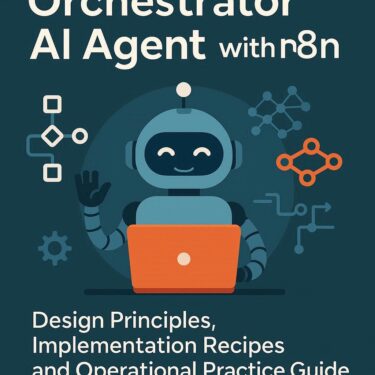AI導入の理想と現実―現場の抵抗を「推進力」に変えた、コミュニケーションの舞台裏
先日公開した記事、「AIエージェント時代の業務効率化ガイド」。あの記事では、AI導入を成功させるための「7つのステップ」や「KPI設計」といった、いわば地図を示しました。
AIエージェント時代の業務効率化ガイド|導入7ステップとKPI設計で成果を出す方法 生成AIを導入したものの、「チャットで質問するだけ」で終わっていませんか?「PoC(概念実証)は華々しかったが、現場に定着しない」「ツールが[…]
しかし、実際のプロジェクトという”航海”は、地図通りに進むことなんて、まずありません。そこには、計画書には書かれない生々しい人間ドラマがあり、予測不能な”嵐”が吹き荒れます。最新のAI技術や完璧な計画論だけでは、決して乗り越えられない壁がそこにはあります。
今日は、あの綺麗な地図の裏側で、私たちがクライアントと共に経験した、もっと泥臭くて、人間臭い「裏話」を少しだけお話ししようと思います。これは、ある地方の中堅製造業でAI導入プロジェクトを担当したときのこと。主役は、最新のAIではなく、現場で働く「人」でした。
最初の壁:「AIなんて、うちの仕事じゃ無理ですよ」
プロジェクトが始まって早々、私たちは最初の壁にぶつかりました。元記事で言うところの「ステップ1:業務の可視化」のフェーズです。キーパーソンとして紹介されたのは、業務課の佐藤さん(仮名)。30代の女性で、その部署の業務を知り尽くしたエースです。彼女の協力なくして、このプロジェクトは一歩も進みません。
意気揚々とヒアリングに臨んだ私に、彼女は開口一番、こう言いました。
「お話は伺いました。でも、うちの業務はAI化なんて無理ですよ。例外処理だらけで、マニュアル化できない部分がほとんどなんです。それに、今のやり方でもう何年も問題なく回っていますし…」
教科書通りの、見事なまでの”抵抗”でした。しかし、私はこの時、彼女の言葉の裏にある「本心」を読み解こうと必死でした。彼女は決して、変化を嫌うだけの保守的な人ではない。むしろ、自分の仕事に誇りを持ち、今のやり方で業務を守ってきた自負があるからこそ、得体の知れない「AI」という”侵略者”に強い警戒心を抱いているのだ、と。
ここでやってはいけないのが、「いえ、最新のAIならその例外処理も学習できます」とか「AIを導入すれば年間〇〇時間の工数が削減できるんですよ」といった正論で”論破”することです。それは火に油を注ぐだけ。相手は心を閉ざし、私たちは「現場を知らないよそ者」のレッテルを貼られて終わりです。
私はアプローチを180度変えました。
「佐藤さん、この業務フロー、すごいですね。こんなに複雑な手順を、どうやって皆さんに共有しているんですか?正直、ここまで整理されている現場は初めて見ました。このフロー自体が会社の資産ですよ」
まず、彼女の仕事を徹底的に肯定し、リスペクトを伝える。彼女が今まで築き上げてきたものを、私たちは壊しに来たのではなく、「もっと良くするため」のパートナーであることを理解してもらう必要がありました。
すると、彼女の表情が少しだけ和らぎました。「…まあ、色々トラブルがあって、そのたびに改訂してきただけですけど」
これが、厚い氷が溶け始めた、最初の瞬間でした。
巻き込みの極意:「AIの先生になってください」
信頼関係の小さな芽生え。これを大きな木に育てるためには、彼女を「やらされ仕事」の対象者から、「プロジェクトの当事者」へと引き込む必要がありました。元記事の「ステップ2:ユースケースの選定」と「ステップ4:プロトタイプの開発」は、まさにそのための重要なステップです。
私は、佐藤さんにもう一歩踏み込んだお願いをしました。
「佐藤さん、正直に言います。このプロジェクトは、佐藤さんがいないと絶対に成功しません。そこで、お願いがあるんです。私たちと一緒に作るAIの”先生”になっていただけませんか?」
「…先生、ですか?」
「はい。今のAIは、生まれたての赤んちゃんみたいなもので、業務のことなんて何も知らないんです。だから、佐藤さんが普段やっている仕事のやり方、判断の基準、気をつけているポイントを、一つひとつ教えてあげてほしいんです」
「AIに仕事を教える…」
この「AIの先生」という役割は、彼女のプライドを巧みにくすぐりました。「AIに仕事を奪われる」のではなく「AIを育てる」という構図に変わったことで、彼女の中にあった警戒心が、次第に好奇心へと変わっていったのです。
もちろん、すんなり進んだわけではありません。プロトタイプ開発では、技術担当の若手エンジニア△△さんと佐藤さんの間に、新たな壁が生まれました。
△△さん:「ここの業務ロジックは、APIを叩いて取得したJSONをパースして…」
佐藤さん:「…すみません、ジェイソン? パーカー? 横文字ばかりで、何を言っているのか全然…」
技術者と現場担当者の”言語”の違い。これはどんなプロジェクトでも起こりうることです。ここで私が果たした役割は「通訳」でした。
私:「△△さん、つまり『システムから取ってきたデータを、AIが分かる形に翻訳する』ってことですよね? 佐藤さん、今△△さんが知りたいのは、請求書の日付が複数あった場合に、どれを正とするか、というルールの部分なんです」
佐藤さん:「ああ、なるほど。それなら、基本は発行日が優先ですけど、特記事項に指定日があればそっちが正になりますね」
私:「△△さん、聞きましたか? 今の『特記事項があれば』という部分が、佐藤先生にしか教えられない、AIが学ぶべき重要な『例外ルール』ですよ」
地道な通訳作業を繰り返すうちに、最初はよそよそしかった二人も、次第に直接コミュニケーションを取るようになっていきました。佐藤さんが△△さんに業務の勘所を教え、△△さんがそれをAIのロジックに落とし込む。いつしか二人は、同じゴールを目指す最強のタッグになっていたのです。
数字の魔力:「部長、佐藤さんの残業が半分になりました」
プロトタイプは、ささやかながらも着実な成果を出し始めました。佐藤さんが担当していた問い合わせ対応業務の一部をAIが担うことで、彼女の作業時間が目に見えて減ってきたのです。
しかし、次なる壁は彼女の上司、業務部長の鈴木さん(仮名)でした。御年58歳、この道35年の大ベテランです。山形県鶴岡市出身の彼は、独特の庄内弁でこう言いました。
「んだがぁ…。なんかおもちゃみてぇなもんで遊んでるようにしか見えねでのぉ。そんなんで、本当に仕事が速くなるんだがぁ?」
鈴木部長のようなマネジメント層を説得する際、陥りがちな罠があります。それは、元記事で紹介したような「月間アクティブ率」だの「自動化率」だのといった、小難しいKPIレポートを見せてしまうことです。彼らが知りたいのは、そんな数字の羅列ではありません。
彼らが本当に知りたいのは、ただ一つ。「それで、俺の部下は楽になるのか?」です。
私は、鈴木部長に見せる資料を、たった一枚のシンプルなグラフに絞りました。
「部長、こちらをご覧ください。これが、AIのプロトタイプを導入する前の、佐藤さんの月の平均残業時間です。そして、こちらが導入後の残業時間。半分以下になりました」
鈴木部長は、グラフと私の顔を交互に見比べ、そしておもむろに口を開きました。
「おぉ…。そういや、佐藤さん、最近顔色がええど思っでだんだ。早ぐ帰れるようになったのがぁ。そんだら、ええごどだのぉ」
複雑な費用対効果の計算シートよりも、部下の残業時間が半分になったという、たった一つの事実。それが、誰よりも部下思いの部長の心を動かしたのです。
これは、KPI設計の重要な裏話でもあります。数字は使い方次第で”魔力”にも”罠”にもなります。「利用回数」だけを追いかければ、意味のない質問を繰り返すだけの不毛なAI利用が横行するかもしれません。「削減時間」を自己申告に頼れば、実態とかけ離れた、希望的観測の数字が独り歩きする危険性があります。
本当に価値のあるKPIとは、現場で働く人の「楽になった」「助かった」という実感に直結しているものなのです。
全社展開の落とし穴:「うちは、あの部署とは違う」
佐藤さんの部署での成功は、すぐに経営陣の耳に入りました。「素晴らしい! すぐに全社展開したまえ!」。トップダウンで号令がかかるのは、成功プロジェクトの常です。
しかし、これが最大の落とし穴でした。
私たちは、佐藤さんの部署で作り上げた成功パターン(テンプレート)を手に、意気揚々と他部署へ乗り込みました。しかし、そこで待っていたのは、以前の佐藤さん以上の冷ややかな反応でした。
「経理部のやり方を、そのまま営業に持ってこられてもね。うちは、ああいう定型業務ばかりじゃないんだよ」
「うちのシステムは特殊だから、そんな簡単な話じゃない」
一つの成功体験は、時に組織の油断を招きます。「標準化」という名の下に、各部署の個別事情を無視した「画一化」を押し付けようとしてしまうのです。
ここでの私たちの教訓は、「すべての部署に、その部署の”佐藤さん”がいる」ということでした。成功のテンプレートを押し付けるのではなく、再びゼロから始める覚悟で、各部署のエース担当者を探し出し、彼らの仕事へのリスペクトから始める。そして、彼らを新たな「AIの先生」として巻き込んでいく。
急がば回れ。この泥臭いコミュニケーションの繰り返しこそが、AIという新しい文化を組織の隅々にまで浸透させる、唯一の方法だったのです。
まとめ:AI導入の成否は、技術ではなく「人」が決める
元記事で解説した「7つのステップ」や「2つの型」、「4つのKPI」。これらは、AI導入という航海を成功に導くための、非常に有効な”地図”や”羅針盤”であることは間違いありません。
しかし、忘れてはならないのは、その船を動かしているのは、現場で働く一人ひとりの人間だということです。彼らの心の中にある、変化への不安、仕事への誇り、仲間への思いやり。そうした”感情”という名の天候を読まずして、航海を乗り切ることはできません。
AI導入プロジェクトの成否を最終的に分けるのは、最新のAIモデルの性能や、緻密なプロジェクト計画書ではありません。
あなたの隣にいる、少しだけ頑固で、だけど仕事に誇りを持っている「佐藤さん」の心を、どうすれば動かせるか。部下の幸せを誰よりも願っている「鈴木部長」に、何を伝えれば響くのか。
AIという最先端のテーマに取り組む私たちにとって、最も大切なスキルは、技術力以上に、相手の立場を想像し、寄り添い、共に汗をかく、極めて人間的なコミュニケーション能力なのかもしれません。
もし、あなたの会社でAI導入が思うように進んでいないのなら、一度、最新の技術トレンドを追いかけるのをやめて、現場の声にじっくりと耳を傾けてみてはいかがでしょうか。そこにこそ、プロジェクトを成功に導く、一番の近道が隠されているはずですから。