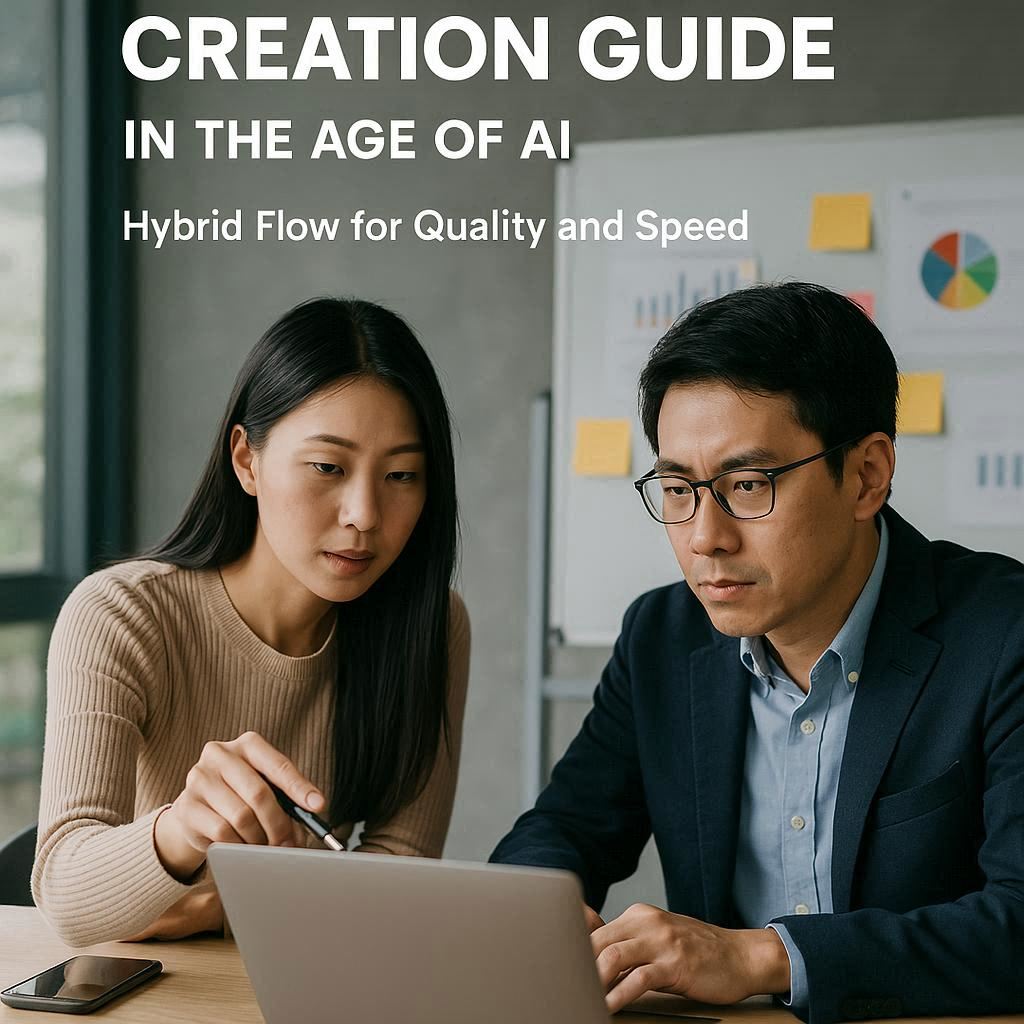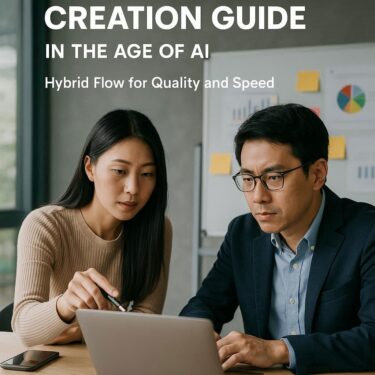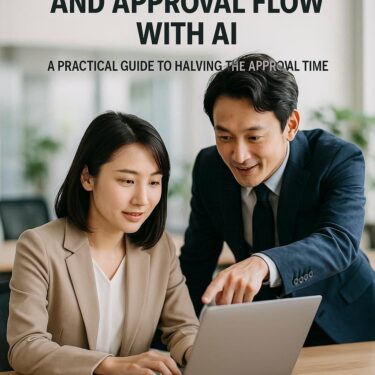AI導入の壁は「正論」だった?現場のホンネと向き合った、コンテンツ改革の舞台裏
先日、ありがたいことにご好評をいただいた「AI時代のSEOコンテンツ制作ガイド」という記事。あれは、あるクライアント企業で進めた、コンテンツ制作改革プロジェクトの知見を体系的にまとめたものです。
AI時代のSEOコンテンツ制作ガイド|質と速さを両立するハイブリッドフロー 「コンテンツの量も質も求められるのに、人手と時間はいつも足りない」。これは、現代のコンテンツマーケターや編集者が抱える共通の悩みではないでしょうか。市場には[…]
記事で紹介したフレームワークやチェックリストは、一見すると非常にロジカルで、これさえあれば誰でも高品質なコンテンツが作れるように見えるかもしれません。しかし、現実はそんなに甘いものではありません。
綺麗なフローチャートの裏側には、いつだって生身の人間の感情が渦巻いています。プライド、不安、縄張り意識、そして長年培ってきた仕事へのこだわり。新しいツールや正論だけを振りかざしても、人の心は動かないどころか、頑なに閉ざされてしまうことさえあるのです。
今回は、あの記事が生まれるまでの、決して表には出ることのない舞台裏をお話ししようと思います。AIという「黒船」に直面した現場の担当者やベテラン社員と、私がどのように向き合い、彼らの「行動変容」を引き出していったのか。これは、ツール導入の成功が、いかに泥臭いコミュニケーションの上になりたっているか、という生々しい記録です。
「私の仕事、なくなるんでしょうか?」警戒心から始まったプロジェクト
「来月から、コンテンツ制作にAIを本格導入します」
役員会議で承認されたプロジェクトのキックオフ。会議室に集まったのは、Webマーケティングを推進する若手メンバーと、長年、製品の技術広報を担当してきた方々でした。その中に、今回のプロジェクトのキーパーソンとなる佐藤さん(仮名・30代女性)がいました。
彼女は、技術部門とマーケティング部門の間に立ち、一人で黙々と質の高いコンテンツを作り続けてきた、いわば職人気質の担当者。その表情は、期待よりも明らかに不安と警戒心で曇っていました。
無理もありません。彼女からすれば、「AI導入」は自分の聖域に土足で踏み込まれ、「お前の仕事はもう古い」と宣告されたようなもの。キックオフの冒頭、私はあえてAIの強みではなく、弱点から話を切り出しました。
「まず、皆さんに誤解してほしくないのですが、AIは万能ではありません。平気で嘘をつきますし、実際の経験がないので、どこかで読んだような薄っぺらい文章しか書けません。正直、今のままでは使い物にならない代物です」
ざわつく会議室。私は続けます。
「この“使えない新人”を、皆さんの力で一人前に育て上げる。それが今回のプロジェクトの本当の目的です」
ミーティング後、佐藤さんが私の元へやってきました。
「あの…お話は分かりましたが、やっぱり不安です。AIがもっと賢くなったら、私の仕事は、いつかなくなるんじゃないでしょうか?」
彼女の目は真剣でした。ここで「大丈夫ですよ」と安易に返すのは逆効果です。私は、彼女の目を見てはっきりと伝えました。
「佐藤さんの仕事は、なくなりません。ただし、役割が変わります。これからは、記事を“書く”ことよりも、佐藤さんの頭の中にある“経験”や“知見”をAIに与え、出来上がったものを“監督”し、最終的な品質に責任を持つことが、新しい仕事になります。佐藤さんが監督で、AIは使いっぱしりの新人アシスタント。そう考えてみてください」
「私が、監督…」
彼女の表情が、ほんの少しだけ和らいだ気がしました。AIを「脅威」ではなく「部下」として位置づける。この認識の転換が、すべての始まりでした。
最初の壁:「コンテンツブリーフ」という名の“翻訳”作業
プロジェクトの最初のステップは、記事でも紹介した「コンテンツブリーフ(制作要件定義書)」の作成でした。誰に、何を、どのように伝え、どんな行動を促すのか。記事制作の設計図です。ロジカルに考えれば、これほど重要なものはありません。
しかし、現場にとっては、これが最初の大きな壁でした。
「こんなに細かい要件、今まで書いたことありません…。いつもは、技術の担当者と話して、『まあ、こんな感じで』で伝わってきましたから」
佐藤さんは困惑していました。彼女にとって、頭の中にある「こういう読者には、この表現が刺さるはずだ」といった“暗黙知”を、わざわざ言語化することは、これまで培ってきた自身の感覚を否定されるような、まどろっこしい作業に感じられたのでしょう。
ここで「ルールですから、書いてください」と正論を押し付けても、心が離れるだけです。私はアプローチを変えました。
「分かりました。じゃあ、まず1本、いつも通りに佐藤さんのやり方で記事を作ってみてください。その代わり、完成したら、僕の質問にいくつか答えてもらえませんか?」
数日後、彼女は質の高いドラフトを書き上げてきました。私はその記事をプロジェクターに映し出し、ブリーフの項目に沿って、一つひとつ質問を投げかけていきました。
「この記事で、読者に一番『なるほど!』と思ってほしい、核心の一文はどこですか?」
「それは、ブリーフで言うところの『コアメッセージ』ですね」
「読者がこの記事を読み終えた後、次に知りたくなることは何だと思いますか? 問い合わせでしょうか、それとも別の製品情報でしょうか?」
「それが、『CTA(次のアクション)』です」
「この記事は、どんなことで困っている人が検索すると思いますか? その人は、どんな言葉で検索するでしょう?」
「それが、『ペルソナ』と『検索意図』ですね」
この“逆コンパイル”のような対話を通じて、彼女は自らの頭の中で無意識に行っていた思考プロセスを、客観的に言語化していきました。それは、誰かから強制されたものではなく、彼女自身による「発見」のプロセスでした。
「なるほど…。私がいつも頭で考えていたことって、このブリーフの項目そのものだったんですね」
彼女のこの一言が、プロジェクトが大きく前進した瞬間でした。面倒な「やらされ仕事」だったブリーフ作成が、彼女の職人技をチームで共有するための「翻訳ツール」へと変わったのです。
「わしらの経験は、そんな簡単な言葉では語れん!」ベテラン技術者との共創
コンテンツの骨格はできましたが、魂を入れる作業はこれからです。記事の「6-2. 人間が付加すべき『経験』という名の価値」を実践するため、製造現場で「生きる伝説」と呼ばれるベテラン技術者の鈴木さん(60代)にヒアリングを申し込みました。もちろん、彼は庄内弁の使い手です。
AIが生成した、製品の特徴をまとめたドラフトを見せたとたん、鈴木さんの眉間に深いシワが刻まれました。
「なんだ、このペラッペラの文章は。AIだかなんだか知らねぇけど、こんなんでウチの技術が伝わるわけねぇべ。舐めでんのが?」
予想通りの反応です。鈴木さんのような職人にとって、効率化やテンプレート化は、技術や経験を軽んじる行為に他なりません。「E-E-A-Tが重要でして…」などという横文字の正論が通用する相手ではないことは、火を見るより明らかでした。
ここでの私の役割は、教えることではなく、「教えを請う」ことです。
「鈴木さん、おっしゃる通りです。この記事、ひどいですよね。正直、どこから手をつけていいか分からなくて…。どうか、先生として、この“ダメな新人”が書いた文章に赤入れをしていただけないでしょうか。新人に技術を教えるみたいに、お願いできませんか?」
プライドをくすぐられたのか、鈴木さんは少しだけ表情を和らげ、腕を組みながら画面を睨みつけました。
「んだがぁ…。まず、この『簡単に接続可能』ってどごだ。こごが一番大変なんだぞ、わがっか? こん時なぁ、ワッシャーの向きば間違えで、何台もダメにしたもんだ。夜中に社長さ電話して、こっぴどぐ怒鳴られたっけのぉ。その失敗談ば書かねば、誰も信用しねぇでや」
堰を切ったように、鈴木さんの口から溢れ出す言葉。それは、仕様書には決して書かれない、生々しい失敗談、試行錯誤のプロセス、感覚的なコツといった「経験」の塊でした。隣では、佐藤さんが必死にその言葉をメモしています。
AIが作った無味乾燥なドラフトは、鈴木さんの貴重な記憶を引き出すための、最高の「呼び水」となったのです。鈴木さんは、自分の技術や苦労が正しく伝わることに喜びを感じ、佐藤さんは、これまでリーチできなかった「本物の一次情報」を手に入れることができました。
AIが作った土台があったからこそ、ヒアリングの的を絞り、深い話を引き出せた。これこそが、人間とAIの「ハイブリッド」が生み出す真の価値だと確信した出来事でした。
レビューは“批判”じゃない。組織の壁を溶かした「感謝の可視化」
一次情報が加わり、記事の質は格段に上がりました。しかし、次の関門は「7. 3段階レビュー体制」の定着でした。品質を担保する生命線ですが、これもまた、組織の壁と人間の感情に阻まれます。
ある日、佐藤さんが浮かない顔で相談に来ました。
「鈴木さんにお願いして追記した部分を、マーケティングの担当者にSEOの観点で見てもらったら、『専門的すぎて分かりにくい』って修正依頼が来たんです。それを鈴木さんに伝えたら、『俺の言ったことを疑うのか』って、すごく怒られちゃって…」
片や、鈴木さんに話を聞くと、
「わしが話したごどば、なんでマーケの若造さ見せねばなんねなや。素人に何がわがんのだ」
典型的なセクショナリズムと、「レビュー=人格否定」という根深い誤解です。このままでは、部門間の断絶が深まるばかり。
そこで私が導入したのが、「役割分担の明確化」と「感謝の可視化」でした。
まず、レビューシートにそれぞれのレビューアの「役割」を明記しました。
- 専門チェック(技術部・鈴木様): 技術的な正確性と、現場のリアルさが伝わるか、という観点でのご確認をお願いします。
- SEOチェック(マーケ部・〇〇様): 専門知識のないお客様にも分かりやすい言葉になっているか、という観点でのご確認をお願いします。
「これは、どちらが正しいかという“批判”の場ではありません。それぞれの専門家が、この記事を“最強”にするための共同作業です」と、全員に伝えて回りました。
さらに、完成した記事の管理シートに、「貢献者」の欄を設けました。
「この記事の価値を高めたキーパーソン」
- リアルな失敗談の提供: 技術部 鈴木様(30年の経験がこの記事の信頼性を担保しています!)
- 分かりやすい図解の作成: マーケ部 佐藤様(複雑な構造が、この図で一目瞭然になりました!)
自分の貢献が具体的に認められ、感謝される。この小さな仕組みが、人々の意識を劇的に変えました。レビューは「面倒な指摘作業」から、「自分の専門性を発揮できる誇らしい共同作業」へと変わっていったのです。
行動変容の兆し:彼女が見せた「自走」の瞬間
プロジェクトが半年ほど経過した頃。新製品のコンテンツ企画会議で、私は静かに彼らのやり取りを見守っていました。
私が口火を切る前に、佐藤さんがごく自然にホワイトボードの前に立ち、あのコンテンツブリーフのテンプレートを書き出しました。そして、集まったメンバーに問いかけます。
「さて、今回の製品ですが、まずターゲットは誰にしましょうか? その人が一番知りたいことは何でしょう? それから、競合の記事をざっと見ましたが、私たちにしか書けない『体験談』が足りないように思います」
そして、彼女は会議室の隅に座っていた鈴木さんの方を向き、にっこりと笑って言いました。
「鈴木さん、この製品で一番苦労された時の話、またぜひ聞かせてください! あのヒリヒリするような失敗談、今回も絶対に記事に入れましょう!」
鈴木さんも、まんざらでもないといった表情で「おう、任せでけ」と力強く頷きました。
もう、私の出る幕はありません。私が伝えた「型」は、いつしか彼らの血肉となり、自分たちの言葉で、自らの力でチームを動かし始めていたのです。ツールが導入されただけではない、組織の「文化」が、確かに変わり始めた瞬間でした。
◇
「AI時代のSEOコンテンツ制作ガイド」に書かれたフローは、単なる制作マニュアルではありません。それは、異なる部署、異なる世代、異なる専門性を持つ人々が、同じゴールに向かって力を合わせるための「コミュニケーション・プロトコル」なのです。
AIは、人と人を分断するためにあるのではありません。むしろ、人と人を繋ぐための強力な「触媒」となり得ます。AIが作った無機質な「たたき台」があるからこそ、ベテランは自身の経験を語りやすくなり、若手はそれを構造化して世に届けることができる。
結局のところ、どんな改革も、その成否を分けるのは最新ツールの機能やスペックではないのです。現場で働く一人ひとりの不安やプライドと真摯に向き合い、彼らが「自分ごと」として前を向けるような、泥臭いコミュニケーションを積み重ねられるか。すべては、そこに懸かっているのだと、私は信じています。