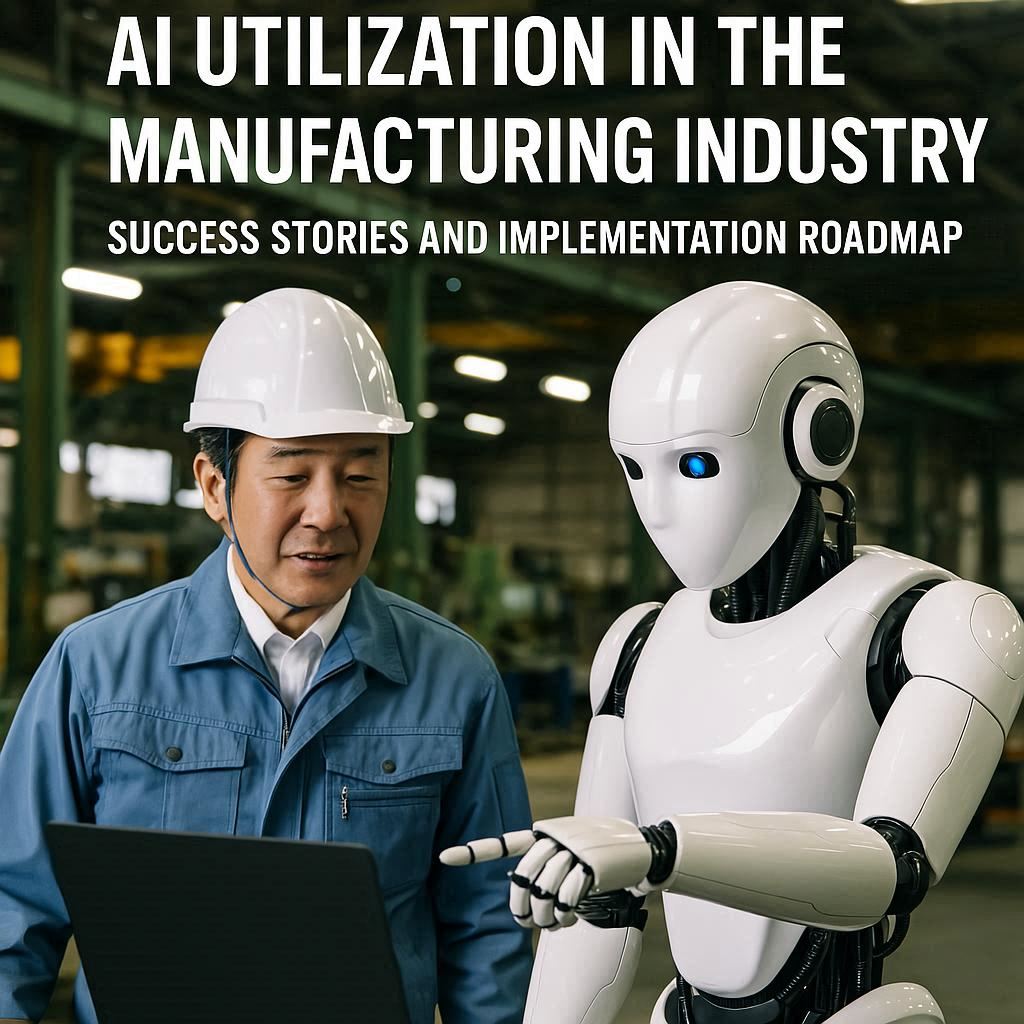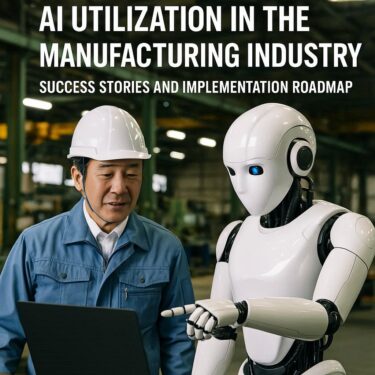「AI導入ガイド」には書けなかった、プロジェクトの本当の話
先だって公開した「製造業のAI活用完全ガイド」。おかげさまで多くの方にお読みいただき、たくさんの反響をいただきました。あの記事は、いわばAI導入という航海を成功させるための、いわば最新の「海図」です。進むべきルート、避けるべき岩礁、目指すべき港が記されています。
製造業のAI活用完全ガイド|成功事例と導入ロードマップ 「人手不足が深刻化し、熟練技術者のノウハウが継承できない」 「海外の競合に価格やスピードで負けてしまう」 「不良品の発生率がなかなか下がらず、コストを圧迫している」 […]
しかし、実際の航海は、海図通りには進みません。突然の嵐に見舞われ、船員が対立し、羅針盤が狂うことだってある。海図だけでは、荒れ狂う海を乗り越えることはできないのです。
今回は、あの海図には描くことができなかった、泥臭くて、ひどく人間臭い「航海日誌」の一部を、皆さんにご紹介したいと思います。これは、最新テクノロジーを導入する現場で繰り広げられた、マネジメントとコミュニケーションの、生々しい裏話です。
キラキラした成功事例の裏側で、私たちはどんな壁にぶつかり、どうやってそれを乗り越えてきたのか。これから改革の舵を取るあなたの、何かしらのヒントになれば幸いです。
最初の嵐:「AIで何とかしろ」という名の、”目的のない出航命令”
あのガイド記事の冒頭、「失敗しないための5つの条件」で、私はこう書きました。
条件1:目的の明確化 – 「AIで何をするか」より「何を解決したいか」
まったくもって正論です。しかし、プロジェクトの9割は、この正論とは真逆の地点からスタートします。ある日、社長室に呼ばれた私に、経営者はこう言いました。
「最近、業界紙でAIの特集ばかりだ。競合の〇〇も何か始めたらしい。ウチもすぐにAIで何かやれ。予算はつけるから」
これこそが、最も危険な「シーズ志向」の号令です。目的も、解決したい課題もない。ただ「AIをやること」が目的化してしまっている。このまま出航すれば、間違いなく遭難します。
経営者の頭の中は「AI=コスト削減、未来への投資」という漠然とした期待でいっぱいです。しかし、その熱量が現場に届くと、まったく違う温度に変わります。
案の定、現場のキーマンである工場長に話を振ると、返ってきたのは冷ややかな反応でした。
私:「社長、AIにえらい乗り気でして。何か現場の課題解決に使えないかと思ってるんですよ」
工場長:「…また始まったが。社長はいつもそうだ。流行りもんにすぐ飛びついで。こっちは毎日、目の前の生産で手一杯だっつーのに、新しいおもちゃば与えられても迷惑なだけだず」
彼の目には、明らかな「不信感」と「諦め」が浮かんでいました。「どうせ俺たちの仕事が奪われるんだろ」「面倒なことを押し付けられるだけだ」という声なき声が聞こえるようでした。
経営の「熱」と、現場の「冷」。この絶望的な温度差を埋めない限り、プロジェクトは一歩も前に進みません。
私がやったこと:全社説明会ではなく、「一人だけの作戦会議」
ここでやってはいけないのが、いきなり全社説明会を開いて「AIで会社はこう変わります!」とブチ上げることです。反発を招くだけです。
私が取ったアプローチは、徹底的な「個別撃破」でした。社長の「AIやれ」という命令は一旦、私のポケットにしまいます。そして、作業着に着替え、工場長の隣に立ち、ひたすら彼の話を聞くのです。
私:「工場長、最近どだなです? 社長、AIだAIだって騒いでっけど、現場は大変でしょ。私も昔、現場にいたがら、気持ちは少しはわがっつもりだず」
工場長:「んだず。いきなり言われても、何がなんだがわがんねしの。それに、ウチの品質検査、ベテランの佐藤さんが辞めだら、もう誰も同じレベルででぎねぐなる。そっちの方が問題だ」
…これです。彼が本当に困っている「課題」が出てきました。AIという言葉は一切使わず、ひたすら彼の「困りごと」に耳を傾ける。そして、少しだけ未来の話をします。
私:「もし、佐藤さんの“目”をカメラで覚えさせて、新人の田中君でも同じように検査ができるようになったら、工場長、少しは楽になりまかね?」
工場長:「…ほだなごと、でぎんなら、そりゃ助かるどもな…。んだども、機械なんがに、佐藤さんの“神業”がわがっもんだべが」
疑念の中に、ほんの少しの「期待」が混じりました。これが第一歩です。社長の「AIを導入しろ」という命令を、現場の「佐藤さんの技を残したい」という切実な願いに「翻訳」する。この翻訳作業こそが、私たちの最初の仕事なのです。
重要なのは、AIを主語にしないこと。あくまで主語は「現場のあなた」であり、AIはあなたの困りごとを解決するための「便利な道具」でしかない、というスタンスを貫くことです。
第二の壁:最強の抵抗勢力は、マニュアルにない”見えないルール”
ガイド記事では、こうも書きました。
条件4:現場の受容性 – テクノロジー導入は「人」が最大の鍵
プロジェクトが少し進み、外観検査AIのPoC(概念実証)が始まりました。最新のカメラとAIを導入し、現場のベテラン社員の方に協力をお願いして、不良品のデータを学習させていきます。
システムは順調に稼働し、テストでは高い精度を示しました。しかし、いざ本番のラインで動かしてみると、どうも結果が安定しない。AIが見逃すはずのない不良品が後工程で見つかったり、逆に良品を不良品だと判定したりするのです。
システムのログを見ても、パラメーターを調整しても原因がわからない。頭を抱えていた私に、一人のベテラン社員がボソッと言いました。
ベテラン社員:「おめさん、まだいたのが。こんだな新しい機械入れたって、おらだのやり方にはかなわねって」
私:「〇〇さん、何か気づいたことでもありますか? 正直、お手上げなんです。ぜひ、知恵を貸してください」
プライドを捨てて、弟子入りする覚悟で教えを乞いました。すると彼は、少し得意げにこう教えてくれたのです。
ベテラン社員:「はっはっh、こいだば長年の勘だ。…いいが、この製品はな、プレスした直後はちょっと歪んで見えんだ。んでも、30分もすっと馴染んで良品になる。おらだはそればわがってるがら、その場で判断しねで、一度保留にして後でまた見んだ。おめさんの機械、それば全部ハネでっぺ?」
…愕然としました。そんなルールは、作業標準書のどこにも書かれていません。完全に「暗黙知」。彼らの頭の中にしかない、長年の経験則だったのです。AIは正直ですから、学習したデータ通りに「歪んでいる=不良品」と判断していただけでした。
私がやったこと:スーツを脱ぎ、”共通言語”で話す
この一件で、私は自分の過ちを悟りました。会議室でヒアリングシートを埋めるだけでは、本当の現場は見えてこない。彼らが日々、何を考え、どんな工夫をしているのか。その「見えないルール」こそが、品質を支える宝の山だったのです。
翌日から、私はスーツを脱ぎ、会社から支給された作業着を着て、現場に立ち続けました。仕事の邪魔にならないように、しかし彼らの動きが常に見える場所で。そして、休憩時間には缶コーヒーを片手に、積極的に話しかけました。
私:「〇〇さんのその手際の良さ、見てて惚れ惚れしますよ。なんでそんなに早く判断できるんですか? ちょっとコツを教えてくださいよ」
最初は訝しげだった職人さんたちも、毎日顔を合わせるうちに、少しずつ心を開いてくれるようになりました。「このメーターがちょっと振れだら、こっちのバルブを気持ち…こんくらい…開げんなだ」「今日の材料は、いつもより湿気っから、乾燥時間を5分長ぐすんだ」など、次々と「マニュアル外のノウハウ」が出てくるようになりました。
私はそれをメモし、データとして記録し、AIのロジックに反映させていきました。これは、単なるシステム開発ではありません。現場の職人たちの「暗黙知」を、AIというツールを使って「形式知」に変換していく、共同作業なのです。
「AIに仕事を奪われる」と思っていた彼らが、「俺たちの技をAIに教えてやる」「俺たちの技が会社の財産になる」と意識を変えた瞬間、プロジェクトは一気に加速しました。
抵抗勢力だったはずのベテラン社員が、いつしか最高の協力者になっていたのです。
最後の罠:”小さすぎる成功”がもたらす、”大きすぎる期待”
多くの苦労の末、PoCは素晴らしい結果を出しました。特定の製品の外観検査において、ベテラン社員の目視を超える精度とスピードを達成したのです。
この成功は、すぐに経営陣の耳に入りました。そして、新たな嵐がやってきます。
経営者:「素晴らしいじゃないか! やはり私の目に狂いはなかった。よし、明日から全ラインにこのシステムを導入しよう! すぐに見積もりを出してくれ!」
現場:「…やっぱりな。あの機械が本格的に入ったら、俺たちの検査の仕事はなくなるんだ。次はどの仕事がなくなるんだろうな…」
最悪の事態です。PoCの成功が、経営陣には「過度な期待」を、現場には「深刻な不安」を同時に与えてしまったのです。スモールスタートの「小さな成功」は、両刃の剣。扱いを間違えれば、プロジェクト全体を切り裂いてしまいます。
ガイド記事では、こう書きました。
Step1: PoC(概念実証)フェーズ – 課題を絞り込み、効果を小さく試す
このステップで最も重要なのは、技術的な検証だけではありません。関係者全員の「期待値コントロール」こそが、真の目的なのです。
私がやったこと:「成功の翻訳」と「次の物語」の提示
私はすぐに、経営陣と現場、それぞれに向けた「翻訳」作業に取り掛かりました。
【経営陣への翻訳】
「今回の成功は、あくまで“実験室レベル”での話です。例えるなら、F1マシンがテストコースで最高速度を記録したようなもの。これを一般道で、誰もが安全に運転できるようにするには、エアバッグやブレーキ、燃費の改善など、やるべきことが山積みです。全社展開には、Aというデータの整備、Bというネットワークインフラの増強、そしてCという現場の運用トレーニングが必要です。そのための現実的なロードマップと予算案がこちらです」
ただ「できません」と否定するのではなく、成功を認めつつも、次のステップに進むための具体的な課題と計画をセットで提示する。これにより、経営者の熱量を「無謀な拡大」から「計画的な投資」へと導きます。
【現場への翻訳】
「皆さん、ご協力ありがとうございました! 皆さんがあのAIに“匠の技”を教えてくれたおかげで、あの単純で、目が疲れる検査作業から解放される目処が立ちました。これで空いた時間で、皆さんにしかできない、もっと高度な改善活動や、新しい設備の立ち上げといった、創造的な仕事に時間を使えるようになります。これは、皆さんの仕事を奪うものではなく、皆さんの価値をさらに高めるための武器なんです」
成功を「脅威」ではなく、明確な「メリット」として伝える。そして、PoCが終わった直後に、彼らを巻き込んで「次の課題」を考えるワークショップを開きました。「次は、どの作業を楽にしたいですか?」「このAI、他に何に使えそうですか?」と。
自分たちの成功体験を元に、次の未来を自分たちで描かせる。これにより、彼らは「変革の対象」から「変革の主体」へと変わっていきます。
終わりに:AI導入は、最も人間臭い仕事である
「製造業のAI活用完全ガイド」で書いたフレームワークやロードマップは、今でもプロジェクト成功のための普遍的な真理だと信じています。
しかし、そのフレームワークを動かすのは、ロジックやデータだけではありません。経営者の焦り、現場のプライド、変化への不安、成功への期待…。そうした、理屈では説明できない人間の「感情」のエネルギーです。
私たちの仕事は、AIという最新テクノロジーを駆使しながらも、実はそのほとんどの時間を、人と向き合い、対話し、時にはぶつかり、同じ船に乗ってもらうための泥臭いコミュニケーションに費やしています。
もし、あなたがこれから改革の荒波に漕ぎ出そうとしているのなら、ぜひ覚えておいてください。
最新の海図を手に入れることと同じくらい、いや、それ以上に大切なのは、船員たちの声に耳を傾け、彼らの心を理解しようと努めることです。
遠回りに見えるその航路こそが、あなたの船を目的地へと導く、唯一の道なのかもしれません。