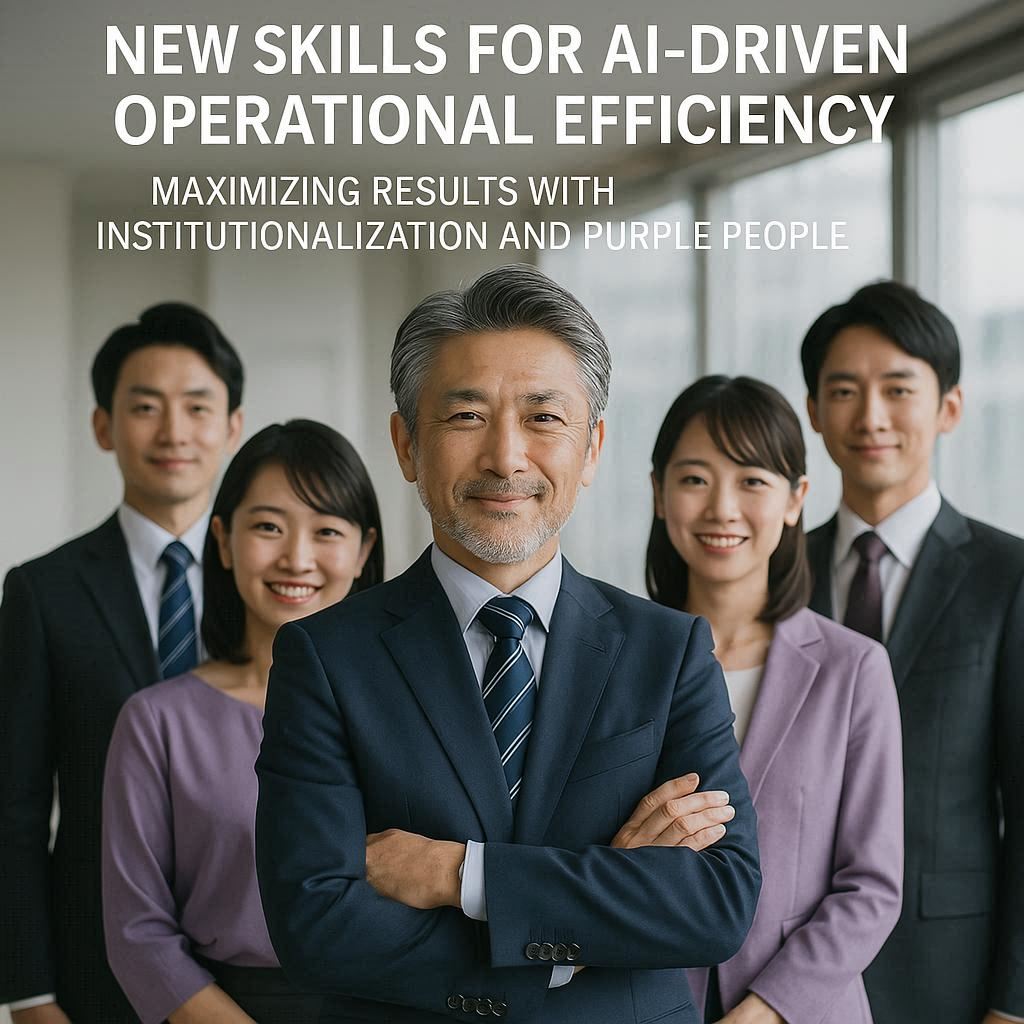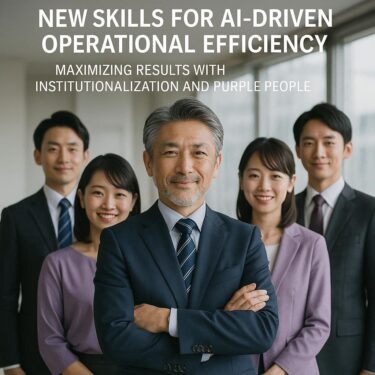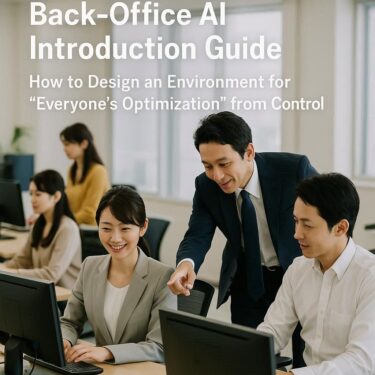AI導入のスキルの現実、そのギャップを埋めた「たった1枚の模造紙」の話
「AIで成果を最大化する新スキルとは」――先日の記事で、私はそんな大見出しを掲げました。AIを個人の「飛び道具」で終わらせず、業務の「仕組み」に組み込み、「成果を標準化」することの重要性を説いた内容です。
AIによる業務効率化の新スキルとは:仕組み化とパープルピープルで成果を最大化する 「あの人はAIを使いこなしていてすごい」――あなたの職場では、そんな声が聞こえてきませんか? 生成AIの登場で、私たちの働き方は静かに、しかし確実に変[…]
読者の方からすれば、「そんなの、うちの会社じゃ無理だよ」「理想論だ」と感じるかもしれません。ええ、その気持ちは痛いほど分かります。なぜなら、あの記事で綺麗に体系化した理論は、数々の現場で体験した、もっと泥臭く、人間臭い試行錯誤の末に生まれたものだからです。
今日は、あの記事の裏側にある、ある地方の中堅製造業での物語をお話ししようと思います。主役は、改革への熱意が空回りしがちな業務課の木村課長(40代)、優秀さゆえに現状を冷静に見つめ、どこか諦めを漂わせる担当者の佐藤さん(30代)、そして、工場の隅で黙々と機械を見つめる、現場一筋のベテラン、本間工場長(60代)です。
これは、最新技術を前にした人々の戸惑いと成長、そして、すれ違う想いを繋いだ「たった1枚の模造紙」を巡る、ささやかだけれど、とても大切な物語です。
第1章:すれ違う「効率化」の定義という名の、最初の壁
プロジェクトが始まった当初の会議室の空気は、今でも忘れられません。木村課長が、目を輝かせながら熱弁をふるっていました。
「AIを導入して、とにかく業務時間を短縮したいんです! 特に、毎日やっている資料作成や報告書業務を自動化して、みんなの残業を劇的に減らす。これが今回のゴールです!」
彼の言葉は力強く、前向きでした。しかし、その熱量とは対照的に、担当者である佐藤さんの表情は曇ったまま。彼女の心の声が聞こえてくるようでした。「また始まった…。課長の言う『自動化』って、具体的にどの業務のことなんだろう。私たちの仕事って、そんなに単純じゃない。イレギュラーな注文、急な仕様変更、そのたびに手作業で調整してるのに…。そんなところにAIなんて入れたら、例外処理ばかりで、逆に手間が増えるだけじゃないの?」
これこそが、多くの企業がAI導入で最初にぶつかる壁です。経営層や管理職が考える「個人の作業を速くする効率化」と、現場が日々直面している「複雑な業務全体の流れをどうにかしたいという課題感」。この認識のズレが、プロジェクトをあらぬ方向へと導いてしまうのです。
会議の後、私は佐藤さんと二人で話す時間をもらいました。
「佐藤さん、さっきの木村課長の話、どう思いましたか?」
案の定、彼女からはため息混じりの本音がこぼれました。
「正直、『またか…』って。AIって、魔法の杖じゃないですよね。私たちの部署が扱う受注処理って、お客様ごとに仕様が微妙に違うんです。だから毎回、過去の類似案件を探して、設計部に確認して、見積もりを再計算して…。その『探す』『確認する』っていう部分に一番時間がかかるのに、そこを無視して『報告書を自動化だ!』って言われても、根本的な解決にはならないんです。現場は混乱するだけですよ」
彼女の言葉に、このプロジェクトの本当の課題が隠されていました。それは、単純なツールの導入ではなく、彼女が「面倒くさい」と感じている、属人化された複雑な業務プロセスそのものにメスを入れることだったのです。
第2章:「翻訳者」の不在が引き起こす悲劇
後日、木村課長は意気揚々とITベンダーを連れてきました。会議室のスクリーンには、最新AIツールの華やかなデモ画面が映し出されます。自動でグラフが生成され、流暢な文章が紡ぎ出される様子に、木村課長は「すごい!これだよ、これ!」と大興奮。
しかし、佐藤さんをはじめとする現場メンバーの反応は、真逆でした。皆、スクリーンを呆然と眺め、「…で、これを私たちのあのドロドロした業務に、一体どうやって使うんですか?」という心の声が、会議室の空気を重くしていました。
ビジネスサイドの要求(木村課長)と、テクノロジーの可能性(ITベンダー)。この二つの言語が、通訳不在のまま飛び交っている。これは、プロジェクトが失敗する典型的なパターンです。
私はそっと木村課長に耳打ちし、ITベンダーの方に少し席を外してもらうようお願いしました。そして、がらんとした会議室で、ホワイトボードの前に全員を集めたのです。
「皆さん、一旦ツールのことは忘れましょう」
私はペンを手に取り、こう問いかけました。
「木村課長、このプロジェクトで解決したい、一番の『痛み』は何ですか? 佐藤さん、今の業務で、一番『もう、うんざり!』と感じる瞬間はいつですか?」
この問いかけが、魔法の言葉でした。抽象的な「効率化」から、具体的な「業務の課題」へと、一気に議論の焦点が切り替わったのです。
「うーん、痛みか…。やっぱり、月末の報告書のために、あちこちから数字を集めてくるのが本当に大変で…」と木村課長。
「私は、お客様から『あの時の仕様と同じやつ』って言われた時に、過去の膨大な資料から該当のものを探し出す作業ですね。あれで半日潰れることもあります…」と佐藤さん。
記事で書いた「パープルピープル」という存在は、最初から組織にいるわけではありません。こうした地道な対話を通じて、ビジネスの課題と技術の可能性を繋ぐ「翻訳」の重要性に気づき、現場の担当者自身がその役割を担っていく。そのための環境を作ることこそ、私の仕事なのだと改めて感じた瞬間でした。
「パープルピープル」という言葉は、ビジネスとテクノロジーのスキルを兼ね備えた人材を指す概念として、デロイト トーマツ グループなどで提唱されています。「青(ビジネス)」と「赤(テクノロジー)」を融合した「紫色の人材」という比喩が由来です。
https://www.deloitte.com/jp/ja/services/consulting/perspectives/human-resources-ai-era.html
出典:デロイト トーマツ グループ「AI時代に求められる人材とは」
第3章:魔法の言葉と「たった1枚の模造紙」
議論が具体的な業務課題に向かい始めた時、新たな壁が立ちはだかりました。「いや、でもウチの業務は本当に複雑で、マニュアル化なんて無理ですよ」という、長年染みついた固定観念です。
その重い空気を破ったのは、これまで黙って話を聞いていた、本間工場長でした。彼はゆっくりと立ち上がると、穏やかな庄内弁で口を開きました。
「木村課長、そだなごど言うても、わがんねでの。佐藤さん、あんたが毎日やってる仕事で、一番時間のかかる仕事、なんだっけが?」
突然指名された佐藤さんは、少し驚いたように答えました。
「え…と、A部品の受注処理ですね。お客様ごとに仕様が違うので、過去の類似案件を探して、設計部に確認して…」
「んだが。そんじゃ、その仕事の流れ、この紙さ書いでみでけろ。箇条書きでいいさげ。わだしにもわがるように」
本間工場長が指さしたのは、私が用意しておいたA1の大きな模造紙でした。記事で言うところの「標準作業手順書(SOP)」ですが、そんな小難しい言葉は使いません。ただの「仕事の流れを書いた模造紙」です。
佐藤さんは戸惑いながらも、マーカーを走らせ始めました。
- お客様から注文書(メール)が届く
- 過去の類似案件を共有フォルダから探す
- 見つからなければ、設計部の鈴木さんに確認の電話をする
- …
書き進めるうちに、彼女の頭の中で暗黙知として存在していた業務プロセスが、みるみる可視化されていきました。何が「入力」で、どんな「処理」と「判断」があり、最終的に何が「出力」されるのか。
それを見ていた木村課長の目が、カッと見開かれました。
「え、佐藤さん、ここの確認、毎回鈴木さんに電話してたのか!? この判断基準、共通化できるんじゃないか?」
AIに仕事を任せるには、まず人間が自分たちの仕事の構造を理解し、言葉で説明できなければなりません。この「たった1枚の模造紙」が、それまでバラバラだったチームの認識を一つに繋ぐ、共通言語になったのです。技術的な議論の前に、まず自分たちの足元を見つめ直す。AI導入の本質は、実はこんな地味な作業の中に隠されています。
第4章:最高の「学び」としての失敗
業務プロセスが見える化したことで、プロジェクトは一気に加速しました。佐藤さんが書き出した「過去の類似案件を探す」というプロセスに、AIを試験的に導入することになったのです。
しかし、現実はそう甘くありません。早速、佐藤さんが作ったプロンプトを試すと、AIは自信満々に、まったく関係のない10年前の案件や、コストを完全に無視した特殊仕様の案件を「これが類似案件です」と提示してきたのです。いわゆる「ハルシネーション(もっともらしい嘘)」です。
その結果を見た木村課長の肩が、がっくりと落ちました。
「ほら、やっぱりAIは使えないじゃないか…」
佐藤さんも「だから言ったのに…」と下を向いてしまい、会議室には再び重い空気が流れました。
私は、ここぞとばかりに割って入りました。
「木村課長、これは失敗じゃありません。最高の『学び』です! 我々は今日、『AIに何を探せと指示するだけでは不十分で、何を探してはいけないか、というルールも教える必要がある』という、非常に重要な知見を得たんですから!」
記事で解説した「ガードレールの設定」や「制約条件の提示」は、こうした実践的な失敗から生まれるのです。
すると、その言葉に反応するように、本間工場長がポンと膝を打ちました。
「ミズさんの言う通りだの。失敗しねでの、良ぐなるわげがね。佐藤さん、気にすんな。今度は、『5年以内の案件で、標準部品を7割以上使ってるものだけ探せ』って条件さ付けでみだら、どんだべ?」
この工場長の一言が、チームを救いました。失敗を個人の責任として責めるのではなく、チームの学びとして次に繋げる。経営トップが「心理的安全性が大事だ」といくら唱えても、現場のリーダーが具体的な行動でこうして示さなければ、文化として根付くことはありません。この日、チームは技術的なスキルだけでなく、失敗から学ぶという、もっと大切なスキルを手に入れたのです。
第55章:評価の壁を越え、「仕組み」を讃える文化へ
小さな成功と失敗を繰り返しながら、最終的にA部品の受注処理にかかるリードタイムは、平均で30%も削減されました。これは大きな成果です。しかし、プロジェクトが終盤に差しかかった頃、新たな、そして非常に根深い問題が顔を出しました。
それは、佐藤さんの評価です。
確かに、彼女自身の作業時間は短縮されました。しかし、その空いた時間で彼女がしていたのは、より精度の高いプロンプトの開発や、他のメンバーでも使えるような手順書の更新といった、「仕組みを作る」ための裏方作業でした。従来の評価制度では、こうした間接的な貢献は個人の成果としてカウントされにくく、目に見える数字として表れにくいのです。
ある日の1on1で、佐藤さんがぽつりと本音を漏らしました。
「正直、時々、割に合わないなって感じることがあります。業務が楽になったのは周りの人たちで、私はなんだか、新しい雑用が増えただけのような気がして…」
この声を聞き逃してはならない。私はすぐに木村課長と、その上司である事業部長(50代)を交えた会議の場を設けました。事業部長もまた、現場上がりのベテランで、温かみのある庄内弁を話す方でした。
「今回の成果は、紛れもなく佐藤さんの『仕組み作り』への貢献が大きい。しかし、今の評価制度のままでは、彼女の頑張りが正当に評価されにくい構造になっています」
私の説明を聞き、事業部長は深く頷きました。
「んだな。佐藤さん、いっつも大変そうだもんなぁ。木村、こんただごどは、ちゃんと評価してやんねばまいねど。個人の成果だけじゃねぐ、チーム全体の底上げさ貢献したごどを評価する仕組み、早急に考えろ」
鶴の一声でした。この一言をきっかけに、人事部も巻き込んだ議論が始まり、評価項目に「業務プロセスの標準化・改善への貢献度」という一文が加えられることになったのです。記事で書いた「評価制度の再設計」は、机上の空論ではありません。現場のリアルな声と、それを拾い上げる中間管理職の動き、そして最終的に決断する経営層のリーダーシップ。この三位一体があって初めて、組織は変わることができるのです。
結論:AIは、組織の強さと弱さを映し出す「鏡」である
あの記事で私が伝えたかったことの本質は、結局のところ、この物語の中にすべて詰まっています。AI導入とは、単なるツール導入プロジェクトではありません。それは、自分たちの仕事のやり方、コミュニケーションの癖、評価のあり方といった、組織の文化そのものを見つめ直す「組織改革プロジェクト」なのです。
AIという最新技術の鏡は、チームの連携が取れていない部分、長年見て見ぬふりをしてきた非効率、そして特定の個人に依存する属人化というリスクを、良くも悪くも容赦なく映し出します。
しかし、その鏡に映った自分たちの姿から目をそらさず、対話を重ね、試行錯誤を続けた先には、本当の意味での「ゆとり」が生まれます。そして、佐藤さんのように、日々の作業から解放されたメンバーが、より創造的で、付加価値の高い「仕組み作り」へとその能力を発揮し始めるのです。
あの工場で、佐藤さんがおずおずと書き始めた「たった1枚の模造紙」。あれが、彼らの組織の未来を変える、大きな第一歩でした。
あなたの職場にも、きっとまだ誰も気づいていない「1枚目の模造紙」が、眠っているはずです。