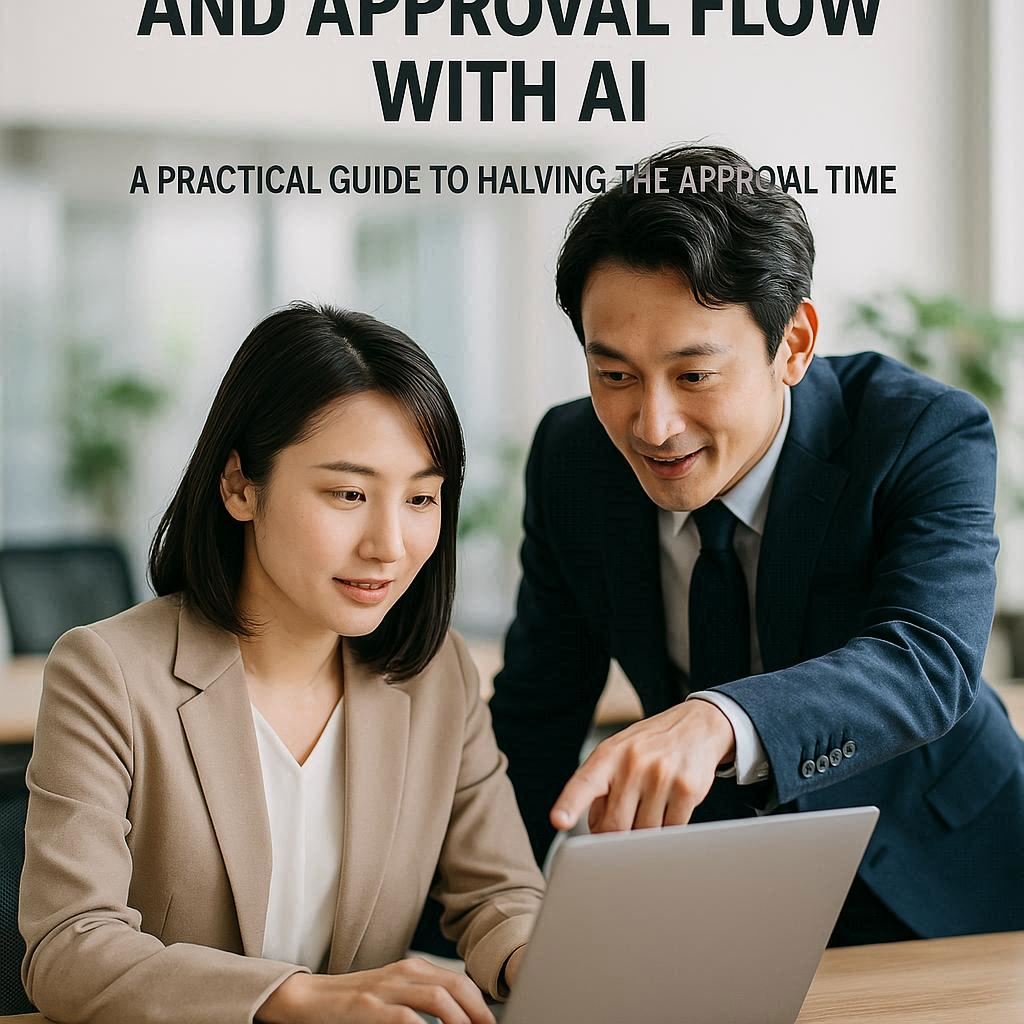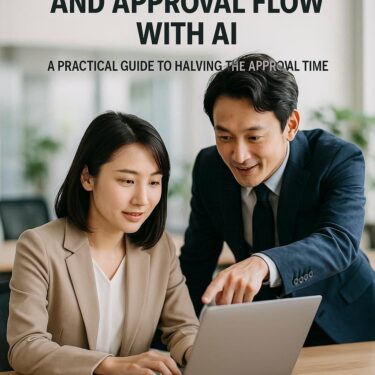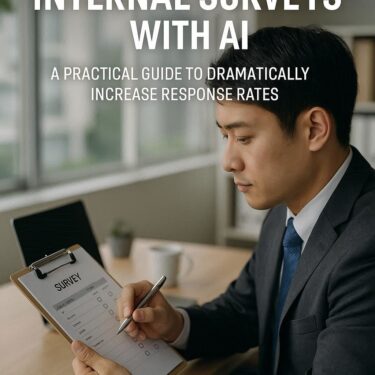AI導入の「きれいごと」の裏側。稟議改革で私が戦った「見えない壁」の話
先日、AIを活用して稟議・承認フローを劇的に改善する方法について、体系的な記事を執筆しました。あの記事は、いわば理想を詰め込んだ「設計図」です。しかし、皆さんが本当に知りたいのは、設計図通りにいかない現場で、一体何が起きていたのか、ではないでしょうか。
AIで稟議・承認フローを自動化|決裁時間を半減させる実践ガイド はじめに:あなたの会社の稟議は、なぜいつも遅れるのか? 「提出した稟議が、どこで止まっているのか分からない」「承認者ごとに指摘されるポイントが違い、何度も[…]
今回は、あの華やかな成功事例の裏側で繰り広げられた、もっと泥臭く、人間くさい物語をお話ししようと思います。これは最新ツールの導入事例というより、変化を恐れる人々の「心」と、長年染み付いた「習慣」という見えない壁に、一人の担当者と共に挑んだ記録です。
主役は、この改革の推進担当に任命された、入社8年目、企画部の佐藤さん(30代女性)。そして、彼女の前に立ちはだかる、長年現場を支えてきたベテランの部長たち。
もしあなたが今、社内改革の孤独な戦いの最中にいるなら、この話はきっと、あなたの心を少しだけ軽くするはずです。
第1章:最初の壁 – 「どうせまた、新しいおもちゃだろ?」という冷めた視線
プロジェクトのキックオフの日。私が外部の専門家として会議室に入ると、そこには重苦しい空気が漂っていました。推進担当として紹介された佐藤さんは、緊張で顔がこわばっています。彼女の視線の先には、腕を組み、明らかに「どうせまた上からの押し付けだろ」という顔をした各部署の部長たちが座っていました。
特に、製造部門を半世紀近く支えてきた御年65歳の高橋部長は、このプロジェクトの最大の壁になるだろうと、一目でわかりました。彼は、キックオフの場でこう言い放ったのです。
「稟議なんてのはな、一枚一枚に重みがあんだ。ハンコば押す時にゃ、それだけの覚悟も伴う。なんでもかんでも、早ければいいってもんじゃねぇんだ」
その一言で、会議室の空気は完全に「抵抗」の色に染まりました。佐藤さんは、この分厚い壁を前に、完全に途方に暮れている様子でした。
最初の1on1で、彼女は堰を切ったように話し始めました。
「皆さん、全然協力的じゃないんです。AIって言っただけで、SF映画みたいに思ってるのか、逆に『自分たちの仕事がなくなる』ってひどく警戒されたり…。特に高橋部長が怖くて、何を話せばいいのか…」
私は静かに頷きながら、こう切り出しました。
「佐藤さん、いきなり『AIで全社の業務を効率化します!』なんていう正論をぶつけても、長年守ってきたやり方を変えるのは誰だって怖いんですよ。高速道路を造りますと言われても、自分の家が立ち退き対象だったら、素直に喜べないでしょう? まずは、我々が『敵』じゃないことを証明しないといけない。特に、高橋部長にはね」
「敵じゃないこと…ですか?」
「そうです。そのためには、まず彼の懐に飛び込む必要がある。高橋部長が、今一番困っていることは何だと思います? 稟議について、彼が一番時間を取られていること、一番イライラしていることは何でしょう?」
私の戦略は、正論で組織全体を動かそうとするのではなく、まず「個別撃破」と「味方作り」から始めることでした。そして、その最初のターゲットは、最も手ごわい反対派の急先鋒、高橋部長です。
しかし、彼をいきなり説得しようなどとは考えません。彼の「困りごと」に徹底的に寄り添うのです。
後日、私は佐藤さんと共に高橋部長のもとを訪れました。AIの話は一切せず、ひたすら彼の話を聞きました。そして、頃合いを見計らってこう尋ねたのです。
「部長、最近、若手の方から上がってくる稟議で、差し戻しが増えていませんか? 部長がおっしゃりたい重要なポイントと、彼らが書いてくる内容に、少しズレがあるんじゃないかと感じることがあるのですが…」
その瞬間、高橋部長の険しい表情が、ほんの少しだけ緩んだのを私は見逃しませんでした。
改革の第一歩は、壮大な構想を語ることではありません。目の前にいる「たった一人」のどうしようもないペイン(苦痛)を見つけ出し、それを解消することに全力を注ぐこと。組織からの信頼残高は、そうやって地道に貯めていくしかないのです。
第2章:突破口は「叩き台」にあらず。承認者の「判断疲れ」を癒すことから
当初のプロジェクト計画では、元記事のフェーズ①で紹介したように、申請者向けの「稟議書作成支援機能」から始める予定でした。AIが稟議書の叩き台を自動で作ってくれる、という機能は派手で分かりやすく、多くの社員にメリットを感じてもらいやすいと考えたからです。
しかし、高橋部長をはじめとする管理職へのヒアリングを重ねるうちに、計画を変更すべきだという確信が芽生えました。本当に疲弊しているのは、稟議を「書く側」以上に、毎日何十件もの稟議に目を通し、判断を下す「承認する側」だったのです。
ある日の高橋部長との雑談。彼は山のような書類の束を前に、大きなため息をつきました。
「毎日こんげな量の書類さ目ぇ通すの、正直しんどいんだでの。若ぇのが書いでくる稟гиは、結局何が言いたいのさっぱりわがんねぇ時もあっでの。全部読まねばなんねぇし、かと言って、いちいち呼びつけで聞く時間ももったいねぇしな」
チャンスだ、と私は思いました。
「部長、もしこの10ページの稟議書の要点が、最初の1ページに『目的』『費用対効果』『一番のリスク』の3行でまとまっていたら、どうです?」
高橋部長は、キツネにつままれたような顔で私を見ました。
「…そりゃ、助かるな。どこば重点的に見ればいいのが、すぐわがっからの」
この一言で、私はプロジェクトの優先順位を大胆に切り替える決断をしました。「申請者の手間を省く」という価値よりも、まず「承認者の認知負荷を減らす」という価値を提供することを最優先する。
すぐに、私たちはシンプルなプロトタイプを開発しました。稟議書のファイルをドラッグ&ドロップすると、AIが瞬時に内容を解析し、「1分で読める要約」「想定されるリスク3点」「過去の類似案件との比較」を画面に表示するだけのツールです。
私はこのツールを高橋部長のPCにインストールし、こう説明しました。
「部長、これはAIが勝手に承認するシステムではありません。あくまで、部長の『判断』を助けるための、優秀な秘書だと思ってください。読む時間を短縮して、考える時間を作るための道具です」
半信半疑だった部長が、初めてそのツールを使った時の驚いた顔を、私は今でも忘れません。彼が「これは使える」と心から実感した瞬間でした。
影響力の大きい人物が「これは便利だ」と体感すること。それが、組織全体を動かす何よりのエンジンになります。高橋部長は、自分が楽になったことで、部下たちにも「おい、あれ使ってみろ。稟議出す前に、AIで要約とリスクをチェックしてもらえ。そしたら俺の確認も早くなる」と、自然に利用を促すようになったのです。
最強の反対者から、最強の推進者へ。彼の変化が、プロジェクトが大きく前進する転換点となりました。
第3章:データが暴いた「聖域」- 承認ルートに潜む本当のボトルネック
プロトタイプの効果が口コミで広がり、プロジェクトは本格導入のフェーズへと移行しました。次に私たちが取り組んだのは、元記事のフェーズ③にあたる「分析・改善」です。過去数年分の稟議データをAIで分析し、プロセス全体のどこに滞留が起きているのかを可視化しました。
そして、データは残酷な事実を突きつけました。
「…このデータを見ると、決裁ルートの最終段階、〇〇常務のところで必ず3〜4日間、流れが滞留しています」
佐藤さんが、青い顔で分析レポートを指さしました。〇〇常務は、誰もが認める切れ者ですが、同時に非常に慎重で、彼の決裁が下りずに頓挫したプロジェクトは数知れず。社内では一種の「聖域」として、誰もその判断の遅さに意見できる者はいませんでした。
「データでボトルネックだと分かっても、どうやってあの方に『もっと早く承認してください』なんて言えばいいんでしょうか…」
佐藤さんが再び壁にぶつかった時、意外な助け舟を出してくれたのは、他ならぬ高橋部長でした。彼は、私たちの会議にいつの間にか顔を出すようになっていたのです。
「ああ、常務は昔からそうだからのぉ。石橋を叩いで、叩いで、叩き割っちまうくらい慎重な人だ。わだしも若い頃、よく待たされだもんだ」
私は二人に言いました。
「犯人探しをしたいわけじゃないんです。常務が『なぜ』そこで時間をかけているのか、その理由をデータで探ってみませんか? おそらく、彼は毎回同じようなポイントで悩み、確認に時間を要しているはずです」
私たちの戦うべき相手は「人」ではなく、「プロセスの欠陥」です。
「誰が遅いか」ではなく、「なぜ遅くなるのか」に焦点を当てる。私たちは、常務のところで滞留した稟議の種類をAIで追加分析しました。
結果は、驚くほど明確でした。彼が特に時間をかけていたのは、「法務関連のリスク」と「外部委託先の信頼性評価」に関する項目が含まれる稟議だったのです。そして、それらの稟議の多くは、申請段階でその部分の情報が不足しているケースがほとんどでした。
原因が分かれば、対策はシンプルです。私たちは〇〇常務を責めるのではなく、彼を助けるための仕組みを提案しました。
- 稟議テンプレートの「法務リスク」「委託先評価」の欄を、より具体的な必須項目に変更する。
- 該当する稟議は、常務に回る前に、必ず法務部門の事前チェックを入れるフローを組み込む。
常務への報告の仕方も工夫しました。
「常務のご判断時間を少しでも短縮するため、申請段階で関連情報をより充実させる仕組みを導入いたしました。これにより、今まで以上に本質的なご判断に集中していただけるかと存じます」
彼は、自分の判断が遅いことを指摘されたのではなく、自分の判断を助ける仕組みができたと理解し、この提案を快く受け入れてくれました。
データは、人を責めるために使うのではありません。声なきプロセスの「欠陥」を明らかにし、仕組みで解決するために使うのです。個人の問題から組織の課題へと視点を転換させること。それこそが、改革を前に進めるための鍵でした。
最終章:文化になった「AI稟議」と、一人の担当者の成長
プロジェクト開始から1年。あの稟議AIは、すっかり社内に定着しました。
差し戻し率は7割減少し、平均決裁時間は半分以下に短縮。数字上の成果はもちろんですが、それ以上に大きな変化が組織に生まれていました。
かつて最大の抵抗勢力だった高橋部長は、今や「AI稟議のエバンジェリスト」です。新任の管理職に「昔は稟議書ば読むのが憂鬱だったけどの、今では要点だけ見ればいいさげ、本当に楽になったもんだ。お前もちゃんと使えよ」と、自身の経験を語って聞かせています。
そして、何よりも変わったのは、このプロジェクトを最後までやり遂げた佐藤さんでした。
彼女はもう、周りの顔色をうかがうだけの担当者ではありません。データとロジックを武器に、他部署の部長たちと堂々と渡り合い、臆することなく改善提案をリードする存在へと成長していました。
プロジェクトの完了報告会を終えた後、二人でささやかな打ち上げをしました。
「本当に、ありがとうございました。最初の頃はどうなることかと思いました。AIという言葉だけで、みんなが壁を作ってしまって…。でも、今なら分かります。結局はAIがどうこうじゃなくて、一人ひとりが何に困っていて、どうすれば楽になるかを、ちゃんと考えることだったんですね」
彼女の晴れやかな顔を見て、私は心から嬉しくなりました。
「その通りです。僕の仕事は、AIというちょっと便利な『翻訳機』を使って、皆さんの言葉にならない困りごとを、解決策という言葉に翻訳する手伝いをしただけですよ。この改革の本当の主役は、佐藤さん、あなたです」
AI導入や業務改革の成功は、華麗なテクノロジーによってもたらされるのではありません。それは、一つ一つの地道なコミュニケーションと、相手の立場を想像する人間力の積み重ねの先に、ようやく見えてくるものです。
もしあなたが今、組織を変えようと一人で戦っているのなら、この泥臭い裏話を思い出してください。正論を振りかざすのではなく、目の前の人の「困りごと」に寄り添うこと。そして、改革のプロセスを通じて、あなた自身が成長する物語をデザインすること。
それこそが、どんな高度なAIにも真似できない、変革を成功に導く唯一の道筋なのですから。