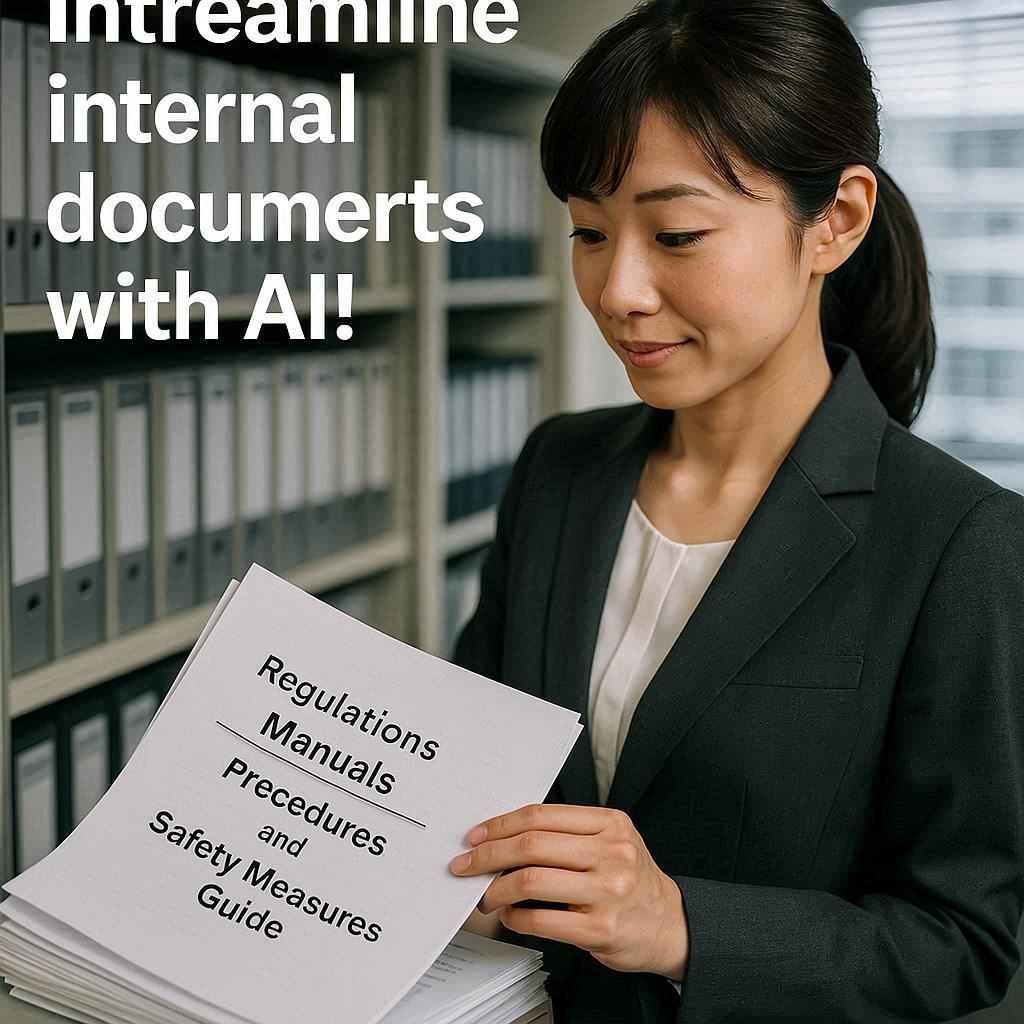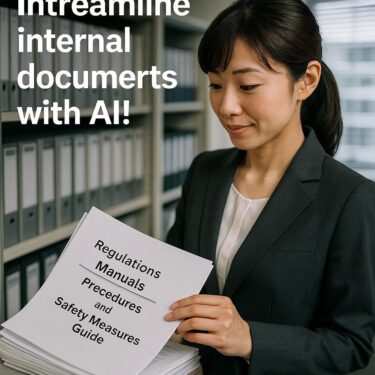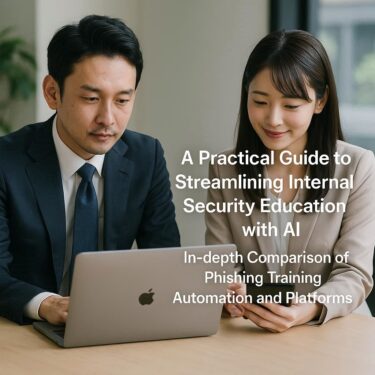AIマニュアル作成、現場が動かない理由と、心を動かすコミュニケーション術
先日公開した『AIで社内文書を劇的に効率化!規定・マニュアル作成の手順と安全対策ガイド』という記事、ありがたいことに多くの方にお読みいただいています。記事では、それぞれ特徴が異なるAIツールをリレー方式で使いこなし、効率よくマニュアルを作成するというフローをご紹介しました。
AIで社内文書を劇的に効率化!規定・マニュアル作成の手順と安全対策ガイド はじめに:「作成に時間がかかる」「更新が追いつかない」その悩みをAIで根本解決へ 「この業務のマニュアル、どこかにありましたっけ?」「最[…]
しかし、です。
現実のプロジェクトは、あんなに綺麗に進むことなんて、まずありません。ツールの導入は簡単でも、人の心と組織の文化を変えるのは、一筋縄ではいかない。むしろ、本当の仕事はそこから始まると言ってもいいでしょう。
今日は、あの記事の裏側で、私が実際にクライアントの皆さんと共に格闘した、泥臭くて人間味あふれる「もう一つの物語」をお話ししようと思います。これは、ツールを導入するだけでは決して変わらない、現場の「心理」と「行動変容」を巡る、マネージメントとコミュニケーションの記録です。
第一の壁:『便利そうだけど、私の仕事が増えるだけ』という静かな抵抗
その会社は、創業70年を超える、地方の優良製造業でした。長年培われた職人の技と、紙ベースの緻密な管理体制が強み。しかし、その「強み」が、変化への大きな足かせにもなっていました。
今回のプロジェクトの担当者に任命されたのは、入社8年目の佐藤さん(30代)。真面目で責任感が強く、現場からの信頼も厚い、まさにエース級の人材です。AIによるマニュアル作成の効率化というテーマに、彼女の上司である鈴木課長(40代)は乗り気でした。
「すごいですね! これで長年の課題だったマニュアルの形骸化が解決できますよ! 佐藤さん、頼んだよ!」
しかし、私の隣で説明を聞いていた佐藤さんの表情は、どこか晴れません。初回の打ち合わせが終わった後、彼女は私にそっと尋ねました。
「あの…結局、AIに指示を出すための動画を撮影したり、AIが作った文章が正しいか全部チェックしたり、最後は体裁を整えたり…って、私の作業が増えるだけじゃないでしょうか? 今までのやり方の方が、慣れている分、速いかもしれません…」
これです。これが、多くの現場で最初にぶつかる、最も本質的で、そして最も厄介な壁です。
「効率化」という美しい言葉の裏で、担当者は「新しいやり方を覚える負担」「AIの不確実性」「結果への責任」という三重苦を直感的に感じ取っているのです。
ここで、「いや、AIを使えば最終的には楽になりますよ」と正論を振りかざすのは最悪の一手。彼女の不安を無視して進めれば、プロジェクトは必ず「やらされ仕事」になり、魂のないマニュアルが量産されるだけでしょう。
私は、PCを閉じ、彼女にこう問いかけました。
「佐藤さん、ありがとうございます。その視点が一番大事なんです。逆に教えてください。今、佐藤さんがやっているマニュアル作成の仕事で、一番『面倒くさい』とか『正直、これは自分の仕事じゃないよな』って思う部分って、どこですか?」
彼女は少し驚いた顔をしましたが、ぽつりぽつりと話し始めました。
「…そうですね、一番は、各部署のベテランの方々にヒアリングして回ることです。皆さん忙しいので、なかなか時間を取ってもらえなくて。それに、人によって言うことが違ったり、専門用語ばかりで、それを誰にでも分かる言葉に翻訳するのが本当に大変で…」
「なるほど。つまり、一番大変なのは『情報を集めて、翻訳する』作業なんですね」
「はい、そうです。そこだけで、全体の8割くらいの時間がかかっている気がします」
「もし、AIがその『情報を集めて、翻訳する』作業の8割を肩代わりしてくれるとしたら、どうでしょう? 例えば、ベテランの田中さんがPCを操作している様子を、許可をもらって15分だけ動画で撮らせてもらう。その動画をAIに放り込んだら、自動で手順とスクリーンショット付きの草案が出てくる。佐藤さんは、その草案を元に、田中さんに『ここ、AIはこう言ってますけど、合ってますか?』と確認するだけで済む。これなら、負担は減りそうですか?」
佐藤さんの目に、少しだけ光が差したのが分かりました。
「…それなら、できるかもしれません。ヒアリングより、ずっと楽です」
大切なのは、「AIで全部やります」という魔法の言葉ではなく、「あなたの一番嫌な仕事を、AIに押し付けましょう」という、現実的な提案です。彼女の負担を理解し、共感し、具体的な解決策を「一緒に」考える。この対話こそが、彼女を「やらされ担当者」から「プロジェクトの当事者」へと変える第一歩なのです。
第二の壁:『ウチのやり方は特殊だから』という職人のプライド
佐藤さんの協力も得られ、いよいよ現場での素材収集が始まりました。ターゲットは、製品検査工程のマニュアル。この工程のヌシ的存在が、勤続40年の大ベテラン、斎藤さん(60代)です。
早速、佐藤さんが録画した操作動画を元に、AIに手順書の下書きを作らせました。記事で紹介した通り、驚くほど整った、論理的な手順書がわずか数時間で完成。意気揚々と、私たちは斎藤さんの元へ向かいました。
「斎藤さん、AIでマニュアルの元ネタを作ってみました。これ、見ていただけますか?」
斎藤さんは、老眼鏡ごしに資料をじっと眺め、一言、こう言い放ちました。
「んだばて、こげな教科書通りにはいがねでの。この部品はな、季節によって微妙に伸び縮みすっさげ、ゲージの当て方も変えねばねんだ。そげなこと、AIさわがんのが?」
(だけど、こんな教科書通りにはいかないんだよ。この部品はな、季節によって微妙に伸び縮みするから、ゲージの当て方も変えなければいけない。そんなこと、AIにわかるのか?)
出ました。これが「暗黙知の壁」です。標準化された手順書は、イレギュラーな対応や、言葉にならない「勘」や「コツ」を削ぎ落としてしまいます。そして、その「勘」や「コツ」にこそ、現場の職人さんたちは誇りを持っているのです。
ここで「ですが、標準化しないと品質が安定しません」と反論するのは、彼らの誇りを踏みにじる行為に他なりません。
私は、すかさず身を乗り出しました。
「斎藤さん、まさにそれです! その『季節による当て方の違い』こそ、我々が一番知りたいことで、AIに覚えさせたい会社の『宝』なんです。申し訳ないんですが、斎藤さんに、このポンコツAIの『先生』になってもらえませんか?」
「先生…? わだすがか?」
(先生…? 私がかい?)
「はい。このAIは、言われたことしかできません。なので、『夏場は、ゲージを少し内側から滑らせるように当てる』とか、『冬の朝イチは、部品が冷え切ってるから、一呼吸待ってから測る』とか、斎藤さんが当たり前にやっている『コツ』を、言葉にして教えていただきたいんです」
プライドを傷つけられると思っていた斎藤さんの表情が、みるみるうちに和らいでいくのが分かりました。彼は「先生」という言葉に、自分の存在価値を認められたと感じたのでしょう。
その日から、斎藤さんは実に協力的になりました。私たちは彼の横について、彼のつぶやく「コツ」をICレコーダーで録音し、それをAIでテキスト化。AIが作った無機質な手順書の「注意書き」の欄に、斎藤さんの生きた言葉がどんどん追記されていきました。
記事でスマートに書いた「ステップ6:レビューと実機検証」の裏では、いつもこんな人間臭いやり取りが繰り広げられています。抵抗勢力を「敵」と見なすか、「知恵袋を持つ先生」と見なすか。この視点の転換が、プロジェクトの成否を分けるのです。
第三の壁:『セキュリティはどうなってるんだ?』という最後の砦
プロジェクトが軌道に乗り始めた頃、最後の砦が立ちはだかりました。情報システム部門です。
「新しいクラウドのAIツールを使うだど? わけわがんねツールさ、ウチの製造ノウハウば入れで大丈夫なんだがの? 漏れたらどだなすんねや」
(新しいクラウドのAIツールを使うだと? わけのわからないツールに、ウチの製造ノウハウを入れて大丈夫なのか? 漏れたらどうするんだ)
情シスの高橋課長(50代)の指摘は、至極もっともです。彼らは会社全体の情報を守る責任を負っています。彼らの懸念を無視して、プロジェクトを進めることはできません。
ここでの鉄則は、ツールの機能説明から入らないこと。まず、彼らの「不安」をすべて吐き出してもらうのです。
「高橋課長、ご指摘ありがとうございます。我々もセキュリティが最重要だと考えています。恐れ入りますが、課長が懸念されている点を、箇条書きで構いませんので、すべて教えていただけないでしょうか。我々がそれを一つ一つクリアできるか、ご一緒に確認させてください」
高橋課長は、ホワイトボードに「情報漏洩」「不正アクセス」「ID管理の煩雑化」「利用データの学習利用」といった懸念点を書き出していきました。
私たちは、そのリストに対して、記事の「第5章:セキュリティとガバナンス」で解説した内容を、一つずつ丁寧に、彼らの言葉で説明していきました。
- 「情報漏洩」に対しては、「動画撮影は、個人情報や機密情報が映り込まないダミー環境で行うというルールを徹底します」
- 「不正アクセス」に対しては、「利用するツールは、二要素認証が設定できるものに限定し、アクセス権限も佐藤さんと鈴木課長だけに絞ります」
- 「利用データの学習利用」については、「今回使うツールの利用規約を確認し、入力したデータがAIの学習に使われない設定(オプトアウト)が可能なことを確認済みです」
技術的な説明をするのではなく、「具体的な運用ルールを一緒に作る」という姿勢を示すこと。彼らを「許可を出すお役所」ではなく、「プロジェクトの安全を守るパートナー」として巻き込むことで、彼らは頑なな門番から、頼れる味方へと変わってくれるのです。
変化の瞬間:小さな成功体験が、組織を動かす
数週間後、佐藤さんと斎藤さんがタッグを組んで作り上げた、初の「AI+職人ハイブリッドマニュアル」が完成しました。従来なら2ヶ月はかかっていたものが、わずか2週間でドラフト完成。しかも、斎藤さんの「暗黙知」がふんだんに盛り込まれた、かつてないほど実践的な内容です。
私は、この成果を役員会で私が華々しく発表するのではなく、ある仕掛けをしました。
それは、各部署のマニュアル担当者を集めた小さな報告会を開き、佐藤さん自身にプレゼンをしてもらうことでした。
「私がやったのは、斎藤さんの隣で操作動画を撮ったことと、AIが出してきた草案の日本語を少し直したことだけです。今まで一番大変だったヒアリングと翻訳作業のほとんどを、AIがやってくれました。おかげで、斎藤さんと『もっとこうした方が分かりやすい』という、本来一番大切な部分に時間を使うことができました」
彼女自身の言葉で語られる成功体験は、どんな立派なプレゼンよりも説得力がありました。報告会の後、他の部署の担当者たちが、次々と佐藤さんの元に集まってきました。
「佐藤さん、うちの部署でもやってみたいんだけど、どうすればいい?」
「その動画撮るのって、スマホでも大丈夫?」
鈴木課長がトップダウンで「やれ」と言っても動かなかった現場が、一人の担当者の小さな成功体験によって、自発的に動き始めた瞬間でした。
記事に書いたようなスマートなフレームワークや最新ツールは、確かに強力な武器です。しかし、その武器を振るうのは、いつだって「人」です。
新しいことへの不安、変化への抵抗、自分の仕事へのプライド。そうした現場一人ひとりの感情に寄り添い、対話を重ね、小さな成功を共に喜び、次のステップへと導いていく。AI導入のプロジェクトは、最新技術を扱う一方で、実はこれ以上ないほど人間臭い、泥臭い仕事なのです。
もし、あなたがこれからAI導入や業務改革に取り組むのであれば、ぜひ思い出してください。本当の課題は、技術仕様書の中にはなく、現場で働く人々の心の中にあるということを。そして、その心を開く鍵は、正論ではなく、共感にあるということを。