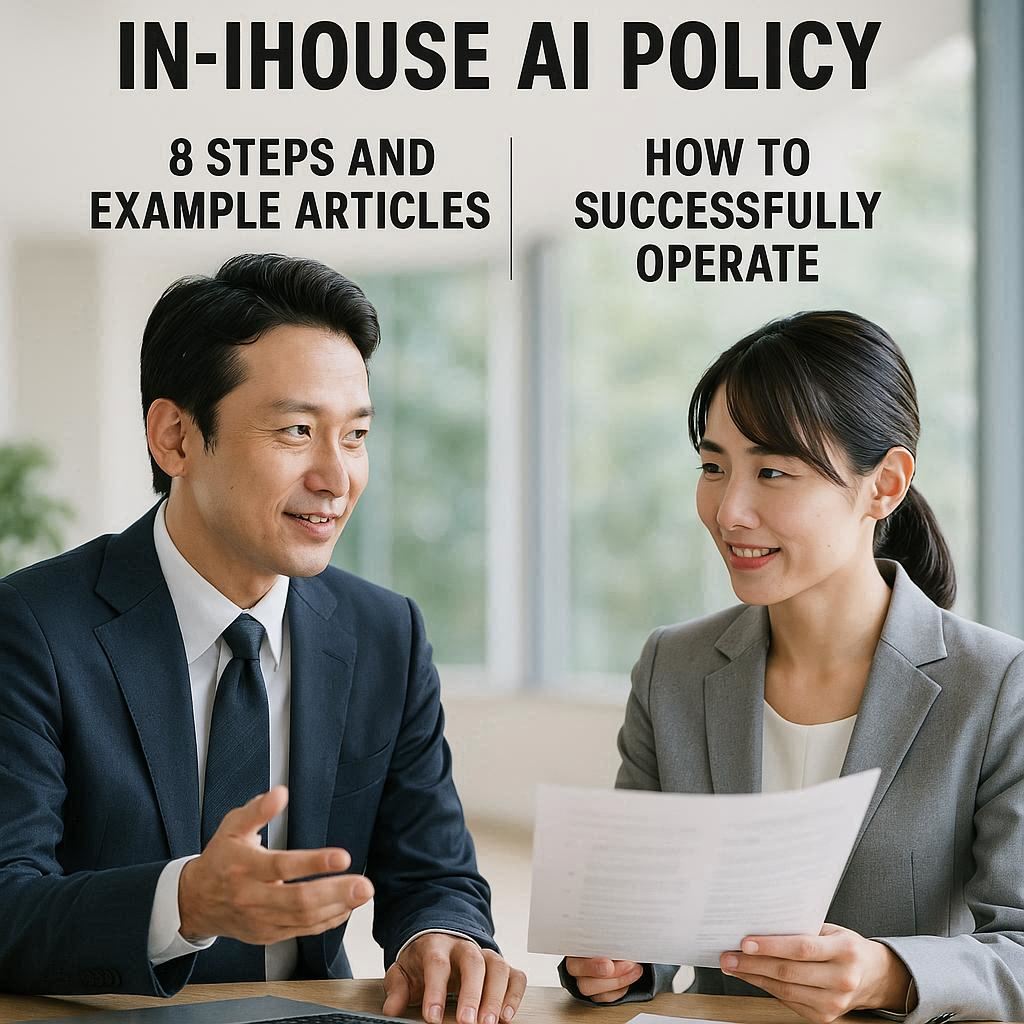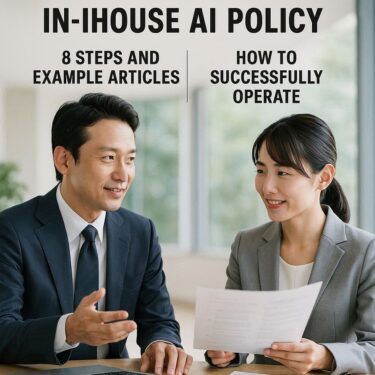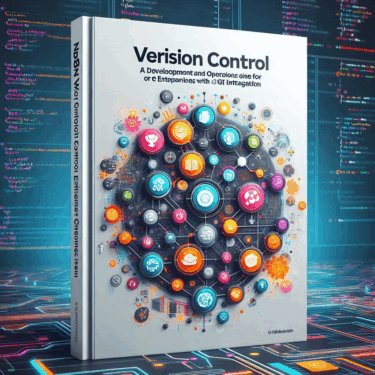AIポリシー策定の壁、「きれいごと」の裏側で本当に起きていたこと
先日公開した「社内AIポリシー策定ガイド」の記事、おかげさまで多くの方に読んでいただけたようです。あの記事は、いわば「理想の航海図」。ステップ通りに進めば、安全な港にたどり着けるように設計したつもりです。
【雛形あり】社内AIポリシー策定ガイド|策定8ステップと条文例、運用を成功させる秘訣 生成AIの登場により、多くのホワイトカラー業務が劇的に効率化される可能性が現実のものとなりました。文章作成、情報収集、データ分析、プログラ[…]
しかし、実際の航海は、いつも凪(なぎ)とは限りません。突然の嵐、見えない岩礁、そして何より、船員たちの不安や反発という「船内の嵐」が待ち構えています。
今日は、あの整然としたガイド記事の裏側で、私たちがクライアント企業の皆さんと共に体験した、もっと泥臭く、人間臭い「もう一つの物語」をお話ししようと思います。これは、ルール作りの現場で本当に起きる、マネジメントとコミュニケーションの苦労話。机上の空論ではない、生々しい奮闘の記録です。
「また禁止ですか?」凍り付いた会議室と、一枚の付箋
ある製造業のクライアントでのこと。AIの積極活用を目指す経営層の意向を受け、情報システム部の若手課長と、各部署から選抜されたメンバーでAIポリシー策定プロジェクトが始まりました。私もその支援役として参加していました。
プロジェクトの推進役を任されたのは、入社10年目の佐藤さん(仮名・30代女性)。非常に優秀で、AIの可能性にも熱い思いを持つ、真面目な担当者です。彼女は完璧な資料を用意し、プロジェクトのキックオフ会議に臨みました。
「本日は、生成AI利用におけるリスクと、その対策としてのポリシー策定の重要性についてご説明します。情報漏洩、著作権侵害、ハルシネーション…」
佐藤さんがリスクを列挙するたびに、会議室の空気が少しずつ重くなっていくのが分かりました。そして、製造部門を長年束ねてきた還暦過ぎの木村部長(仮名)が、腕を組んだまま、重い口を開きました。
「佐藤さんよ。んだって、そげなもんでがんじがらめに縛られて、仕事になんねべ。現場はな、もっと自由でねば、いい知恵も出ねもんだ。また『禁止』『禁止』って、新しい鎖ば増やすだけだんねのが?」
庄内弁の朴訥(ぼくとつ)な、しかし芯のある言葉に、他のメンバーも頷きます。「確かに…」「結局、何も使えなくなりそうですね」。佐藤さんの顔から血の気が引いていくのが見えました。彼女がやろうとしていることは正しい。しかし、伝え方が「正論」すぎたのです。
このままでは、プロジェクトは初日から座礁する。私はすかさずホワイトボードの前に立ち、一枚の大きな付箋を貼りました。そして、マジックでこう書いたのです。
「禁止リスト」ではなく、「安全な遊び方マニュアル」を作る。
「木村部長、おっしゃる通りです。新しい技術を鎖で縛ったら、宝の持ち腐れになります。今回のプロジェクトの目的は、皆さんが安心してAIという新しいオモチャで遊べるように、『この遊び方ならケガしないよ』というガイドブックを作ることなんです。どうせなら、みんなでワクワクするようなルールを作りませんか?」
続けて、こう提案しました。
「まず、皆さんが『AIでこんなことできたら面白いのに』『実はこっそりこんな風に使ってみた』という話を、良いことも悪いことも含めて全部出してみませんか?犯人捜しはしません。そこから『じゃあ、どうすれば安全にできるか』を考えましょう」
この一言で、会議室の空気が変わりました。「実は、報告書の構成案を作らせたら、結構使えて…」「海外の部品メーカーとのメールで、翻訳機能を使ってみたんだよな」。少しずつ、本音が漏れ始めました。
ここで得た教訓は、人は「禁止」という言葉にアレルギー反応を示すということです。特に、自分の仕事にプライドを持っている現場のプロフェッショナルほど、その傾向は強い。彼らを動かすのは、トップダウンの「命令」ではなく、「自分たちの仕事がもっと面白くなるかもしれない」という「期待」なのです。
完成しないルールブック。「ドラフト地獄」からの脱出劇
現場の協力も得られ、プロジェクトは少しずつ前進し始めました。しかし、次なる壁は、策定チームの内部にありました。「ドラフティング(草案作成)」の段階で、私たちは深刻な「沼」にはまってしまったのです。
情報システム部や法務部のメンバーは、当然ながらリスク管理のプロです。彼らはあらゆる可能性を想定し、条文に盛り込もうとします。
「『主要な指示(プロンプト)を記録する』とありますが、『主要』の定義は?すべてのプロンプトを記録すべきでは?」
「例外申請のフローですが、承認権者は部長決裁だけでなく、役員決裁も必要ではないでしょうか?」
「このツール、利用規約を細かく読むと、準拠法がアメリカのデラウェア州法に…」
議論はどんどん細かくなり、ポリシーのドラフトは日に日に分厚く、複雑になっていきました。最初は乗り気だった佐藤さんも、各方面からの矢のような指摘を受け、疲れ果てていました。
「すみません…、また修正指示が。これじゃ、いつまで経っても完成しません。現場からは『まだできないのか』と催促されていて…」
完璧を目指すあまり、一歩も前に進めなくなっていたのです。私はチーム全員を集め、宣言しました。
「皆さん、100点のルールを初めから作るのは諦めましょう。」
一瞬、全員がキョトンとしていました。
「これは、一度作ったら変えられない石版の法律を作るプロジェクトではありません。AIの世界は、来月には常識が変わっているかもしれない。だから、まずは60点でいいから世に出しましょう。 そして、実際に使いながら、みんなで70点、80点に育てていくんです。そのための『パイロット運用』期間であり、そのための『定期見直し』条項なんですから」
そして、こう付け加えました。
「完璧なルールで事故をゼロにするのは不可能です。本当に重要なのは、事故が起きたときにパニックにならず、正直に報告でき、組織として迅速に対応できる『体制』と『文化』を作ること。ガチガチのルールは、むしろ問題を隠蔽する文化を生みます。『困ったらすぐ相談できる』。その安心感こそが、最強のリスク管理だと思いませんか?」
この方針転換で、チームは息を吹き返しました。「まずやってみよう」という空気が生まれ、複雑だった条文は、現場の誰もが理解できるシンプルな言葉に書き換えられていきました。
教訓は、ポリシー策定はウォーターフォール開発ではなく、アジャイル開発で進めるべきだということです。完璧な設計図を引くことに時間を費やすより、最低限動くもの(Minimum Viable Product)を早く市場(社内)に出し、ユーザー(社員)からのフィードバックで改善を繰り返す。この考え方が、変化の速い技術への対応には不可欠なのです。
誰も投稿しない「成功事例共有チャンネル」の気まずい沈黙
紆余曲折を経て、ポリシーは無事に全社展開されました。私たちは、ポジティブな活用を促すため、社内SNSに「AI活用事例共有チャンネル」を立ち上げました。「皆さんのちょっとした工夫が、会社の大きな力になります!」と華々しく告知したものの…現実は非情でした。
一週間経っても、投稿はゼロ。佐藤さんが投稿した「皆さん、活用していますか?」という呼びかけに、「いいね」が数個つくだけ。気まずい沈黙が続きます。
「どうして誰も投稿してくれないんでしょうか…。やっぱり、みんなAI活用に興味がないんでしょうか…」
落ち込む佐藤さんに、私は尋ねました。
「佐藤さん自身は、最近AIで何か便利なこと、ありました?」
「え?あ、はい。海外の技術文献を要約させたら、リサーチ時間がすごく短縮できて…」
「それ、すごく良い事例じゃないですか!なぜ投稿しないんです?」
「いえ、こんなこと、当たり前すぎて…。もっとすごい、画期的な使い方じゃないと、投稿するのは恥ずかしいかなって…」
原因はこれでした。誰もが「すごい成功事例を投稿しなきゃ」と心理的なハードルを高く設定してしまっていたのです。さらに言えば、「自分の部署のノウハウを、他の部署にタダで教えたくない」という部署間の壁も、見えない要因として存在していました。
そこで、私たちは作戦を180度変えました。
- 「すごい事例」ではなく「ゆるい事例」から始める:
まず私と佐藤さんで、「今日のランチ、AIに相談してみた(笑)」「時候の挨拶、考えるの面倒だからAIに作らせた」といった、業務と関係ないような、どうでもいい投稿を連発しました。チャンネルの「いいね」ボタンを「ウケるね」ボタンに変えたりもしました。 - 失敗談を歓迎する:
「こんなプロンプト書いたら、トンチンカンな答えが返ってきて笑った」「AIに煽られた話」など、あえて「失敗談」を投稿しました。これにより、「完璧じゃなくていいんだ」という安心感が生まれました。 - 名指しで褒めて、巻き込む:
会議などで「そういえば〇〇部のAさんが、データ分析で面白い使い方してたらしいですよ!」と聞きつけたら、すかさずチャンネルで「Aさん、ぜひ皆にも教えてあげてください!」とメンション付きで投稿。持ち上げられたAさんは、少し照れながらも投稿してくれます。その投稿には、チーム全員で「すごい!」「真似します!」とコメントの嵐。この「小さな承認の連鎖」が、次の投稿者を生むのです。
この地道な活動を1ヶ月ほど続けた頃、チャンネルの雰囲気がガラリと変わりました。「この作業、AIで自動化できませんかね?」という相談が投稿され、それに対して別の部署の人が「このプロンプト試してみては?」とアドバイスするような、自然なコミュニケーションが生まれ始めたのです。
最後の教訓。文化は、仕組みだけでは醸成されない。 それは、誰かが意図的に「最初の熱」を生み出し、地道に薪をくべ続けることで、初めて燃え広がるもの。特に、日本企業特有の「完璧主義」や「部署の壁」を乗り越えるには、トップダウンの指示よりも、こうしたボトムアップの「楽しそうな雰囲気づくり」が、時として何倍も効果的なのです。
結論:ルール作りは、人の心と向き合う仕事
あの整然とした「社内AIポリシー策定ガイド」の記事は、いわば完成した料理のレシピです。しかし、その裏側には、食材(現場の声)を集め、火加減(議論の進め方)を調整し、アク(反発や停滞)を取り除き、味見(パイロット運用)を繰り返すという、実に人間臭い調理のプロセスがありました。
AIという最先端の技術を導入する話なのに、結局、私たちが最も時間を費やしたの は、テクノロジーそのものではなく、人の不安や期待、プライド、そして縄張り意識と向き合うことでした。
AIポリシーの策定は、単なる文書作成プロジェクトではありません。それは、会社の文化そのものを問い直し、変革していくための、壮大なコミュニケーション・プロジェクトなのです。
もしあなたが今、同じような壁にぶつかっているのなら、思い出してください。その壁の向こうにいるのは、あなたと同じように、自分の仕事に誇りを持ち、変化に少しだけ臆病になっている「人間」です。
正論で壁を壊そうとせず、まずは扉をノックして、彼らの話を聞くことから始めてみてはいかがでしょうか。きっと、あなたが思っているよりもずっと面白い「もう一つの物語」が、そこから始まるはずです。