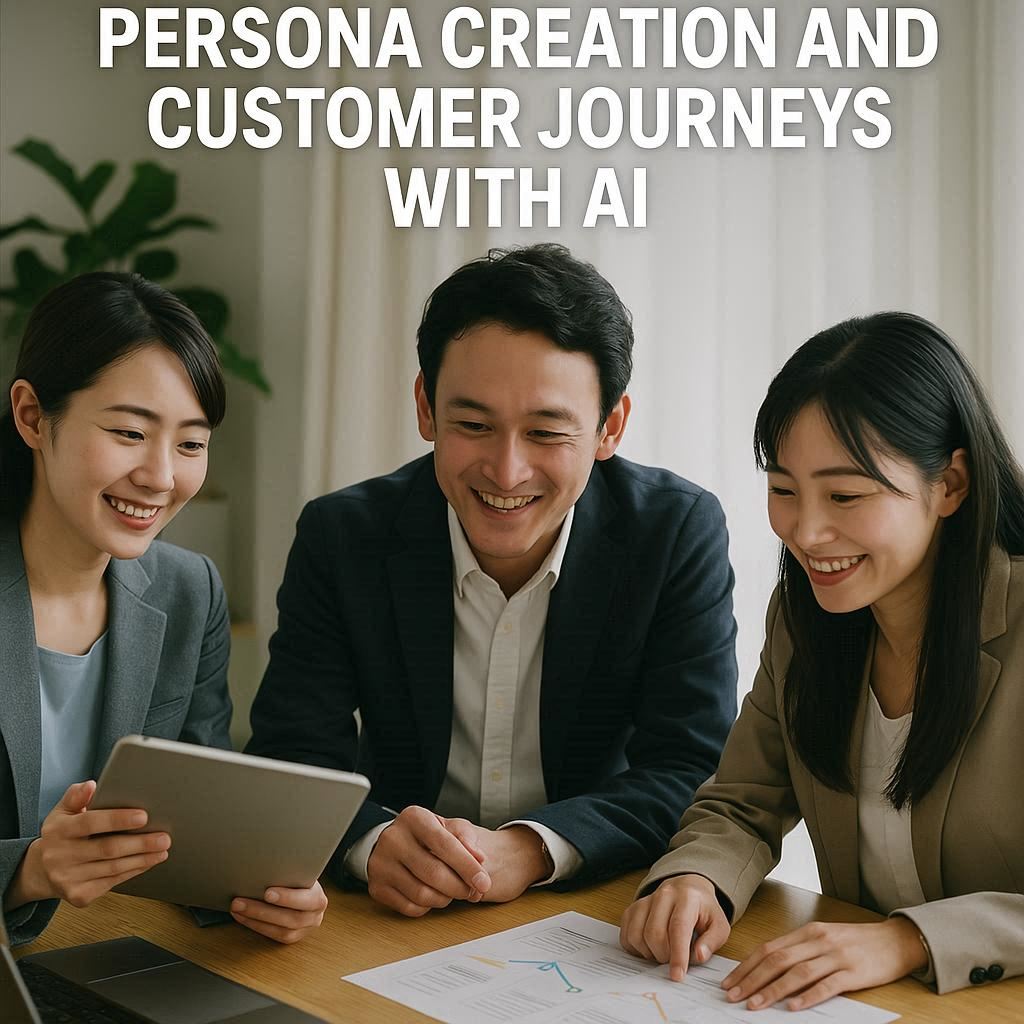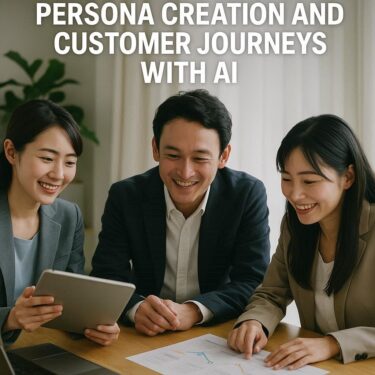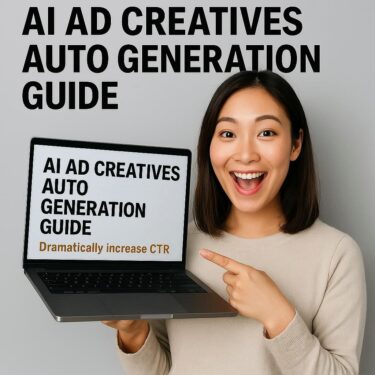AIペルソナは「銀の弾丸」ではない。データと現場の溝を埋めた、泥臭いコミュニケーションの裏側
先日公開した『AIでペルソナ作成・カスタマージャーニーを自動化する実践ガイド』という記事、ありがたいことに多くの方にお読みいただいているようです。あの記事では、LINEやGA4、CRMデータを連携させ、AIを使って成果を出すための「綺麗な方法論」を体系的にまとめました。プロンプトの例も載せて、明日からでも使えるように、と。
AIでペルソナ作成・カスタマージャーニーを自動化する実践ガイド|LINE/GA4/CRM連携で成果を出す方法 「うちのペルソナ、現場の肌感覚とズレてるんだよな…」「時間とコストをかけて作ったカスタマージャーニーマップが、更新されずに[…]
しかし、です。
あの記事を読んだ方の中には、こう思った方もいるかもしれません。「本当にこんなにスムーズに進むのか?」と。
ええ、その通りです。進むわけがありません。
あのフレームワークやプロンプトは、いわば料理のレシピのようなもの。最高のレシピがあったとしても、キッチンが汚れていたり、食材が揃っていなかったり、何より料理人の気持ちが乗っていなければ、美味しい料理は作れませんよね。
プロジェクトの現場とは、まさにそんな場所です。最新のAIという調理器具を前に、「そんなものより、長年使い込んだこの包丁の方が切れる」と主張するベテランがいて、「そもそも、うちの冷蔵庫にはロクな食材が入っていない」と嘆く担当者がいる。
今回は、あの「綺麗なレシピ」の裏側で、私たちがクライアントと繰り広げた、もっと人間臭くて、泥臭い「キッチンでの奮闘記」をお話ししようと思います。これは、教科書には載っていない、人と組織のリアルな物語です。
第1章:最初の壁。「AIの言うことなんて、信じられますか?」
ある消費財メーカーでのプロジェクトでした。マーケティング部長は「これからはAIとデータドリブンだ!」と意気軒昂。しかし、キックオフミーティングの空気は、どこか冷ややかでした。特に、最前線で顧客と向き合ってきた担当者の佐藤さん(仮名・30代女性)の表情は硬いままでした。
会議の終盤、彼女は意を決したように口を開きました。
「今まで私たちが、お客様に何度もインタビューを重ねて作ってきたペルソナがあるんです。それを無視して、AIが出した数字だけのペルソナなんて…なんだか、血が通っていない気がして。本当に信じられるんでしょうか」
この言葉の裏には、様々な感情が渦巻いていたはずです。「自分の仕事が否定されるんじゃないか」「積み上げてきた経験や顧客との関係性が、無価値だと言われているようだ」…そんな不安と、プロとしてのプライド。
ここで私が「いえ、AIは膨大なデータを客観的に分析するので、より正確な顧客像を描き出せます」なんて正論を言ったところで、彼女の心のシャッターは固く閉ざされてしまうだけでしょう。
私はまず、彼女たちの仕事への敬意を伝えることから始めました。
「佐藤さん、ありがとうございます。皆さんが作られたペルソナ資料、事前に拝見しました。お客様一人ひとりの生活や悩みが目に浮かぶようで、本当に素晴らしいと思いました。感動しましたよ」
少しだけ、彼女の表情が和らぎます。
「今回ご提案しているAIは、皆さんのその素晴らしい仕事を否定するものでは全くありません。むしろ、そのペルソナをもっと強く、もっとリアルタイムにするための『新しい武器』だと考えてほしいんです。例えば、皆さんが肌で感じている『お客様の変化の兆し』を、AIがデータで裏付けてくれる。あるいは、皆さんがまだ気づいていない新しい顧客層の可能性を、AIが見つけてきてくれる。そんな風に、皆さんの経験とAIの分析力を掛け合わせるためのプロジェクトなんです」
AIを「自分たちの仕事を奪う代替物」ではなく、「自分たちの能力を拡張してくれる道具」として再定義する。これが、変化に対するアレルギーを和らげる最初の、そして最も重要な一歩でした。人は、自分が主役であり続けられる物語にしか、本気で参加してはくれないのです。
第2章:データ統合という名の「部門間調整」という迷宮
あの記事では『Step 2: データ統合の設計を行う』と、たった一行で書きました。しかし、このステップこそがプロジェクト最大の難所であり、技術的な課題というよりは、ほとんど「社内政治」に近いものでした。
マーケティング部はWebの行動履歴(GA4)を、営業部は顧客情報(CRM)を、そして店舗運営部は購買データ(POS)を、それぞれが「自分たちの聖域」として守っていました。
特に手強かったのが、長年この会社を支えてきたベテランの営業部長(50代・庄内弁)でした。
「んだ、うちのCRMさ入ってる情報は、営業が足で稼いで、汗水垂らして入力した大事なもんだぞ。なんで、ようわからんマーケの連中に、ホイホイ見せねばなんねんだ?」
彼の言い分も分かります。各部署にはそれぞれのKPIがあり、守るべきものがある。しかし、顧客は「マーケティング部の顧客」「営業部の顧客」と分かれているわけではありません。顧客にとっては、すべてが「この会社」との一つの体験なのです。
ここでも、正論は通用しません。私はアプローチを変えました。各部署のキーマンを個別に回り、技術の話ではなく、「共通の敵」と「共通の目的」について語ることにしたのです。
「部長、最近、競合のA社がECサイトと店舗の会員IDを統合して、かなり巧みなキャンペーンを仕掛けてきているのはご存知ですか?このままでは、我々が長年かけて築いてきたお客様との関係を、根こそぎ彼らに奪われかねません」
そして、こう続けます。
「我々の本当の敵は、社内の隣の部署じゃないはずです。市場にいる競合であり、お客様を満足させられない我々自身の旧態依然としたやり方なんです。お客様は、我々の部署のことなんて気にしていません。『この会社』として、一貫した最高の体験を提供できるかが問われています。そのために、皆さんの力を貸していただけませんか?」
さらに、データが統合されることで、それぞれの部署にどんな具体的なメリットが生まれるのかを、徹底的に説明して回りました。
営業部長には、「Webサイトで特定の製品ページを何度も見ている『見込み客リスト』を、毎日自動でCRMにお届けできます。アポの成功率が格段に上がりますよ」と。
店舗運営部長には、「オンラインで下見してから来店されるお客様の行動が事前に分かるので、店舗での接客がスムーズになります」と。
技術の導入プロジェクトでありながら、やっていることは実にアナログです。何度も足を運び、相手の言葉に耳を傾け、メリットを説き、少しずつ信頼の貯金を積み立てていく。巨大な岩を、少しずつ動かしていくような、地道な作業でした。
第3章:「幻のペルソナ」と現場の肌感覚を繋ぐ
数ヶ月にわたる調整の末、ようやくデータ基盤が整い、私たちはAIによる最初のペルソナを出力しました。あの記事で言う『Step 3: AIで「動的ペルソナ」の骨格を作る』の段階です。
しかし、そのアウトプットを見た佐藤さんの表情は、またしても曇っていました。
「…なるほど。データ上は、こういうお客様が多いということなんですね。でも、何かが違うんです。私たちの知っているお客様は、もっと…こう…ECサイトで買うか、お店で買うかすごく迷ったり、買った後で『本当にこれでよかったのかな』って不安になったりするんですよ。このペルソナ、なんだか優等生すぎて、リアルじゃないというか…」
これこそが、多くの企業が陥る「幻のペルソナ」問題です。データは「WHAT(何をしたか)」は教えてくれますが、「WHY(なぜそうしたか)」や、その裏にある感情の機微までは雄弁に語ってくれません。
私は、待ってましたとばかりに言いました。
「佐藤さん、最高のフィードバックです!その『何か違う』という感覚こそ、このプロジェクトの宝なんです。AIが出してきたのは、あくまで骨格です。ここに血肉を通わせ、生きたペルソナに育てていくのは、佐藤さんたち現場のプロにしかできない仕事です」
私たちは、AIが生成したペルソナをスクリーンに映し出し、付箋を片手にワークショップを開きました。
「このペルソナが、なぜこのタイミングで商品を買ったのか?」「購入前に、どんなサイトと比較したと思うか?」「彼女が一番不安に思っていることは何だろう?」
AIが提示した定量的な骨格に、現場の皆さんが持つ定性的な知見、つまり顧客の生々しい感情やストーリーを肉付けしていく。この共同作業を通じて、佐藤さんたちの表情はみるみる変わっていきました。「AIに評価される」立場から、「AIを使いこなし、育てる」立場へと、彼女たちの意識がシフトした瞬間でした。
AIの出した答えは、完成品ではありません。それは、人間がより深い洞察を得るための、最高の「叩き台」なのです。
第4章:完璧なシナリオより、不完全な一歩を
ペルソナが固まり、いよいよカスタマージャーニーに基づいたシナリオの実装(『Step 5: シナリオを実装する』)に移った時、また別の壁が立ちはだかりました。
「カゴ落ち30分後にこのメッセージを送り、24時間後にはこのレビューコンテンツを…」
「初回購入者には、1週間後にこの使い方ガイドを送り、1ヶ月後には…」
私たちが設計した精緻なシナリオ案に対して、今度はコンテンツ制作やシステムの担当者から悲鳴が上がったのです。
「こんなにたくさんのパターンのバナーやメッセージ、誰が作るんですか?リソースが全然足りません!」
「この複雑な条件分岐、今のMAツールじゃ実装できませんよ。追加開発には最低でも3ヶ月はかかります」
理想を追い求めれば求めるほど、実行のハードルは高くなる。プロジェクトが「絵に描いた餅」で終わる典型的なパターンです。
私は、チーム全員を集めて言いました。
「おっしゃる通りです。すべてを一度にやろうとしても、絶対にうまくいきません。失敗します。だから、やめましょう。たった一つ、一番インパクトが大きくて、今すぐ始められることからやりませんか?」
私たちは、数あるシナリオ案の中から、「カゴ落ち30分後のリマインドLINE」という、たった一本の施策に絞ることにしました。クリエイティブもA/Bテストもなし。まずは、今あるツールで実現可能な、最もシンプルな形でリリースする。
完璧を目指さない。まずは不格好でもいいから、一歩目を踏み出す。小さな成功体験を積み重ね、その成果をもって経営層に「ほら、効果が出ました。だから、次はこの施策のために追加のリソースをください」と交渉する。この「MVP(Minimum Viable Product)」のアプローチこそが、巨大な組織を動かす唯一の方法だったのです。
終章:データが「共通言語」になった日
最初にリリースした「カゴ落ち対策シナリオ」は、2週間後、驚くべき成果を上げました。LINE経由での売上が、月間で数百万円単位で上乗せされたのです。
この「小さな成功」が、組織の空気を劇的に変えました。
これまで懐疑的だった佐藤さんが、「次は、初回購入者向けのフォローシナリオを試してみたいです」と、自ら企画書を持ってきてくれました。あれだけデータの提供に渋っていた営業部長が、「Webの行動データと連携したら、もっと面白いことができそうだな」と、マーケティングの定例会に顔を出すようになりました。
極めつけは、普段は工場にこもり、製品のことしか頭にないような強面の工場長(60代・庄内弁)が、ふらっとやってきて言った一言でした。
「おめだぢ、今こんげなごどやってるんだな。このペルソナっちゅうのを見たけどよ、うちの工場で作ってる製品A、もっとこんげ風にアピールした方が、この人だぢさ響くんでねぇか?」
鳥肌が立ちました。
AIが生み出した「データに基づく顧客像」が、これまで交わることのなかったマーケティング、営業、そして製造という部署を繋ぐ「共通言語」になった瞬間でした。組織のサイロが、少しだけ溶け始めたのです。
あの記事で書いた華やかなフレームワークやAIの技術は、あくまできっかけに過ぎません。その裏側には、必ずこうした人間臭いドラマがあります。
変化を恐れる人の心を解きほぐし、部門間の壁を地道な対話で乗り越え、完璧な計画より不完全な一歩を勇気を持って踏み出す。AI導入の成否を分けるのは、技術の知識以上に、こうした泥臭いコミュニケーションの積み重ねなのだと、私は確信しています。
AIは、答えをくれる魔法の杖ではありません。それは、私たちがこれまで見えていなかったものを見せてくれ、対話を促し、組織を変えるための「賢い鏡」であり、「強力な触媒」なのです。
もし、あなたが今、新しいプロジェクトの壁にぶつかっているのなら。思い出してください。どんなに優れた技術も、動かすのは「人」の心です。まずは、目の前の人の声に、真摯に耳を傾けることから始めてみてはいかがでしょうか。