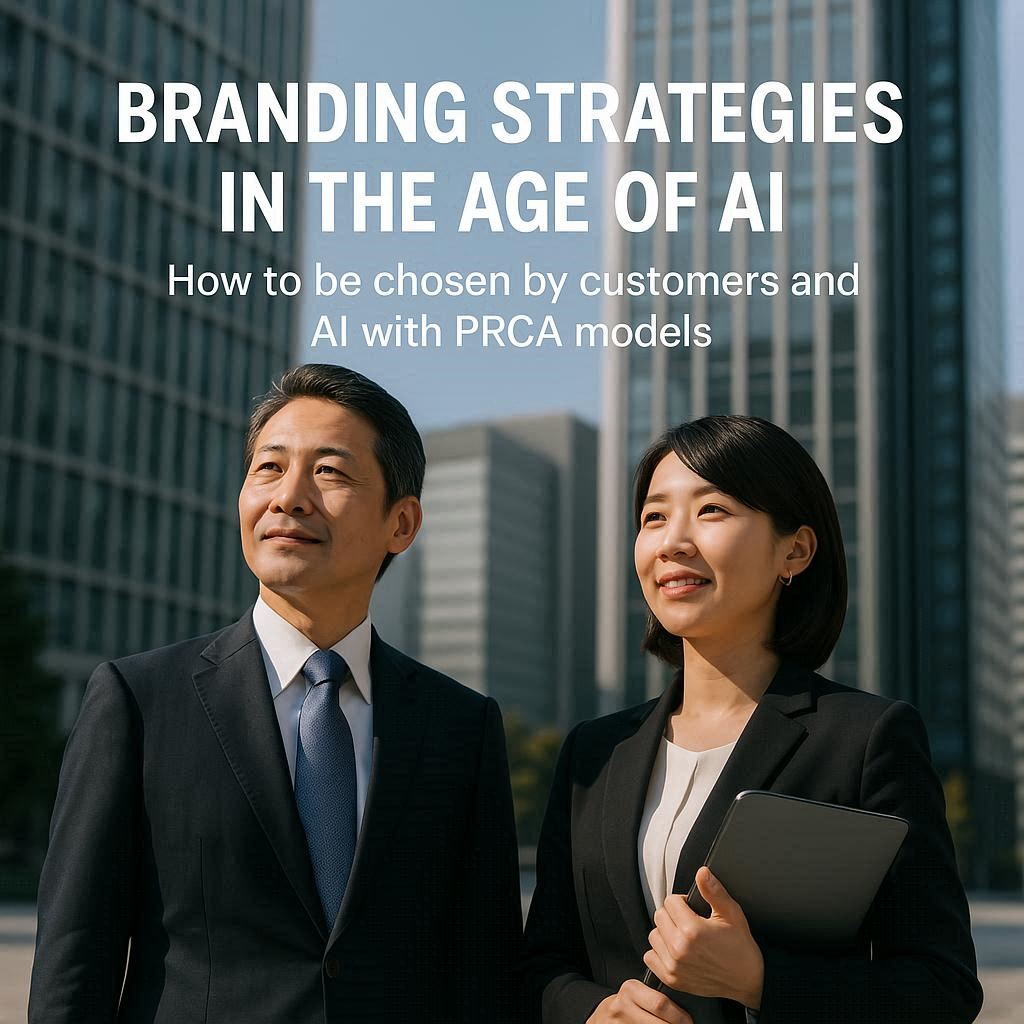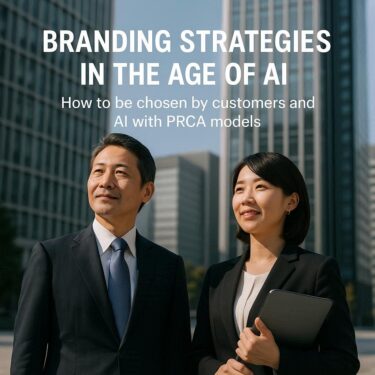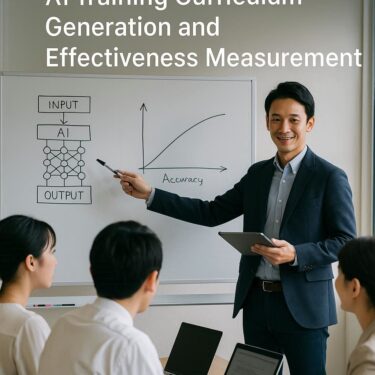AIブランディング戦略、その“綺麗ごと”の裏側で本当に起きていたこと
先日公開した「AI時代のブランディング戦略実践ガイド」の記事、おかげさまで多くの方に読んでいただけたようだ。プロンプト例など、すぐに使える具体的なノウハウを詰め込んだつもりだ。
AI時代のブランディング戦略実践ガイド|顧客とAIに選ばれる方法 あなたのブランド、AIにどう見られていますか? 「生成AIがマーケティングを変える」——この言葉を、あなたも一度は耳にしたことがあるでしょう。しかし、そ[…]
…しかし、正直に白状しよう。あの記事に書かれているのは、いわば“理想の姿”であり、磨き上げられた完成形だ。あの綺麗な戦略図やワークフローにたどり着くまでに、クライアントの現場では一体何が起きていたのか。
この記事では、あのガイドブックには書ききれなかった、もっと泥臭くて、人間臭い、生々しい現実の話をしようと思う。これは、最新のAIツールやフレームワークの話ではない。組織の壁に阻まれ、孤独に戦う担当者と、変化を恐れるベテランたちが、どうやって一枚岩になっていったか。そんな、コミュニケーションとマネジメントを巡る、ささやかな奮闘の記録だ。
担当者の涙と「見えない壁」
そのプロジェクトの始まりは、一本の電話だった。クライアントは、地方で何十年も高品質な産業用部品を作り続けてきた、実直な中堅メーカー。技術力には絶対の自信がある。しかし、どうも最近、Webからの引き合いが競合に流れているらしい。
初回の打ち合わせで私を迎えてくれたのは、Webマーケティング担当の佐藤さん(仮名・34歳)。彼女はPCの画面に映る複雑なデータを示しながら、憔悴しきった顔でこう切り出した。
「うちの会社、バラバラなんです…」
聞けば、状況は深刻だった。
広報部門は、長年付き合いのある業界紙向けに「伝統と職人技が光る、最高品質」というメッセージを発信し続けている。
Webマーケティング担当の彼女は、上から「とにかくWebサイトからの問い合わせを増やせ」と厳命され、SEO対策に必死。しかし、技術的な詳細がわからず、中身の薄いコンテンツを量産してしまっている。
そして、会社の売上の大半を稼ぎ出す営業部門は、昔ながらの付き合いと足で稼ぐ営業スタイルに誇りを持っているため、Webマーケティングを「小手先の遊び」と見下している節さえある。
「私が『これからはAIも意識しないと…』なんて話をしても、誰も真剣に聞いてくれないんです。広報は『ブランドイメージが…』、営業は『そんなことより今月の数字だ』って…。みんな自分の部署の目標しか見てなくて、私はただの板挟み。もう、何から手をつけていいのか…」
話の途中、彼女の目には涙が浮かんでいた。
これは、決して珍しい光景ではない。多くの企業が、程度の差こそあれ同じ問題を抱えている。各部署がそれぞれのKPIを追い、部分最適を繰り返した結果、顧客から見ると「言っていることがバラバラで、よくわからない会社」になってしまう。
問題の本質は、AIという新しい技術そのものではない。長年かけて組織に染み付いた「サイロ化」という病だ。私の最初の仕事は、立派な戦略を提示することではなかった。まず、社員たち自身が気づいていない、この分厚い「見えない壁」を、彼らの目の前に突きつけることから始める必要があった。
「AIなんて、わがんねごどばっかり」ベテラン部長の抵抗
事を進めるには、各部署のキーマンを巻き込む必要がある。私は佐藤さんと相談し、広報、マーケ、営業、そして開発の責任者を集めた合同の会議を開いた。
会議の空気は、予想通り重かった。そして、案の定というべきか、一番の“抵抗勢力”となったのは、営業部隊を30年以上束ねてきた鈴木部長(58歳)だった。日に焼けた顔に、深い皺。叩き上げの自信が全身から滲み出ている。
私がAI時代の顧客行動の変化について説明し始めると、鈴木部長は腕を組んだまま、訝しげな表情で口を挟んだ。
「佐藤さんから話は聞いでだども…なんだば、その『ぷろんぷと』だの『えるえるえむおー』だの。横文字ばっかりで、さっぱりわがんねな。あんたが言いでるごどは、つまりパソコンさ聞げば、うちの製品の良さがわかるようにしろってごどか?」
「はい、お客様の情報収集の仕方が変わってきていますので…」
「うちの製品の良さはな、こやって顔合わせで話して、時には酒飲んで、腹割って話して、それでやっと伝わるもんだ。パソコンさ聞いでわかるような、安っぽいもんでねんだでば。そんなもんに時間使うより、一件でも多く客先回った方がよっぽど売上になっぞ」
正論だ。彼の言うことにも一理ある。ここで私が「いや、時代は変わったんです」と正論をぶつけても、彼の固いプライドを傷つけ、より頑なにするだけだろう。
私は一度、大きく頷いてみせた。
「部長、おっしゃる通りです。部長たちがお客様と直接向き合い、築き上げてきた信頼関係こそが、この会社の何よりの財産です。それはAIには絶対に真似できません」
まず、相手の土俵に乗り、敬意を払う。そして、彼の言葉を借りて、視点を少しだけズラしてみる。
「ただ…その一番大事な財産が、今、私たちが知らないところで、ネット上の不正確な情報のせいで、お客様に届く前に誤解されてしまっているとしたら…それは、ものすごく悔しくないですか?」
彼のプライドを「守るべきもの」として肯定し、それを脅かす「共通の敵(ネット上の誤解)」を提示する。鈴木部長の眉が、ピクリと動いた。反論の言葉は出てこなかった。会議室の重い空気が、ほんの少しだけ変わった瞬間だった。
動かぬ組織を動かした、たった一枚の「健康診断書」
次の会議で、私が提示したのは、分厚い戦略提案書ではなかった。A3用紙数枚にまとめた、シンプルなレポートだ。記事で紹介した「AIブランド認識監査」の結果である。
私はそれを「会社のWeb上の健康診断書です」と説明し、プロジェクターに映し出した。
「まず、一般的な質問です。『〇〇(社名)の製品の評判は?』とAIに聞いてみました。すると、一番最初に『高品質だが、価格が高いという意見もある』という回答が出てきます」
「次に、競合A社と比較させてみました。すると、A社は『導入後のサポートが手厚いと評判』と絶賛されています。うちのサポート体制も負けていないはずですが、AIは残念ながら一切言及してくれません」
「そして…一番の問題はこれです。広報部門が5年前に発信した『最高品質へのこだわり』というプレスリリースと、Webサイトの隅に残っている古い料金表。これをAIが同時に学習した結果、『伝統的な高品質を謳うが、料金体系が不透明で結果的に割高になる可能性がある』という、最悪の要約を生成してしまっています」
会議室は、水を打ったように静まり返った。
誰もが、自分たちの仕事がバラバラだった結果、意図せずして「ネガティブなブランドイメージ」をAIに作り上げさせていたという事実を突きつけられたのだ。
これは「誰が悪い」という犯人捜しではない。ただ、組織が同じ方向を向いていなかった結果生まれた「客観的な事実」だ。
沈黙を破ったのは、鈴木部長だった。
「…うちの客になるかもしんねぇ人が、最初にそんなごど言われでんのが…」
その声には、怒りよりも戸惑いと悔しさが滲んでいた。
初めて、全部署の視線が同じ一点、「顧客からどう見られているか」という事実に集まった。隣に座る佐藤さんの目に、安堵の色が浮かんでいるのがわかった。この「健康診断書」こそが、動かなかった組織を動かすための、強力な処方箋になったのだ。
「共通言語」が、見えない壁を溶かしていく
「健康診断書」で危機感を共有した後、私は初めて、あの記事で紹介した“地図”を全員の前に広げた。
「皆さん、これが今のお客様が買い物をする時の『地図』だと考えてください。まずAIに質問し、次にネットで裏を取り、AIで再比較し、ようやく行動に移します」
私は鈴木部長の方を向いて続けた。
「鈴木部長の営業部隊が圧倒的に強いのは、お客様が最終的に購入を決める、この最後の『行動』の段階です。しかし、今のお客様はそこに至る前の、AIに質問、裏取り、再比較という長い道のりを旅してきます。この前半戦で、うちの会社は道に迷い、競合という名の脇道に逸れてしまっているんです」
鈴木部長は、腕を組んだまま、深く頷いた。
「…なるほどな。俺たちの出番が来る前に、試合の趨勢はほとんど決まってだんか」
「その通りです。だからこそ、前半戦の道のりを整備する必要があるんです。お客様が安心して、迷わずに部長たち営業の元へたっぱり着けるように、広報の皆さんには『信頼できる道しるべ』を、Web担当の佐藤さんには『分かりやすい地図』を用意してほしいんです」
シンプルなフレームワークが、部署間の「共通言語」になった瞬間だった。
それまで「ウリは品質」「いや、Webの集客だ」「最後は営業力だ」と、それぞれが違う山の頂上を目指していた彼らが、初めて同じ地図を囲み、同じ頂上を目指すためのルートを話し合い始めた。
「じゃあ、うちの広報としては、製品の強みを定義した『メッセージ骨格』をまず作らないとダメだな」
「Webチームでは、その骨格に沿って、比較検討されやすいFAQページを充実させます」
「だったら営業からは、お客様からよく聞かれる質問や、競合の動向を全部提供すっぞ」
もう、そこに「それはウチの仕事じゃない」という言葉はなかった。
佐藤さんは、もはや孤独な板挟みの担当者ではなかった。各部署の意見を引き出し、地図の上に整理していく、プロジェクトを推進する立派なファシリテーターの顔つきになっていた。
最後に
先日公開した、あの小綺麗にまとまったブランディング戦略の記事。その裏側には、こうした人間臭い衝突と、理解と、そして協調のプロセスがあった。
AI戦略の成否を分けるのは、結局のところ、最新のAIツールでも、精緻なフレームワークでもない。それは、組織という複雑で感情的な“生き物”の中で、いかにして「対話の場」を作り出し、「共通の地図」を広げ、一人ひとりの当事者意識に火をつけるかどうかにかかっている。
もしあなたが今、かつての佐藤さんのように、組織の壁の前で孤独を感じているなら、思い出してほしい。
あなたの最初の仕事は、完璧な計画を作ることじゃない。
まずはたった一枚の「健康診断書」を手に、勇気を出して、関係者との対話のテーブルにつくことだ。
そこから、あなたの会社の変革は、きっと始まるのだから。