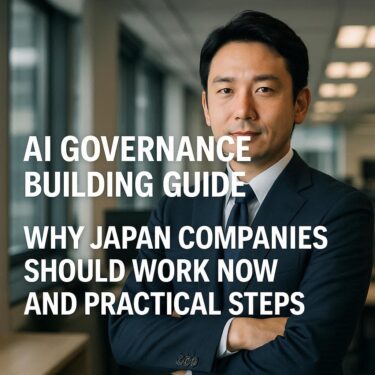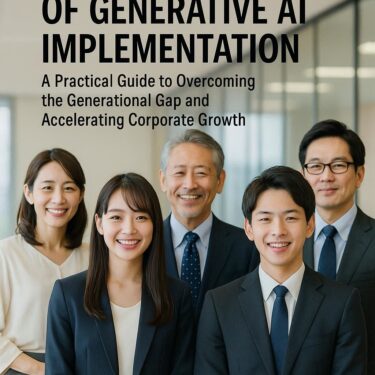AIガバナンス構築の裏側にある、泥臭くて人間くさい物語
先日公開した「AIガバナンス構築ガイド」の記事、おかげさまで多くの方に読んでいただけたようです。ありがとうございます。あの記事では、専門家の知見を基に、構築のステップを体系的かつロジカルに解説しました。いわば、綺麗な「完成予想図」です。
しかし、物造りや企業改革の現場を渡り歩いてきた人間として、皆さんに本当に伝えたいのは、その図面通りには決していかない「現場のリアル」です。立派なルールや体制を作ること自体は、実はそれほど難しくありません。本当に難しいのは、それを血の通ったものとして組織に根付かせ、動かしていくプロセス。そこには必ず、人の「心理」や「感情」が絡んできます。
今日は、あの綺麗な記事の裏側で繰り広げられていた、もっと泥臭くて、もっと人間くさい「マネージメントとコミュニケーション」の話を、少しだけお聞かせしようと思います。これは、AIガバナンスに限らず、あらゆる改革プロジェクトに共通する「壁」と、それを乗り越えるためのヒントになるはずです。
第一の壁:「ウチもAIで一発逆転だ!」熱血社長と「また面倒な…」冷めた役員会
プロジェクトの始まりは、いつも経営トップの一声です。ある中堅製造業の社長も、そうでした。メディアでAIの成功事例を見るたびに目を輝かせ、私を呼び出したのです。
社長室のドアを開けるなり、満面の笑みでこう言われました。
「ミズさん、頼むぞ!うちもAIで業務ば効率化して、世界さ打ってでる新製品ば開発するべ!」
熱意は素晴らしい。しかし、その後の役員会で、私は早速、現実の壁にぶち当たります。社長が熱弁をふるう横で、役員たちの顔は一様に曇っていました。財務担当の役員が、重い口を開きます。
「社長、そだな威勢のいいごど言うても、リスクはどだなだや?うちの重要な技術情報ばAIさ入力して、外さ漏れたら一巻の終わりだぞ。」
開発担当の役行も続きます。
「そもそも、AIだなんだって言ったって、現場は日々の生産で手一杯だ。新しいごどば覚えさせる時間も人もいねべした。」
これは典型的なパターンです。社長は「攻め」のアクセルを全開で踏みたがり、役員たちは「守り」のブレーキを必死でかけようとする。どちらも会社を思っての発言だからこそ、議論は平行線をたどりがちです。
ここで私が「AIガバナンスが必要です。リスクを管理し、ルールを策定しましょう」なんて正論を振りかざしても、役員たちにとっては「ほら見たことか、やっぱり面倒なだけじゃないか」という話になってしまいます。
私がいつもやるのは、彼らの「言葉」と「価値観」に翻訳してあげること。
財務担当役員には、リスク管理の話を「コスト」ではなく「投資」の文脈で語ります。
「おっしゃる通り、情報漏洩は致命的なリスクです。だからこそ、今ここで『うちはAIを安全に使いこなしています』というお墨付き、つまり信頼を内外に示すことが、将来的に金融機関からの評価や、厳しい基準を持つ海外企業との取引を有利に進めるための『戦略的投資』になるんです。EUのAI法をご存じですか?今やガバナンス体制がないと、欧州とはビジネスすらできない時代がそこまで来ていますよ」
開発担当役員には、現場の負担という視点からアプローチします。
「現場の皆さんが混乱しないためにも、最初に明確な『交通整理』が必要なんです。『この道は通ってOK、でもこっちは危ないから注意』というシンプルな標識があれば、現場は迷わず安心してAIという新しい道具を使えるようになります。結果的に、それが一番の生産性向上につながるんですよ」
AIガバナンスを「守りの規制」としてではなく、「攻めの武器」として再定義してあげる。すると、あれほど硬い表情だった役員たちの間に「なるほど、そういう考え方もあるのか」という空気が生まれ始めます。これが、全社を巻き込むための最初の、そして最も重要な一歩なのです。
第二の壁:誰も舵を取りたがらない「部門横断プロジェクト」という名の無法地帯
経営層の合意が取れると、次に作られるのが「AI活用推進タスクフォース」といった名の、部門横断プロジェクトチームです。法務、IT、人事、そして各事業部のエース級が集められ、キックオフミーティングは華々しく開催されます。
しかし、その実態は「寄せ集め部隊」。メンバーの頭の中は、自部門の利益と責任範囲でいっぱいです。
ある電機メーカーでのプロジェクト会議は、まさにカオスでした。
法務担当「AIが生成した設計図に欠陥があった場合、製造物責任法上のリスクが考えられます。利用規約に免責事項を明記すべきです!」
事業部担当「そんなごどばっかり言ってだら、いつまで経っても実用化でぎねべした!スピードが命なんだぞ!」
IT担当「そもそも、皆さんが使いたいそのAIツール、うちのセキュリティポリシーで許可でぎるんだべが…?シャドーITは絶対に許さんねぞ。」
全員が自分の専門分野から「あるべき論」と「リスク」を主張するばかりで、議論はまったく前に進みません。プロジェクトリーダーに任命された中間管理職は、各部門からの突き上げと、経営からの「まだ進まないのか」というプレッシャーの板挟みで、すっかり疲弊していました。
こうなると、私の役割は「交通整理の警察官」であり、「通訳」です。
まずは、心理的安全性を確保する。どんな意見も否定せず、「なるほど、法務の観点ではそういうリスクがあるんですね」「事業部としては、そのスピード感が重要なんですね」と、一度すべて受け止め、ホワイトボードに書き出していきます。自分の意見が尊重されたと感じるだけで、人は少し冷静になれるものです。
次に、彼らの専門用語を「共通言語」に翻訳します。
「法務さんの言う『免責事項』というのは、言い換えれば『AIはあくまでアシスタントだから、最後は人間がちゃんと確認しようね』というルールを、みんなで共有するってことですよね?事業部さん、最終確認のプロセスを入れることは可能ですか?」
「ITさんの言う『シャドーIT』がなぜ怖いかというと、会社が把握できないところで万が一情報漏洩が起きたら、誰にも気づかれず、対応もできなくなってしまうからなんです。だから、まずは『どんなツールを使っているか』を正直に教えてもらうことから始めませんか?怒るためじゃなく、みんなで安全な使い方を考えるために」
そして、最も効果的なのが、「As-Is分析(現状把握)」を共同作業にさせること。
元記事では「全社的にアンケートを取る」とさらっと書きましたが、それだけでは不十分です。各部署の代表者が他の部署に直接ヒアリングに行く、というワークショップを設計するのです。
法務の担当者が、開発の現場に行って「へぇ、こんなふうにAIを使おうとしてるんだ」と知る。開発の担当者が、営業の現場で「お客様のこんな情報を入力しちゃいそうになるのか」と気づく。
この「他者理解」のプロセスを通じて、初めて「これはうちの部署だけの問題じゃない」「全社で取り組むべき課題なんだ」という当事者意識が芽生え始めます。「部門の代表」だった彼らが、少しずつ「全社のためのプロジェクトメンバー」へと変容していく瞬間です。この地道な相互理解のプロセスをすっ飛ばして、立派な会議体だけ作っても、機能するはずがないのです。
第三の壁:本社が決めた「立派なルール」と現場の「そだなの使ってらんね」という本音
数々の議論を経て、ついに全社統一の「AI利用ガイドライン」が完成。経営承認も得て、意気揚々と全社に通達されます。しかし、数ヶ月後、プロジェクトリーダーが青い顔で私のところにやってきました。
「ミズさん、大変です。現場が、ガイドラインをまったく守ってくれていません。それどころか、面倒くさがってAI自体を使わなくなったり、逆に隠れてこっそり使ったりする『地下活動』が横行しているようなんです…」
現場のリーダーに話を聞きに行くと、案の定、不満が噴出しました。
「本社はまたわけわがんね小難しいルールば作って…。『プロンプトに入力する個人情報は適切にマスキング処理を行うこと』だど?おらだ、ただでさえ忙しいのに、そだなごどまでやってらんねぞ。」
隣にいた若手の社員は、もっとストレートでした。
「こっそり使ったほうだば、絶対に早えべした。バレねって、バレね。」
これもまた、改革プロジェクトにおける「あるある」です。どんなに論理的に正しいルールも、現場の業務実態や感情から乖離していれば、ただの「絵に描いた餅」になってしまう。
ここでの鉄則は、「完璧な100点のルール」を押し付けるのではなく、「現場と一緒に育てる60点のルール」から始めること。
私は、完成したガイドラインを一旦横に置き、各現場から「AIを一番使いこなしている若手」と「一番懐疑的なベテラン」の両方を数人ずつ集めて、小さなチームを作ってもらいました。そして、彼らにこうお願いするのです。
「この本社のルール、正直、現場じゃ使いにくいですよね?じゃあ、皆さんの現場で本当に守れる『自分たちの言葉』に翻訳してもらえませんか?『マスキング処理』なんて言わずに、『お客さんの名前とか電話番号は、絶対に入れねでけろな』とか、そういう言葉でいいんです」
「禁止」ばかりのルールではなく、「こうすればもっと仕事が楽になる・安全になる」という「虎の巻」を、彼ら自身に作ってもらうのです。
このプロセスには、魔法のような効果があります。
まず、「やらされ感」が「自分たちで決めた感」に変わる。自分たちが作ったルールなら、守ろうという意識が働きます。
次に、彼らが現場の「公式エバンジェリスト(伝道師)」になってくれる。本社から言われるより、同じ現場の仲間から「このやり方だと、マジで安全だし早いよ」と言われる方が、何倍も説得力があるのです。
こうして作られた「現場翻訳版ガイドライン」は、もしかしたら法務の専門家が見れば少し言葉足らずかもしれません。しかし、現場で確実に守られる60点のルールは、誰も守らない100点のルールより、はるかに価値があるのです。
終わりに:ルール作りは、組織変革の始まりにすぎない
AIガバナンスの構築は、テクニカルなルール作りのプロジェクトではありません。それは、経営層のビジョンと現場のリアルを繋ぎ、部門間の壁を壊し、会社全体のコミュニケーションを再設計する、壮大な「組織変革プロジェクト」そのものです。
そこに必要なのは、完璧なフレームワークやロジックだけではありません。立場の違う人々の声に真摯に耳を傾ける「傾聴力」。専門的な言葉を誰もがわかる言葉に置き換える「翻訳力」。そして、バラバラな個人を一つのチームへとまとめ上げる「ファシリテーション能力」。
綺麗な完成予想図の裏側には、常にこうした泥臭いコミュニケーションの積み重ねがあります。もしあなたが今、AI導入や何らかの改革プロジェクトで壁にぶつかっているのなら、少しだけ思い出してみてください。ロジックや正論で人を動かそうとしていないか。相手の立場や感情を、置き去りにしていないか。
その小さな視点の変化が、固く閉ざされた扉を開ける、一番の鍵になるかもしれません。