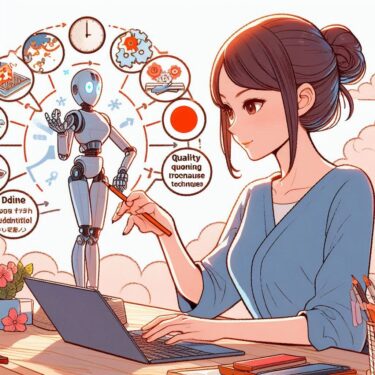AIを「作る」前に、あなたの会社は「壊れて」いませんか? “AIミニアプリ”狂想曲の裏で本当に起きていたこと
先日、「AIは『使う』から『作る』時代へ」という記事を発表した。プログラミング不要で、現場の誰もが自分の業務に合った「AIミニアプリ」を作れるようになる。パナソニック コネクトは年間18.6万時間、七十七銀行は3.2万時間の業務を削減――。そんな輝かしい未来と、具体的な方法論を提示した。
あの記事は、AI活用の最前線で起きている紛れもない事実だ。しかし、光が強ければ、その影もまた濃くなる。
今日は、あの記事ではとても書けなかった「影」の部分、つまり、その裏側で起きていた壮絶な人間ドラマについて語りたい。「誰でもAIを作れる」という魔法の言葉が、一つの組織に何をもたらし、私たちはそれをどう乗り越えようとしたのか。
これは、ある部品メーカーで実際に起きた物語だ。AIという名のパンドラの箱を開けてしまった人々の、混乱と再生の記録。もし、あなたの会社が今まさに「AIを作ろう」と息巻いているなら、この記事は、未来のあなたを救うための、ささやかな処方箋になるかもしれない。
「明日までに100個作れ!」社長の“AIアプリ工場”化計画という悪夢
すべての始まりは、五十嵐社長(仮名)が例の記事を読んだ、その翌日のことだった。彼は血気盛んな創業者で、新しいもの好き。その行動力で会社を大きくしてきたが、時にそのスピードが嵐を呼ぶ。
「ミズさん、読んだか、これ!AIミニアプリ!プログラミングがいらねんだど!こりゃ革命だ!ウチも明日から全社員に作らせるぞ!推進室はサポートしろ!部署ごとに最低5個、今週中にアイデアを出させて、来週末までにプロトタイプを100個作るんだ!」
早朝の役員会議で、彼はそう高らかに宣言した。その目は少年のように輝いていたが、私にはその言葉が悪夢の始まりにしか聞こえなかった。「プログラミング不要」「誰でも作れる」という手軽さが、彼のアクセルをベタ踏みにさせてしまったのだ。
「作る」こと自体が目的化し、現場が本当に困っていること、解決すべき課題が完全に置き去りにされている。このままでは、誰も使わない「ガラクタアプリ」が100個生まれるだけ。そして、現場は疲弊し、「AIなんてやっぱり使えない」という最悪の結末を迎えるだろう。
私は、彼の熱意という名の暴走列車を、なんとか止めなければならなかった。
「社長、素晴らしいスピード感ですね。その熱意こそが、この会社の強みです。ただ、一つだけご提案があります。100個のガラクタを作るより、現場が涙を流して喜ぶ『たった1個の宝物』を、まず作ってみませんか?」
「宝物?なんだそら」
五十嵐社長は怪訝な顔をした。
「例えば、製造二課の鈴木さん。彼はこの道40年のベテランで、彼の目でなければ見つけられない製品の微細なキズがあります。でも、彼はあと2年で定年です。彼の『神の目』を、彼の退職と同時に失ってしまっていいのでしょうか?もし、彼の判断を学習した『鈴木さんAIミニアプリ』が作れたら、それはこの会社にとって、100個のガラクタアプリよりも価値のある、まさに『宝物』になりませんか?」
具体的な人物の名前と、具体的で切実な課題を提示する。数字の目標ではなく、物語を語る。社長の「数を追う」という思考を、「価値を創る」という思考へと、そっと切り替えてあげるのだ。
彼はしばらく腕を組んで黙っていたが、やがて「…わかった。その鈴木とかいうのを、まずなんとかしてみろ」と呟いた。暴走列車は、なんとか減速を始めた。
「おれの仕事はアプリにできねぇ」現場の“職人魂”という名の壁
社長という名の嵐を乗り越えた先に待っていたのは、「現場」という名の、静かだが、底知れないほど深い海だった。
製造二課の鈴木さん(仮名・58歳)は、私が現場を訪れると、手元の部品から目を離さずに言った。
「んだ、ミズさんか。またパソコン持ってうろちょろしったな。社長がなんか騒いでるそうじゃねぇか。悪いけど、おれの仕事は、そんなおもちゃでできるほど甘ぐねぞ。この傷が見えるようになるまで、40年かかってるんだ。ボタン一つでわかるような仕事じゃねぇ」
彼の言葉には、棘があった。しかし、その棘の根元にあるのは、自分の仕事に対する圧倒的な誇りと、それが軽んじられていることへの怒り、そして、自分の存在価値が脅かされることへの恐怖だ。ここで「いえ、AIはすごいんです」と技術論を語っても、彼の心を閉ざさせるだけだ。
私の仕事は、AIを作ることではない。彼の信頼を勝ち取ることだ。
私はそれから一週間、毎日彼の持ち場に通い、ただひたすら彼の仕事を見続けた。質問はしない。口も挟まない。安全靴を履き、ヘルメットを被り、ただ黙って彼の隣に立つ。彼が不良品を見つけ、箱に投げ入れる。その一連の動きを、目に焼き付けた。
四日目の午後、彼が初めて口を開いた。
「…ミズさん、見ててもわがんねべ」
「はい、全くわかりません。でも、鈴木さんが不良品を投げ入れる時の、迷いのない動きが、見ていて惚れ惚れするほど美しいということだけは、わかりました」
彼は一瞬、虚を突かれたような顔をして、それから少しだけ口元を緩めた。
その週末、私は彼が見つけた不良品を何百個も借り受け、一つひとつ写真に撮り、どこにどんな傷があるのかを自分なりに分類した。そして月曜日、その写真と分類表を持って、再び彼の元を訪れた。
「鈴木さん、おれの仕事はアプリにできねぇ、とおっしゃいました。その通りです。鈴木さんの40年の経験そのものをアプリにすることなんて、誰にもできません。でも、鈴木さんの『弟子』を作ることはできるかもしれません」
私は一枚の写真を見せた。
「これは、僕のような素人が見ても絶対にわからない、微細な歪みです。この写真を見せて、『これは良品?不良品?』とAIに問い、AIがもし間違えたら、鈴木さんが『違う、これはこうだから不良品なんだ』と教えてあげる。そうやって、鈴木さんの『判断基準』を少しずつ学んでいく、出来の悪い弟子のようなアプリを作る。これなら、どうでしょうか?鈴木さんの仕事を奪うのではなく、鈴木さんの技術を、未来に残すための道具です」
彼は、じっと写真と私の顔を交互に見ていたが、やがて、ぽつりと言った。
「…まあ、そんなどうしようもねぇ弟子なら、育ててやってもいい」
それは、AIというテクノロジーが、彼の40年の職人人生に敬意を払い、弟子入りを許された瞬間だった。
“野良アプリ”の氾濫と、疲弊する担当者の悲鳴
社長の号令と、ベテラン職人の軟化。これで万事うまくいくかと思われたが、組織はそう単純ではない。社長が振りかざした「誰でも作れる」という錦の御旗は、思わぬ副作用を生んでいた。
情報システム部に所属する、このプロジェクトの担当者、田中さん(仮名)は、日に日に憔悴していた。
「ミズさん、大変です。営業部のAさんが、自分で顧客管理のミニアプリを作ったんですが、セキュリティがガバガバで、個人情報が丸見えなんです。経理部のBさんは、交通費精算のアプリを作ったけど、バグだらけでかえって手間が増えたとクレームが殺到しています。社長は『どんどん作れ』と言うし、現場からは苦情が来るし…。もう、何がなんだか…」
「誰でも作れる」という自由は、無法地帯を生んだ。管理部門の許可なく、各々が勝手に作った「野良アプリ」が社内システムを汚染し始めていたのだ。これこそ、「ツールの民主化」がもたらす最も恐ろしい罠だ。自由には、責任が伴う。しかし、そのルールがないまま自由だけが与えられると、組織は内側から崩壊していく。
田中さんは、善意のアプリ開発者と、それによって迷惑を被るユーザーとの間で、たった一人、サンドバッグになっていた。
私の役割は、田中さん個人の問題ではなく、組織全体の問題として、このカオスを再定義することだった。私は五十嵐社長を交えた会議で、一枚のスライドを見せた。そこには、蛇口が壊れて水が溢れかえっているキッチンのイラストが描かれていた。
「社長、今、社内で起きているのはこういうことです。『誰でも料理していいよ』と言った結果、みんなが好き勝手にコンロを使い、食材を散らかし、後片付けもせずにキッチンが水浸しになっている状態です。このままでは、食中毒が起きるか、火事になるかです」
「じゃあ、どうすればいいんだ!」
「ルールを作るんです。まず、『安全なキッチンの使い方』を決めましょう。火を使う時は換気扇を回す、包丁を使ったら必ず洗って元の場所に戻す、といった基本的なルールです。AIミニアプリで言えば、『個人情報を扱う場合は必ず情報システム部の承認を得る』『公開前に必ず三人以上でテストする』といったガイドラインです。そして何より、『作った人には、後片付け、つまりメンテナンスの責任がある』ことを明確にする。まずは、このルール作りから始めませんか?」
自由を制限するのではなく、安全に自由を謳歌するための「ガードレール」を設置する。私たちは、田中さんを中心に「AIミニアプリ開発ガイドライン」を作成し、野良アプリの横行に歯止めをかけた。それは、トップダウンの熱狂から、ボトムアップの秩序へと、改革の舵を切り直す、重要な転換点となった。
終わりに:「作る」から「共に育てる」へ
プロジェクト開始から半年後。鈴木さんの「神の目」を学習する検品支援アプリは、バージョン3になっていた。まだまだ彼の足元にも及ばないが、新人でも8割方の不良品を見つけられるようになり、教育係の負担は劇的に減った。
先日、現場を訪れると、鈴木さんが若い技術者である田中さんと、モニターを囲んで議論していた。
「田中くん、このパターンの傷、まだAIは『良品』って言うんだよな。光の当て方をこう変えると、微妙な影が出るんだ。この影を覚えさせられねぇか?」
「なるほど…。じゃあ、照明の角度データをパラメータに追加してみましょうか。鈴木さん、来週、また不良品のサンプルをいくつか貸してください!」
その光景を見て、私は確信した。
AIミニアプリ開発の本当の価値は、アプリを「作ること」それ自体にはない。それは、これまで決して交わることのなかった、現場のベテラン職人と、デジタルの知識を持つ若手技術者が、一つの目的のために知恵を出し合い、「共に育てる」という関係性を「作ること」にあるのだ。
AIは、完成品ではない。それは、現場の知恵とデジタルの力を掛け合わせ、対話を繰り返しながら、共に成長していく「生き物」だ。
元の記事で、私は「AIを作るスキルが、あなたの市場価値を高める」と書いた。今、それをこう訂正したい。
AIを、現場の人々と共に「育てていく」スキルこそが、これからの時代、あなたの、そしてあなたの会社の、本当の価値になる、と。
あなたの会社がAIを作ろうとする時、それは単なるツール導入ではない。それは、組織の文化と、人と人との関係性を、根底から問い直す、壮大な旅の始まりなのである。