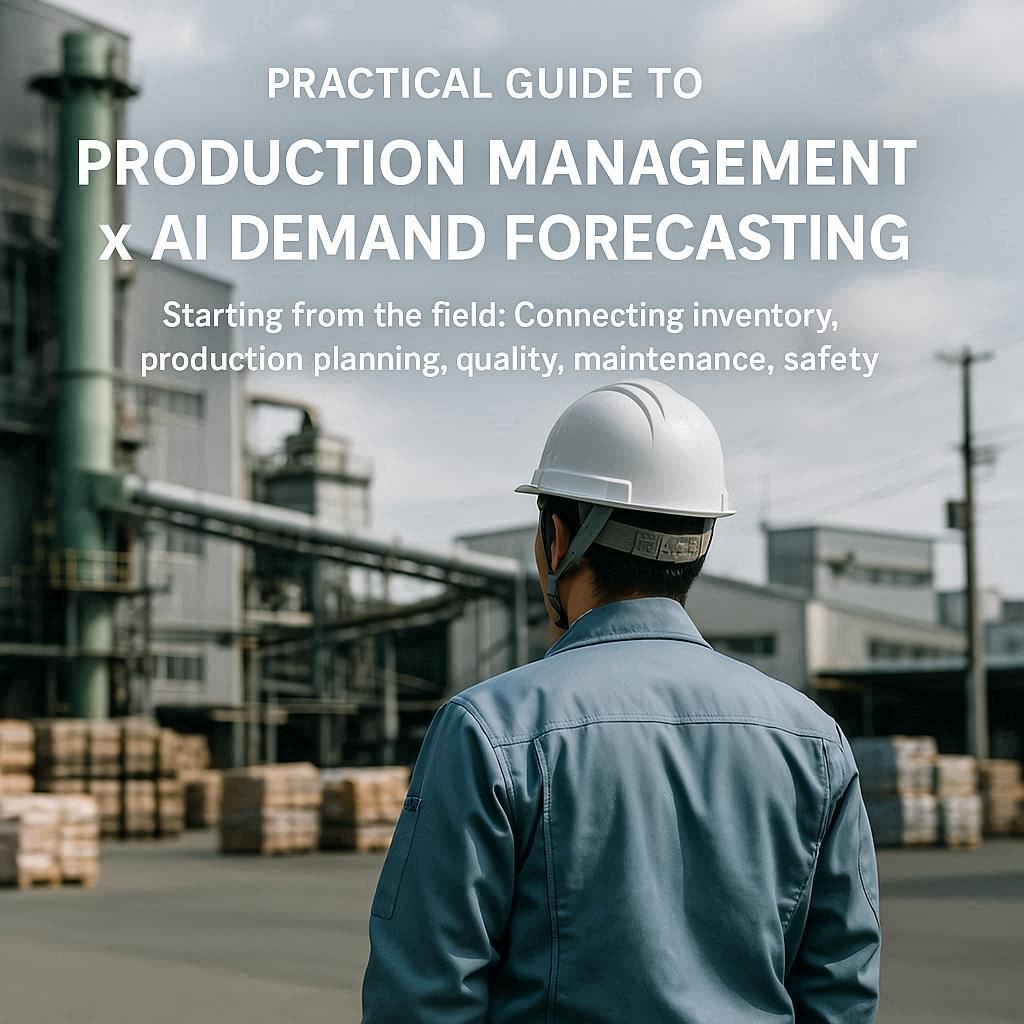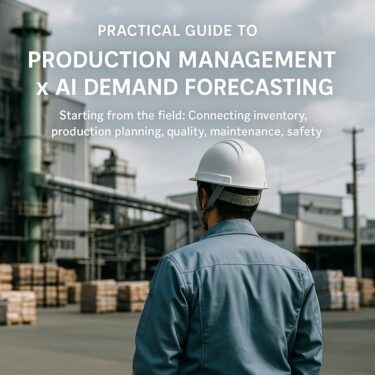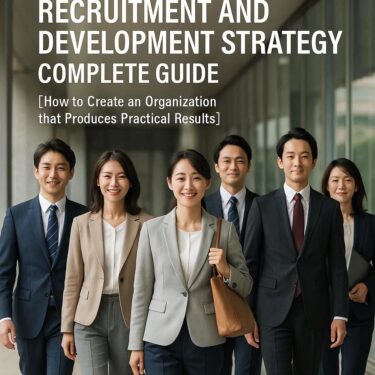AIは魔法の杖じゃない!生産管理DXの裏側で本当に起きていた“人と組織”の泥臭い物語
先日公開した『現場から始める「生産管理×AI需要予測」実践ガイド』という記事、ありがたいことに多くの方にお読みいただいているようです。あの記事では、AI導入の成功に向けたステップを、いわば「理想の地図」として描きました。
しかし、実際のプロジェクトという“旅”は、地図通りに進むことなんて、まずありません。道なき道を進み、予期せぬ嵐に見舞われ、時には仲間とぶつかりながら、泥だらけになって目的地を目指す。それが現実です。
今日は、あの綺麗な地図の裏側で、私たちがクライアント企業の皆さんと共に経験した、もっと人間臭くて、もっと泥臭い「もう一つの物語」をお話ししようと思います。これは、最新技術の導入が、いかに「人の心」と向き合う仕事であるかという、現場からのリアルなレポートです。
プロジェクトの幕開け:期待と不安が渦巻く会議室
今回の舞台は、長年の勘と経験、そして無数のExcelファイルによって支えられてきた、実直なものづくりで評価の高い中堅製造業のA社。社長の号令一下、「AIを活用した生産管理改革プロジェクト」が立ち上がりました。
プロジェクトの担当に任命されたのは、入社10年目の佐藤さん(30代)。聡明でやる気に満ち溢れた女性ですが、経営層からの「AIで在庫を30%削減しろ」という高い期待と、現場の「また新しいお題目が降ってきた…」という冷めた空気との間で、早くも板挟みになっていました。
そして、この物語のもう一人の主役が、生産管理課の鈴木課長(50代後半)。この道35年の大ベテランで、工場の隅から隅まで知り尽くした生き字引のような存在です。彼の頭の中にある生産計画こそが、A社の心臓部でした。
最初の会議で、私が意気揚々とAI導入のメリットを説明した後のこと。鈴木課長は腕を組んだまま、静かに、しかし芯のある声でこう言いました。
「あんたの言うこどは、わがる。理屈は立派だの。でもな、うぢの現場は、そんげな綺麗な数字遊びで動いでるんねぞ。天気もあれば、機械のご機嫌もある。隣のラインのBさんが急に休むごどもある。AIだかなんだか知らねぇけど、それに全部対応でぎんのが?」
庄内地方独特の温かみがありながらも、鋭いその言葉。これが、私たちの長い旅の始まりを告げる号砲でした。
【裏話①】最初の壁:「本当の課題」はデータの中にはない
あの記事では、ステップ1を「課題定義とKPI設定」と簡単に書きました。しかし、これが最初の、そして最大の関門でした。
経営層が掲げるKPIは「在庫削減率」や「欠品率」。もちろん重要です。しかし、佐藤さんと一緒に現場を回り、鈴木課長や担当者の皆さんに話を聞くと、彼らの口から出てくるのは、もっと生々しい悲鳴でした。
「一番困っているのは、営業からギリギリで入る仕様変更と納期変更です。そのたびに鈴木課長が徹夜で計画を練り直してるんです」
「製品マスタがぐちゃぐちゃで、似たような名前の部品コードがいくつもあって…。発注ミスが絶えません」
「そもそも、どのExcelファイルが最新の在庫数なのか、担当者しか分からない状態なんです」
見えてきたのは、AIで需要予測をする以前の、もっと根深い問題。データの信頼性が低く、部門間の連携もスムーズではない。この状態でAIを導入しても、それは砂上の楼閣になるだけです。
私は佐藤さんに言いました。「佐藤さん、社長には私から話します。最初のKPIは『在庫削減率』の前に、『生産計画の修正にかかる時間』や『手戻り工数』を置きませんか?まずは、鈴木課長や現場の皆さんの負担を減らすこと。それが一番の近道です」
そして、鈴木課長にはアプローチを変えました。
「鈴木課長、AIは万能ではありません。むしろ、鈴木さんのその35年の経験と勘を、どうにかしてAIに学習させられないかと考えているんです。鈴木さんの“弟子”として、AIを育てていただけませんか?」
私の言葉に、鈴木課長の険しい表情が少しだけ和らいだのを、今でも覚えています。
「…ほう、わしの弟子、ね。そんげだば、悪ぐねぇかもしんねな」
【コンサル術のヒント】
AI導入の目的を、経営層が求める「経営指標の改善」だけに置かない。現場が日々感じている「痛み」や「負担」を軽減するという目的を加え、それを測るKPIを設定することが、現場を味方につける第一歩です。AIを「仕事を奪う脅威」ではなく、「自分たちの仕事を楽にしてくれるアシスタント」として位置づけることが重要になります。
【裏話②】データの海で溺れる:「宝の山」か「ゴミの山」か
ステップ2の「データ棚卸し」。これもまた、言葉にするのは簡単ですが、現実は想像を絶するものでした。佐藤さんが各部署から必死で集めてくれた過去数年分の販売実績や生産履歴のExcelファイル。それらは、まさに「魔窟」でした。
- 製品コードの全角と半角が入り乱れ、ハイフンがあったりなかったり。
- 日付の書式が「2023/4/1」もあれば「R5.4.1」もある。
- 担当者だけが分かる謎の記号が入力された「備考欄」。
- 月の途中で集計のロジックが変更されているシート。
「これ…どうしましょう…」
膨大なファイル群を前に、佐藤さんは青ざめていました。このままでは、AIが学習する以前の問題です。データを綺麗にする「データクレンジング」だけで、プロジェクトが終わってしまいかねない勢いでした。
ここで私は、一つの決断をしました。
「佐藤さん、完璧を目指すのはやめましょう。100点満点のデータなんて、この世に存在しません。まずは60点でいい。いや、30点でいいから、一度この『汚れたデータ』をAIに食わせてみませんか?」
「え、でも、そんなことをしたら、おかしな結果が出ませんか?」
「はい、きっと出ます。でも、それでいいんです。『AIはこんなおかしな予測をしちゃいました。なぜなら、ここのデータが汚いからです』と、事実を突きつける方が、みんなデータ入力の重要性を理解してくれます。失敗を可視化するんです」
私たちは、最低限のルール(コードの統一、日付形式の変換など)だけを決めて、不完全なデータで最初の予測モデルを回してみました。結果は、案の定、突拍子もないものでした。ある製品の需要が、来月突然10倍になるという予測が出たのです。
しかし、これがカンフル剤になりました。
「なんでこんな予測になるんだ?」と集まってきた関係部署のメンバーに、私たちが「原因はこの部分のデータ入力が抜けているからです」と具体的に示すと、皆が「なるほど…」と頷きました。
【コンサル術のヒント】
データ整備において完璧主義は禁物です。「今あるデータで何ができるか」をまず試し、その結果(多くは失敗例)を関係者に見せることで、「自分ごと」としてデータ品質への意識を高めてもらうアプローチが有効です。データ品質をスコア化し、部署ごとにフィードバックするのも、ゲーム感覚で改善を促す良い方法です。
【裏話③】AI vs ベテランの勘:世紀の対決と和解
いよいよPoC(実証実験)の段階。私たちは過去のデータを使って、「もしあの時AIがあったら、どんな予測をしていただろうか」というバックテストを行いました。
AIが弾き出した来月の主力製品の需要予測数は「1,500個」。
それを見た鈴木課長は、鼻で笑いました。
「甘っだな。こんげな数字、あだになるわげねべ。来月は3連休があるし、近隣のイベントで人が集まる。それに、競合のB社が設備の定期修理で生産が落ちるっていう情報も入ってきてる。最低でも1,800…いや、1,900は行ぐべ」
まさに、AIの弱点が露呈した瞬間でした。AIは過去のデータパターンからしか学習できません。鈴木課長の頭の中にある、業界の裏情報や、長年の経験で培われた「市場の空気感」といった暗黙知は、データ化されていないため、予測に反映されていなかったのです。
現場からは、「ほら、やっぱりAIなんて使えないじゃないか」という空気が漂い始め、佐藤さんの顔にも不安の色が浮かびます。プロジェクト最大の危機でした。
ここで私が取った行動は、AIの正当性を主張することではありませんでした。
「鈴木課長、お見事です。その『競合の生産が落ちる』という情報、それこそが私たちが一番欲しい“データ”なんです。それをAIに教えていただけませんか?」
私たちは、ホワイトボードに鈴木課長が語る「予測を左右する特殊要因」をすべて書き出しました。
「3連休」「近隣のイベント」「競合B社の定期修理」「原料価格の変動」…。
そして、それらの情報を「イベントフラグ」という形でデータ化し、AIに再学習させたのです。
すると、次にAIが弾き出した予測値は「1,870個」。
鈴木課長の予測に、驚くほど近い数字でした。
その数字を見た鈴木課長は、しばらく黙っていましたが、やがてニヤリと笑いました。
「ほう…。こいつ、なかなか見所がある弟子だの。よし、もうちっと鍛えでやるか」
この瞬間、AIは現場にとっての「得体の知れない脅威」から、「経験の浅い、だけど素直で優秀な部下」へと変わったのです。AIの予測を叩き台に、ベテランが最終的な補正を加える「人とAIの協調」という運用スタイル(ヒューマン・イン・ザ・ループ)が、A社に生まれた瞬間でした。
【コンサル術のヒント】
AIの予測が人の勘とズレた時こそ、最大のチャンスです。AIを人と対立させるのではなく、人の知見をAIに「教え込む」プロセスを共有することで、AIへの信頼と理解を深めることができます。「AIに仕事をさせる」のではなく、「人とAIが一緒に仕事をする」という協調の形を具体的に示すことが、現場の抵抗感を和らげる鍵となります。
旅の終わりに:地図は自分たちで描くもの
あの後、プロジェクトは驚くほどスムーズに進みました。現場から積極的に「こんなデータも使えるんじゃないか?」という声が上がるようになり、佐藤さんは経営と現場をつなぐ立派なブリッジ役として成長しました。
最終的に、AIは生産管理の様々な場面で「優秀なアシスタント」として定着し、当初の目標だった在庫削減はもちろんのこと、鈴木課長をはじめとする現場の皆さんの計画業務にかかる残業時間を大幅に削減するという、副次的ですが最も価値のある成果を生み出しました。
私が書いた『実践ガイド』は、あくまで一般的な地図に過ぎません。どんな道を選び、どんな景色を見るかは、旅をする皆さん自身が決めることです。AI導入という旅の成功は、結局のところ、技術の優劣ではなく、いかに多様な立場の人々を巻き込み、同じ目的地に向かって歩いていけるかにかかっています。
もしあなたが今、DXやAI導入の入り口に立っているなら、まずやるべきことは、最新ツールを調べることではありません。
現場のベテランの話に、ただひたすらに耳を傾けること。
彼らが何に誇りを持ち、何に苦しんでいるのかを知ること。
そこから、あなたの会社だけの「オリジナルの地図」を描き始めるのが、きっと一番の近道なのだと、私は信じています。