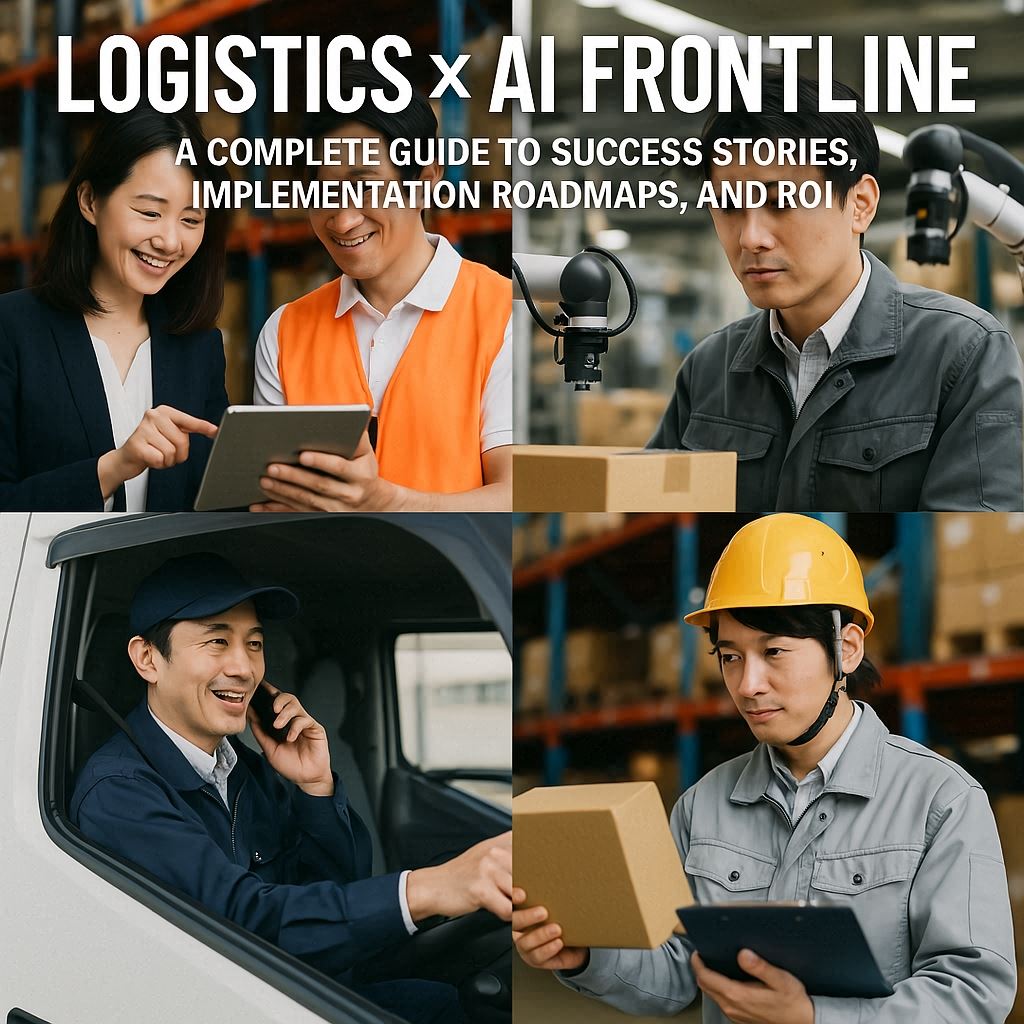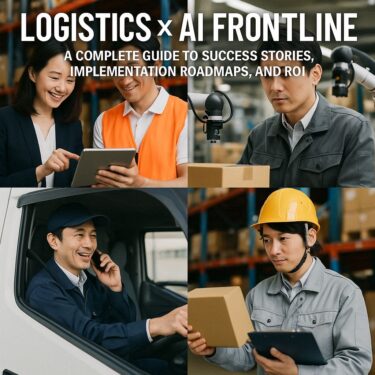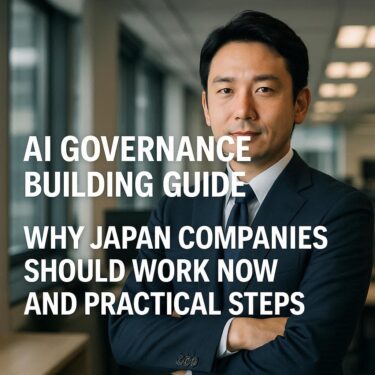AIは銀の弾丸じゃない。物流改革の現場で本当に起きていた「人と組織」の泥臭い話
先日、「物流×AI最前線」という記事を公開させてもらった。おかげさまで多くの方に読んでいただき、「自社でも検討したい」「ロードマップが参考になった」といった嬉しい声をいただいた。
あの記事では、AI導入の成功事例や具体的な手順を、できるだけ分かりやすく、体系的にまとめたつもりだ。アクシアルリテイリングさんの需要予測、ファミリーマートさんの配送計画、NTTロジスコさんの検品自動化…。どれも素晴らしい成果であり、物流業界の未来を照らす希望の光だ。
だが、今日はあえて、あの記事では書ききれなかった「裏側」の話をしたい。
華々しい成功事例や、きれいに整理されたロードマップの裏には、必ずと言っていいほど、生々しい人間ドラマがある。経営者の期待と焦り、現場のプライドと抵抗、そして板挟みになるプロジェクトメンバーの苦悩。AIという最新技術を導入するプロジェクトは、その実態の9割が、こうした「人と組織」を相手にした、実に泥臭い仕事の連続なのだ。
この記事は、AI導入の「きれいごと」に疲れたあなた、理想と現実のギャップに悩むあなたのために書いた。これは、ある物流会社の改革プロジェクトで、私が実際に体験した物語だ。技術論や方法論だけでは決して越えられない壁に、我々がどう立ち向かったのか。その奮闘の記録が、あなたの現場の「今」を乗り越える、ささやかなヒントになれば幸いだ。
「AIで全部解決だべ?」経営者の”魔法の杖”願望との戦い
プロジェクトの始まりは、いつも経営トップの一言からだ。
「ミズさん、ウチもAIだ。AIで物流をなんとかしたい。2024年問題も人手不足も、AIがあれば一発で解決できるんだべ?」
ある中堅物流会社の社長、佐藤さん(仮名)は、目を輝かせながら私にそう語った。彼は業界紙で読んだAIの成功事例に感銘を受け、「ウチも乗り遅れるわけにはいかない」と息巻いていた。その熱意は素晴らしい。しかし、この「AI=魔法の杖」という認識が、最初の、そして最大の落とし穴になる。
私は、あえて水を差すことから始めた。
「社長、素晴らしいですね。ただ、AIは魔法の杖ではねんですよ。優秀ですけど、万能じゃない。それに、AIを導入したからといって、明日から突然ドライバーが増えたり、倉庫が自動で動いたりするわけでもないんです」
佐藤社長は少し不満そうな顔をした。無理もない。彼は「投資」に見合う「即効性のある劇的な成果」を期待しているのだ。ここで専門用語を並べ立ててROI(投資対効果)の複雑な計算式を見せても、彼の心には響かないだろう。
私が取ったアプローチは、徹底的な「目線の引き下げ」だった。
「社長、まずは一つだけ、社内で『これは本当に勘弁してほしい』と思っている面倒な作業を教えてください。どんな些細なことでもいいです」
彼は少し考えた後、「うーん…」と唸りながらこう言った。
「毎日、ベテランの配車係の鈴木が、夜遅くまでウンウン唸りながら翌日の配送ルートを組んでるんだ。あいつが倒れたら、ウチの配送は止まる。あれを何とかできねぇもんかな…」
これだ。私は心の中でガッツポーズをした。
「それ、やりましょう。まずは鈴木さんの『頭の中』をAIに学習させて、鈴木さんの負担を半分にする。そこから始めませんか?鈴木さんが早く帰れるようになって、家族と晩酌できるようになったら、それは立派な改革の第一歩です」
AIでコストを10億円削減する話ではない。AIで鈴木さんの仕事を楽にする話だ。具体的な人の顔が浮かぶ小さな目標。これが、壮大な「AI導入」という名の航海の、信頼できる最初の羅針盤になる。
経営者との対話で重要なのは、「期待値のコントロール」と「成功の再定義」だ。彼らが求める「大きな成果」を否定するのではなく、そこへ至るまでの「確実な一歩」を共に設定してあげる。壮大なビジョンと、現場の現実。その両方を見据え、両者の翻訳者となること。それが、我々の最初の仕事なのだ。
「おれの勘が一番だ!」現場のベテランをどう巻き込むか
経営者の説得が第一関門なら、第二関門は「現場の抵抗」だ。特に、長年の経験と勘で現場を支えてきたベテランほど、この壁は高く、厚い。
例の配車係、鈴木さん(仮名・58歳)は、まさにその典型だった。私が挨拶に行くと、彼はパソコンの画面から目を離さずにこう言った。
「んだ、あんたがミズさんか。AIだのデータだの、わがんねごどばり言うなでの。おれはこの道30年だ。この辺の道の混み具合も、客先のクセも、全部この頭さ入ってら。おれの勘の方が、機械なんかよりずっと当たるわい」
これだ。これこそ、私が聞きたかった言葉だ。
多くのプロジェクトでは、こうしたベテ…ランを「抵抗勢力」や「変化を嫌う古い人間」とレッテルを貼ってしまう。だが、それは大きな間違いだ。彼の言葉は、AIに対する拒絶ではない。自分の仕事に対する誇りと責任感の裏返しなのだ。彼を敵に回した瞬間、プロジェクトは頓挫する。
私は、彼の隣に椅子を持ってきて座った。そして、こう切り出した。
「鈴木さん、おっしゃる通りです。AIなんて、鈴木さんの30年の経験には到底敵いません。だから、お願いがあるんです。鈴木さんのその『勘』、そのすごい技術を、AIに教えてやってくれませんか?」
鈴木さんは、怪訝な顔で私を見た。
「AIさ教える?なんだそら」
「つまりですね、鈴木さんの『分身』をAIで作るんです。例えば、『この道は朝8時台は混むから避ける』とか、『A社は午前中に持っていかないと担当者がうるさい』とか、鈴木さんの頭の中にあるノウハウを、全部AIに覚えさせるんです。そしたら、鈴木さんの分身がルートのたたき台を作ってくれるようになる。鈴木さんは、それを見て最後に微調整するだけで済むようになるんです。そしたら鈴木さん、もっと若い連中の指導とか、本当に大事な仕事に時間を使えるようになると思いませんか?」
私は、AIを「鈴木さんの仕事を奪う脅威」ではなく、「鈴木さんの技術を継承し、彼の負担を軽くする弟子」として位置づけた。
それから一週間、私は毎日鈴木さんの隣に座り、彼が配車を組む様子をただひたすら観察した。なぜそのルートを選んだのか、なぜその順番にしたのか、一つ一つ質問した。彼は最初こそ面倒くさそうにしていたが、私が彼の仕事に真摯な敬意を払い、熱心に彼の「技術」を学ぼうとする姿勢を見せるうちに、少しずつ心を開いてくれた。
ある日の夕方、彼がぽつりと言った。
「ミズさん、明日のB興業への配送な、午前中指定だけど、あそこは新しい事務員が入ってから、受け入れに時間かかって後の便が全部遅れるんだ。だから、ほんとは11時半ギリギリさ着くように組むのが一番いいんだ。…まあ、そんなごど、AIさわがんねべけどな」
「鈴木さん!それです!それこそAIが一番学びたい『生きた知恵』なんですよ!」
私は彼の言葉をメモしながら、心の中で再び叫んだ。データだけでは決して見えてこない「暗黙知」。これこそが、現場に眠る本当の宝なのだ。
「現場巻き込み」とは、単に説明会を開いて協力を要請することではない。現場一人ひとりの仕事に敬意を払い、彼らのプライドを尊重し、彼らを「改革の主役」として舞台に上げることだ。AIという最新技術が、現場のベテランの知恵と経験を「見える化」し、「継承」するための最高のツールになり得る。その事実に彼ら自身が気づいた時、最も強固だった壁は、最も頼もしい推進力へと変わる。
板挟みのプロジェクトリーダーを救え!孤立させないための防波堤
経営トップの「早くやれ」という圧力。現場からの「余計な仕事増やすな」という反発。その巨大な圧力のど真ん中に立たされ、押し潰されそうになるのが、プロジェクトリーダーだ。
このプロジェクトでも、情報システム課の若きリーダー、高橋さん(仮名)がその役目を担っていた。彼は真面目で優秀だったが、日に日にその顔から生気が失われていくのが分かった。
「上からは『進捗はどうなってるんだ!』と詰められ、現場に行けば『また来たのか』と嫌な顔をされる…。一体、誰のためにやってるのか分からなくなります…」
元記事で紹介した「90日で成果を出す導入ロードマップ」は、あくまで理想形だ。現実には、データの収集が遅れたり、現場の協力が得られずテストが中断したり、予期せぬトラブルの連続。計画通りに進むことなど、まずない。
そんな時、孤独なリーダーを支えるのが、我々のような外部の人間の重要な役割だ。私は、高橋さんの「防波堤」となり、「翻訳者」となることに徹した。
まず、毎週の進捗会議のやり方を変えた。経営陣が出席する会議では、遅延やトラブルといった「悪いニュース」を私が引き受けて報告した。
「佐藤社長、申し訳ありません。現場の鈴木さんの『秘伝のタレ』とも言えるノウハウをAIに学習させるのに、想定より少し時間がかかっています。しかし、これができれば、単なるルート最適化ソフトとは次元の違う、まさに『ウチの会社だけの』最強の武器が手に入ります。もう少しだけ、現場の職人技をAIに叩き込む時間をください」
このように、遅延を「問題」ではなく「価値向上のための必要な投資」と再定義して伝える。経営者には、現場の奮闘ぶりや、目には見えない「納得感の醸成」といった定性的な進捗を伝えることが重要だ。
一方で、現場との打ち合わせでは、経営陣のメッセージを彼らの言葉に翻訳して伝えた。
「鈴木さん、社長が『鈴木さんが早く帰れるようになるのが一番の成果だ』って言ってましたよ。会社の宝である鈴木さんの技術を、ちゃんと会社に残したいんだそうです」
リーダーが一人で矢面に立つのではなく、私のような外部の人間が緩衝材になる。そして、それぞれの立場が持つ善意や期待を、誤解のないように翻訳して繋ぎ合わせる。このコミュニケーションのハブ機能こそが、疲弊するリーダーを守り、プロジェクトの推進力を維持するために不可欠なのだ。
また、「スモールスタート」や「PoC(概念実証)」といった手法は、技術的なリスクを低減するだけでなく、プロジェクトメンバーの「心理的安全性」を確保するための重要な安全装置でもある。「まずは配車係の鈴木さんの分だけ」「まずは1台のトラックだけ」で試す。この小さく区切られた成功体験が、「自分たちにもできるかもしれない」という自信を生み、次のステップへ進む勇気を与えてくれるのだ。
データは宝の山か、ゴミの山か。泥の中から宝を探す旅
「AIにはデータが命」。これは紛れもない事実だ。元記事でも「データ棚卸し」の重要性を説いた。しかし、この一言の裏には、想像を絶するほど地道で、泥臭い作業が隠されている。
いざ「データを集めましょう」となっても、現場から出てくるのは、フォーマットがバラバラのExcelファイル、手書きの汚い文字で書かれた日報の束、特定のPCの中にしか存在しない謎の管理ファイル…。まさに「ゴミの山」だ。
データサイエンティストたちは頭を抱えた。「これでは分析できません…」。
完璧なデータなど、どこにも存在しない。それが現実だ。「完璧なデータを待っていたら、プロジェクトは一生始まらない」。これが私の信条だ。
私たちは、方針を大きく転換した。
「ないものは仕方ない。今、ここにあるもの、そして、明日から取れるものだけで始めよう」
具体的には、全トラックに搭載されていたGPSロガーのデータと、鈴木さんが毎日つけていた手書きの配車計画表。この二つに絞った。GPSデータから「実際に走ったルートと時間」を、手書きの計画表から「鈴木さんが意図したルートと時間」を抽出する。そして、その「差分」こそが、鈴木さんの頭の中にしかない「渋滞予測」や「顧客の特性」といった暗黙知が隠れているのではないか、と仮説を立てた。
データサイエンティストは、手書きの計画表をスキャンし、AI-OCRでテキスト化することから始めた。誤認識も多く、最後は人海戦術で修正するしかなかった。まさに、DX(デジタルトランスフォーメーション)ならぬ、MX(手作業トランスフォーメーション)だ。
しかし、この泥臭い作業の中から、宝物が見つかり始めた。鈴木さんが無意識に避けていた「魔の時間帯」や「特定の曜日にだけ混む抜け道」などが、データとして可視化され始めたのだ。
それを見た鈴木さんの目が、初めて変わった。
「なんだこれ…。おれ、いつもここば避けてたけど、データで見ると、ほんとにこっちの方が早ぇんだな…。おれの勘も、まんざらでもねぇな」
データは、彼の経験を否定するものではなく、彼の「勘」の正しさを証明する「証拠」となった。この瞬間、彼はデータに対して心を開き、より積極的に情報をくれるようになった。
AI導入プロジェクトとは、突き詰めれば「業務の見える化」と「データ文化の醸成」に他ならない。最新のアルゴリズムを導入する前に、自分たちの仕事がどんな情報(データ)に基づいて行われているのかを、全員で直視するプロセスが必要なのだ。それは決して華やかな作業ではない。むしろ、泥臭いゴミ拾いのような作業の連続だ。しかし、そのゴミの山の中から、自分たちだけの宝物を見つけ出した時、組織は初めて変わることができる。
終わりに:AIは人を映す鏡だ
プロジェクト開始から約半年後。鈴木さんの「分身」とも言える配車計画支援システムは、なんとか形になった。AIが算出したルートのたたき台を、鈴木さんが最終チェックして修正する。彼の作業時間は、半分以下になった。
先日、夕方5時半に会社を訪れると、いつもなら難しい顔でパソコンと睨めっこしているはずの鈴木さんが、帰る支度をしていた。
「お、ミズさん。お先に失礼します。今日は孫の誕生日なんでな。AIの野郎が、おれより気の利いたルートば出すもんだから、仕事が早く終わって助かるわ」
そう言って笑う彼の顔を見て、私はこの仕事の本当の価値を改めて感じた。
AIは、決して魔法の杖ではない。それは、組織の強みも弱みも、人間の知恵も怠惰も、全てを映し出す「鏡」のようなものだ。AI導入がうまくいかない時、問題は技術にあるのではなく、その鏡に映し出された我々自身にあることが多い。
元記事で紹介した華々しい成果やロードマップは、ゴールではなく、あくまで航海図だ。実際の航海は、時に嵐に見舞われ、時に凪で進まなくなりながらも、船に乗る全員で知恵を出し合い、オールを漕ぎ続ける泥臭い旅路そのものだ。
もしあなたが今、AI導入の壁にぶつかっているのなら、思い出してほしい。その壁は、きっと「人」の壁だ。焦る必要はない。一人で抱え込む必要もない。目の前にいる人の話に耳を傾け、彼らの仕事に敬意を払い、共に汗をかくこと。遠回りに見えても、それが改革を成功に導く、唯一の道なのだから。