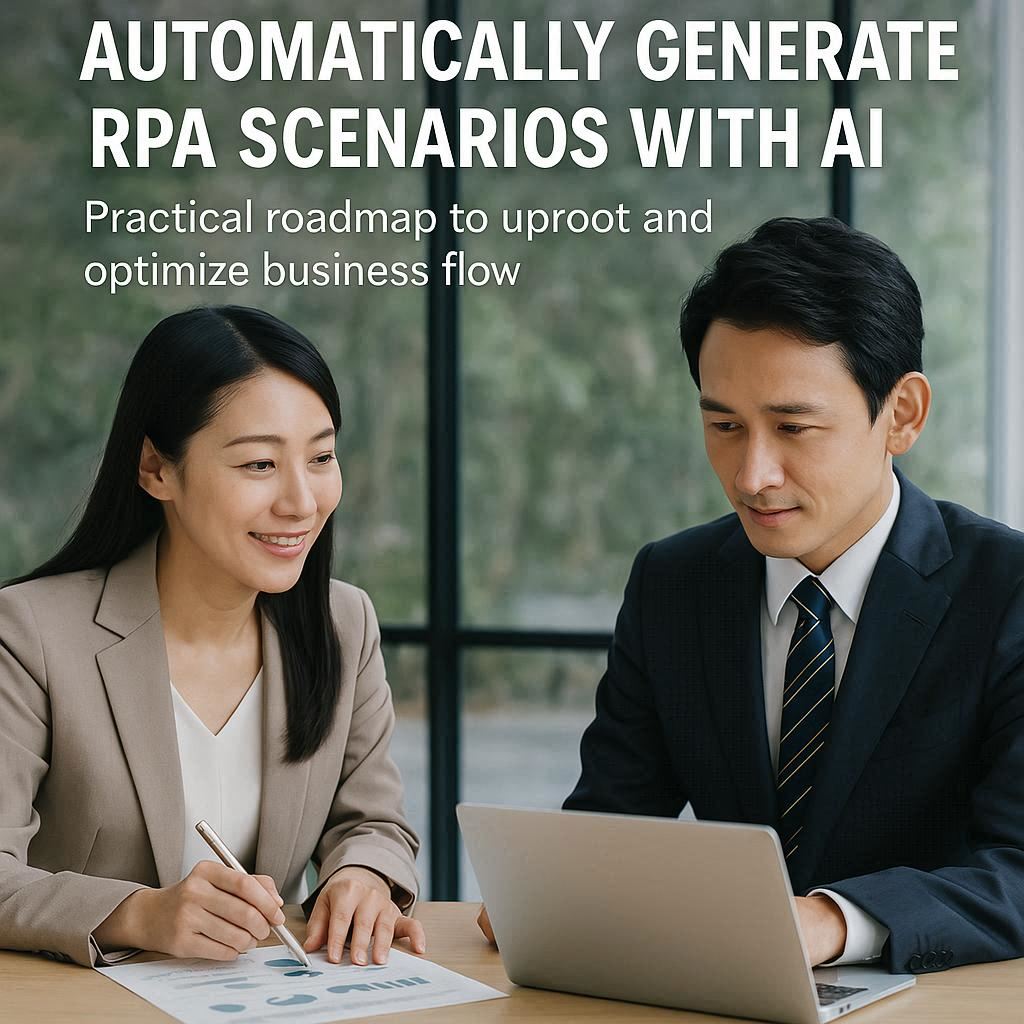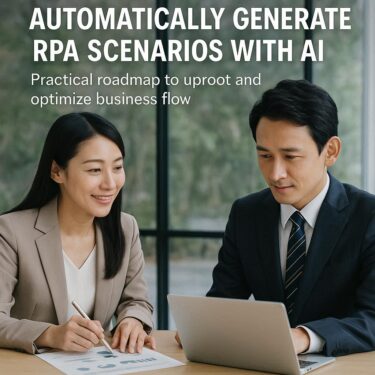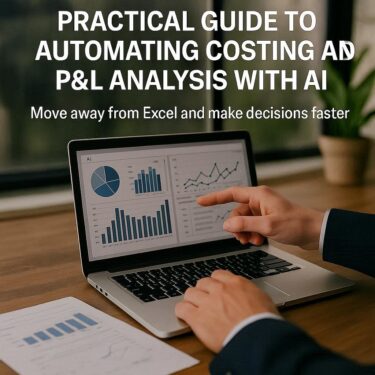AIでRPAシナリオの裏側で。成功の鍵は「業務フロー図」より先に描くべき「人の地図」だった話
先日公開した『AIでRPAシナリオを自動生成!業務フローを根こそぎ最適化する実践ロードマップ』という記事、ありがたいことに多くの方に読んでいただけたようです。記事では、As-IsからTo-Beへ、理想の業務プロセスを設計するためのステップを、さも当然のように、整然と解説しました。
AIでRPAシナリオを自動生成!業務フローを根こそぎ最適化する実践ロードマップ 「RPAを導入したが、定型業務の自動化だけでは思ったほど成果が出ない…」「話題の生成AI、どう業務に活かせばいいのか具体的なイメージが湧かない…」 […]
しかし、正直に告白します。あの綺麗なロードマップの裏側には、教科書には決して書かれない、もっと泥臭くて、人間臭いドラマが必ず存在します。
ツールを導入すれば業務が効率化される。AIを使えばバラ色の未来が待っている。そんな幻想は、現場の分厚い扉の前でいとも簡単に砕け散ります。なぜなら、どんなに優れたツールやフレームワークも、それを使う「人」の心を動かせなければ、ただのガラクタになってしまうからです。
今日は、あの記事の行間には書ききれなかった、あるプロジェクトでの裏話をお話ししようと思います。これは、ロジックや技術論だけでは乗り越えられない「見えない壁」と、私たちがどう向き合ってきたかの記録です。もしあなたが今、社内改革の渦中で孤軍奮闘しているのなら、きっと共感していただける部分があるはずです。
最初の壁:「As-Isの可視化」は、実は「感情の可視化」だった
プロジェクトの第一歩は、いつだって現状把握から始まります。記事では「泳線付きフロー図で現状を解剖する」なんて、格好いい言葉を使いました。しかし、現実はヒアリングという名の「道場破り」から始まるのです。
今回のプロジェクトの担当窓口は、入社8年目の佐藤さん(30代)。非常に真面目で勉強熱心な女性です。彼女は我々にこう切り出しました。
「すみません、業務フロー図って言われても、何から書けばいいのか…。それに、この業務を一番よく知っているのは業務部の鈴木部長なんですけど、あの方、昔気質で…。私が聞いても『そんなの見てわかるだろ』って言われちゃいそうで、ちょっと怖いんです」
この「ちょっと怖い」という感情。これこそが、改革を阻む最初の、そして最大の壁です。
案の定、鈴木部長(50代)の元へ挨拶に伺うと、腕を組んだまま、パソコンの画面から視線を外さずにこう言いました。
「ああ、あんたらか。なんだか知らねども、社長がAIだかなんだか騒いでっでの。俺は忙しいんだ。そんな面倒なごどしなくても、この業務のことは俺の頭さ全部入ってる。わがるように説明すっからの、あとはうまいごどやってけろ」
出ました。典型的な「俺の頭の中」パターンです。これは、単なる非協力的な態度ではありません。長年、自分だけがこの業務を支えてきたという自負と、自分の聖域(サンクチュアリ)を荒らされたくないという強い警戒心の表れなのです。ここで正面から「いえ、部長。業務は可視化して標準化しないと属人化が…」なんて正論を振りかざしたら、その瞬間にプロジェクトは詰みです。
私は鈴木部長にこう話しました。
「部長、おっしゃる通りです。部長の頭の中には、この会社の宝とも言える“ノウハウの地図”が完璧に入っているんですね。本当にすごいことです。ただ、その宝の地図が部長の頭の中にしかないのは、会社にとってものすごいリスクだと思いませんか? 私たちの仕事は、その地図を盗むことじゃないんです。部長に先生になってもらって、その素晴らしい地図を、誰もが見える大きな模造紙に一緒に書き写して、会社の公式な『資産』にしたいんです」
ポイントは2つ。彼の経験とプライドを最大限にリスペクトすること。そして、彼の知識を「個人商店の秘伝のタレ」から「会社全体の資産」へと昇華させる、という大義名分を提示することです。
鈴木部長は、しばらく黙っていましたが、少しだけ口角を上げて「…まぁ、そこまで言うなら、しゃねごったな」と呟きました。心の扉が、ほんの少しだけ開いた瞬間でした。
一方、担当者の佐藤さんには、こう伝えました。
「佐藤さん、完璧なフロー図なんて最初から書ける人はいませんよ。パワーポイントもいりません。まずは、今日の朝、出社してから今までの仕事を“絵日記”みたいに、手書きでいいので書き出してみませんか? 『メールを確認した』『Excelに転記した』『鈴木部長にハンコをもらいに行った』…そんなレベルで十分です」
高いハードルを一度取り払い、とにかく手を動かしてもらう。すると、佐藤さんは少しずつ自分の業務を客観視できるようになっていきました。そして、数日後には「この転記作業、一日30回もやってるの、無駄じゃないですか?」と、自ら問題点を見つけられるようになったのです。
「As-Isの可視化」とは、業務プロセスというロジックを整理する作業であると同時に、現場の人々が抱える「面倒だ」「怖い」「誰にも分かってもらえない」といった“感情”を可視化し、受け止めるプロセスでもあるのです。
部門間の“翻訳”という名の泥臭い仕事
さて、なんとか各部署のAs-Isフロー図が出揃い、次はいよいよ「To-Be(あるべき姿)」の設計です。記事では、さも簡単に理想のフローが描けるように書いていますが、現実は「部門最適」という名の“国盗り合戦”が始まります。
会議室に集まったのは、営業部、業務部、経理部の代表者たち。ホワイトボードに貼り出されたフロー図を見るなり、議論は紛糾しました。
営業部長(40代):「だから言っただろ!業務部の処理が遅いから、月末の請求書発行がいつもギリギリになるんだ! RPAで自動化すれば、もっと早く出せるはずだ!」
鈴木部長(業務部):「んだごど言ったって、おめだぢ営業が持ってくる伝票の数字が、いっつも間違ってっからの!こっちはそごの確認で時間取られんだ!」
経理課長(女性、50代):「あら、お二人さん、まだそんなごど言ってるんだがね。そもそも、その伝票のフォーマットがバラバラなのが問題なんだっでば。こっちはそれを全部ウチのシステムさ手で打ち直しだのよ。大変なんだがら」
全員が正しい。しかし、全員が自分の部署の立場からしか物事を見ていない。これぞ「サイロ化」の典型です。部分最適の要求をいくら足し合わせても、決して全体最適にはたどり着きません。
ここで私たちの役割は、ファシリテーターであり、「翻訳家」です。
私はホワイトボードの前に立ち、ペンを片手に言いました。
「皆さん、ありがとうございます。今出たご意見は全部、それぞれの部署にとっての『正義』ですよね。誰も間違っていません。ただ、今日は一旦、自分の部署の帽子を脱いで、『この会社を良くする探偵団』の帽子を被ってみませんか?」
そして、私はフロー図のある一点を指さしました。それは、営業部から業務部に手書きの伝票が渡され、業務部がそれをExcelに転記し、さらに経理部がそのExcelを見て基幹システムに入力している箇所でした。
「営業部長、請求書を早く出したいのは、お客様を待たせて信頼を失いたくないからですよね? 鈴木部長、伝票の数字を厳しくチェックするのは、会社のお金を1円たりとも間違いたくないという責任感からですよね? 経理課長、フォーマットを統一してほしいのは、入力ミスを防いで、正確な経営データを作りたいからですよね?」
それぞれの要求の裏にある「目的」や「想い」を言語化し、全員に共有する。
「あなたの部署の都合」ではなく、「あなたの部署が会社のために果たしている役割」という視点に変換するのです。
「この、紙の伝票と二度の手入力。これこそが、皆さんの想いを邪魔している『共通の敵』じゃないでしょうか。もし、営業さんが最初からシステムに直接入力すれば、鈴木部長のチェックは楽になり、経理課長の手入力はゼロになり、結果として請求書はもっと早く、正確にお客様に届く。誰も損しないですよね?」
As-Isフロー図は、部門間の対立を生むための“証拠資料”ではありません。部署という壁を越えて、プロセスという一本の川の流れとして問題を捉え、全員が共通の課題意識を持つための“地図”なのです。
この「翻訳」作業には、膨大なエネルギーと忍耐が必要です。しかし、ここを乗り越えて初めて、バラバラだった部署が「同じ船に乗るクルー」となり、本当の意味でのTo-Be設計が始まるのです。
AIは魔法の杖じゃない。「プロンプト設計」で露呈した“暗黙知”の壁
プロジェクトも中盤に差し掛かり、いよいよAIの活用を具体化するフェーズに入りました。記事に載せた、あの綺麗なJSON形式で出力されるプロンプト。あれが出来上がるまでには、ベテラン担当者の「暗黙知」という、最後の巨大な壁が立ちはだかっていました。
今回の自動化対象の一つに、顧客からの問い合わせメールをAIが読み取り、内容を要約して緊急度を判定し、担当者に割り振る、というプロセスがありました。
私は、この業務のベテランである佐藤さんにヒアリングしました。
「佐藤さん、この問い合わせメールの緊急度って、どうやって判断しているんですか?」
「うーん…そうですねぇ…なんかこう、文章の雰囲気とか、いつもと違う言い回しとか…総合的に判断してますかね…」
出ました、「雰囲気で判断」。これこそが、AI導入で最も厄介な「暗黙知」の塊です。長年の経験で培われた“勘”や“コツ”は、本人でさえ言語化するのが非常に難しいのです。AIは「雰囲気」では動いてくれません。明確なルールが必要です。
そこで、私は実際の問い合わせメールを50件プリントアウトし、佐藤さんと一緒に一枚一枚仕分けをするワークショップを行いました。
「佐藤さん、このメールはなぜ『緊急度:高』なんですか?」
「あ、これはですね、『システムが完全に停止』って書いてあるので。あと、このお客様はA社さんで、うちにとって一番大事な取引先なので、優先順位は一番上なんです」
「なるほど。『システム停止』というキーワードと、顧客ランクですね。じゃあ、こっちのメールはなぜ『中』なんですか?」
「これは『操作方法がわからない』という内容なので、業務は止まってないんです。ただ、文末に『明日朝の会議で使いたいので』とあるので、急ぎではあるな、と」
この地道な対話を通して、彼女の頭の中で無意識に行われていた思考プロセスを、一つひとつ言語化し、分解していくのです。
「もし、今日入社したばかりの新人の高橋さん(仮名)に、この仕分け作業を教えるとしたら、どんなマニュアルを作りますか? 『これを読めば、君も明日から佐藤さんと同じ判断ができるよ』っていう、魔法のマニュアルです」
この「新人教育に例える」というアプローチは、暗黙知を形式知に変換する上で非常に有効です。人に教えるためには、判断基準を具体的かつ網羅的に言語化せざるを得ないからです。
このワークショップの結果、以下のようなルールが洗い出されました。
- キーワード: 「停止」「緊急」「決済できない」→ 高
- 顧客ランク: Aランク、Bランク → 優先度を上げる
- 期限の有無: 「本日中」「明日の会議」→ 中
- 内容: 「仕様確認」「資料請求」→ 低
これらの具体的なルールを組み合わせ、記事にあるような構造化されたプロンプトに落とし込んでいくのです。AIに仕事を教えるプロセスは、実は、組織のノウハウを形式知化し、属人化を解消するという、人材育成そのもののプロセスなのです。
まとめ:改革とは、人の心を動かす旅である
あの記事でご紹介した10のステップやフレームワークは、確かにプロジェクトを成功に導くための強力な羅針盤です。しかし、羅針盤だけでは船は進みません。船を動かすのは、現場で働く一人ひとりの熱意と納得感、そして「自分たちの仕事をもっと良くしたい」という当事者意識です。
私たちの仕事は、最新のAIツールを導入することでも、綺麗な業務フロー図を描くことでもありません。部署間の壁を溶かし、通じ合わなかった言葉を“翻訳”し、ベテランの頭の中に眠る“宝の地図”を掘り起こし、人々の心を同じゴールへと向かわせる「触媒」となることです。
もしあなたが今、何かの改革を任され、現場の抵抗や無関心に心を折られそうになっているなら、思い出してください。あなたの目の前にいる人たちの「面倒だ」「怖い」「わからない」という感情の裏には、必ず「仕事をうまくやり遂げたい」という真摯な想いが隠されています。
まずは、その想いに耳を傾けることから始めてみてください。ロジックで説得する前に、感情で共感する。それが、どんな高価なツールや難解な理論よりも、プロジェクトを力強く前進させる、最も確かな原動力になるはずですから。