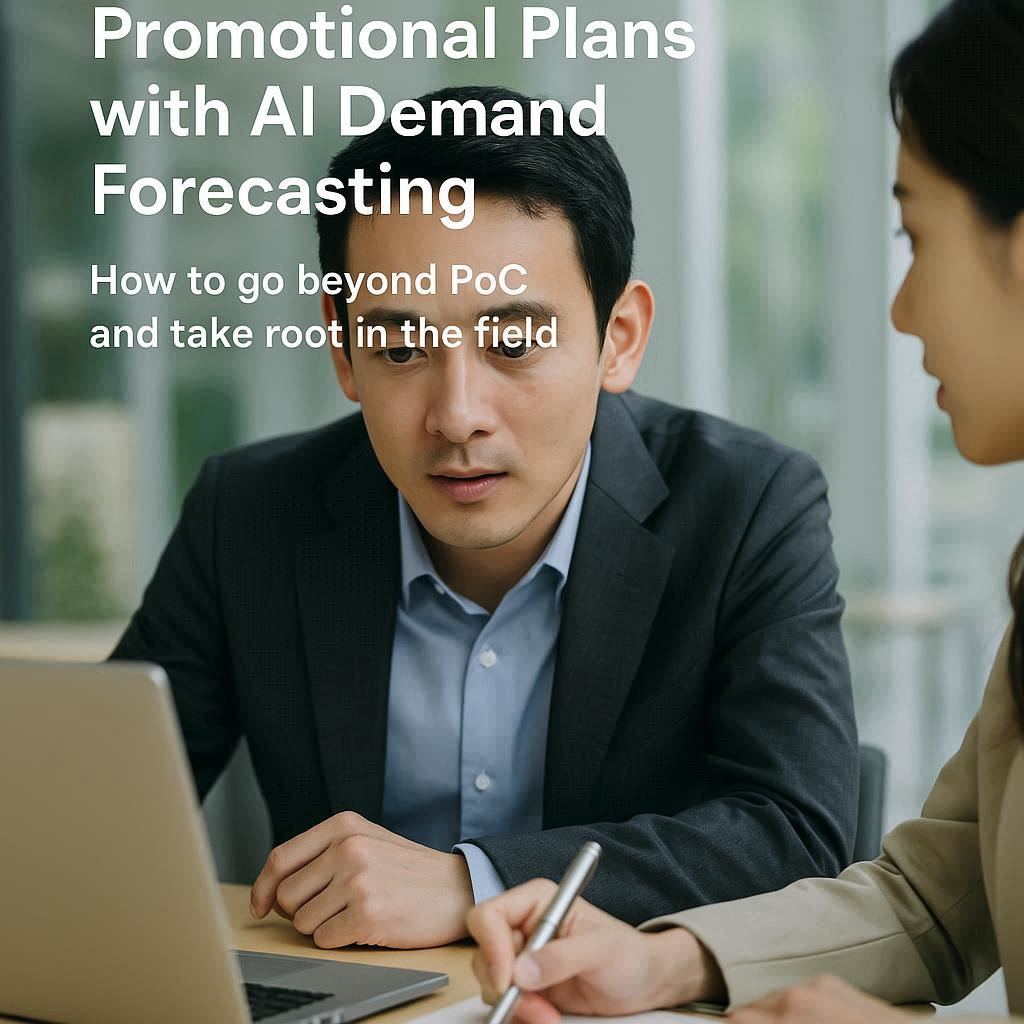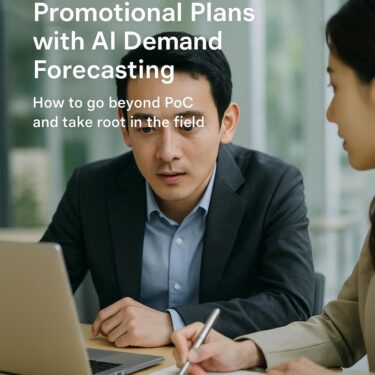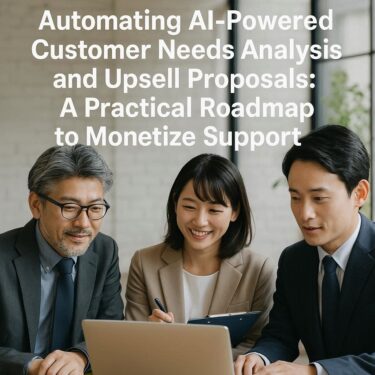AI需要予測が弾き出した「正解」より、現場の「勘」が勝る時。その裏側の人間ドラマ
先日公開した『AI需要予測で販促計画を最適化する実践ガイド』という記事は、AI導入のロードマップや成功のステップを体系的に解説した、いわば「優等生」な内容だった。
AI需要予測で販促計画を最適化する実践ガイド|PoC止まりを越え現場に根付かせる方法 はじめに:その販促、本当に利益につながっていますか? 「天気が崩れて大量の廃棄が出てしまった」「鳴り物入りで販促を打ったのに、売上は[…]
しかし、あの整然としたステップの裏側では、いつも汗と涙、そして笑いに満ちた泥臭い人間ドラマが繰り広げられている。システムはロジックで動くが、それを動かすのは感情を持った人間だ。どれだけ高性能なAIを導入しても、現場で働く人々の心が動かなければ、それはただの「高価な箱」に成り下がる。
今日は、あの記事には書ききれなかった、ある食品スーパーでのAI需要予測プロジェクトの舞台裏をお話ししたい。これは、正論だけでは乗り越えられない「現場の壁」に、生身の人間たちがどう向き合い、変化していったかの物語だ。
第一幕:「また本社の思いつきか…」冷めた空気と板挟みの担当者
プロジェクトのキックオフミーティング。会議室に集まったのは、本社の商品部長や情報システム部長といった「推進派」と、現場代表として呼ばれたエリアマネージャー、そして惣菜部門のベテラン工場長だった。今回のプロジェクトの主担当に任命されたのは、商品部で販促企画を担当する入社8年目の佐藤さん(32歳)。非常に真面目で優秀な女性だ。
私が自己紹介を終え、プロジェクトの概要を説明し始めると、すぐに空気の温度が下がっていくのが肌で感じられた。特に、最前列で腕を組んでいた白髪頭の工場長(高橋さん、65歳)の視線は、値踏みをするように鋭い。
会議後、佐藤さんが不安そうな顔で私の元へやってきた。
「なんだか、現場の皆さんの反応が…。『また本社の連中が、よくわからない横文字のシステムを押し付けようとしてる』って顔に書いてありましたよね…」
「ええ、まあ、正直に言えば。特に高橋工場長は手強そうですね」
「工場長は、この道40年の大ベテランなんです。あの人の勘の鋭さは伝説的で…。天気や近所の学校行事まで頭に入れて、毎日作る惣菜の量を決めるんです。それがまた、本当によく当たるんですよ。そんな人に『これからはAIの言う通りに作ってください』なんて、口が裂けても言えません…」
彼女の悩みは痛いほどよくわかる。本社からは「DXの成功事例を作れ」とプレッシャーをかけられ、現場からは「俺たちの仕事をわかっていない」と突き上げられる。この板挟みのポジションこそ、改革プロジェクトで最も疲弊する場所だ。
私は彼女にこう伝えた。
「佐藤さん、焦る必要はありません。まずは、私たちが現場を『知らない』ということを認めるところから始めましょう。高橋工場長の『勘』は、AIが学ぶべき最高の教師です。敵対するのではなく、弟子入りするつもりで話を聞きに行きませんか?」
第二幕:「AIだか何だか知らねぇが、こっちには40年の経験があんだ」
翌週、私と佐藤さんは、朝早くから高橋工場長のいる惣菜工場を訪れた。白衣に着替え、湯気の立ち上る調理場に入ると、高橋工場長が大きな釜をかき混ぜながら、私たちを一瞥した。
「高橋工場長、お時間いただきありがとうございます。今日は、工場長の普段のお仕事ぶりをぜひ勉強させていただきたくて」
佐藤さんが切り出すと、工場長は手を止めずにぶっきらぼうに言った。
「んだが。勉強だなんて、そんな大したごどはしてねぇ。長年やってれば、誰だってわかるようなごどだ」
私たちは邪魔にならないように隅に立ち、工場長が次々とスタッフに指示を出す様子を眺めていた。彼は壁に貼られた天気予報と、手元の小さなメモを交互に見ながら、よどみなく指示を飛ばしていく。
「明日は雨で気温も下がるがら、煮物はいつもより二割増しだ。揚げ物は、昼過ぎから売れ行きが鈍る。特売のコロッケは300個でいいべ。多めに作ったって、残ったら捨てるだけだからの」
その姿は、まさに職人。経験とデータが頭の中で融合し、最適解を瞬時に導き出す人間AIそのものだ。
休憩時間、私たちは工場長にお茶を差し入れ、話を聞いた。
「工場長の予測は本当にすごいですね。何か特別なデータを使っているんですか?」
私が尋ねると、彼は少しだけ表情を和らげた。
「データだなんて、そんな難しいもんは使ってねぇよ。ただ、この辺は年寄りが多いから、雨が降ると客足がぱったり止まる。逆に、近くの小学校で運動会でもあれば、唐揚げやいなり寿司が飛ぶように売れる。そういう、この土地ならではの事情があるんだ。あんたたちのAIだか何だか知らねぇが、そんなことまでわかるのが?」
痛いところを突かれた。これこそ、多くのAI導入が失敗する「現場の肌感覚との乖離」だ。私は正直に答えた。
「いえ、わかりません。だから、教えていただきたいんです。工場長のその『勘』の正体を、AIに学習させたい。工場長の分身のようなものを作って、他の店舗でもその知恵を活かせるようにしたいんです。AIは、工場長の仕事を奪うものではなくて、その技を未来に残すための道具なんです」
高橋工場長は、黙って湯呑のお茶をすすっていた。まだ納得はしていない。しかし、最初の険しい表情は少しだけ、本当に少しだけ、氷解したように見えた。
第三幕:小さな「負け」から始まった、AIと職人の共闘
そこから私たちの地道な作業が始まった。まずは、AIに過去の販売実績と天気、カレンダー情報などを学習させ、基本的な予測モデルを作った。そして、高橋工場長の予測とAIの予測を、毎日並べて比較することにしたのだ。これは佐藤さんのアイデアだった。
「AI vs 工場長」の小さな対決。最初の1週間は、面白いほどAIが負けた。
「ほれ見ろ。今日の特売、AIは450個って言ったろ。わしは300個でいいって言った。結果、312個しか売れなかった。危なく140個も廃棄出すどごだったぞ」
高橋工場長は、少し得意げに結果を突きつけてくる。佐藤さんは申し訳なさそうにしているが、私はむしろ手応えを感じていた。
「工場長、ありがとうございます! なぜ今日は売れないとわかったんですか?」
「今日はな、給料日前の最後の平日だ。みんな財布の紐が固くなる。それに、向かいのスーパーが卵の特売やってるから、客がそっちに流れるんだ」
「なるほど! 『給料日サイクル』と『競合の特売情報』ですね…! すぐにAIに学習させます!」
私たちは、工場長が「負けた原因」を教えてくれるたびに、それをデータとしてAIに追加していった。地域のイベント情報、競合のチラシ情報、近隣の工場の給料日…。それはまさに、ベテラン職人の頭脳をデジタルデータに翻訳していく作業だった。
2週間が経つ頃には、AIの予測精度は目に見えて向上し、工場長の予測と僅差の勝負をするようになった。そして3週目、ついにAIが工場長に勝つ日が来た。
その日、AIは「台風接近の予報が出ているため、カップ麺とパンの需要が急増します」と予測した。一方、工場長は「まだ雨も降ってねぇのに、そんなに売れるはずがねぇ」と懐疑的だった。
結果は、AIの圧勝。夕方には棚が空になり、欠品による機会損失が出てしまった。
翌朝、工場長は少しばつが悪そうな顔で私に言った。
「…昨日は、わしの負けだ。まさか、あんなに売れるとは思わなかった。台風情報がテレビで流れると、みんな買いだめに走るんだな。勉強になった」
この日を境に、工場の空気が変わった。高橋工場長が、AIを「得体の知れない敵」ではなく、「ちょっと経験の浅いが、素直で物覚えのいい若いやつ」として見るようになったのだ。彼は毎朝、AIが出した予測値を見て、「うん、今日のこいつの予測は悪くねぇな」とか「いや、ここはもう少しこうした方がいい」と、まるで弟子に教えるように、予測値を微調整するようになった。
佐藤さんも、この変化を肌で感じていた。彼女は、高橋工場長や現場スタッフがAIの予測結果を直感的に理解できるよう、専門用語を一切使わないシンプルな報告画面を自らデザインした。彼女が、AIと現場の心をつなぐ「通訳者」になった瞬間だった。
最終幕:経営会議での逆転劇。「こいつは、使える」
3ヶ月のスモールスタート期間が終わり、成果を報告する経営会議の日が来た。私は佐藤さんに、報告の主役を担ってもらった。
彼女は、AIの予測精度がMAPE(平均絶対パーセント誤差)で何%改善したか、などという技術的な話はほとんどしなかった。代わりに、一枚のスライドを映し出した。
「この3ヶ月で、惣菜部門の廃棄ロスは、金額にして月平均で80万円削減できました。これは、従来のやり方と比較して35%の改善です。また、欠品による機会損失は15%減り、売上向上にも繋がっています」
具体的な「金額」が出た瞬間、それまで静かだった役員たちの目の色が変わった。さらに佐藤さんは続けた。
「そして、何より大きな成果は、高橋工場長の作業時間が変わったことです」
彼女は、高橋工場長へのインタビュー動画を流した。そこには、はにかみながら話す工場長の姿があった。
「今まではな、毎朝2時間かけて、天気予報見たり、去年のノート見返したりして、仕込む量ば決めったんだ。今は、こいつ(AI)が出した数字ば10分くらい確認して、ちょちょって直すだけで済む。おかげで、新しい惣菜のレシピば考えたり、若い連中に仕事を教えたりする時間が増えだ。正直、体も楽になったのぉ」
動画が終わると、会議室は静まり返っていた。そこに、意見を求められた高橋工場長本人が、ゆっくりと口を開いた。
「社長。わしは最初、こんなもんは信用してませんでした。じゃが、こいつは使える。わしら現場の人間が楽になるだけじゃねぇ。無駄をなくして、ちゃんとお客さんの欲しいもんを届けられるようになる。全店でやった方がいいと思います」
大ベテランからの、力強い推薦の言葉。それは、どんな精緻なデータよりも説得力があった。プロジェクトの全社展開が決まったのは、言うまでもない。
改革の主役は、AIではなく「人」だ
AI需要予測のプロジェクトは、単なるツール導入ではない。それは、組織の文化を変えるための、壮大なコミュニケーション・プロジェクトだ。
現場の経験や勘を否定するのではなく、敬意を払い、その知恵をテクノロジーで「形式知化」する。
AIをブラックボックスにせず、現場が納得し、使いこなし、「育てる」ことができる仕組みを作る。
そして、本社と現場の板挟みで苦しむ担当者を孤立させず、彼女や彼がヒーローになれる舞台を整える。
どれだけ技術が進歩しても、ビジネスの最前線で価値を生み出しているのは、生身の人間だ。彼らの心が動いた時、初めてテクノロジーはその真価を発揮する。
もしあなたが今、同じような壁にぶつかっているのなら、思い出してほしい。あなたの仕事は、システムを導入することではない。人の心に火を灯し、変化への一歩を共に踏み出すことなのだと。その泥臭くて人間味あふれるプロセスこそが、改革を成功に導く唯一の道なのだから。