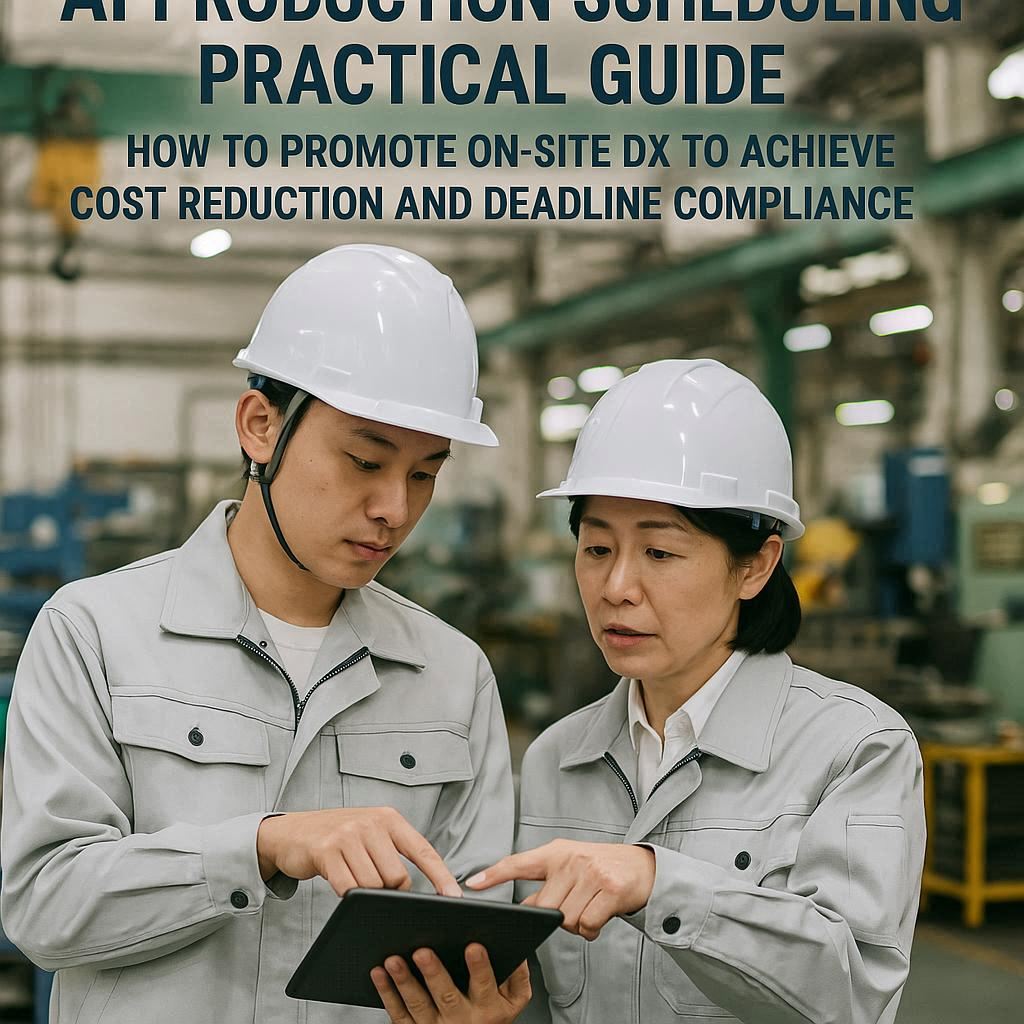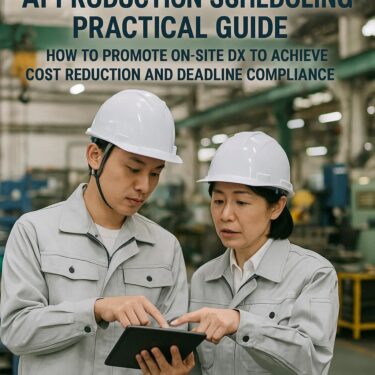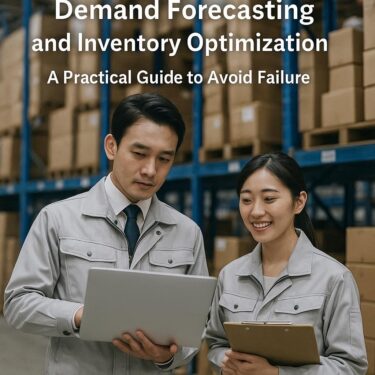生産スケジューラ導入、AIは『計算』できても『説得』はできない。現場の心を動かした話
先日公開した『AI生産スケジューリング実践ガイド』、おかげさまで多くの方にお読みいただけたようです。あの記事では、AI導入を成功に導くための体系的なステップや思考法を、いわば「模範解答」としてまとめました。KPIを設定し、データを整備し、PoCを回してROIを評価する。教科書通りに進めば、確かに成果は出るはずです。
AI生産スケジューリング実践ガイド:コスト削減と納期遵守を両立する現場DXの進め方 今の生産計画で、本当に明日の競争を勝ち抜けますか? 「設備は空いているのに、なぜかいつも納期が厳しい」「急な差し込みや仕様変更で、計画[…]
しかし、皆さんが本当に知りたいのは、その綺麗なステップの裏側で、私たちがどんな壁にぶつかり、どんな泥臭いやり取りを繰り広げてきたのか、ではないでしょうか。
AIは最適な答えを数分で弾き出せます。しかし、その答えを現場の人たちに納得してもらい、行動に移してもらうには、数ヶ月、いや一年以上かかることだってある。最新のアルゴリズムも、現場の「まあ、そう言うけどさ…」という一言の前では無力です。
この記事は、あの実践ガイドの「行間」を埋める裏話です。私が数々の製造現場で見てきた、システム導入の成功を本当に左右する「マネジメント」と「コミュニケーション」の生々しい現実をお話ししたいと思います。主役はAIではなく、最後まで抵抗し、そして最後には最強の味方になってくれた「現場の人々」です。
「そんなデータ、ありません」から始まった宝探し
『実践ガイド』の「準備2:データ基盤の整備」の章で、私は「完璧主義は禁物」と書きました。これは綺麗事ではなく、切実な現実から得た教訓です。
ある化学メーカーでのこと。プロジェクトが始まり、私は生産管理課の担当者である佐藤さん(30代・女性)に、AIの計算に必要なマスターデータのリストを渡しました。
私:「佐藤さん、まずはこのリストにある工程マスタと、製品ごとの標準時間を集めていただけますか?」
佐藤さん:「…無理です。うちの工程マスタは10年前に作ったきりで、今の実態と全然合っていません。標準時間なんて、あってないようなものです。いつも現場の鈴木職長の頭の中にある『勘』で調整してますから」
初日からこれです。教科書通りの「データ整備」なんて、夢のまた夢。これが日本の製造現場のリアルです。しかし、ここで引き下がるわけにはいきません。私はPCを閉じ、ヘルメットと安全靴を借りて、問題の「鈴木職長」がいる現場に向かいました。
現場は機械の駆動音と独特の薬品の匂いに満ちています。鈴木さん(60代・男性)は、私が近づくと警戒心丸出しの目で一瞥しました。
私:「鈴木さん、はじめまして。今回、生産計画の新しいシステムを担当します、ミズです。少しだけお時間を…」
鈴木さん:「んだが?また何か面倒なごど始めんだろ。こっちは毎日てんてご舞いだいうのに、パソコンさ数字入れろどが言うんでねべな?」
典型的なアレルギー反応です。彼らにとって、私たちは「現場の苦労も知らないで、上から理想論を押し付けてくる厄介者」にしか見えません。ここでシステムの優位性を説いても無駄です。私がやったことは、ただ一つ。「教えを乞う」ことでした。
私:「鈴木さん、実は困っているんです。佐藤さんから、この工場で一番すごいのは鈴木さんの『勘』だって聞きました。例えば、このA製品の後にB製品を流すと、いつもより段取りに時間がかかるって本当ですか?」
鈴木さん:「ったりめだ。Aの後はタンクさ特殊な膜が張るんだ。そいだら、Bさ切り替えるどぎの洗浄時間が倍かかる。だから、Aの後はなるべく同じ系列のCば流すように、おれが調整してるんだず。そんなごど、事務所の若い衆は誰も知らねべ」
…これです。これこそがAIが学習すべき「暗黙の制約」であり、この会社が守り続けてきた「無形の資産」です。
私:「それです!鈴木さん!そのノウハウこそ、会社の宝じゃないですか!もしよろしければ、その『鈴木ルール』を私に教えてもらえませんか?それを新しいシステムに覚えさせて、鈴木さんの技を会社の正式なルールにしたいんです。そうすれば、鈴木さんがお休みの時でも、誰もが最高の生産計画を立てられるようになります」
私の言葉に、鈴木さんの険しい表情が少しだけ和らぎました。「仕事を奪われる」のではなく、「自分の技が認められ、継承される」。この一点を伝えるだけで、相手の心理は大きく変わります。
その日から、私は毎日現場に通い、鈴木さんの「語り」をメモし続けました。「この機械は午後に止めると再起動に時間がかかる」「雨の日は湿度が上がるから、この材料の乾燥時間を少し延ばす」…出てくるのは、どんな設計書にも載っていない生きたデータばかり。
事務所に戻り、私はそのメモを佐藤さんに見せました。
私:「佐藤さん、これが新しいマスターデータです。これをシステムが分かる言葉に『翻訳』するのが、佐藤さんの新しい仕事です。鈴木さんの『勘』を、会社の『仕組み』に変える、ものすごく重要な役割ですよ」
彼女の目が、初めて輝いたのを今でも覚えています。「データがない」と諦めていた彼女は、ベテランの知恵とAIを繋ぐ「翻訳家」という新たな役割を見つけたのです。
『実践ガイド』に書かれた「データ整備」のたった一行の裏には、こうした現場との地道な人間関係の構築があります。データはサーバーの中にあるのではなく、現場で汗を流す人の「頭の中」と「経験の中」にあるのです。
「AIの言うことなんて聞けるか!」反発の壁を溶かしたシミュレーション
さて、データも集まり、いよいよPoC(概念実証)です。『実践ガイド』のステップ6〜7にあたる部分ですね。AIが導き出した、人間には到底思いつかないような「最適」なスケジュール。これにはプロジェクトメンバーも「おおっ!」とどよめきました。しかし、本当の戦いはここからでした。
AIが作った計画表を製造課の田中課長(40代・男性)に見せた時のことです。
田中課長:「なんだこれは!なんで3号機を1時間も遊ばせておくんだ!今すぐ動かせば、今日の生産目標は達成できるじゃないか。こんな計画、現場に出せるか!」
AIの計画では、目先の生産数よりも、来週発生するかもしれない部材の欠品リスクを回避するため、あえて3号機を温存し、別の製品の生産を優先する、という判断をしていました。いわゆる「全体最適」です。しかし、長年「今日の目標達成」「設備の稼働率最大化」を至上命題としてきた現場のリーダーにとって、それは「サボっている」ようにしか見えないのです。
ここで「いえ、AIの方が正しいんです。全体最適で考えれば…」と理屈で反論するのは最悪の手です。相手の経験とプライドを否定することにしかなりません。
私:「課長、おっしゃる通りです。今日の生産数だけを見れば、すぐに3号機を動かすべきです。課長の判断は何も間違っていません。ただ、少しだけ、未来を覗いてみませんか?」
私は課長を会議室に招き、プロジェクターで2つのシミュレーションを見せました。
パターンA:課長の言う通り、今すぐ3号機を動かす計画
- 今日の生産数:目標達成(グラフが青色)
- 3日後の生産数:主要部材が欠品し、ラインが半日停止(グラフが真っ赤に)
- 週末の残業時間:ライン停止の遅れを取り戻すため、8時間の休日出勤が発生
パターンB:AIの提案通り、3号機を1時間待機させる計画
- 今日の生産数:目標未達(グラフが黄色)
- 3日後の生産数:部材の欠品は発生せず、ラインは通常稼働
- 週末の残業時間:ゼロ
田中課長は、黙って画面に映し出された2つの未来を見比べていました。感情論や精神論ではなく、客観的なデータが示す「起こりうる未来」。これこそが、AI導入がもたらす最大の価値の一つです。
私:「AIは、課長のような経験豊富な方が『より良い未来を選択する』ための判断材料を提供する、ただの道具です。最終的にどちらの未来を選ぶかを決めるのは、現場を知り尽くした課長、あなたです。もし、AIの計画を採用しない場合でも、その理由をメモに残していただけませんか?その『人間の判断』こそ、AIが次に学習すべき最高の教師データになるんです」
これが、『実践ガイド』で述べた「Human-in-the-Loop(人間参加型ループ)」の本質です。AIを「押し付ける」のではなく、あくまで「副操縦士」として位置づける。そして、人間の判断をフィードバックする「仕組み」を運用に組み込む。この「逃げ道」と「役割」を用意することで、現場の心理的抵抗は劇的に下がります。
田中課長はしばらく腕を組んでいましたが、やがてポツリと言いました。
田中課長:「…分かった。今日はAIの言う通りにやってみよう。ただし、もし問題が起きたら、お前のせいだからな」
この「お前のせいだからな」は、私たちにとっては勝利の言葉でした。彼は、変化を受け入れる決断をしたのです。
経営会議で語ったのは、数字ではなく「一人の担当者の成長物語」
プロジェクトは軌道に乗り、半年後には目に見える成果が出始めました。計画作成時間は80%削減され、特定の製品ラインの納期遵守率は95%を超えました。いよいよ、経営層へのROI(投資対効果)報告会です。
しかし、私は悩んでいました。削減された残業代や外注費を金額換算しても、今回のシステム投資額を回収するには、まだ時間がかかる計算だったからです。数字だけを並べても、厳しい指摘を受けることは目に見えていました。
報告会の席には、この工場のトップである高橋事業部長(50代後半・男性)が座っています。
高橋部長:「…で、結局、この高いシステムを入れて、うちはいくら儲かったんだ?残業代が少し減ったぐれで、大したごどねな。まだ投資額に見合う効果どは言えねべ?」
冷ややかな空気が流れます。私は用意していたROIの計算シートを脇に置き、向き直りました。
私:「部長、今日は数字のお話をする前に、一人の担当者のお話をさせてください。生産管理の佐藤さんです」
私は、プロジェクトが始まった当初、彼女が「無理です」と言って俯いていたこと、鈴木職長の「暗 tacit knowledge 」を必死に翻訳してくれたこと、今では空いた時間を使って、これまで誰もできなかった在庫のABC分析や、現場への改善提案まで始めていることを、具体的なエピソードを交えて話しました。
私:「このプロジェクトが生んだ最大の利益は、削減された残業代ではありません。佐藤さんという、未来の工場を担う人材が『考える時間』を手に入れ、自律的に改善を始めたことです。ベテランの鈴木さんの頭の中にしかなかった『宝の地図』は、今や会社のデジタル資産になりました。これは、5年後、10年後のこの工場の競争力そのものです。この価値は、残念ながら今の会計基準では金額に換算できませんが、私はこの『未来へのリターン』こそが、最大の投資対効果だと確信しています」
そして、私は最後にこう付け加えました。
私:「この後の具体的な成果については、プロジェクトリーダーとして見事に成長された、佐藤さんご本人から説明させていただきます」
スポットライトを浴びた佐藤さんは、最初は緊張した面持ちでしたが、自分の言葉で、自分たちの現場がどう変わったのかを堂々と語り始めました。彼女の言葉には、私が語るどんな美辞麗句よりも強い説得力がありました。
報告会が終わった後、高橋部長が私のところにやってきて、こう言いました。
高橋部長:「ミズさん、あんたはシステム屋でねな。人ば育てるプロだな。…佐藤のこと、これからも頼むな」
『実践ガイド』に書いたROIの計算式は、もちろん重要です。しかし、経営者の心を本当に動かすのは、無機質な数字の羅列ではなく、生きた人間の「成長物語」なのかもしれません。
終わりに:本当のDXは「対話」から始まる
『AI生産スケジューリング実践ガイド』は、DXを進めるための地図です。しかし、地図だけでは目的地にはたどり着けません。そこには、共に旅をする仲間が必要です。
AI導入とは、突き詰めれば「変化のマネジメント」です。そして変化とは、常に不安と抵抗を伴います。その不安を解消し、抵抗を乗り越える力は、AIの計算能力にはありません。それは、現場に足を運び、相手の言葉に耳を傾け、そのプライドと経験に敬意を払う、地道な「対話」の中にしか存在しないのです。
もし、あなたの会社で新しいシステムを導入しようとして、「うちには無理だ」「今のやり方が一番だ」という声が聞こえてきたら、それはプロジェクトの終わりを告げるゴングではありません。
それは、本当の対話の始まりを告げる、スタートのゴングなのです。