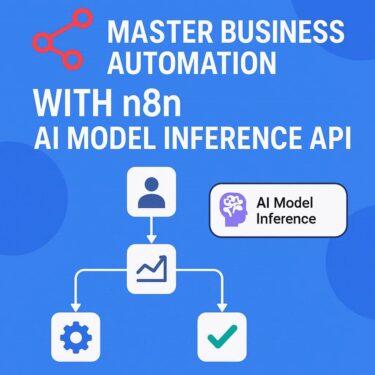『このExcelが一番なんだ』――イベント自動化の裏で、私が担当者と乗り越えた「見えない壁」の話
先日、イベント運営の自動化に関する実践ガイドの記事を公開しました。そこでは、まるで綺麗な設計図を描くように、計画から実装までの7つのステップや、4つのツール選定のアプローチについて解説しました。
イベント運営の参加者管理とメール配信を自動化する実践ガイド:規模・体制・予算で選ぶ最適解 「またリストの突き合わせか…」「リマインドメール、送り忘れてないよな…」イベントの成功を夢見て企画したはずが、気づけば申込者リストの管[…]
しかし、正直に告白します。実際の現場は、あんなにスムーズに進むことなんて、まずありません。
机上の空論と現場の現実の間には、深くて見えない溝があります。その溝の正体は、最新のツールや難解な技術ではありません。それは、長年組織に根付いてきた「文化」や「慣習」、そして何より「人の心」そのものです。
この記事では、あの綺麗なノウハウ記事の裏側で、私たちが実際にどんな泥臭い現実に直面し、どうやってそれを乗り越えてきたのか、ある地方の中堅製造業での実話を元にお話ししたいと思います。これは、ツール導入の成功事例というよりは、変化を恐れる人々の心と向き合い、共に汗を流した、マネジメントとコミュニケーションの記録です。
もしあなたが今、業務改善を進めようとして「でも、今のやり方で問題ないから」「新しいことは覚えるのが大変」といった現場の抵抗に心を折られそうになっているなら、きっとこの記事が、明日へ進むための小さな灯火になるはずです。
壁その1:「あなたの仕事を見せてください」が言えなかった最初の1週間
その会社は、地方で長年堅実な経営を続けてきた、社員100名ほどの中堅製造業でした。年に数回、新製品の発表会や顧客向けのセミナーといったイベントを開催しており、その担当者が、入社10年目の佐藤さん(30代・女性)でした。
最初の打ち合わせで、彼女は少し疲れた顔でこう言いました。
「イベントの企画自体は楽しいんです。でも、申し込みが始まると…。Excelへの転記、入金確認のチェック、何種類もの案内メールの送信。毎回、イベント直前は深夜残業が当たり前で、ミスしないか常にビクビクしています」
典型的な「手作業地獄」でした。あの記事で書いた通り、まさに自動化が劇的な効果を発揮するケースです。私はすぐに業務フローのヒアリングを始めようとしました。
しかし、そこに現れたのが、佐藤さんの上司である製造部長の鈴木さん(50代・男性)でした。筋金入りの現場主義者で、勤続30年以上のベテランです。
「先生、わざわざ来てもらったども、うぢは大丈夫だ。このイベントも、佐藤さんがしっかりやってくれてっからのぉ。年に数回のことだもの、そんくらいは気合でなんとかなんべ」
穏やかな庄内弁の口調とは裏腹に、その言葉には「外部の人間があれこれかき回すな」という強い牽制が感じられました。佐藤さんは、そんな部長の横で、申し訳なさそうに小さくなっています。
ここが最初の壁でした。当事者である佐藤さんは困っている。しかし、その上司は「問題ない」と言う。この状況で「じゃあ、具体的にどんな作業をしているか見せてください」と踏み込んでも、「だから問題ないと言っているだろう」とシャッターを下ろされてしまうのが目に見えています。
正論は、ここでは通用しない。私は戦略を変えることにしました。
一週間、私はただ、彼らの部署に通いました。業務改善の話は一切せず、鈴木部長の昔の武勇伝――「昔は図面も全部手書きでなあ」「あの機械の立ち上げは徹夜続きだったんだず」――といった話に、ひたすら耳を傾けました。佐藤さんとは、お昼休憩の時に「最近、駅前に新しいカフェできたらしいですよ」なんて雑談をするだけです。
そして、打ち合わせから一週間が経った金曜日の午後。私は鈴木部長にこう切り出しました。
「鈴木部長、一週間お話を聞かせていただいて、部長がいかにこの会社の物造りを支えてこられたか、本当によく分かりました。その『魂』みたいなものを、イベント運営にもしっかり反映させたいんです。そこでお願いがあるんですが、一度でいいので、佐藤さんがやっている作業を最初から最後まで、隣で見学させていただけませんか? 改善のため、というより、まず私が『皆さんの仕事と誇りを理解するため』に、です」
ポイントは2つ。
- 彼の功績への最大限のリスペクトを示すこと。
- 目的を「改善」から「理解」にすり替えること。
鈴木部長は少し驚いた顔をしましたが、やがて「…んだが。まあ、見るだけなら、構わんよ」と許可をくれました。
翌週、私は佐藤さんの隣に座り、申込メールが1通届いてから、彼女がExcelを開き、名前をコピーし、別のシートの顧客ランクと照合し、セグメントに応じてセルの色を変え、そしてOutlookでメールの文面を少し変えて送信する…という一連の流れを、黙って観察し続けました。
その作業をビデオに撮らせてもらい、一つ一つの操作を付箋に書き出していきました。「メール受信」「A列に氏名をコピー」「F列の顧客ランクを確認」「VIPなら黄色に塗る」「『様』を手入力」…。
夕方には、会議室のホワイトボードが、青や黄色の付箋で埋め尽くされていました。
それを見た鈴木部長が、ぽつりと呟きました。
「…こりゃあ、思ってたよりも、大変なごどやってんなや、佐藤さん」
これが、全ての始まりでした。業務の「大変さ」は、当事者の口から語られるよりも、客観的な事実として「可視化」された時、初めて組織の共通認識になるのです。
壁その2:「秘伝のタレ」Excelと、ベテランのプライド
業務の全体像が見えたことで、プロジェクトは一気に進むかのように思えました。私は、元記事で紹介したような「GoogleフォームとGASを使った自動化」や「イベント管理SaaSの導入」といった具体的な解決策を提示しました。
しかし、ここで最大の壁が立ちはだかります。鈴木部長です。
彼は、おもむろに自分のPCで一つのExcelファイルを開いて見せました。
「先生、あんがとさん。でもな、うぢにはこれがあっからの。わだしが若い頃に作った、イベント管理用のExcelだ。マクロも組んであっでの、ボタン一つで集計もできる。完璧だ」
それは、まさに「秘伝のタレ」でした。何代も前の担当者から引き継がれ、鈴木部長がVLOOKUPやIF文を継ぎ足し、挙句の果てには見よう見まねでマクロまで組み込んだ、複雑怪奇なモンスターExcel。一見すると高機能ですが、その実態は完全にブラックボックス化しており、少しでも前提が崩れるとエラーを吐き出す代物でした。
佐藤さんが恐る恐る口を開きます。
「あの…部長。このファイル、すごく助かっているんですが、たまにマクロが動かなくなると、私では原因が分からなくて…。あと、申込フォームの項目が少しでも変わると、全部手作業で列を直さないといけないのが…」
すると、鈴木部長は少しムッとした顔で言いました。
「んだって、そんくらいは気合でなんとかなんねぇが? やり方は全部教えてっぺ? 新しいシステムだの、英語だのだらけで、わがんねぇのより、よっぽどいいべ」
私は悟りました。これは単なるツールへの固執ではない。このExcelファイルは、鈴木部長にとって、自分の経験と知識の結晶であり、長年この部署を支えてきたという自負、すなわちプライドそのものなのだと。
ここで「そのExcelは古いですよ」とか「属人化のリスクが…」などと正論をぶつければ、彼のプライドを傷つけ、プロジェクトは即座に頓挫するでしょう。
私は、彼のExcelをモニターに映しながら、こう話しかけました。
「鈴木部長、このExcelは本当にすごいですね。特に、この顧客ランクに応じて自動で色が変わる仕組みや、ボタン一つで集計が出る機能。この『思想』は、絶対に次の仕組みにも引き継ぐべきです。これは、部長が長年培ってきたノウハウそのものですから」
まず、徹底的に肯定し、リスペクトする。それから、本題に入ります。
「その上で、ご提案があります。この素晴らしいExcelを『なくす』のではなく、『進化』させませんか? 例えば、一番大変な『申込フォームからの転記』の部分だけをロボットにやらせるんです。データは自動でどんどん追加されていく。そして、部長が作ったこのExcelは、その最新データを元にした『分析用のレポート』として、今まで通り使い続ける。これなら、佐藤さんの手間は激減しますし、部長のノウハウも活かせます」
これは、元記事で言うところの「RPAによる橋渡し」のアプローチです。
しかし、ここで重要なのは技術的な話ではありません。
- 「捨てる」のではなく「活かす」という言葉を選ぶ。
- 彼の功績(Excel)を否定せず、役割を変えて存続させる提案をする。
- 彼が最も価値を置く「分析・集計」の部分は残し、最も価値の低い「転記」の部分を差し出す。
鈴木部長は、腕を組んでしばらく唸っていましたが、やがて「…まあ、転記が自動になんなら、佐藤さんも楽になるがな。わだしは別に構わんよ」と、承諾してくれました。
変化に対する抵抗は、多くの場合、変化そのものへの恐怖ではなく、「自分がこれまで築き上げてきたものが否定されることへの恐怖」から生まれます。相手の歴史とプライドに敬意を払い、それを新しい未来へと繋げる「橋」を架けること。それが、見えない壁を乗り越えるための、唯一の方法でした。
壁その3:「やらされる改善」から「自分たちでやる改善」へ
部分的な自動化は、すぐに効果を現しました。申込フォームに入力された情報は、夜間バッチで自動的に共有フォルダのスプレッドシートに転記されます。佐藤さんは、毎朝出社すると、昨日までの申込者リストが完璧な形で出来上がっているのを見て、最初は「魔法みたいです…」と感動していました。彼女の残業時間は、目に見えて減っていきました。
鈴木部長も、毎日定時に自動送信される「申込状況サマリーメール」を見ては、「ほう、昨日は5件も申し込みあっだが。順調だのや」と、まんざらでもない様子です。
しかし、ここで新たな、そして最も厄介な壁が生まれました。それは「満足」という名の停滞です。
一番の苦痛だった転記作業がなくなったことで、部署内には「もう、これで十分じゃないか?」という空気が流れ始めました。このままでは、部分最適で終わってしまい、イベント運営全体の抜本的な改革には繋がりません。
私が「次のステップとして、決済やリマインドメールの自動化も…」と切り出しても、どこか他人事のような反応です。彼らにとって、これはまだ「外部の専門家がやってくれている改善」でしかありませんでした。
このままではいけない。私は、ある日のミーティングで、やり方を大きく変えました。
ホワイトボードに、改善案を書くのをやめたのです。代わりに、佐藤さんにこう質問しました。
「佐藤さん、転記作業が自動化されて、毎日1時間、時間が生まれたとします。その1時間があったら、本当は何をしたいですか? もっとイベントを良くするために、どんなことに時間を使いたいですか?」
佐藤さんは最初、キョトンとしていました。しかし、少し考えてから、ぽつり、ぽつりと話し始めました。
「…そうですね…。いつもアンケートの集計が後回しになってしまって、自由回答をちゃんと読めていないのが気になっていました。もっと早く分析できれば、次の企画に活かせるのにって…」
「あと、参加者の方から『会場までの道順が分かりにくい』って毎回言われるので、もっと丁寧な案内図を作ってあげたいです」
「遠方から来る方のために、近隣のホテル情報とかも送ってあげられたら、親切かなって…」
次々と出てくるアイデア。それは、私が提示するような「業務効率化」の視点ではありませんでした。すべて、「参加者にもっと喜んでもらうためには?」という、彼女本来のホスピタリティから生まれたものでした。
私は、すかさず鈴木部長にも話を振りました。
「部長、もしアンケートの分析が翌日に出てきたら、営業会議の資料にも使えませんか? 顧客の生の声が、次の製品開発のヒントになるかもしれませんよ」
鈴木部長は「…んだな。そりゃあ、いいかもしんねぇな」と頷きます。
その瞬間、会議室の空気が変わりました。
「やらされる改善」が、「自分たちの仕事をもっと良くするための改善」へと、当事者たちの意識の中で切り替わったのです。
そこからは、驚くほどスムーズでした。「アンケートの集計を楽にするなら、Webアンケートにして、回答を自動でグラフ化してくれるSaaSがいいかも」「丁寧な案内を送るなら、参加ステータスごとにメール文面を変えられる仕組みが必要だね」と、彼ら自身が、自発的に解決策を考え始めたのです。
最終的に、彼らはイベント管理SaaSを導入することを自分たちで決定しました。私が最初に提示した選択肢の一つでしたが、その意味合いは全く違います。それは、外部から与えられた「正解」ではなく、彼らが自分たちの未来のために、主体的に選び取った「道具」でした。
結論:本当の変革は、人の心から始まる
あの綺麗なノウハウ記事でお伝えしたフレームワークやツールは、確かに強力です。しかし、それらはあくまで地図やコンパスに過ぎません。実際に荒野を切り拓き、道を作っていくのは、現場で働く人々自身です。
もし、あなたが今、古い慣習や「見えない壁」に行く手を阻まれているのなら、一度立ち止まってみてください。
あなたの掲げる「正論」は、相手のプライドを傷つけていませんか?
あなたの進める「効率化」は、相手から大切な仕事や役割を奪うものになっていませんか?
変革の第一歩は、最新のツールを導入することではありません。相手の歴史に敬意を払い、その仕事ぶりを徹底的に「理解」しようと努めること。そして、効率化によって生まれた時間で「どんな素晴らしい未来が手に入るのか」を、一緒に夢見ることです。
自動化は、仕事を奪う技術ではありません。人にしかできない、もっと創造的で、もっと温かい仕事をするための時間を取り戻す技術です。
そのことを、あのモンスターExcelを愛した実直な部長と、参加者を想う心優しい担当者が、私に教えてくれました。