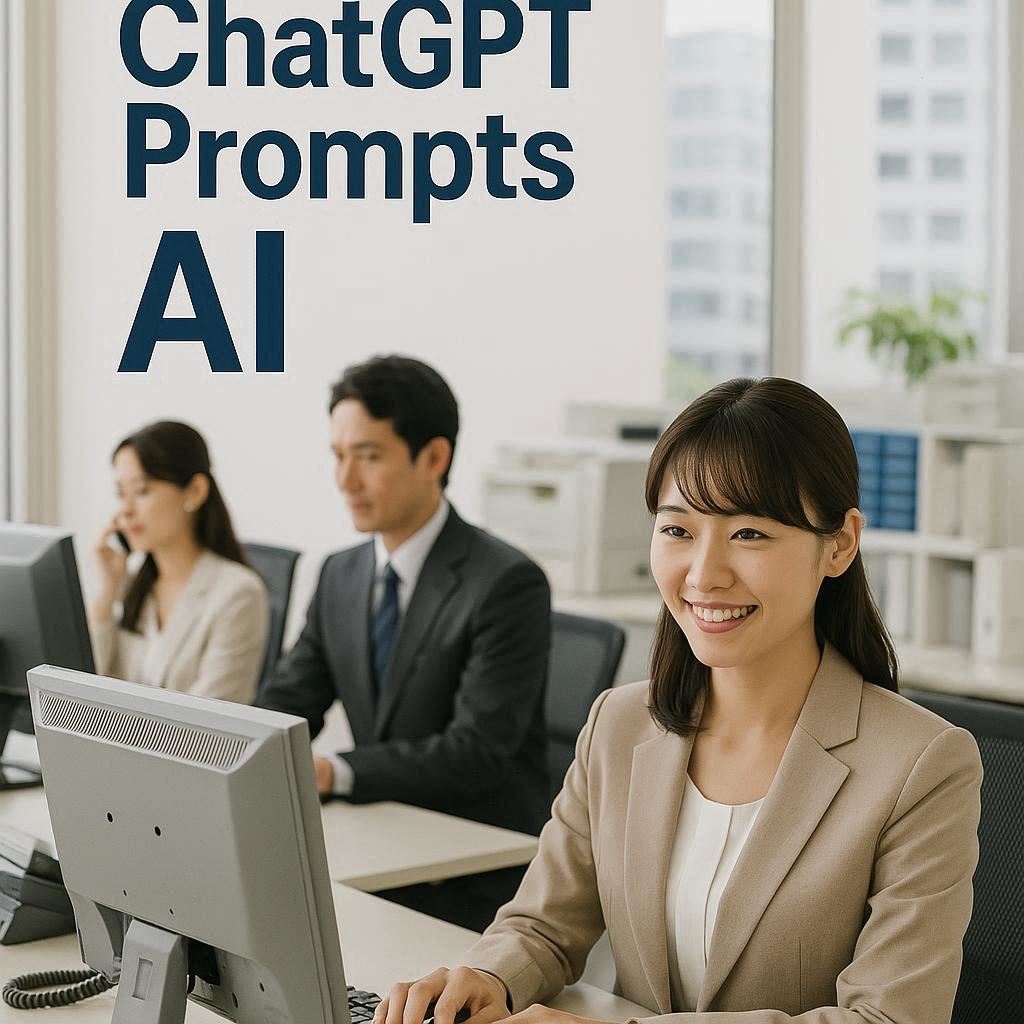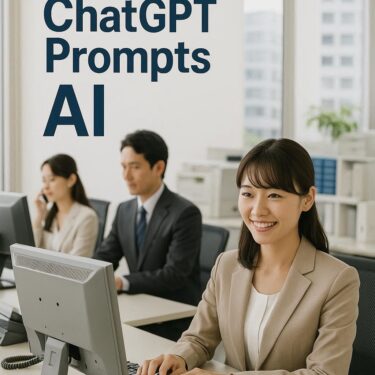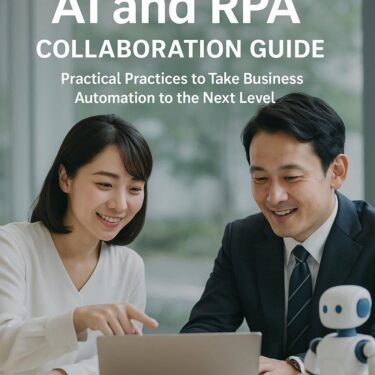「AIは私の仕事を奪う」と泣いた彼女が、部署のエースに変わった日
先日公開した「ChatGPTプロンプトの教科書」の記事、おかげさまで多くの方に読んでいただけたようです。あの記事には、AIの性能を最大限に引き出すための実践的なテクニックを、これでもかと詰め込みました。
しかし、今日はあの記事には書ききれなかった、もう一つの物語…いわば「裏話」をしようと思います。
それは、日々黙々と目の前の業務をこなし、会社を根底で支えている、声の大きくない大多数の人々です。
彼らは変化を声高に拒否しません。しかし、その心の中には「今のやり方を変えたくない」「新しいことを覚えるのが怖い」という、静かですが、非常に根深い抵抗感が渦巻いています。この「サイレント・レジスタンス(静かなる抵抗)」こそが、AI導入のような大きな変革を、いつの間にか骨抜きにしてしまう最大の要因なのです。
今回は、教科書には決して書けない、そんな「普通の人々」の心をどう解きほぐし、彼らが自ら変革の担い手へと変わっていったのか。特に、経理部で起きた、ある女性社員との忘れられないエピソードをお話ししようと思います。
「前例がありませんので」―中間管理職という名の“鉄壁の門番”
製造現場でのAI活用が軌道に乗り始めた頃、社長の次なる号令は「この流れを全社に広げるぞ!」でした。白羽の矢が立ったのが、会社の心臓部ともいえる管理部門、その中でも特に正確性が求められる経理部です。
しかし、そこに立ちはだかったのが、経理部の高橋部長(52歳)。真面目で部下思い、しかし極めて慎重派。彼の口癖は「前例がありませんので」でした。
AI活用の説明に伺った私に、高橋部長は困ったような笑顔で言いました。
「いやー、ミズさんのやっていることは素晴らしいと思います。んだどもなぁ…ウチの仕事は、製造現場とは訳が違う。1円の間違いも許されねぇ世界なんだ。AIなんていう、ようわからんもんに任せて、もし何かあったら誰が責任取るんでがす?」
彼の言葉は、典型的な中間管理職の心理を表しています。新しいことへの挑戦よりも、リスクを回避し、波風を立てずに部下を守ること。その責任感こそが、皮肉にも変化を阻む厚い壁となっていたのです。
ここで、教科書の「企業で生成AIを導入・成功させるための4ステップ」を思い出してください。いきなり「Step3:スモールスタート」から入ろうとしても、門前払いされてしまいます。大事なのは、その部署に合わせた「Step1:目的の明確化と業務の棚卸し」を、相手の土俵で丁寧に行うことです。
私は、真正面からAIのメリットを説くのをやめ、まず彼の「守りたいもの」に焦点を合わせました。
「部長、おっしゃる通りです。経理業務の正確性と信頼性は、会社の根幹です。それを揺るがすようなことは絶対にあってはなりません。だからこそ、ご相談したいのです。部長や皆さんのようなプロがやるべき仕事と、正直、誰がやっても同じ退屈な作業を、一度切り分けてみませんか?」
高橋部長は、少し身を乗り出してきました。
「退屈な作業…?」
「はい。例えば、毎月大量に来る請求書の内容をExcelに転記する作業。あれは、AIが最も得意とするところです。AIに転記作業を任せ、部長や担当の伊藤さんは、そのデータを見て『この経費、先月より突出して高いな。何かあったのか?』と分析したり、不正の芽を見つけたりする。そちらの方が、よっぽどプロの仕事だと思いませんか?部長の管理業務も、もっと本質的な部分に時間を使えるようになりますよ。」
私は、AIを「仕事を奪う脅威」としてではなく、「面倒な下働きを肩代わりしてくれる部下」として描き出しました。そして、彼のマネジメント責任を脅かすのではなく、むしろ彼の管理能力を「強化する武器」として位置づけたのです。
高橋部長は、腕を組んでしばらく考え込んだ後、ポツリと言いました。
「…なるほどのぉ。わがった。とりあえず、担当の伊藤に話を聞いてみてけろ。ただし、あいつの仕事を邪魔するようなことだけは勘弁してくれ。」
厚い壁に、ほんの少しだけ扉が開いた瞬間でした。
「このExcelは、私の“城”なんです」―完璧主義者が流した涙
高橋部長から紹介された伊藤さん(32歳)は、非常に優秀な経理担当者でした。彼女が一人で管理している経費集計用のExcelファイルは、複雑な関数とマクロで完璧に作り込まれており、まさに職人芸。しかし、その業務は完全に属人化しており、彼女が休むと誰も手を出せない状態でした。
ヒアリングの場で、私はまず彼女の仕事を徹底的に称賛しました。
「伊藤さん、このExcel、すごいですね!ここまで作り込める人はなかなかいませんよ。これはもう、伊藤さんの作品ですね。」
しかし、AI活用の話になると、彼女の表情はみるみる曇っていきました。そして、俯きながら、震える声でこう言ったのです。
「…このExcelは、私が5年間、試行錯誤しながら育ててきた、私の“城”なんです。非効率なのは分かっています。でも、これをなくしてしまったら、私には何が残るんでしょうか。AIが全部やってくれるようになったら、私は…いらなくなっちゃいますよね?」
その目には、涙が浮かんでいました。
これは、前回の記事で紹介したベテラン職人の「仕事を奪われる恐怖」とは、また少し違う感情です。それは、自分の努力と時間を注ぎ込んできたアイデンティティそのものが否定されることへの、深い悲しみと喪失感でした。
教科書のテクニックだけでは、この涙を拭うことはできません。必要なのは、まず彼女の感情に寄り添い、安心感を与えることです。
「伊藤さん、ありがとうございます。その気持ちを話してくれて。AIは、伊藤さんの“城”を壊すために来たのではありません。その“城”を、もっと強固で、もっと立派な“王国”にするための、新しい仲間なんです。」
私はPCを開き、ChatGPTの画面を見せました。
「例えば、です。伊藤さんは普段、伝票をチェックする時、どんなルールで『これはおかしい』と判断していますか?頭の中で、無意識にやっていることでも構いません。」
最初は戸惑っていた伊藤さんでしたが、ぽつりぽつりと話し始めました。
「えっと…例えば、営業部の人は、基本的にタクシー代の経費は認められていないとか、交際費が5万円を超える場合は、必ず参加者のリストが添付されていなければならない、とか…」
「素晴らしい!それです!そのルールを、AIに教えてあげましょう。」
私は、教科書の「原則3:具体的な指示と条件を盛り込む」を使い、彼女の言葉を箇条書きの指示文(プロンプト)に変えて入力していきました。
あなたは経験豊富な経理監査人です。
以下のルールに基づき、添付された経費データに問題がないかチェックしてください。
# チェック項目
1. 営業部の申請に「タクシー代」が含まれていないか?
2. 「交際費」が5万円を超える場合、「参加者リスト」の記載があるか?
3. 出張申請がない日に、遠隔地の交通費が申請されていないか?
(以下、伊藤さんのルールが続く)
そして、テストデータを入力し、実行ボタンを押しました。すると、AIは一瞬で、ルール違反の項目をリストアップし、その理由まで添えて回答を返してきたのです。
「…すごい。私がいつも目で追って、一つひとつ確認していることを、一瞬で…。」
伊藤さんの目に、先ほどとは違う種類の輝きが宿りました。それは、恐怖や悲しみではなく、「驚き」と「好奇心」の光でした。
「そうなんです。AIは、伊藤さんのルールがなければただの箱です。このすごいアウトプットを生み出したのは、AIではなく、ルールを教えた伊藤さん自身なんですよ。伊藤さんは、AIの“先生”なんです。」
この日を境に、伊藤さんの行動は劇的に変わりました。彼女はAIを「仕事を奪う敵」ではなく、「自分の知識をインストールできる、超優秀なアシスタント」と捉えるようになったのです。
AIに“伊藤さん”を降臨させた、たった一つのプロンプト
数週間後、高橋部長から興奮した声で電話がかかってきました。
「ミズさん、大変だ!伊藤さんが、とんでもないもん作ったぞ!」
急いで経理部へ向かうと、そこには自信に満ちた表情の伊藤さんと、彼女のPC画面を食い入るように見つめる同僚たちの姿がありました。
彼女が作ったのは、単なるチェックツールではありませんでした。教科書の「プロンプトテンプレート8. アンケート結果の分析と示唆」を応用し、彼女が長年の経験で培った「経理の勘」を言語化した、独自の“不正経費検知プロンプト”だったのです。
# 役割
あなたは、当社の経理業務に10年間従事してきた、非常に注意力深く、数字の裏側を読むことに長けたベテラン経理担当者「伊藤さん」です。あなたの口癖は「何かおかしいな?」です。
# 目的
以下の経費データ全体を俯瞰し、単なるルール違反だけでなく、「不正の可能性」や「経費の無駄遣い」を示唆する、通常とは異なるパターンの申請を5つ指摘してください。単なる事実の列挙ではなく、あなたの経験に基づいた「懸念点」や「追加で確認すべき事項」を、人間味のある口調で報告してください。
# お手本(Few-Shotプロンプティング)
例1:
【指摘】Aさんの交通費が、先月比で3倍に急増しています。
【懸念点】営業先が変更になったのでしょうか?それとも、非効率なルートを使っている可能性があります。一度、訪問スケジュールと照らし合わせて確認した方が良いかもしれませんね。
例2:
【指摘】B部署の消耗品費で、同じ日に3回に分けて同じ店舗から購入履歴があります。
【懸念点】合計すれば経費申請の上限を超えるため、意図的に分割して申請した可能性があります。購入した品目の詳細を確認すべきです。
このプロンプトは、もはや単なる指示書ではありません。AIに「伊藤さん」という人格と経験を憑依させる、魔法の呪文でした。教科書の「原則1:役割を与える」と「原則5:お手本を示す」を、彼女自身の言葉で完璧に融合させた傑作です。
このツールによって、今まで見過ごされてきた不自然な経費が次々と発見され、経理部の業務は「作業」から「分析・監査」という、より高度な知的労働へとシフトし始めました。伊藤さんは、自分の“城”を手放した代わりに、会社全体のガバナンスを強化する“要塞”を築き上げたのです。そして何より、彼女は自分の仕事に、以前とは比べ物にならないほどの誇りとやりがいを見出していました。
まとめ:最高のプロンプトは、「誰かの物語」から生まれる
AI導入のプロジェクトは、いつも合理的に進むわけではありません。むしろ、その道のりは非合理的な「人の感情」との戦いの連続です。
- 変化を恐れる中間管理職の「保身」。
- 自分の存在価値を守ろうとする担当者の「プライド」。
- 「よくわからない」という純粋な「不安」。
これらの感情を無視して、正論や効率論だけを振りかざしても、何も動きません。
教科書に載っているプロンプトの原則やテンプレートは、あくまで設計図です。その設計図に魂を吹き込み、本当に現場で機能する「生きたプロンプト」を創り上げるのは、いつだって現場で働く一人ひとりの「物語」なのです。
私たちの仕事は、AIという新しい筆を彼らに渡し、彼ら自身が自分の物語を、より輝かしい未来へと書き換えるお手伝いをすること。
そのためには、まず相手の“城”を尊重し、その歴史に敬意を払い、そして「あなたこそが、この改革の主役なんですよ」と伝え続けること。この人間臭いコミュニケーションこそが、どんな高度なプロンプトエンジニアリングにも勝る、最強のマネジメント術なのだと、私は信じています。
あなたの職場にもきっと、自分だけの“城”に閉じこもっている「伊藤さん」がいるはずです。その城の扉を、あなたなら、どうやってノックしますか?