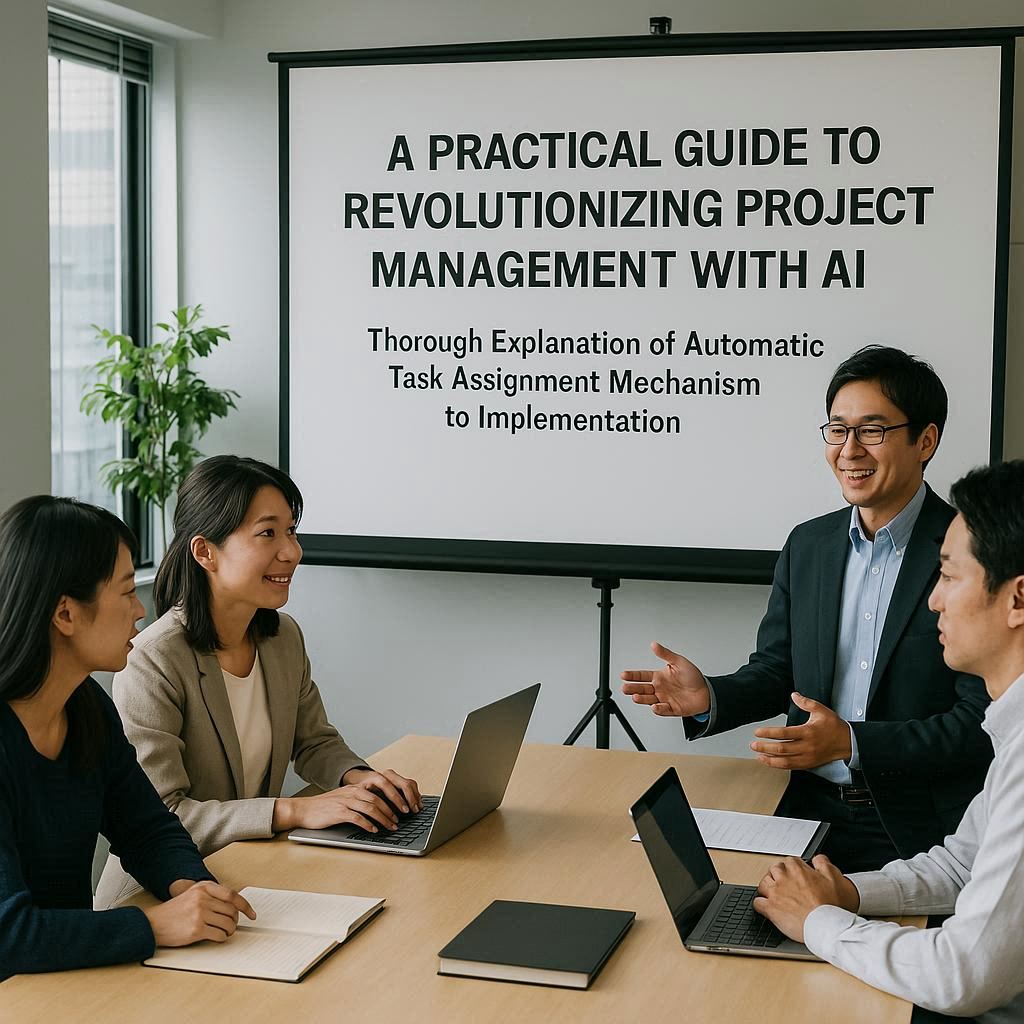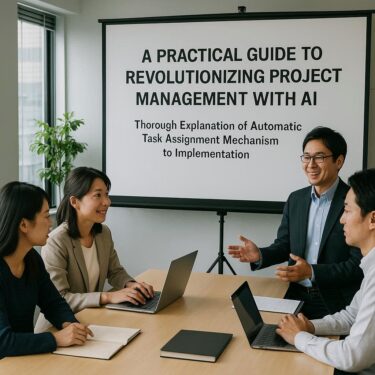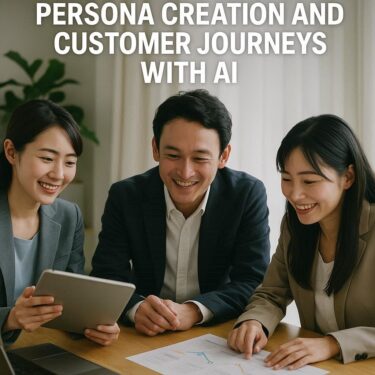「AIは正論を言う。でも、現場は動かない」――タスク自動化の裏で起きていた、泥臭いコミュニケーションのすべて
先日、「AIでプロジェクト管理を革新する実践ガイド」という記事を寄稿しました。タスクの自動割り当てから導入の7ステップまで、理論的かつ体系的に、いわば「模範解答」を書き上げた つもりです。
AIでプロジェクト管理を革新する実践ガイド|タスク自動割り当ての仕組みから導入まで徹底解説 あなたのチームでは、こんな悩みを抱えていませんか? 「この急なタスク、誰に任せるのが最適なんだろう…」「またAさんにばかり仕事が集中し[…]
しかし、今日はあの記事には一行も書けなかった、書かなかった話をしようと思います。
AI導入のプロジェクトは、綺麗なガントチャートやKPI設計図の通りに進むことなど、まずありません。現実はもっと泥臭く、人間臭い。最新のAIアルゴリズムを前にして私たちが対峙するのは、技術的な課題ではなく、いつだって「人」の感情や習慣、そしてプライドの壁なのです。
これは、私が携わったある中堅製造業での、AI導入プロジェクトの裏話。あの記事の行間に埋もれていた、本当の物語です。
「データが8割」の真実。それは絶望から始まる
「プロジェクトの成否はデータ整備で8割決まる」
記事では、さも当然のようにこう書きました。しかし、この一文を現場で口にした瞬間、目の前に座っていた担当者の佐藤さん(30代・仮名)の顔から、すっと血の気が引いていくのを私は見逃しませんでした。
彼女は非常に優秀で、この改革プロジェクトのキーパーソンとして抜擢された、部署のエースです。私は、キックオフミーティングの場で、自信満々に切り出しました。
「では佐藤さん、まずは過去1年分のプロジェクトデータを集めていただけますか?タスク内容、担当者、見積工数、実績工数、遅延理由などが分かるものをお願いします」
佐藤さんは数秒間、何かをこらえるように唇をきつく結んだ後、絞り出すように言いました。
「…データ、ですか。一応、サーバーに報告書のフォルダはあります。でも…」
その「でも」の後に続く言葉は、この手のプロジェクトで何度も聞いてきた、お決まりのセリフでした。
実態はこうです。プロジェクト管理は名ばかりで、実質は各担当者のPC内にある無数のExcelファイル。フォーマットは担当者ごとにバラバラ。「見積工数」は経験と勘で入れられた努力目標値。「実績工数」に至っては、月末に記憶を頼りにまとめて入力されているため、実態とはかけ離れている。遅延理由は「別途報告」とだけ書かれ、その別途報告書はどこにもない。
AIという最新鋭のF1エンジンがあっても、燃料である「データ」が泥水では、エンジンがかかるどころか錆びついてしまう。私たちは、広大な泥沼の真ん中に立たされていることに、早々に気づかされたのです。
正論という名のナイフと、ベテランが守る「聖域」
データがないなら、作ればいい。私はまず、タスク管理のルール化を提案しました。タスクを起票する際の必須項目を定め、作業ログをリアルタイムで記録する。ごく当たり前の、正攻法です。
しかし、この提案が、最初の大きな壁を呼び寄せました。部署の責任者である、鈴木課長(50代後半)です。この道30年のベテランで、現場の職人たちからの信頼も厚い、いわばこの部署の「主」のような人物でした。
説明の場で、彼は腕を組んだまま黙って私の話を聞いていましたが、やがて重々しく口を開きました。その言葉は、彼の故郷である庄内地方の、温かくも厳しい響きを持っていました。
「あんたの言ってることは、理屈ではわかる。だがのぉ…」
一拍置いて、彼は続けました。
「んだば、わだしらの仕事ば増やすだけでの。毎日PCに細かい数字ば入力する暇があったら、手を動かしていいもん作った方がよっぽどマシだ。今までこのやり方で、なんとかやってきたんだ。AIだかなんだか知らねども、現場ば見ねで数字だけいじくっても、いいもんはでぎねぞ」
正論でした。彼の言葉は、現場の誰もが感じていたであろう本音を代弁していました。新しいルールは、短期的に見れば確実に彼らの負担を増やします。そして何より、彼の言葉の奥には「俺たちの仕事のやり方に、部外者が土足で踏み込んでくるな」という、仕事への誇りと聖域を守ろうとする強い意志が感じられました。
会議の後、佐藤さんは疲れ切った顔で私に言いました。
「すみません…。課長はああ見えて、誰よりも部署のことを考えている人なんです。みんなも今の業務で手一杯で、これ以上は正直、厳しいと思います…」
板挟みになった彼女の苦悩が、痛いほど伝わってきました。ここで私が「しかし、これは決定事項ですから」と正論を振りかざせば、プロジェクトは開始と同時に空中分解していたでしょう。
「翻訳者」になる。相手の言葉で、未来を語る
私がすべきことは、AIの素晴らしさを説くことではありませんでした。経営層が使う「生産性向上」「業務効率化」という言葉と、現場が発する「これ以上無理」「負担が増える」という言葉。この二つの間に立ち、双方の言語を「翻訳」することでした。
私は佐藤さんに頼んで、後日、鈴木課長の仕事が終わる時間を見計らって、二人で彼の席を訪ねました。
「鈴木課長、先日は失礼いたしました。少しだけ、お時間をいただけますか?」
警戒する課長に、私はこう切り出しました。
「おっしゃる通りです。課長や皆さんの経験と勘は、どんなAIにも真似できません。私たちがやりたいのは、その素晴らしい経験や勘を奪うことではなくて、もっと楽に、そしてチーム全体の力にすることなんです」
まず、相手を肯定する。敵ではない、味方であることを示す。そして、彼のチームが「本当に困っていること」に焦点を当てました。事前に佐藤さんからヒアリングしていた、現場の「痛み」です。
「佐藤さんから伺いました。急な仕様変更が入ると、いつも設計担当のA君に負担が集中してしまうそうですね」
鈴木課長の眉が、ぴくりと動きます。
「月末の進捗報告書を作るのに、皆さんで丸一日以上かかってしまうとか」
彼は、ぐっと言葉を飲み込みました。
そこですかさず、私は「翻訳」した未来を提示します。
「もし、急な変更が入った時に、『今、この変更に一番早く対応できるのはBさんです。A君は別の重要タスクを抱えていますから』とAIがそっと教えてくれたら、鈴木課長がA君に無理をさせずに済むかもしれません」
「もし、月末の報告書がボタン一つで自動で出来上がったら、皆さんの貴重な時間を、もっと製品の品質を高める議論に使えませんか?」
「効率化」という漠然とした言葉を、「A君の負担軽減」や「報告書業務からの解放」という、極めて個人的で具体的なベネフィットに翻訳して伝える。AIを導入する目的は、会社のためだけでなく、他ならぬ「あなたたち自身のため」なのだと。
鈴木課長はしばらく黙っていましたが、やがて「…まあ、理屈はな」とだけ、ポツリと呟きました。大きな変化ではありませんでしたが、分厚い氷に、小さな亀裂が入った瞬間でした。
ゲーム感覚で「共犯者」を増やす、小さな成功体験の演出
大きな抵抗が予想される改革は、決して全社一斉に始めてはいけません。記事で「ステップ5:パイロット運用」と書いた部分です。
私は鈴木課長に、「まずは課長の部署だけで、しかも目標を『月末報告書の自動作成』という一点に絞って試させてほしい」と提案しました。失敗したら、すぐにやめる。その約束を取り付け、私たちは小さな実験を開始しました。
問題は、どうやって日々の作業ログを入力してもらうか。ただ「ルールなので入力してください」では、義務感から形骸化するだけです。
そこで、佐藤さんと一緒に一計を案じました。タスク完了時に、必須項目に加えて「任意の一言コメント欄」を設けたのです。そして、入力されたコメントの中で、最も改善に繋がる良いコメントをした人を「今週のMVP」として、朝礼で発表し、ささやかな景品(近くのカフェのコーヒーチケット)を贈ることにしたのです。
最初は「面倒だ」と誰も見向きもしませんでした。しかし、佐藤さんが粘り強く数人の若手に声をかけ、彼らが「ここの部品、設計変更のせいで手戻り多すぎ」「この作業、マニュアルが古くて分かりにくい」といった生の声を書き込み始めると、空気が変わり始めました。
自分のコメントがMVPに選ばれ、朝礼で課長から「よく気づいたな」と褒められる。そんな小さな成功体験が、徐々に他のメンバーにも伝播していったのです。いつしかコメント欄は、単なる報告ではなく、現場の知恵や改善提案が飛び交う、生きたデータベースへと変わっていきました。
このプロセスを通じて、佐藤さんの役割も大きく変わりました。最初は上から言われた業務をこなす「担当者」でしたが、メンバーからのコメントを拾い上げ、課題を分析し、「次はこれを試してみませんか?」と自ら提案する「改革の推進者」へと成長していったのです。
ある時、彼女は私にこう言いました。
「最初は、なんで私がこんな面倒なデータ集めを…って、正直思ってました。でも、みんなのコメントを見ていると、チームの課題が数字だけじゃなく、人の言葉としてリアルに見えてきて。これをちゃんと集めて分析すれば、本当に何かが変わるかもしれないって、今は本気で思えるんです」
彼女はもう、私の「共犯者」でした。
そして迎えた、実験開始から1ヶ月後の月末。佐藤さんが鈴木課長の目の前で、ツールのボタンをクリックすると、ものの数分で精度の高い進捗報告書のドラフトが出力されました。
鈴木課長は、モニターに映し出されたグラフや数値を食い入るように見つめた後、深く息を吐いて、少しだけ口角を上げて言いました。
「ほう、たいしたもんだのぉ。…こいだば、ちっとは楽になるかもしんねな」
彼が「抵抗勢力」から、私たちの「最大の協力者」に変わった瞬間でした。
結論:AIは最強の「補佐役」。主役は、いつだって人間だ
あの記事で紹介した「AI導入7つのステップ」は、いわば理想的な登山ルートを示した地図です。しかし、実際の現場という山は、地図に載っていないぬかるみや、進路を阻む藪、そして天候の急変に満ちています。
そんな時、必要なのは地図の正しさを主張することではなく、一緒に登る仲間の声に耳を傾け、励まし合い、時には迂回路を探す知恵とコミュニケーションです。
AIは、データに基づいて最も合理的な「正論」を導き出します。それは非常に強力な武器です。しかし、人を動かし、組織を変えるのは、正論だけではありません。その人の痛みに寄り添う「共感」と、困難の先にある未来を共有する「物語」です。
もしあなたが今、現場の抵抗という壁にぶつかっているのなら、一度PCを閉じて、彼らの席に行ってみてください。そして、「何に困っているのか」「本当はどうなりたいのか」という、心の声に耳を傾けてみてください。AIを導入する目的を、会社の言葉から、彼ら自身の言葉へと「翻訳」してみてください。
そこにこそ、どんな高度なアルゴリズムにも勝る、プロジェクト成功への唯一の道が隠されているはずです。
ちなみに、後日談があります。
あのプロジェクトは、鈴木課長という強力な後ろ盾を得て、見事に全部署への展開を果たしました。そして、その中心にいたのは、すっかり改革のリーダーとしての顔つきになった、佐藤さんでした。彼女は今、AIが弾き出したデータを見ながら、メンバー一人ひとりと「君の次のキャリア、どう考えてる?」なんて話をしています。
AIはタスクを最適化しますが、人の心を動かし、成長を促すのは、やはり人の役割なのです。結局のところ、私たちはそのための「時間」と「きっかけ」を作るために、テクノロジーを使っているのかもしれません。