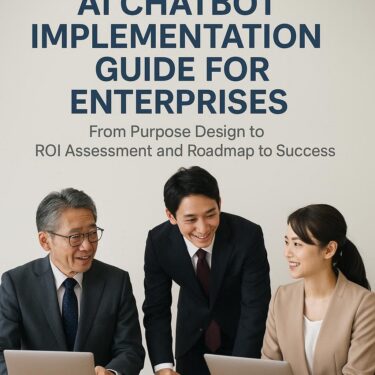「AIは儲かるのか?」その問いの裏で起きていた、現場と経営の静かなる戦い
先日、AI導入の費用対効果(ROI)に関する記事を公開しました。フレームワークや計算式を並べ、いかに論理的に投資価値を説明するか、その手法を解説したものです。おかげさまで多くの方に読んでいただき、「参考になった」とのお声も頂戴しました。
しかし、正直に告白します。あそこに書いた綺麗なフレームワークや数式だけで、プロジェクトがすんなり進むことなんて、まずありません。むしろ、本当の戦いは、そのExcelシートの外側で繰り広げられる、もっと泥臭くて人間臭いものなのです。
今日は、あの記事には書ききれなかった「裏側」の話をしようと思います。これは、ある地方の製造業でAI導入を担当することになった30代の女性、佐藤さん(仮名)と、私が共に奮闘した数ヶ月間の記録です。テーマは「数字の裏にある、人と組織の動かし方」。もしあなたが今、社内の調整や説得に頭を悩ませているなら、きっと共感していただける部分があるはずです。
第1幕:「隠れコスト」という名の“サービス残業予算”との戦い
「これで見積もりを取りました!このAIツールを導入すれば、年間これだけのコスト削減が見込めます!」
佐藤さんが意気揚々と持ってきた資料には、ベンダーから提示されたライセンス費用と、それによって削減される作業時間の試算が見事にまとめられていました。しかし、私にはそれが見積もりではなく、ただの「請求書」にしか見えませんでした。
「佐藤さん、素晴らしい資料ですね。ただ、いくつか質問があります。このプロジェクトを進めるための会議、誰が参加して何時間使いますか? 現場でのテストやヒアリングは? 既存システムとの連携仕様を決める打ち合わせは? それらに関わる佐藤さんや、各部署の方々の人件費は、どこに計上されていますか?」
私の問いに、佐藤さんの顔がみるみる曇っていきます。
「…それは、業務時間内に、各自がなんとかする、というか…。そんなことまで計上したら、予算が膨れ上がって、絶対に承認されません」
彼女の不安は痛いほどわかります。多くの企業で、こうした社内調整コストは「見えないもの」として扱われ、担当者の頑張りや“サービス残業”によって吸収されてきました。しかし、AI導入のような全社的な変革プロジェクトでそれをやると、必ず破綻します。
そこに、同席していた製造部長(50代、この道30年のベテラン)が口を開きました。
「ミズさんの言うごどもわがるけども、んだのぉ。そだな時間、どっから捻出すんだがなぁ。今でさえ、みんな目の前の仕事で手一杯だでの」
これが、多くの現場が抱える本音です。私は佐藤さんと部長に、あの記事で紹介した「コストの氷山モデル」の図を見せました。
「お二人が今見ているのは、この氷山の水面から出ている部分だけです。本当にプロジェクトの成否を左右するのは、水面下にあるこの『隠れコスト』、つまり皆さんの時間です。これを予算に計上しないということは、『このプロジェクトは皆さんのサービス残業を前提に進めます』と宣言するのと同じことですよ。それで本当に、現場の協力を得て、良いものを作れるでしょうか?」
少し厳しい言い方だったかもしれません。しかし、ここで曖昧にしては進めない。沈黙が流れました。先に口を開いたのは、部長でした。
「…わがった。ちゃんと見積もっぺ。佐藤さん、各部署さ声がけして、誰が何ばせねばねのが、時間ば洗い出しでけろ。こごで中途半端なごどすれば、後で自分たちの首絞めるだけだ」
この瞬間、プロジェクトの歯車がカチリと音を立てて噛み合いました。
ROI記事で書いた「隠れコストを洗い出す」という一行。その裏側には、こうした「見えない頑張り」を可視化し、それを正式なコストとして会社に認めさせるという、最初の、そして最も重要な合意形成のプロセスがあるのです。これは単なる予算確保ではありません。プロジェクトに対する会社の「本気度」を測るリトマス試験紙なのです。
第2幕:ベネラント職人の一言が、ROIを2倍にした日
無事にコストの全体像が見え、次はベネフィットの試算です。佐藤さんは、AI-OCRによる帳票入力の「時間削減」効果を算出してきました。数字は悪くない。しかし、投資額に見合うほどのインパクトかと言われると、少し物足りない。経営層を「これはやるべきだ!」と唸らせるには、もう一押し欲しいところでした。
「佐藤さん、一度、現場に話を聞きに行きませんか?数字だけじゃなく、現場の『物語』を集めましょう」
私たちは、帳票処理を担当している部署へ向かいました。そこにいたのは、勤続40年になる大ベテランの木村さん(60代)。今回のAI導入で、最も影響を受ける一人です。
「ミズさん、わざわざどうもなぁ。AIだかなんだが知らねぇけども、わだしらが一番気ぃ遣ってんのは、この手書きの数字なんだでの。特に『1』と『7』、あと汚れて読めねぐなってるどご。これ間違うど、後工程で部品の数が合わねぐなって、ラインが止まっかのよ」
木村さんは、こともなげに言いました。しかし、私と佐藤さんは顔を見合わせます。「ラインが、止まる…?」
「はい。たまにですけど。そうなると、原因究明で半日潰れることもありますし、何よりお客さんへの納期が遅れるのが一番まずいんです。信用問題ですから」
私たちは急いで事務所に戻り、過去の生産日報やトラブル報告書を漁りました。すると、入力ミスが原因とみられる小規模なライン停止が、年に数回発生していることが判明したのです。
- ライン停止による生産機会の損失
- 原因究明に関わる複数名の工数
- 納期遅延による顧客への補償や、最悪の場合の信用失墜
これらは、佐藤さんが最初に作ったROI計算書には一行も書かれていなかった項目です。私たちは、これらの「損失額」を過去のデータから一つひとつ算出し、ベネフィットの項目に加えました。
「AIを導入することで、入力ミスが劇的に減ります。それはつまり、ライン停止のリスクを回避できるということ。これは単なる『時間削減』ではなく、『損失回避』という、もっと大きな価値なんです」
木村さんのあの一言がなければ、私たちはこの価値に気づけなかったでしょう。
ROI記事で書いた「ベネフィットを多角的に洗い出す」という手法。その本質は、Excelと睨めっこすることではありません。現場に足を運び、そこで働く人々の「困りごと」や「こだわり」に耳を傾けることです。彼らの口から語られる何気ない一言こそが、誰も気づかなかった莫大な価値(ベネてフィット)の鉱脈を掘り当てるドリルになるのです。
第3幕:「敵」を「最強の味方」に変えた、たった一つの質問
いよいよ、一部の部署でPoC(概念実証)を始めようという段階まで来ました。しかし、ここで最大の壁が立ちはだかります。「現場の抵抗」です。
PoCの対象部署のリーダーである田中さん(40代)が、プロジェクトの説明会で腕を組み、敵意むき出しの目で私たちを睨みつけていました。
「ただでさえ忙しいのに、そんな新しいことやってる暇なんてないですよ。大体、そんなもんに頼らなくても、俺たちには長年の経験と勘がある。俺たちの仕事を奪うつもりですか?」
典型的な抵抗勢力です。会議室の空気は凍りつき、佐藤さんはすっかり萎縮してしまっています。多くのプロジェクトが、この壁を乗り越えられずに頓挫します。
その日の帰り道、私は落ち込む佐藤さんに言いました。
「佐藤さん、田中さんを敵だと思うのはやめましょう。彼は、このプロジェクトを成功させるための最重要人物、キーマンです」
「え…? あんなに反対しているのに…?」
「だからこそ、です。彼の協力なしでは、絶対にうまくいかない。逆に言えば、彼を味方にできれば、プロジェクトは9割成功したようなものです」
翌日、私たちは改めて田中さんの元を訪れました。ただし、今度は「説明」するためではありません。「相談」するためです。
「田中さん、昨日は失礼いたしました。今日は、田中さんにAI導入の件で『相談』があって来ました」
拍子抜けした顔の田中さんに、私は一枚の帳票を見せました。読み取りが非常に困難な、汚れた手書きの帳票です。
「このAI、まだ完璧じゃないんです。田中さんのようなベテランの目から見て、このAIが正しく読み取れるか、どこで間違いそうか、その『勘どころ』を教えていただけないでしょうか? 田中さんの経験と勘がなければ、このAIはただの箱のままなんです。そのノウハウをAIに教えて、田中さんには、もっと付加価値の高い、田中さんにしかできない仕事に集中してほしい。私たちはそう考えています」
そして、最後にこう付け加えました。
「つきましては、今回のPoCの評価責任者を、田中さんにお願いできないでしょうか。このAIが現場で本当に『使える』か『使えない』か、最終的な判断を田中さんに委ねたいんです」
田中さんの険しい表情が、少しずつ和らいでいくのがわかりました。彼はしばらく黙って帳票を眺めていましたが、やがてペンを取り、こう言いました。
「…この『3』はクセが強いから、たぶん『8』って誤読するな。あと、ここのシミはインクと間違えるかもしれん。…わかった。俺が一度、見てやる」
ROI記事で書いた「現場の巻き込み不足を回避する」という項目。その秘訣は、「説明」ではなく「相談」すること。「指示」ではなく「役割」を与えること。そして、相手へのリスペクトを忘れないことです。人は「やらされる」ことには抵抗しますが、「頼られる」ことには弱い生き物です。特に、自分の仕事にプライドを持っている人ほど、その傾向は強い。
あの田中さんは、その後、誰よりも熱心なプロジェクトの推進者となってくれました。「俺が育てたAIだ」と、嬉しそうに語りながら。
終幕:ROIとは、想いを翻訳するコミュニケーションツールである
AI導入のROIを計算する。それは、決して冷たい数字の計算作業ではありません。
- 見過ごされてきた現場の「時間」というコストに光を当て、
- 数字には表れないベテランの「知恵」という価値を掘り起こし、
- 変化を恐れる人々の「不安」を「期待」へと変えていく。
そのすべてのプロセスを「数字」という共通言語に翻訳し、関係者全員で未来への羅針盤を共有する、極めて人間的なコミュニケーション活動なのです。
あの記事に書いたフレームワークや手法は、そのための強力な武器です。しかし、武器だけでは戦には勝てません。大切なのは、その武器を手に、誰と話し、何を伝え、どうやって心を動かすか。
もしあなたが今、AI導入の分厚い企画書の前で途方に暮れているのなら。まずはパソコンを閉じて、現場に足を運んでみてください。そして、隣の席の同僚や、工場のベテランに、こう尋ねてみることから始めてみてはいかがでしょうか。
「最近、仕事で一番面倒なことって、何ですか?」
あなたのプロジェクトは、きっとそこから動き出すはずです。