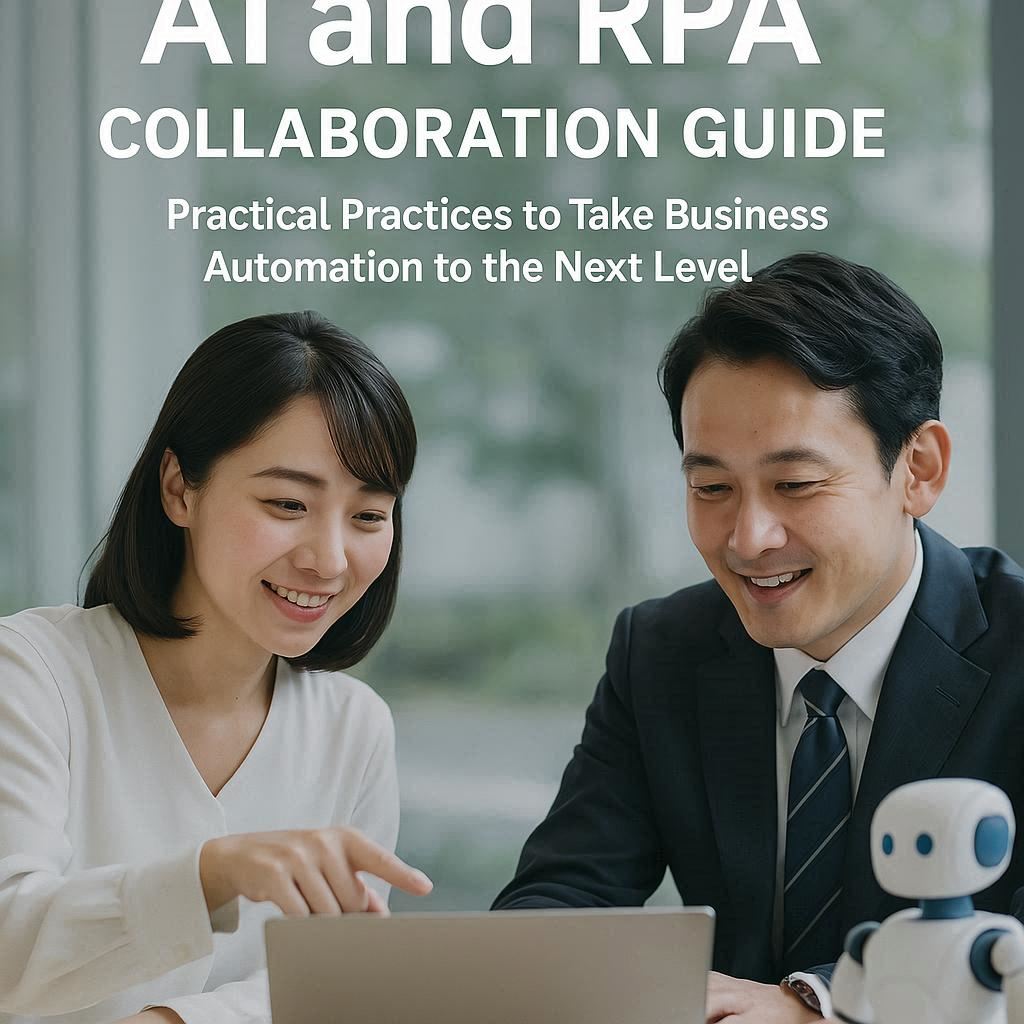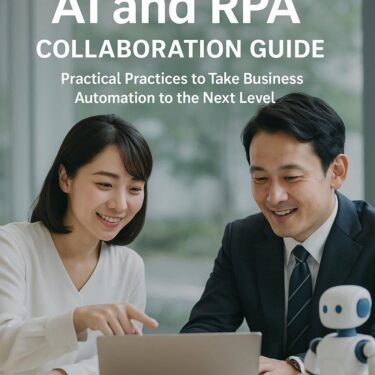「AIとRPAは手と脳」だけじゃ現場は動かない。自動化プロジェクト、本当の壁は“人の心”だった話
先日、あるウェブメディア向けに「AIとRPA連携ガイド」という記事を執筆しました。RPAを「手」、AIを「脳」に例え、両者を連携させることでいかに業務が進化するか、そのパターンから導入ロードマップまで、教科書的に、そして論理的に解説したものです。
書いている私自身、「うん、完璧な整理だ。これさえ読めば、担当者はきっとうまく進められるだろう」と、少しばかり得意になっていたのを覚えています。
しかし、です。この記事を読み返しながら、私はあるクライアントでの、泥臭く、そして人間味あふれる奮闘の日々を思い出していました。机上で描いた美しいロードマップ通りに進むプロジェクトなんて、現実にはほとんど存在しません。本当の戦場は、サーバー室でも会議室でもなく、現場で働く人々の「心の中」にあるのです。
この記事は、あの「完璧なガイド記事」の、どこにも書かれていない舞台裏の物語です。もしあなたが今、社内のDX推進や業務改革で、見えない壁にぶつかっているのなら。きっと「ああ、うちも同じだ」と膝を打つ場面があるはずです。
「俺たちの脳は、もう要らねえってことか?」――比喩が招いた、まさかの抵抗
それは、ある中堅製造業でのこと。長年の紙文化から脱却すべく、RPAとAI-OCRを組み合わせた請求書処理の自動化プロジェクトが立ち上がりました。推進役は、入社8年目の聡明な女性、経理部の佐藤さんです。
最初の経営会議。私は例の「RPAは手、AIは脳」というキャッチーな比喩を使って、プロジェクトの概要を説明しました。役員たちの受けは上々。しかし、会議の終わり際、ずっと腕を組んで黙っていた経理部長の鈴木さん(58歳)が、重い口を開きました。
「先生の話は、わかった。RPAが手で、AIが脳だべ?……つまり、わだしらが今まで頭使ってやってきた仕事は、これからはAIがやる。わだしらの脳みそは、もう要らねえってことか?」
庄内弁の朴訥とした響きとは裏腹に、その言葉には鋭い棘がありました。ハッとしました。効率化や合理化を求めるあまり、そこで長年プライドを持って仕事をしてきた人々の存在を、無意識のうちに軽んじていたのかもしれない。これはまずい。
隣に座る佐藤さんの顔が、さっと青ざめるのが分かりました。
「鈴木部長、とんでもないです。全く逆です」
私は身を乗り出して言いました。
「私たちがやろうとしているのは、皆さんの脳を『不要』にすることではありません。むしろ、鈴木部長のように長年培われた『優れた脳』の働きを、もっと価値のある仕事に使っていただくための仕組み作りです。例えば、毎月何百枚も来る請求書の数字を、ただシステムに打ち込む作業。これは脳を使っているようで、実は思考を止める『作業』です。この作業をAIとRPAに任せることで、部長には『この取引先の支払サイト、本当にこれでいいのか?』とか『このコスト構造は、もっと改善できないか?』といった、会社の利益に直結する『判断』や『分析』に、その貴重な経験と頭脳を使っていただきたい。これが私たちの本当の狙いです」
そして、こう付け加えました。
「そもそも、AIはまだ完璧ではありません。部長が請求書を見て『お、この会社、今月は仕入れが多いな。何か新しい動きがあったのか?』と気づくような、背景を読み取る力はないんです。その『気づき』こそ、AIには真似できない人間の価値であり、会社の宝です。私たちは、皆さんがその『宝』を磨く時間を創り出したいんです」
鈴木部長は、まだ納得しきれない顔つきでしたが、険は少し和らいだように見えました。この一件で、私たちは学びました。新しい技術を導入する時、その「機能」や「効果」を語る前に、まずそこで働く人々の「誇り」と「存在価値」に、最大限の敬意を払わなければならない、と。
「どうせお試しでしょ?」――スモールスタートの罠と“静かなるサボタージュ”
教科書通り、私たちは「スモールスタート」から始めることにしました。まずは鈴木部長の経理部で、特定の取引先からの請求書処理だけを対象にPoC(概念実証)を行う計画です。
しかし、これが新たな壁を生みました。「PoC」や「スモールスタート」という言葉が、現場には「お試し」「本気じゃない」というニュアンスで伝わってしまったのです。
佐藤さんが現場の担当者に協力を依頼しても、
「すみません、今ちょっと月末処理で立て込んでて…」
「そのデータ、どこにありましたっけ?探しておきますね(と言って、3日経っても出てこない)」
あからさまな抵抗はないものの、協力は得られない。いわゆる“静かなるサボタージュ”です。彼らからすれば、日々の忙しい業務に加えて、成果が出るかどうかも分からない「実験」に付き合わされるのは、迷惑以外の何物でもなかったのでしょう。
佐藤さんはすっかり参ってしまいました。
「私の力不足です…。どうすれば、みんなを巻き込めるんでしょうか…」
「佐藤さん、これはあなたのせいじゃありません。マネジメントの問題です。このプロジェクトが『他人事』になっているのが原因です。ちょっと荒療治になりますが、いくつか仕掛けましょう」
私たちはすぐに動き出しました。
- 社長の言葉で「宣言」する:
次の朝礼で、社長から全社員に向けてこう話してもらいました。「経理部で始まる新しい取り組みは、単なる『お試し』ではない。我が社の未来を賭けた『最初の一歩』だ。この挑戦の成功なくして、会社の次の50年はない。経理部のメンバーは、その未来を切り拓くパイオニアだ。全社を挙げて彼らをサポートしてほしい」 - 「ヒーロー」を創り出す:
PoCの対象となった経理部の担当者たちを、社内報のトップ記事で特集しました。「DX時代の挑戦者たち」と銘打ち、彼らの顔写真と意気込みを掲載。少し大袈裟なくらいに「ヒーロー」として持ち上げたのです。人は誰しも、期待され、注目されると、それに応えようとする心理が働きます。 - 成功の「果実」を具体的に見せる:
プロジェクトが成功した場合のメリットを、個人レベルまで落とし込みました。「この自動化で月20時間の残業が削減できれば、その時間を新しいスキルアップ研修に充てられる制度を人事に作ってもらっています」といった具体的な「ご褒美」を提示したのです。
効果はてきめんでした。翌日から、現場の空気が明らかに変わりました。「あのデータ、これですかね?」と、今まで協力が得られなかった担当者から声がかかるようになったのです。
技術導入を成功させるには、技術そのものの優位性だけでなく、関わる人々の「当事者意識」と「動機付け」をいかにデザインするか。これもまた、教科書には載っていない、極めて重要なマネジメント術なのです。
AI導入で炙り出された「帳票の闇」と、部門間の壁という名の“魔物”
PoCが軌道に乗り始め、いよいよ本格導入に向けて対象を広げようとした時、私たちは三つ目の、そして最大の壁にぶち当たります。
AI-OCRで読み取る請求書のフォーマットが、取引先ごとにバラバラなのは想定内でした。しかし、問題はもっと根深く、社内の「帳票文化」そのものにあったのです。
例えば、営業部が使う受注伝票。そこには、いつからあるのか誰も知らない謎のチェック欄や、担当者だけが分かる手書きのメモがびっしり。製造現場から上がってくる作業報告書は、何十年も使い古された独自のフォーマットで、油と埃にまみれています。
「こんなカオスな状態では、AIがいくら賢くてもデータを正確に読み取れません。まずは社内の帳票を標準化する必要があります」
私がそう提案すると、これまで協力的だった各部門の責任者たちが、途端に表情を硬くしました。
営業部長(45歳)が言います。
「いや、うちのフォーマットは変えられないよ。これはお客様の要望に合わせて、長年かけて最適化してきたものなんだ。うちの都合で変えたら、顧客満足度が下がる」
製造現場の工場長(62歳)も、負けていません。
「冗談でねえ。こっちの現場はコンマ1秒を争ってんだ。昔っからのこのやり方が一番早えんだ。パソコンでいちいち入力なんかしてらんねえ」
営業は「顧客のため」、製造は「効率のため」。どちらも正論です。そして、その裏には「自分たちの仕事のやり方を変えたくない」という強い本音が隠れています。佐藤さんは、またしても部門間の板挟みになり、途方に暮れていました。
これが、多くの企業改革を頓挫させる「部分最適の壁」という魔物の正体です。
この魔物を退治するには、小手先の説得では通用しません。必要なのは、議論の土俵そのものを変えること。私たちは、あるワークショップを企画しました。
「全帳票、棚卸し大会」です。
会議室の壁一面に、社内で使われているありとあらゆる帳票(請求書、発注書、報告書…)の現物を貼り出しました。その数、実に50種類以上。そして、各部門の責任者と担当者を集め、一つ一つの帳票、一つ一つの項目について、付箋を使いながらこう問いかけていきました。
「この項目は、誰が、何のために、いつ見ていますか?」
「この情報がなかったら、誰が、具体的にどう困りますか?」
最初は面倒くさそうにしていた参加者たちも、議論が進むにつれて、驚きの事実に気づき始めます。
「あれ、このチェック欄、3年前に退職した山田さんが作ったもので、今は誰も使ってないぞ…」
「この報告書の数字、結局誰も見ずにファイリングしてるだけだった…」
長年「聖域」だと思われていた帳票や業務プロセスの多くが、実は誰も目的を理解しないまま、惰性で続けられていた「思考停止の産物」だったことが、全員の目の前で可視化されたのです。
工場長がポツリと漏らしました。
「……なんだかなあ。わだしらは、今までこんげ無駄なことのために、毎日残業してたってことか」
空気が変わった瞬間でした。
「部分最適」の壁は、「全体像」を見せることでしか壊せません。自分たちの仕事が、他の誰の仕事に、どう繋がり、どう影響しているのか。その全体像を共有できた時、人々は初めて「自分たちのやり方」という小さなこだわりを捨て、「会社全体にとっての最適解」を探し始めるのです。
このワークショップをきっかけに、帳票の統合・標準化は一気に進みました。AIとRPAの導入は、単なるITプロジェクトではなく、会社の業務プロセスそのものを見直し、組織の壁を溶かす「全社改革プロジェクト」へと昇華したのです。
まとめ:地図だけを渡しても、冒険は始まらない
「AIとRPA連携ガイド」のような記事は、いわば冒険に出るための「地図」です。そこには、目的地までの最短ルートや、危険な場所が記されています。しかし、地図を渡されただけでは、誰も冒険に出ようとはしません。
なぜなら、冒険には困難が伴うからです。未知への不安、変化への抵抗、仲間との衝突。プロジェクトの現場で起こるのは、まさにそうした人間臭いドラマです。
私たちの仕事は、ただ綺麗な地図を描いて渡すことではありません。一緒に冒険に出る仲間として、彼らの不安に寄り添い、抵抗の裏にあるプライドを理解し、衝突を乗り越えるための知恵を絞ること。技術の前に、まず人と向き合う。遠回りに見えて、実はそれが改革を成功させる唯一の道なのだと、私は信じています。
AIは「脳」の代わりにはなっても、「心」の代わりにはなれません。プロジェクトを本当に動かすのは、ロジックやデータだけでなく、関わる人々の「やってやろうじゃないか」という熱い心なのですから。