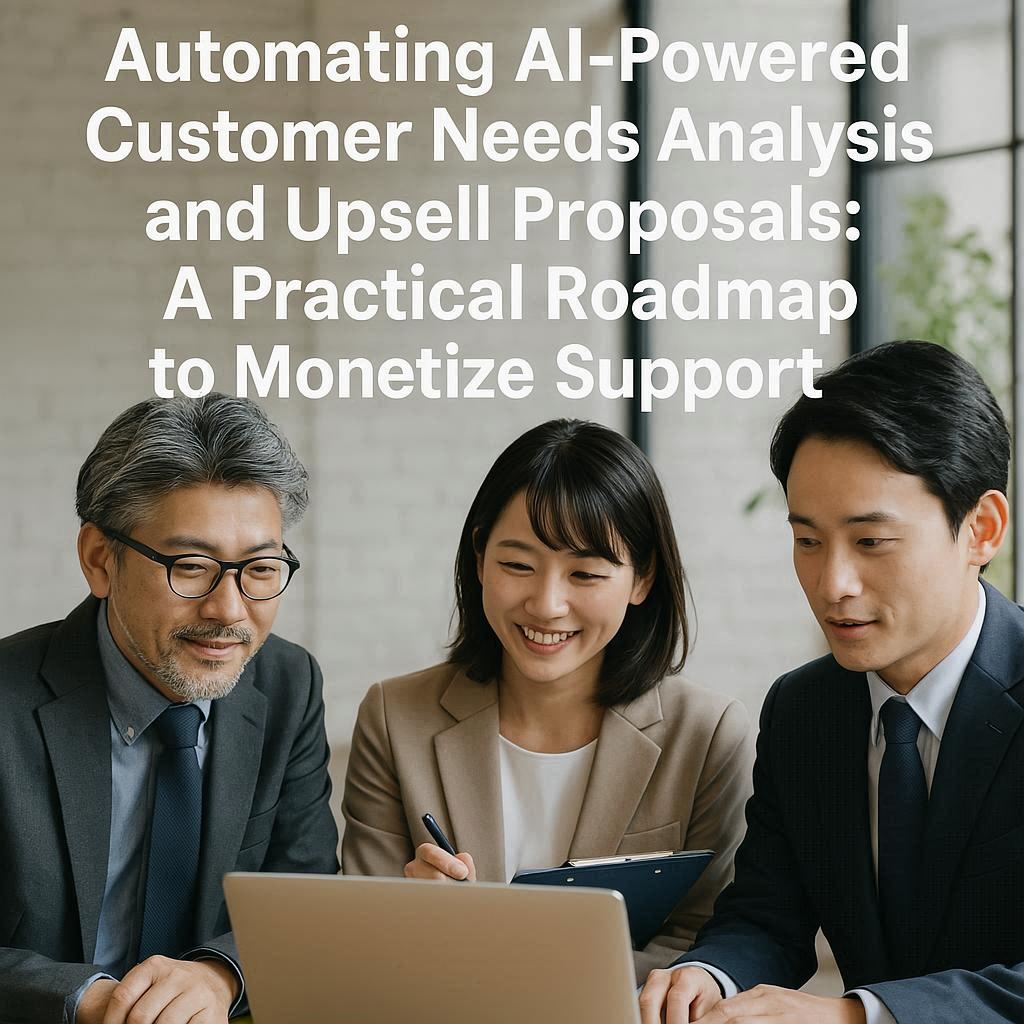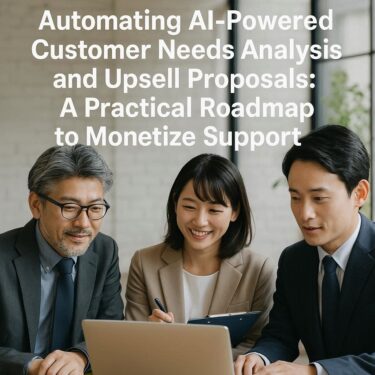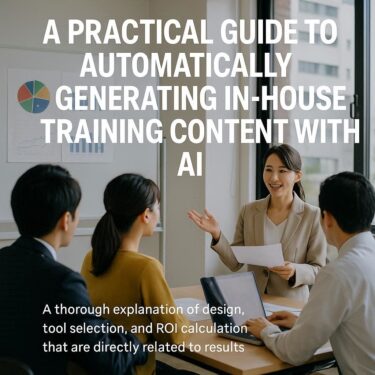「AIでサポートを利益化」その裏側で起きていたこと ― 現場の抵抗と“押し売り”への恐怖を乗り越えた術
先日公開した記事、『AIによる顧客ニーズ分析とアップセル提案の自動化』では、顧客サポートをコストセンターからプロフィットセンターへ変革するための、輝かしいロードマップを描きました。KPIを設計し、データを統合し、AIで顧客ニーズを先読みして最適な提案を行う…。まるで魔法のような未来が、すぐそこにあるかのように。
AIによる顧客ニーズ分析とアップセル提案の自動化:サポートを利益化する実践ロードマップ 顧客サポート部門は、長らく「コストセンター」と見なされてきました。問い合わせ対応に追われ、効率化を求められるものの、その活動が直接的な売上にどう[…]
しかし、現実はどうでしょう。
あの整然としたロードマップの裏側には、常に人間臭い、泥臭い現実が横たわっています。新しい仕組みに対する現場の抵抗、部門間にそびえ立つ見えない壁、そして「AI」という言葉が生む過剰な期待と深い失望。今日は、あの記事では書ききれなかった、あるプロジェクトの「裏話」を少しだけお話ししようと思います。
これは、単なる技術導入の物語ではありません。変化を恐れる人々の心をどう解きほぐし、同じ未来を見てもらうかという、コミュニケーションとマネジメントの奮闘記です。
第一幕:「我々は物売りじゃない」― サポート部門のプライドとKPIへの抵抗
プロジェクトの舞台は、ある中堅のB2Bソフトウェア企業。顧客サポート部門から抜擢された、入社10年目の佐藤さん(30代)が、今回の改革の旗振り役でした。彼女の目は希望に満ちていました。
キックオフミーティングの日。私は佐藤さんと共に、サポート部門のメンバー、特にこの道30年のベテランである鈴木課長(50代)にプロジェクトの概要を説明していました。元記事で言うところの「ステップ1:KPI設計と成功の定義」の場面です。
佐藤さん:「…というわけで、最終的なゴールは顧客満足度の向上と、お客様のビジネス成功への貢献です。その成果を測る指標として、『自己解決率』や『顧客満足度』と並行して、『アップセル転換率』も追っていきたいと考えています」
その瞬間、それまで腕を組んで黙って聞いていた鈴木課長の表情が、明らかに曇りました。
鈴木課長:「…佐藤さん、ちょっと待ってけろ。『アップセル転換率』ってなんだや?」
私:「お客様がサポートサイトを利用する中で、より上位のプランやオプション機能にご契約いただく割合のことです。例えば、ある機能の制限で困っている方に、その制限がない上位プランを情報としてご案内する、といったイメージで…」
鈴木課長:「それって、結局おらだに『もん売れ』ってごどでねぇのが?」
彼の声には、棘がありました。周りのベテラン社員たちも、同意するように頷いています。
鈴木課長:「おらだはサポートだぞ。お客さんが本当に困ってる時に、親身になって助けるのが仕事だ。その信頼関係があるから、お客さんもウチの製品を使い続けてくれるんでねぇのが。それをなんだ、『転換率』だなんて数字で追いかけて、困ってる人さ、さらに高いもん売りつけろって言うのが? そだなごどしたら、お客さんからの信頼、全部なくなんぞ。おらだは物売りじゃねぇんだ。」
これが、最初の、そして最大の壁でした。彼らにとって「サポート」とは聖域であり、そこに「売上」という概念が入ってくること自体が、自分たちの仕事への侮辱だと感じられたのです。「アップセル」という言葉が、「押し売り」という言葉にしか聞こえていなかったのです。
佐藤さんの顔から、さっと血の気が引いていくのが分かりました。正論では、この壁は崩せない。私は彼女の前に一歩出て、鈴木課長に深く頷いてみせました。
私:「鈴木課長、おっしゃる通りです。皆さんが築き上げてこられたお客様との信頼関係こそ、この会社の何よりの財産です。それを壊すようなことは、絶対にあってはなりません。もし、このプロジェクトが少しでもその信頼を損なう可能性があるなら、今すぐ中止すべきだと私も思います」
一瞬、場の空気が緩みました。敵だと思っていた相手が、自分たちの側に立ったからです。
私:「言葉が悪かったかもしれません。『アップセル』ではなく、『問題解決の選択肢を増やすお手伝い』と考えてみてはいかがでしょうか。例えば、あるエラーコードで検索してきたお客様がいるとします。マニュアル通りに対処しても、根本的な解決にはならないケースです。その時、画面の隅に『このエラーは、〇〇プランの自動バックアップ機能で恒久的に解決できます。参考情報はこちら』と小さな案内が出るとしたら…これは『押し売り』でしょうか?それとも『より高度な問題解決策の提示』でしょうか?」
鈴木課長は、腕を組んだまま黙っています。
私:「私たちは、お客様に何かを買わせたいわけじゃないんです。お客様が『次に困ること』を先回りして、『こんな解決策もありますよ』と教えてあげたい。その結果として、お客様が『ああ、そんな便利な機能があったのか』と選んでくれた数を、『お手伝いできた数』として数えたい。それが、『アップセル転換率』の本当の意味なんです。お客様を助ける、という皆さんの仕事の本質は、何も変わりません。むしろ、その武器が増えるんです」
佐藤さんも、私の意図を汲んで言葉を続けます。
「はい。それに、この仕組みがうまく回れば、よくある質問への対応が自動化されて、鈴木課長の皆さんには、もっと複雑で難しい、本当に人でなければ解決できない問題に集中していただけるようになります。皆さんの貴重な経験と知識を、もっと価値のある場所で使っていただきたいんです」
鈴木課長の眉間のしわが、少しだけ和らいだように見えました。
「…まあ、お客さんのためになるんだったら、な…」
技術や理屈の前に、まず相手の価値観を理解し、尊重する。そして、新しい取り組みが彼らのプライドを脅かすものではなく、むしろその価値をさらに高めるものであると、言葉を尽くして翻訳していく。AI導入の第一歩は、いつもこんな泥臭い対話から始まるのです。
第二幕:「ウチの宝は渡せない」― 部門間にそびえるデータの壁
最初の関門をなんとか突破し、プロジェクトは次の「ステップ2:データ収集・統合」に進みました。AIに学習させるためのデータを、社内のあちこちから集めるフェーズです。しかし、ここでも新たな壁が立ちはだかりました。それは、「部門の壁」という、より根深く、厄介な壁でした。
佐藤さんは早速、営業部と開発部を訪ねました。
【営業部にて】
佐藤さん:「高橋部長、お客様の行動をより深く理解するために、営業部門で管理されている契約データの一部と、サポートサイトのアクセスログを連携させて分析させていただけないでしょうか?」
やり手の営業部長である高橋さん(40代)は、にこやかに、しかしきっぱりと首を横に振りました。
高橋部長:「うーん、それは難しい相談だなあ、佐藤さん。契約データは我々の生命線だ。それに、サポートのデータって、要はクレームの集まりだろう?そんなネガティブな情報と、我々が築き上げた顧客情報を混ぜて、一体どんなメリットがあるんだい?」
【開発部にて】
次に訪れた開発部では、創業期からシステムを支えてきた古参エンジニアの渡辺さん(50代)が、山積みの資料の向こうから顔を上げました。
佐藤さん:「渡辺さん、AIに学習させるために、製品の仕様書や過去のマニュアルのPDFデータをいただけないでしょうか?」
渡辺さん:「佐藤さん、悪いけども、そりゃ無理だ。あのPDFマニュアルは、作った担当者も辞めて、中身も古いままだ。どれが最新版がわがんねぇし、間違った情報も混じってるかもしれん。そだなもんAIに食わせで、おかしな回答さへだら、誰が責任とんだや。そもそも、おらだは新しい機能開発で手一杯で、過去の資料整理してる暇はねぇんだ。」
佐藤さんは、完全に板挟みでした。サポート部門は「売上目標なんて」と言い、営業部門は「クレームデータなんて」と言い、開発部門は「古い資料なんて」と言う。誰もが自分の「城」を守ることに必死で、会社全体の利益という視点が抜け落ちていました。これこそ、多くの企業が陥る「サイロ化」の典型です。
オフィスに戻り、頭を抱える佐藤さんに、私は一枚のスライドを見せました。タイトルは「このままでは、一番損をするのは誰か?」です。
私:「佐藤さん、もう一度、視点を変えましょう。これはサポート部門だけのプロジェクトではありません。全社のプロジェクトです。営業も開発も、この船の乗組員です。そして、このままデータの連携ができなければ、一番迷惑を被るのは、我々が大切にしているはずのお客様です」
翌週、私たちは関係部署のキーマンをもう一度集めました。
私:「皆さん、今日は一つだけ、皆さんに想像していただきたいことがあります。お客様は、営業担当者には『こういう機能が欲しい』と言い、サポート担当者には『このエラーが解決できない』と相談し、開発者が作ったマニュアルを読んでいます。お客様にとって、窓口は違えど、相手はすべて『〇〇社』という一つの会社です。しかし、社内ではその情報が全く連携されていない。これは、お客様から見たらどう映るでしょうか?」
高橋部長も渡辺さんも、黙って聞いています。
私:「高橋部長。もし、サポートへの問い合わせ内容から『このお客様は解約寸前だ』というシグナルを検知して、営業担当の方にアラートを飛ばせるとしたらどうでしょう?手遅れになる前に、先回りして手を打てます。逆に、『上位プランのこの機能を頻繁に調べている』というアップセルのチャンスも、データが教えてくれます。無駄なテレアポより、よほど確度の高いアプローチが可能になります」
高橋部長の目が、少し変わりました。
私:「渡辺さん。もし、お客様がマニュアルのどの部分でつまずき、どんなキーワードで検索しているかがデータで分かれば、次の開発でどこを改善すべきか、明確なヒントになると思いませんか?『なんとなく』ではなく、データに基づいて開発の優先順位が決められます。結果的に、問い合わせそのものが減り、皆さんが開発に集中できる時間が増えるはずです」
渡辺さんは、顎に手をやっています。
私:「もちろん、最初から完璧なデータ連携は目指しません。まずは、公開されているマニュアルと、個人情報を完全に除外した問い合わせデータ、そして契約プランの種類だけ。この3つを連携させることから始めませんか?そこで小さな成功事例を作り、『データ連携って、こんなに価値があるのか』と皆さんに実感してもらうこと。そこから始めたいんです」
「敵」を「味方」に変える必要はないのです。彼らを「プロジェクトの当事者」に変える。そのためには、彼らの言語で、彼らのメリットを具体的に語るしかない。全社を巻き込むプロジェクトとは、壮大なビジョンを語ることではなく、地道な「翻訳作業」の連続なのです。
第三幕:「AIは魔法の杖じゃない」― 過剰な期待と、それを乗り越えるための「たとえ話」
数々の壁を乗り越え、ようやくAIプラットフォームの導入が始まりました。PDFマニュアルを読み込ませ、サポートサイトを自動構築し、AIチャットボットが一次対応を開始する。元記事のステップ3と4の段階です。
しかし、ここでまた新たな問題が。今度は、AIへの「過剰な期待」が生んだ、幻滅の波でした。
プロジェクトの進捗会議で、他部署の部長から厳しい声が上がりました。
「君たちが導入したAI、見てみたよ。AIが自動で作ったというマニュアル、まだ日本語がおかしい箇所が散見されるじゃないか。チャットボットにいくつか質問してみたが、見当違いな回答しか返ってこない。これじゃあ、とてもじゃないがお客様には出せない。話が違うじゃないか」
佐藤さんは、必死に説明します。
「申し訳ありません。まだAIの学習とチューニングが不十分で…。ここから私たちが一つひとつレビューして、手直しを加えていく必要があります」
すると、部長は呆れたように言いました。
「なんだ、結局は人の手がかかるのか。AIを入れれば、全部自動でやってくれるんじゃないのか?それじゃあ、高いお金を払って導入した意味がないだろう」
これです。経営層や現場が抱きがちな、「AI = 魔法の杖」という幻想。PDFを放り込むだけで完璧なナレッジベースが完成し、スイッチを入れれば人間のオペレーターが不要になる。そんな都合の良い未来は、残念ながら存在しません。
この幻滅ムードは、プロジェクトの推進力をいとも簡単に奪っていきます。ここで踏ん張れるかどうか。佐藤さんの正念場でした。私は彼女に、一つの「たとえ話」を授けました。
次の会議で、佐藤さんは堂々とこう切り出しました。
「皆さん、今のAIは、まるで『新入社員』のようなものだとお考えください」
会議室が、少しざわめきます。
佐藤さん:「今日配属されたばかりの新入社員に、いきなり完璧な仕事を求める人はいませんよね?最初は間違いも多いし、頓珍漢なことを言うかもしれません。その都度、私たち先輩が『そうじゃない、こうやるんだよ』と根気強く教え、手本を見せる必要があります。AIも同じです。私たちが正しいデータを与え、間違いを修正し続けることで、彼は誰よりも速いスピードで学習し、成長していきます。今は、いわばOJTの真っ最中なんです」
彼女は続けます。
「そして、このプロジェクトの目的は、人を不要にすることではありません。ベテランの皆さんを、単純作業から解放することです。AIという新入社員に、議事録のドラフト作成や、資料集めのような『作業』を任せる。そして、鈴木課長のようなベテランの皆さんには、そのドラフトを見て『ここの表現は、お客様にはこう伝えた方がいい』と判断したり、AIでは解決できない複雑な問題に対応したりという、人でなければできない『価値ある仕事』に集中していただく。AIは私たちの仕事を奪うのではなく、私たちの能力を最大限に引き出してくれる、最高の相棒になるんです」
「AI = 新入社員」。この比喩は、技術に詳しくない人にも、AIとの付き合い方を直感的に理解させます。完璧ではないことへの許容、そして「育てる」という発想への転換。それだけで、会議の空気は「失望」から「期待」へと変わっていきました。
魔法の杖ではない。しかし、共に成長できるパートナーなのだと。
終わりに:地図の裏にある、航海の現実
あの記事で描いた美しいロードマップは、あくまで「地図」です。しかし、実際の航海には、予期せぬ嵐が吹き荒れ、部門という名の暗礁が待ち構えています。
プロジェクトを成功に導くのは、最新のAI技術や精緻な計画書だけではありません。変化を恐れる人の心に寄り添い、異なる立場の人々の言葉を翻訳し、時に巧みな「たとえ話」で未来を指し示す。そんな、人間臭くて泥臭いコミュニケーションこそが、船を前に進める唯一のエンジンなのかもしれません。
もし今、あなたが同じような壁にぶつかっているのなら、思い出してください。あなたの仕事は、システムを導入することだけではない。人の心を変え、組織の文化を育てる、尊い仕事なのだということを。その奮闘の先にこそ、顧客と会社が共に豊かになる未来が待っているのですから。