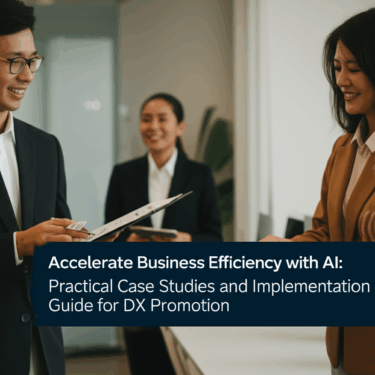「経理は戦略的パートナーへ」その言葉の裏で、私たちは静かに溺れかけていた
先日、「経理のAI革命」という記事を世に出した。ZOZOさんが月次締めを半減させた話、花王さんが年間5万5千時間もの業務を削減した話。キラキラした成功事例を並べ、AIが経理担当者を単純作業から解放し、「戦略的パートナー」へと進化させる未来を描いた。
あの記事に嘘はない。だが、全てでもない。
あの整然としたロードマップや成功事例の裏側には、いつだって、もっとずっと人間臭くて、泥臭い現実が横たわっている。今日は、あの記事では書けなかった、もう一つの物語を話そうと思う。これは、ある中堅メーカーの経理部で、AIという名の黒船を前に、右往左往しながらも必死で未来へ漕ぎ出そうとした人々の、奮闘の記録だ。
「戦略的パートナー」――。その美しい言葉の響きとは裏腹に、現場は日々の請求書の山に埋もれ、静かに溺れかけていた。AIは救いの船か、それとも新たな嵐を呼ぶものか。私たちの、長い長い航海が始まった。
「AIでコスト半分だべ?」社長の期待という名の無茶ぶり
すべての始まりは、いつものように社長の一声だった。
「ミズさん、読んだか、この記事!これからは経理もAIだ。ウチもすぐに導入して、コストを半分にするぞ。明日からだ、明日から!」
血気盛んな五十嵐社長(仮名)が、興奮気味に私に突きつけてきたのは、競合他社がAI導入で劇的なコスト削減に成功したという業界紙の記事だった。その目には「AI=コスト削減の魔法」と書いてある。これが、改革プロジェクトにおける最初の、そして最も厄介な「壁」だ。経営者の過剰な期待。
私は、彼の熱意を冷まさないように、しかし、現実へと引き戻すために、ゆっくりと口を開いた。
「社長、素晴らしいですね。この流れに乗ることは絶対に必要です。ただ、AIは魔法の杖ではねんですよ。例えば、コストを半分にする、というのは最終的な目標として素晴らしいですが、その前に、経理の皆さんが今、何に一番困っているか、聞いてみませんか?」
「困ってること?そりゃ、人が足りなくて毎月残業ばっかりしてることだべ。だからAIで解決するんだろ?」
五十嵐社長は少し苛立ったように言った。彼の頭の中では、AIを導入すれば、人が半分になり、コストも半分になる、という単純な方程式が成り立っている。しかし、現場はそんなに単純じゃない。
私は、あえて具体的な人物の名前を出した。
「経理の佐藤部長、もう30年選手ですよね。それに、入社5年目の鈴木さん。彼女はいつも請求書の締め日前に、目の下にクマを作っています。まずは、鈴木さんの残業時間を、来月は10時間減らす。そこから始めませんか?鈴木さんが定時で帰って、友達とご飯に行けるようになる。それも立派な改革の第一歩です。コスト削減という数字の前に、社員一人の“楽になった”という実感を作ることが、結局は一番の近道なんです」
社長の「大きな絵」を否定しない。しかし、足元にある「小さな石」をまず拾い上げることを提案する。壮大なコスト削減目標を、一人の社員の「働き方の改善」という、手触りのある目標に翻訳してあげること。これが、夢見る経営者と、疲弊する現場との間に橋を架ける、最初の仕事なのだ。
「このやり方で30年やってきたんだ」経理部長の“聖域”との静かな戦い
経営トップの説得が第一関門なら、第二関門は、現場の、特にベテランの「抵抗」だ。経理部というのは、会社の血液である「カネ」を司る心臓部。そこには、長年かけて築き上げられた独自のルールと、それを守ってきた人間の強いプライドが存在する。
経理部長の佐藤さん(仮名・58歳)は、まさにその「聖域」の門番だった。私が挨拶に行くと、彼は分厚いファイルから目を離さずに言った。
「んだ、ミズさんか。社長がまた、AIだのDXだの、騒いでるみたいだなや。悪いけど、ウチのやり方は変えられん。この会社の金の流れは、全部おれの頭に入ってら。それを機械なんかに任せて、もし間違いがあったら、誰が責任取るんだ?」
彼の言葉は、変化への拒絶であり、同時に、彼の仕事に対する矜持(きょうじ)の表れでもあった。この会社のお金の流れを、30年間、たった一人で守り抜いてきたという自負。彼を「古い人間」と断じて敵に回せば、プロジェクトは一歩も進まない。
私は、彼の“聖域”に土足で踏み込むのではなく、弟子入りのつもりで彼の懐に飛び込むことにした。
「佐藤部長、おっしゃる通りです。AIなんて、部長の30年の経験と知識には、到底かないません。だからこそ、お願いがあるんです。部長のそのすごい『技』を、AIに教えてやってくれませんか?言ってみれば、部長の『一番弟子』としてAIを育てたいんです」
佐藤部長は、初めて私の方を見て、訝しげな顔をした。
「おれの…弟子?」
「はい。例えば、『この取引先からの請求書は、いつもここの勘定科目だ』とか、『社長のこの経費は、交際費じゃなくて会議費で落とすのがウチのルールだ』とか。そういう、マニュアルにはない、部長の頭の中にだけある『秘伝のタレ』を、AIに全部覚えさせるんです。そうすれば、AIが作ったたたき台を、部長が最後に『よし』とハンコを押すだけで済むようになります。部長は、もっと大事な、会社の未来のお金のことを考える時間に集中できる。そう思いませんか?」
私は、AIを「仕事を奪う侵略者」ではなく、「彼の技術を継承する弟子」として再定義した。それからの一ヶ月、私は彼の隣に座り、彼が処理する伝票一枚一枚について、「なぜこの科目なんですか?」「なぜこの処理なんですか?」と、ひたすら質問を続けた。
最初は「見てりゃわかるべ」とぶっきらぼうだった彼も、私が彼の知識に純粋な敬意を払い、その「技術」を学ぼうとしていることを理解すると、少しずつ口を開いてくれるようになった。
ある日、彼がぽつりと言った。
「C社からの請求書な、普通なら『消耗品費』で切るけど、これは新しい機械の試作品の部品代だから、『研究開発費』で落とすのが筋なんだ。…まあ、そんなごど、他の誰さもわがんねべけどな」
「それです!部長!それこそが、この会社の『資産』なんですよ!」
データには決して現れない、文脈や背景に基づいた判断。これこそが、ベテランの頭の中に眠る「暗黙知」だ。AI導入の本当の目的は、この暗黙知を「形式知」に変え、組織の資産として未来に残していくことにある。
そのことに彼自身が気づいた時、最も強固だった“聖域”の扉は、静かに、しかし確かに開き始めたのだ。
「また仕事が増える…」若手担当者の“やらされ感”をどう溶かすか
社長が旗を振り、ベテラン部長が少しだけ前向きになった。しかし、実際にAIツールを触り、日々の業務フローを変えていくのは、若手や中堅の担当者たちだ。
このプロジェクトの担当者に任命されたのは、入社5年目の鈴木さん(仮名)だった。彼女は真面目で優秀だが、日々の請求書処理と月次決算に追われ、その瞳には慢性的な疲労と、どこか冷めた諦めの色が浮かんでいた。
「AIですか…。また覚えることが増えるんですね。今でさえ、手一杯なのに…」
彼女の呟きは、多くの現場担当者の本音だろう。「改革」という名のもとに、ただでさえ忙しい日常業務に、新たなタスクが上乗せされる。「やらされ感」。これほどプロジェクトの推進力を削ぐものはない。
元記事で書いた「スモールスタート」は、ここでこそ真価を発揮する。それは技術的なリスクヘッジだけでなく、担当者の心理的なハードルを下げるための、極めて有効な処方箋なのだ。
私は鈴木さんにこう提案した。
「鈴木さん、全部やろうとしなくていいです。まずは、毎月一番たくさん届く、あのA社からの請求書。あれを、AI-OCRで読み取る実験だけ、一緒にやってみませんか?たったそれだけでいいです」
私たちは、無料トライアルできるAI-OCRツールをいくつかピックアップし、A社の請求書をスキャンしてみた。最初はエラーばかりだったが、設定を微調整すると、スキャンした画像から面白いように文字データが会計ソフトに流し込まれていった。いつもなら30分はかかる入力作業が、わずか5分で終わった。
「…え?すごい…。これ、楽になりますね…」
鈴木さんの口から、初めて前向きな言葉が漏れた。この「あ、楽になるかも」という小さな成功体験。これこそが、分厚い氷を溶かす最初の一滴になる。
さらに、私は彼女にこう伝えた。
「どのツールを本格的に使うか、僕が決めるんじゃなくて、鈴木さんが決めてください。毎日使うのは鈴木さんなんだから、一番使いやすいと思うものを、鈴木さんが選ぶべきです。僕はそのサポートをします」
ツール選定の「主導権」を彼女に渡す。ベンダーとの打ち合わせにも同席してもらい、彼女自身の言葉で、現場の要望を伝えてもらう。最初は戸惑っていた彼女も、自分が「やらされる側」から「決める側」になったことで、次第に目に力が宿り始めた。
「このツールは、ウチの会計システムとの連携がスムーズみたいです」「こっちのツールは、サポート体制が手厚いですね」。彼女が自分で情報を集め、比較検討し、最終的に「これで行きたいです」と役員会議で報告した時、彼女はもはや単なる担当者ではなく、このプロジェクトの紛れもない「主役」になっていた。
「やらされ感」を「自分ごと」に変える鍵は、「小さな成功体験」と「主体性の尊重」にある。遠回りのように見えても、担当者自身が自分の意志でハンドルを握る感覚を持てた時、プロジェクトは初めて自律的な推進力を得るのだ。
終わりに:AIは、人の働き方と向き合うための鏡
プロジェクトが始まって一年。経理部の風景は、少しずつ、しかし確実に変わっていった。
AIが請求書の一次処理と仕訳の提案を行い、人間は最終確認と、より高度な分析業務に時間を割くようになった。あれほど残業していた鈴木さんは、最近、定時で帰ってヨガ教室に通い始めたらしい。そして、頑固者だった佐藤部長は、今では若手社員に「このAIの判断は正しいか、お前はどう思う?」と問いかけ、自らの「秘伝のタレ」を伝授する、良き指導者となっている。
元記事で私は、「経理は戦略的パートナーへ」と書いた。それは決して、AIを導入すれば自動的にたどり着ける未来ではない。
AIは、万能の解決策ではない。それは、自分たちの仕事のやり方、コミュニケーションのあり方、そして組織の文化そのものを、良くも悪くも映し出す「鏡」だ。AI導入がうまくいかない時、問題はツールの性能ではなく、鏡に映った我々の姿にある。
ベテランの経験をどう尊重し、未来へ繋ぐか。
日々の業務に追われる担当者の負担を、どうすれば本当に軽くできるか。
部署間の壁を越えて、どうすれば同じ目標に向かって協力できるか。
AI導入プロジェクトとは、結局のところ、こうした極めて人間的な問いと向き合うプロセスそのものなのだ。その泥臭くて面倒な対話から逃げずに、一つ一つ答えを見つけ出そうと奮闘した先にだけ、「戦略的パートナー」という新しい景色が広がっている。
あなたの会社の経理部にも、きっと、そのまばゆい未来へと繋がる、小さな、しかし確かな一歩が隠されているはずだ。