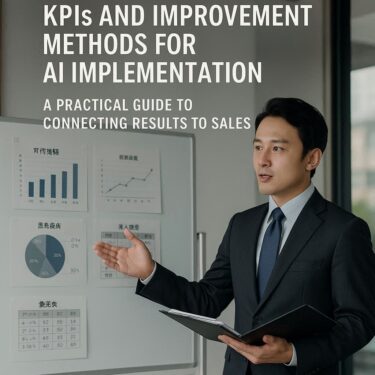「得体の知れないモノは怖い」カミさんの一言から始まった、AIとの本当の付き合い方
この間、シニアのAI活用なんていう小難しいテーマで記事を書かせてもらったんだが、ありがたいことに、色々な人から「面白かったよ」「うちの親にも読ませてみる」なんて声をかけてもらった。まあ、格好いいことばかり書いたが、現実はそんなにスマートなもんじゃない。むしろ、泥臭い失敗の連続だ。
もう怖くない!シニアのためのAI活用ガイド|健康・趣味・暮らしが豊かになる具体例と始め方 「AI(人工知能)は、なんだか難しそうで、自分には関係ない…」「ニュースでよく聞くけど、若い人たちのものなんでしょう?」 もし、あなたが[…]
特に、記事じゃさらっと触れただけの「誤情報・詐欺への懸念」という壁。これが、実は俺たちの世代にとって、一番高く、そして分厚い壁なんじゃないかと、この身をもって痛感させられた出来事があった。今回は、その話をさせてもらおうと思う。主役は、俺じゃない。俺のカミさんだ。
「あんた、そんなもんに大事な話ができるのが?」
始まりは、カミさんが町内会の役員、それも会計の仕事を引き受けてしまったことだった。毎年この時期になると、カミさんは決算報告の書類作りに頭を悩ませる。パソコンなんてものは苦手だし、Excelなんて画面を見るだけでじんましんが出そうだと言う。結局、毎年分厚いノートに手書きで収支をまとめ、回覧板に載せるお知らせも、何度も書き直してはため息をついていた。
その日も、カミさんは食卓に帳簿を広げ、うんうん唸っていた。
「だめだのぉ…、計算が合わねな…。それにこのお知らせの文章、どう書いだらいいべが…」
俺は、ここぞとばかりに口を挟んだ。まさに、AIの出番じゃないか、と。
「おい、そんなのAIに頼めば一発だぞ。『町内会の決算報告、簡潔にまとめて』って言えば、きれいな文章を作ってくれるし、計算だって間違えない」
得意げにスマホを差し出す俺に、カミさんは、信じられないものを見るような、冷ややかな視線を向けた。
「……あんた、本気で言ってるのが?」
「本気も本気だ。こいつは賢いんだぞ」
「違う、そうじゃねくて。そんな得体の知れないもんに、町内会の、みんなから預かってる大事なお金の話を、入力しろって言うのが? 馬鹿なこと言わねでけろ。誰が見てるかわがんねぇのに、個人情報が漏れたらどうすんのや!」
カミさんの剣幕は、俺の想像をはるかに超えていた。それは、単に「操作がわからない」というレベルの話ではなかった。そこには、役員としての「責任感」、そして、未知の技術に対する根源的な「不信感」と「恐怖」が渦巻いていた。
俺はハッとした。これは、昔、工場の生産ラインに新しい品質管理システムを導入しようとした時の光景とそっくりだった。俺たち開発側は「このシステムを使えば、不良品が劇的に減りますよ」とメリットばかりを強調する。だが、現場のリーダーはこう言った。「もし、この機械のせいで不良品が出たら、その責任は誰が取るんだ? 俺たちは、自分の目で見て、手で触って、確かめてきたんだ。画面の数字だけを信じて、お客さんに迷惑はかけられん」
そうだ。彼らが守ろうとしていたのは、古いやり方じゃない。「品質」と「信用」という、仕事の一番大事な部分だった。カミさんが守ろうとしているのも、それとまったく同じ。「町内会の会計」という、みんなからの信用そのものだったんだ。俺は、またしても自分の「正論」を振りかざして、相手の一番大事な部分を踏みつけにするところだった。
思考のカイゼン:目的は「使わせる」ことじゃない
その夜、俺は自分のアプローチを根本から見直した。目的は、カミさんにAIを使わせることじゃない。カミさんが抱えている「決算報告が大変」という問題を、カミさん自身が「安心して」解決できるよう、手伝うことだ。AIは、そのための数ある道具の一つに過ぎない。
工場で新しい機械を導入する時も、いきなり本番のラインには組み込まない。まずは、テスト用のラインで、失敗してもいい材料を使って何度も試運転を繰り返す。そして、オペレーターに機械の「クセ」や「限界」を体感してもらうんだ。「こいつは、こういう指示を出すと、たまにこういうおかしな動きをするな」とか、「この作業は得意だけど、こっちは苦手だな」とか。道具の特性を理解して初めて、人はそれを信頼し、使いこなせるようになる。
カミさんに必要なのも、まさにそれだ。失敗しても誰にも迷惑がかからない、安全な場所での「試運転」。そして、AIという道具の「クセ」と「限界」を知ってもらうこと。俺は、作戦を練り直した。
ステップ1:リスクゼロの「試運転」から始める
翌日、俺はカミさんにこう切り出した。
「なあ、昨日の話なんだが…。会計報告のことは、いったん忘れよう。試しに、こいつに今日の晩ごはんの献立でも考えさせてみねが? 冷蔵庫に、豚肉と大根とネギが余ってただろ」
カミさんは、まだ疑いの目を向けていたが、「晩ごはんの献立」という、あまりにも日常的で、どうでもいいテーマに、少しだけ警戒を解いたようだった。
「…そんなことまで、でぎるのが?」
「できるできる。まあ、遊びだと思ってやってみろよ」
俺はカミさんにスマホを渡し、音声入力のボタンを押してやった。カミさんは、小さな声で、おずおずと話しかけた。
「えーっと…、豚肉と大根とネギで、なにか作れるもんはあるべが?」
すると、AIは即座に、いくつかのレシピを提案した。「豚バラ大根」「豚肉とネギの生姜焼き」「大根と豚肉の味噌汁」…。
「……へぇ」
カミさんの声のトーンが、少しだけ変わった。俺はすかさず畳み掛ける。
「ほらな。別に、町内会の名前も、誰かの名前も、金額も、何も入れなくていいんだ。こういう、誰にも迷惑がかからないことで、まずはこいつがどんなやつなのか、試してみればいいんだよ」
これが、俺の考えた「リスクゼロの試運転」だった。個人情報も金銭も関係ない。AIがトンチンカンな答えを出したとしても、「なんだこいつ、馬鹿だな」と笑って終われる。この「失敗しても大丈夫」という安心感が、新しい道具に触れる第一歩として、何よりも重要なんだ。
ステップ2:「相談役」という新しい関係
それから数日、カミさんは暇を見つけては、AIに色々なことを「相談」するようになった。「庭のトマトの元気がないんだけど、どうしたらいい?」とか、「このシミ、どうやったら落ちる?」とか。まるで、物知りのご近所さんに話しかけるような感覚だったんだろう。
そして、いよいよ会計報告の時期が迫ってきた頃、俺は次のステップに進むことにした。
「なあ、会計報告の文章、いきなりAIに全部書かせるんじゃなくて、まずはカミさんが考えた文章を、こいつに見せてみたらどうだ? 『この言い方、もっと丁寧にならないかな?』って、相談相手として使ってみるんだよ」
この提案が、カミさんの心を大きく動かした。AIを「作成者」として丸投げするのではなく、あくまで自分の作ったものをチェックしてもらう「相談役」と位置づける。そうすることで、作業の主体性はあくまで自分にあると感じられ、恐怖心が和らいだようだった。
カミさんは、自分で考えた回覧板の文章を、AIに音声で読み聞かせた。
「…『会計報告です。ご確認ください』。これじゃ、ちょっとぶっきらぼうだべが?」
AIは、いくつかの代替案を提示した。
- 「町内会の皆様へ。令和〇年度の会計報告がまとまりましたので、ご査収ください」
- 「日頃より町内会活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。さて、…」
- 「皆様からお預かりした大切な会費の使途について、ご報告いたします」
「……なるほどのぉ。こっちのほうが、ずっと丁寧だの」
カミさんは、感心したように頷きながら、AIが提案した言葉を自分のノートに書き写していく。AIに「書かせる」のではなく、AIの提案を参考に、自分で「選んで書く」。この小さな違いが、道具に「使われる」のではなく、道具を「使いこなす」という感覚につながっていく。
ステップ3:「最後はあんたが部長だ」
しかし、試行錯誤はまだ続く。カミさんが決算報告の数字の羅列を入力し、「この収支報告を分かりやすくまとめて」と頼んだ時、AIはとんでもない間違いをしでかした。数字を勝手に丸めたり、存在しない項目を作り出したりしたのだ。
「ほら見ろ! やっぱりこいつは信用ならねぇ! でたらめばっかりじゃないか!」
カミさんは、カンカンになって怒った。だが、俺にとって、これは絶好の機会だった。
「そうなんだよ、カミさん。その通りだ。こいつはな、平気で嘘をつくことがあるんだ。だから、こいつの言うことを全部鵜呑みにしちゃ絶対にいけない」
俺は、工場での経験を話した。
「新しい機械を入れた時もな、画面に出る数字が本当に正しいか、必ずベテランの職人さんが自分の目で見て、手で触って、最後の確認をするんだ。『機械はあくまで補助だ。最後の判断は人間の仕事だ』ってな。それと同じだよ。こいつは、文章作りを手伝ってくれる、ちょっとおっちょこちょいな新入社員みたいなもんだ。最終的に、その内容が正しいかハンコを押すのは、会計部長のカミさん、あんただ。あんたが、最後の砦なんだよ」
この「部長と部下」の例えが、カミさんにはしっくりきたらしい。それ以来、カミさんのAIとの付き合い方は変わった。AIが出してきた答えを、疑いの目でじっくりと吟味するようになった。「この表現はいいけど、この数字は元の帳簿と違うな」と、赤ペンで修正を入れる。まるで、頼りない部下の報告書をチェックする、ベテランの上司のようだった。
数日後、カミさんは見事な決算報告書を完成させた。それは、AIの力を借りながらも、隅々までカミさんの目が光った、手作りの温かみと正確さを兼ね備えたものだった。そして何より、その顔には、大きな仕事をやり遂げたという、晴れやかな自信が満ちあふれていた。
この一件で、俺は確信した。俺たちシニア世代が新しい技術と付き合う上で必要なのは、「何でもやってくれる魔法の杖」じゃない。少し頼りないけど、自分の仕事をちょっとだけ楽にしてくれる「相棒」や「部下」なんだ。そして、その相棒を使いこなすためには、そいつの長所も短所も、得意なことも苦手なことも、全部ひっくるめて理解してやること。最終的な責任は、道具じゃなく、使う人間である自分が持つという、当たり前の覚悟を持つこと。
それは結局、何十年も物作りの現場で叩き込まれてきた、人と道具との付き合い方の原点と、何も変わらないんだよな。