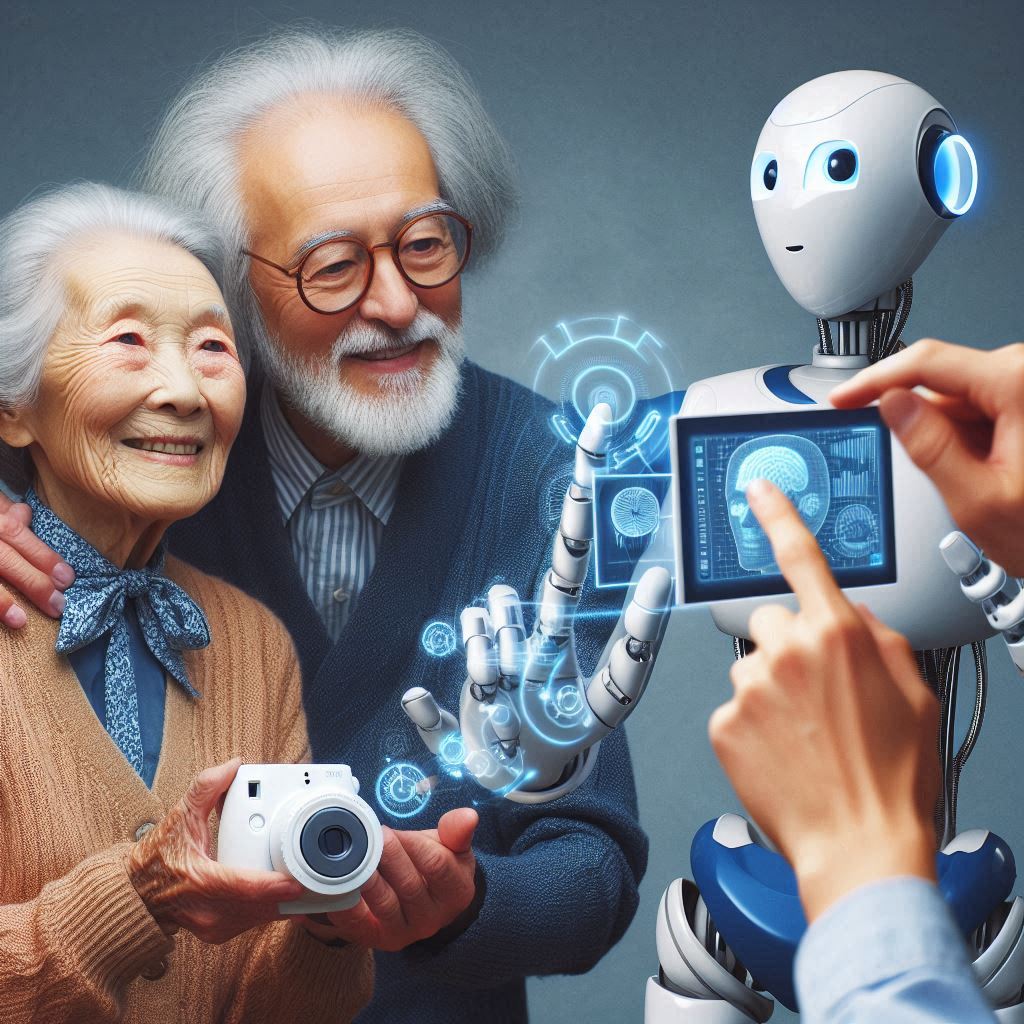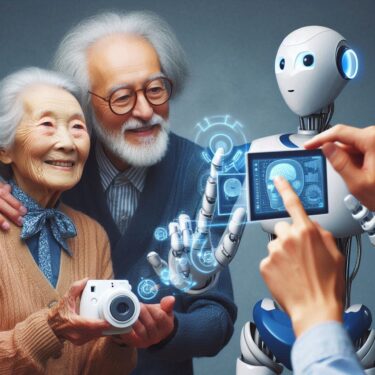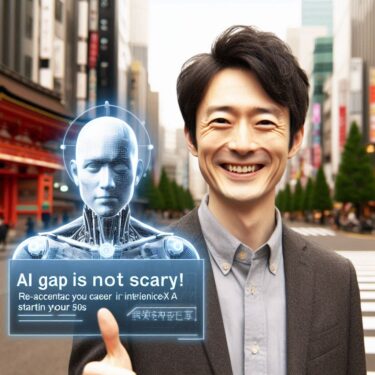「回覧板が回ってこない!」ご近所の小さなSOSから始まった、私のChatGPT奮闘記
先日、「60代から始めるChatGPT活用術」という記事を書かせていただきました。おかげさまで、同世代の方々から「これなら俺にもできそうだ」「早速、孫との話のタネにしてみたよ」なんて嬉しい声をもらい、少しは世の中のお役に立てたかなと、胸をなでおろしているところです。
ですが、正直に白状しますと、あの記事は、そんなに格好のいいものじゃありません。あれは、私自身がこの一年、プライベートで繰り広げてきた、数々の試行錯誤と、ちょっぴり恥ずかしい失敗の記録でもあるのです。
私は長年、物造りの現場で「どうすればもっと効率よく、いいものが作れるか」ということばかり考えてきました。そのせいか、日常生活でもつい「この手間、なんとかならないか」「もっと良いやり方があるはずだ」なんて、改善点を探してしまう癖がついています。
そんな私が、ChatGPTという新しい「道具」を手に入れた。これは面白いことになりそうだ、と。まずは、一番身近な「現場」である我が家やご近所を舞台に、この新しい道具がどこまで通用するのか、壮大な(?)実験を始めてみることにしたのです。
これは、あの記事には書ききれなかった、私のプライベートな奮闘の記録。最新AIと、アナログな人間関係の間で板挟みになった、一人の62歳の男の、汗と笑いの物語です。
最初の壁は、我が家の「絶対的権力者」。妻の一喝から始まった
新しい道具を手に入れたら、まず試してみたくなるのが人情というもの。仕事でも、新しい機械を導入したら、まずは一番簡単な作業から試運転するものです。そこで私も、あの記事でも紹介した「夕食の献立相談」を、我が家で実践してみることにしました。
キッチンで夕飯の支度を始めた妻に、私は得意げにスマホをかざして言いました。
「なあ、今日はChatGPTに献立を考えてもらおう。冷蔵庫にある豚肉とキャベツで、何か美味しいものは作れないかって聞いてみるから」
ピタリ、と妻の包丁を握る手が止まりました。そして、ゆっくりとこちらを振り返ると、静かに、しかし有無を言わせぬ迫力でこう言ったのです。
「あのさ、豚肉とキャベGだば、わだしさ聞けばいいんでねが?何十年も作てるんだもの。そだ、よぐ分がんね機械さ聞ぐなんて、なんだか味気ないごどだべした」
……完敗でした。
頭をガツンと殴られたような衝撃でした。私は「効率化」という物差しだけで物事を見ていたのです。「AIが考えた最適なレシピ」という「正解」を提示すれば、妻も喜ぶだろうと。しかし、彼女にとっては、冷蔵庫の中身を見ながら「今日は何にしようかしら」と考える時間そのものが、日々の営みであり、楽しみだったのかもしれない。それを私は、土足で踏みにじろうとしていたのです。
これは、昔、現場で何度も経験した失敗と同じでした。作業者の気持ちを考えず、データ上の「正しさ」だけで新しいやり方を押し付けて、猛反発を食らったあの頃の苦い記憶が蘇ります。
どんなに優れた道具も、使う相手の「心」や「習慣」を無視しては、ただの押し付けになる。
この一件で、私はAIとの付き合い方の、最も重要な第一歩を学びました。これは「説得」の問題ではない。「共感」から始めなければ、何も始まらないのだ、と。
「回覧板が止まるんだず…」町内会長のSOSと、AIの“惜しい”回答
我が家での失敗に懲りた私は、次に「本当に困っている人」の役に立とうと決めました。そんな時、公民館でばったり会ったのが、古くからの友人で、町内会長を務める鈴木さんでした。彼は、浮かない顔で私にこうこぼしました。
「いやあ、参ったず。回覧板が、いっつも途中で止まっちまてなや。特に一人暮らしの斎藤さんの家で止まることが多くて、電話すっと『ああ、ごめんごめん、忘れてだ』って。みんな忙しいのは分がっども、これでは連絡事項も伝わらんし、困ったもんだ…」
まさに、私が仕事で向き合ってきた「流れの滞留(ボトルネック)」問題そのものです。血が騒がないわけがありません。
「鈴木さん、その問題、ちょっとAIに相談してみないか?」
私は、今度は慎重に切り出しました。妻の時のように「答え」を提示するのではなく、「一緒に相談する」というスタンスで。公民館の隅にあるテーブルで、私はスマホを取り出し、鈴木さんと一緒に画面を覗き込みながら、ChatGPTに語りかけるように入力しました。
あなたはベテランの町内会長です。紙の回覧板が特定のお宅で滞留してしまう問題に悩んでいます。スマホを持っていない高齢者もいるという前提で、誰でも簡単にできて、費用もかからない解決策のアイデアを5つ提案してください。
しばらくすると、AIは実にそれらしい答えを返してきました。
- 回覧板にチェックシートを添付し、受け取った日時を記入してもらう
- 各班に「回覧板担当」を置き、その人が責任を持って回収・配布する
- 回覧板を2部作成し、左右両方から回す
- ポストに「回覧板 確認!」と書いたマグネットを貼ってもらう
- 月一の定例会で、回覧板の重要性を改めて周知徹底する
鈴木さんは腕を組んで唸っています。
「うーん、なるほどなや…。んでも、チェックシートだば、結局書くの忘れっだべ。担当ば決めるのも、押し付け合いになるのが目に見えでるし…」
AIの答えは、どれも正論です。しかし、どこか「机上の空論」感が否めない。現実の町内会で暮らす人々の「面倒くさい」という感情や、人間関係の機微が抜け落ちているのです。AIが出してきたのは、あくまで一般的な「正解」の選択肢。これを、私たちの町内の「現実」に合わせて使いこなすのは、人間の知恵の見せ所です。
そこで私は、仕事でやっていた「なぜなぜ分析」を応用してみることにしました。
「鈴木さん、そもそも、なんで斎藤さんは回覧板を渡し忘れちゃうんだろう?」
「さあな…日中はデイサービスさ行ってるし、帰ってくると疲れで、玄関に置いたまま忘れっちまうんでねがな」
「じゃあ、斎藤さんが次の家に『渡した』ことだけ、簡単に誰かに伝えられる方法があればいいんだな?」
「そだなや。そうすれば、わだしも『斎藤さんは渡したはずなのに、なんで次の家さ届がねんだ?』って、すぐに気づげるしな」
見えてきました。問題の核心は「回覧板そのもの」ではなく、「回覧板が渡されたという事実の伝達」にありました。
この気づきを元に、私はもう一度AIに問いかけました。
ありがとう。とても参考になります。その中で、特に「誰が誰にいつ渡したか」という情報伝達を、スマホを使わずに、アナログで、かつポストに入れるだけで完結できるような、もっと具体的な工夫はありませんか?例えば、小さなカードを使うような方法です。
この追加の質問が、決定打となりました。AIの回答をヒントに、私たちが考え出したのが「回覧板お渡しメモ」作戦です。
やり方は至ってシンプル。回覧板に、名刺サイズのカードを数枚クリップで留めておくだけ。回覧板を次の人のポストに入れたら、そのカードに「〇月〇日、〇〇(自分の名前)より」とだけ書いて、自分の家のポストの分かりやすい場所にペタッと貼っておくのです。
これなら、回覧板が自分の手元を離れたことが一目で「見える化」されます。そして町内会長の鈴木さんは、散歩がてら各家のポストを見て回るだけで、「お、斎藤さんとこのカードが貼られたな。ちゃんと次に渡したんだな」と確認できるのです。
「おお!これならでぎっかもしんねなや!」鈴木さんの顔が、ぱあっと明るくなりました。「電話する手間も省げるし、誰のせいで止まってるかなんて、波風立てずに確認でぎる。これはいい!」
AIは、万能の魔法使いではありませんでした。しかし、私たちの思考を整理し、アイデアの「種」をくれる、優秀な壁打ち相手になってくれたのです。その種を、自分たちの現実に合わせて育て、花を咲かせるのは、やはり私たちの役目。この一連のやり取りを通じて、私はAIとの「協業」のコツを掴んだ気がしました。
「旅行の計画?AIなんて味気ない」を覆した、たった一つの工夫
最後の実験の舞台は、私の趣味である写真サークルでした。気の合う仲間4人で、秋になったら鳥海山に紅葉の写真を撮りに行こうという話で盛り上がっていたのですが、例によって計画が全く進みません。
「宿は温泉がいいな」「いや、俺は飯がうまい方がいい」「どうせなら羽黒山にも寄りたい」「そんな時間ねべした」
みんな言いたい放題で、議論は発散するばかり。そこで私は、満を持して提案しました。
「なあ、みんなの希望を全部AIに伝えて、旅行のたたき台を作らせてみないか?ゼロから考えるより、話が早いはずだ」
返ってきたのは、予想通りの冷ややかな反応でした。
「なんだよ、AIだか何だか知んねけど、そんなもんに決められた旅なんて、ちっとも面白ぐねべした」
「そうだなや。ああでもない、こうでもないって、みんなで言いながら決めるのが楽しいんでねが」
また同じ壁です。私は彼らの「楽しみ」を奪おうとしていたのです。妻の時と同じ轍を踏むわけにはいきません。私は少し考え、ある工夫をすることにしました。AIを「計画の決定者」ではなく、「議論を盛り上げるための、おせっかいなアシスタント」として登場させることにしたのです。
集まった仲間の前で、私はスマホを取り出し、あえて音声入力で、みんなに聞こえるように話しかけました。
「なあ、ChatGPT。俺たち、写真好きの60代のじいさん4人なんだ。11月の初めに、一泊二日で鳥海山と羽黒山の紅葉を撮りに行きたい。車で行く。条件は三つだ。一つ、温泉があって、うまい地酒が飲める宿。二つ、夕日と星空が撮れるスポットが入っていること。三つ、昼飯は絶対にうまい蕎麦屋だ。このわがままな条件で、最高の旅行プランを考えてくれや!」
まるで、旅仲間の一人に話しかけるような口調で。
すると、どうでしょう。スマホの画面に、具体的なモデルコース、宿の候補(ご丁寧に口コミ評価付き)、おすすめの蕎麦屋のリストまでが、ずらずらと表示されたのです。
それまで腕を組んで見ていた仲間たちが、わらわらとスマホの周りに集まってきました。
「ほう、この『湯野浜温泉』の宿、料理の評判いいなや」
「待て待て、このコースだと、鳥海山の夕日に間に合わねんでねが?こっちの道を回った方がいいべ」
「この蕎麦屋、知ってるぞ!うまいけど、昼はめちゃくちゃ混むから、開店と同時に行がねどダメだず」
空気が一変しました。AIが出してきた「たたき台」があることで、漠然とした願望の言い合いだった会話が、具体的な計画を練り上げるための、建設的な議論へと変わったのです。AIは彼らの楽しみを奪うどころか、面倒な情報収集を肩代わりし、私たちが本当に楽しむべき「創造的な対話」の時間を生み出してくれました。
結局、その日はAIのプランを元に大いに盛り上がり、最高の旅行計画が完成しました。
おわりに
あの記事で紹介したAIの活用法は、こうした私の日々の小さな「実験」の中から生まれてきたものです。
AIは、決して私たちの生活から「考える楽しみ」や「人との繋がり」を奪うものではありません。むしろ、面倒なことや、一人では行き詰まってしまうことを手伝ってもらうことで、私たちはもっと人間らしい、創造的な活動に時間を使えるようになります。
大切なのは、AIを「答えをくれる機械」だと思うのではなく、「一緒に考えてくれる相棒」として付き合うこと。そして、AIが出してきた一般論を、目の前の人の顔を思い浮かべながら、血の通ったアイデアに作り変えていく「ひと手間」を惜しまないことです。
それは、私が長年、物造りの現場で大切にしてきた「標準化された手順(マニュアル)」と、現場で働く一人ひとりの「知恵と工夫(カイゼン)」の関係に、とてもよく似ています。
もし、あなたの周りに何か「困ったこと」があるのなら。まずは、AIという新しい相棒に、こう語りかけるところから始めてみてはいかがでしょうか。
「なあ、ちょっと知恵を貸してくれや」と。
きっと彼は、あなたの想像を超える面白いアイデアの「種」を、ポケットから取り出してくれるはずですから。