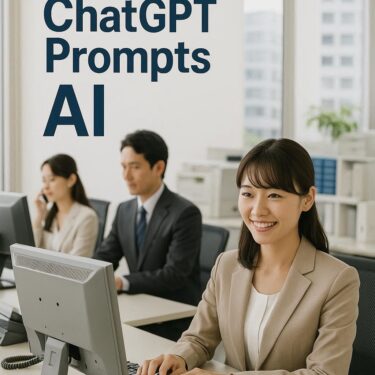「予算がない」は言い訳か? 中小企業のAI導入、本当の壁はお金じゃなかった話
前回の「AIoT導入の裏側」の記事には、本当に多くの反響をいただいた。特に、「ウチの会社のことかと思った」「現場の抵抗、痛いほどわかる」といった共感の声が多かったのは、私にとっても大きな発見だった。やはり、どれだけ技術が進歩しても、物事を動かすのはいつだって「人」の感情なのだと、改めて痛感させられた次第だ。
さて、今日はその続編だ。今回は特に、日本経済の屋台骨を支える、社員数100名前後の、志ある中小企業に焦点を当てたい。
私が日々お会いする中小企業の社長さんたちは、皆、口を揃えてこう言う。「ミズさん、AIだのIoTだの、重要性はわかってる。でもね、ウチにはそんな大金を投資する余裕はないんだよ」。
「予算がない」「人がいない」「時間がない」。
この「ないない尽くし」は、新しい挑戦を諦めるための、魔法の言い訳になってはいないだろうか。
もちろん、予算が潤沢でないのは事実だろう。しかし、私が数々の中小企業の現場で見てきた「本当の壁」は、実は「お金」そのものではなかった。それは、もっと根深く、組織の隅々にまで染み付いた、目に見えない「思考の癖」や「組織の文化」だったのだ。
今回は、限られた予算の中で、AI導入という高い壁に挑んだ、ある食品加工工場の物語をしよう。華々しい成功事例とはほど遠い、地味で、手作り感に溢れた、しかし確かな一歩を踏み出した彼らの奮闘の記録だ。
第一章:「完璧なデータ」という幻を追い求める人々
その会社の挑戦は、「製品の品質検査をAIで自動化したい」という、よくあるテーマから始まった。主に扱っているのは、焼き菓子。これまでは、焼き色や形の崩れを、ベテランのパート従業員、鈴木さん(62歳)の「神の目」に頼りきっていた。しかし、鈴木さんも数年後には引退を考えている。技術継承は待ったなしの課題だった。
プロジェクトリーダーに任命されたのは、入社5年目の若手社員、田中くん(27歳)。少しITに詳しい彼は、意欲満々だったが、すぐに壁にぶち当たった。
「ミズさん、困りました。AIで画像認識をやるには、照明条件が一定で、カメラの解像度も高くて、ピントも常に合っているような、完璧な画像データが最低でも数万枚は必要だと本に書いてありました。ウチの工場はそんな環境じゃないし、そもそも過去のデータも整理されていません。このままでは、プロジェクトは始められません…」
彼の言うことは、教科書的には正しい。しかし、この「教科書通りの正しさ」こそが、多くの中小企業のDXプロジェクトを頓挫させる「完璧主義の病」なのだ。完璧な環境が整うのを待っていたら、日は暮れ、会社は傾いてしまう。
経営層からは「田中くん、例の件どうなってる?」と催促され、現場からは「どうせ無理でしょ」と冷ややかな視線が注がれる。彼は完全に「分析麻痺(Analysis Paralysis)」に陥っていた。
私は、頭を抱える田中くんの隣で、こう言った。
「田中くん、100点満点のAIを作るのは一旦やめよう。僕らが目指すのは、『60点でも鈴木さんを助けられるAI』だ。どうかな?」
「60点、ですか…?」
「そう。完璧な判定はできなくてもいい。例えば、誰が見ても明らかに『これは焦げすぎ』『形が崩れすぎ』っていう、分かりやすい不良品だけをAIに弾かせる。それだけでも、鈴木さんが一日中、神経をすり減らしてベルトコンベアを睨み続ける負担を、半分にはできるんじゃないかな?」
目標のハードルを、ぐっと下げる。そして、こう続けた。
「高価な産業用カメラを買うのは、その後でいい。まずはさ、みんなが持ってるそのスマホで、不良品の写真を撮りまくるところから始めてみない?」
「えっ、スマホですか!?そんなバラバラな画質や角度で撮った写真、データとして使えないんじゃ…」
「使えるかどうかは、やってみないと分からないじゃないか。大事なのは、まず一歩踏み出すこと。これは宝探しみたいなもんだよ。ガラクタの中から、何か光るものが見つかるかもしれない」
私はそのまま製造ラインへ行き、検査を担当していた鈴木さんに声をかけた。
「鈴木さん、お疲れ様です。ちょっと教えてほしいんですが、こんげな焼き色のやつは、もうダメなんだっけ?」
(鈴木さん、お疲れ様です。ちょっと教えてほしいのですが、こんな焼き色のやつは、もうダメなんですか?)
「あらまあ、ミズさん。そだな真っ黒なのは、お客さんに出せねって。わだすの目をごまがすのは無理だでの」
(あらまあ、ミズさん。そんな真っ黒なのは、お客さんに出せませんよ。私の目をごまかすのは無理ですからね)
「さすがですね!じゃあ、この鈴木さんの『神の目』を、このスマホの中のAIにミズさんとして教えてやってもらえませんか?鈴木さんが『これはダメだ』って思うやつを見つけたら、このスマホでパシャっと写真を撮ってほしいんです」
「わだすが、AIのミズさん?」
鈴木さんの目が、少し輝いた。彼女を単なる作業員ではなく、「AIのミズさん」としてプロジェクトの主役になってもらう。これが、現場を巻き込むための重要なスイッチだ。
数日後、田中くんと鈴木さんを中心に、パートさんたちが休憩時間などに面白がって撮ってくれた、数百枚の不揃いな画像データが集まった。我々は、Googleが提供している「Teachable Machine」のような、無料で使えるAIの学習ツールにそれらの画像を放り込んでみた。
するとどうだろう。驚いたことに、7割以上の精度で、明らかな不良品を識別できたのだ。
「す、すごい…スマホの写真でも、ここまでできるなんて…」
田中くんが、呆然とつぶやいた。この瞬間、「完璧なデータがなければ始まらない」という彼の呪いは解けた。大切なのは、高価な設備投資ではない。今あるもので、どう工夫して最初の一歩を踏み出すか。その知恵と勇気なのだ。
第二章:「部署の壁」という名の城と、たった一杯のコーヒー
「スマホAI」の小さな成功で、プロジェクトは一歩前進した。しかし、次に立ちはだかったのは、もっと厄介で、根深い壁だった。それは、「部署間の壁」という、社内にそびえ立つ見えない城壁だ。
この会社も例外ではなかった。
製造部は「とにかく計画通りの数を生産すること」が至上命題。
品質管理部は「不良品の流出を一件でも減らすこと」が正義。
設備保全部は「機械を止めずに動かし続けること」が仕事。
それぞれの部署が、それぞれのKPI(重要業績評価指標)だけを追いかけ、お互いを敵視している。
AIで不良品の原因を特定しようにも、製造部は「そんなデータ取るためにラインを止めるなんて冗談じゃない!」と協力しない。品質管理部は「そもそも製造の連中が無理な生産をするから不良が出るんだ!」と文句を言う。設備保全部は「ウチは壊れたら直すのが仕事。予防とか言われても、人が足りないんだ」とそっぽを向く。
公式な会議を開けば、始まるのは犯人探しと責任のなすりつけ合いだ。こんな状態では、どんな素晴らしい技術も宝の持ち腐れになってしまう。
私は、この不毛な会議に見切りをつけた。そして、ある作戦を実行することにした。名付けて「缶コーヒー一本釣り作戦」。
工場の片隅にある、古びた自販機前の休憩スペース。私は、各部署のキーマン…課長クラスや、現場で人望の厚いリーダーを、一人、また一人とそこに呼び出した。議題もアジェンダもない。ただ、缶コーヒーを片手に雑談をするだけだ。
「〇〇課長、お疲れ様です。いやあ、最近暑いですね。そういえば、娘さんの受験、どうなりました?」
仕事の話は後回し。まずは、くだらない世間話で心のガードを解いてもらう。そして、ポツリと本題を切り出す。
「実は、最近ライバルのB社が、ウチと同じような製品で、品質を上げてきたみたいなんですよね…。このままだと、ちょっとマズいかもしれませんね」
部署間の対立構造を煽るのではなく、会社全体が直面している「共通の敵」の存在を、それとなく匂わせるのだ。内輪揉めをしている場合ではない、という空気を作る。
次に、別の部署のキーマンを呼び出し、同じように雑談から入る。
「いやー、この前、製造の△△さんがボヤいてましたよ。『最近、機械の調子が悪くて、不良ばっかり出しちまう。品管の連中に申し訳ない』って。みんな、本当は良くしたいと思ってるんですよね」
直接対決させると喧嘩になるが、第三者から「実は相手も悩んでいる」と聞かされると、少し見方が変わるものだ。
そして、仕上げに、各部署のリーダーが偶然居合わせるタイミングを見計らって、休憩スペースでこう切り出した。
「もしですよ、もし、製造部がほんの少しだけ機械のデータを取ることに協力してくれたら、保全部は故障する前に部品を交換できる。そうすれば、製造部が一番嫌がる『突然のライン停止』がなくなって、生産計画も守れる。そうなれば、品管が頭を抱える『突発的な不良品の大量発生』も防げる。…これって、もしかしてみんなが得しませんか?」
誰か一人が得をするのではなく、「全員が勝てるゲーム」のシナリオを提示する。最初は訝しげだった彼らの表情が、少しずつ変わっていくのが分かった。
「まあ…ラインを止めずにデータが取れるなら、考えてやってもいいが…」
製造部の課長が、ポツリとつぶやいた。
強固だった城壁に、ほんの小さな穴が空いた瞬間だった。公式な会議室で振りかざされる正論よりも、休憩スペースで交わされる本音と、たった一杯の缶コーヒーが、人の心を動かすことがある。組織のサイロ化を溶かすのは、そんな地道なコミュニケーションの積み重ねなのだ。
第三章:「失敗は許されない」という呪いを解く方法
多くの人々の協力を得て、ついに焼き菓子の不良品を検知する簡易的なAIシステムが完成し、現場に導入された。しかし、新たな問題が発生した。
誰も、そのシステムを使おうとしないのだ。
理由は単純明快だった。「もし、AIが見逃した不良品がお客様の手に渡ったら、誰が責任を取るんだ?」「もし、AIが良品を不良品だと間違って判断したら、その分のロスはどうするんだ?」。
特に、真面目で責任感の強い現場リーダーほど、この新しい道具を使うことに躊躇した。中小企業にありがちな、「一度の失敗も許されない」という減点主義の文化が、最後の最後で人々の行動を縛り付けていたのだ。
この「失敗への恐怖」という呪いを解かない限り、プロジェクトは成功しない。私は社長に直談判した。
「社長、お願いがあります。次の朝礼で、全社員にこう宣言していただけませんか。『このAIプロジェクトの目的は、不良品をゼロにすることではない。AIの使い方を学び、まずはやってみるという文化を作ることが目的だ。だから、AIが間違うのは当たり前。どんどん失敗して、そこから学んでくれたまえ。その責任は、すべて社長である私が取る!』と」
社長は最初、少し戸惑っていたが、私の意図を理解し、力強く頷いてくれた。
翌日の朝礼。社長の力強い宣言は、社員たちの心に深く響いた。「失敗してもいいんだ」。その言葉が、現場の空気を一変させた。
さらに、私たちは事務所の壁に「やってみっかボード」(庄内弁で「やってみようか」の意)と名付けたホワイトボードを設置した。
「AIでこんなこと試してみた!」
「こんな不良品、見つけられたよ!」
「AIが良品と不良品を間違えた!(笑)次から気をつけよう!」
成功も失敗も、すべてをオープンに共有し、笑い飛ばせる場所を作ったのだ。小さな挑戦をした社員がいれば、すかさず朝礼で「〇〇さんのチャレンジ、素晴らしい!」と社長自ら褒め称えた。結果の良し悪しではない。「挑戦した」という行動そのものを評価する文化を、意図的に作り上げていった。
すると、どうだろう。現場の従業員たちが、まるでゲームのようにAIシステムを使い始めたのだ。「今日はAIに勝てるか!」「こんなパターンはAIも騙されるだろう」と、楽しみながらデータを蓄積し、AIの精度を自分たちで高めていくようになった。
技術を導入するとは、突き詰めれば、組織の文化をデザインすることなのだと、私はこの時、改めて学んだ。
終わりに:AIは、組織文化を変えるための「触媒」
結局、この会社の物語でも、AIの高度なアルゴリズムの話はほとんど出てこなかった。
予算がない中小企業の挑戦を阻む本当の壁。それは、「完璧主義の罠」「部署間の対立」、そして「失敗への恐怖」という、組織に根付いた文化そのものだった。
これらの壁を乗り越える鍵は、大金をつぎ込むことではない。
今あるもので工夫して「不完全な一歩」を踏み出す勇気。
部署の垣根を越え、本音で語り合うための「一杯のコーヒー」。
そして、失敗を許容し、挑戦を称える「心理的安全性」。
AIoTは、単に工場の生産性を上げるための魔法の杖ではない。それは、会社に染み付いた古い常識や思考の癖を壊し、人々が前向きに挑戦できる文化を育むための、強力な「触媒」なのだ。
もし、あなたが「ウチには予算がないから」と一歩を踏み出せずにいるのなら、一度立ち止まって考えてみてほしい。あなたの会社が本当に変えるべきは、帳簿の数字だろうか。それとも、社員一人ひとりの心の中にある、見えない壁なのだろうか。