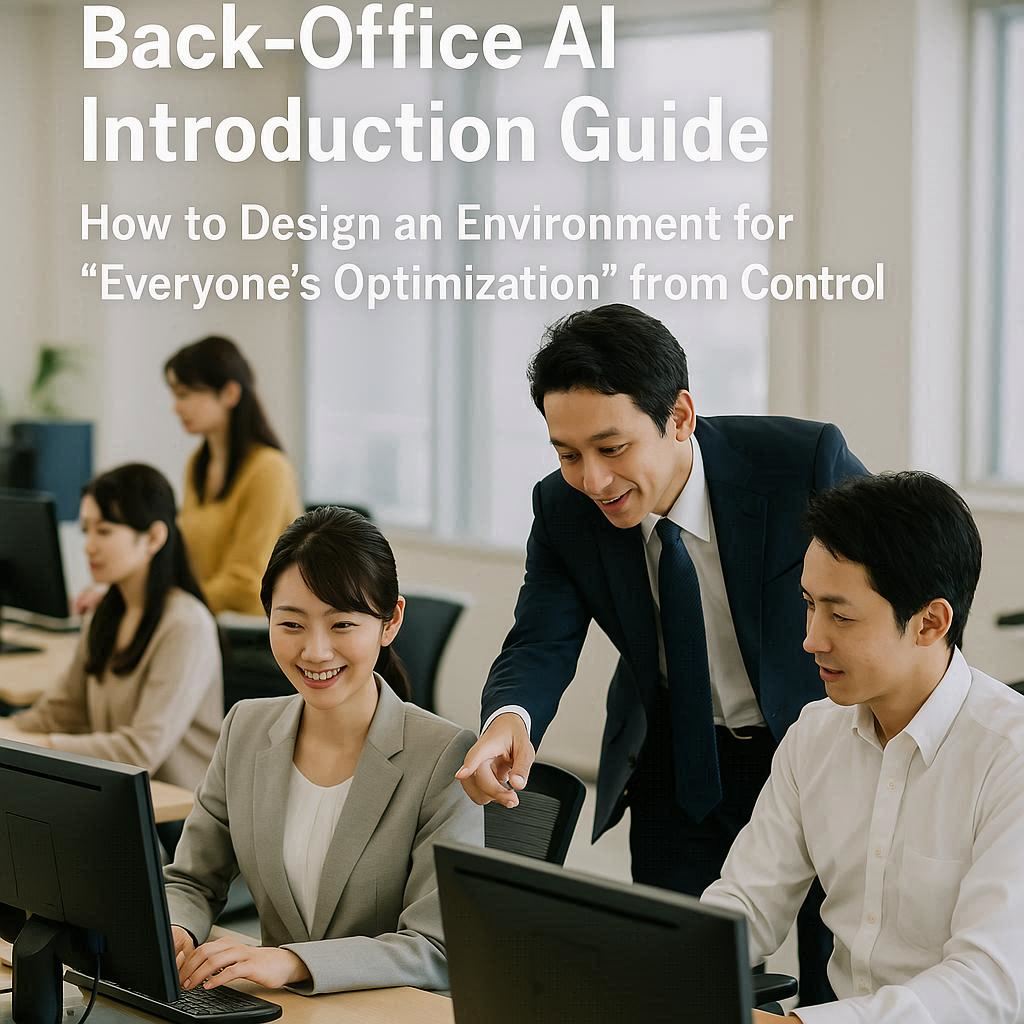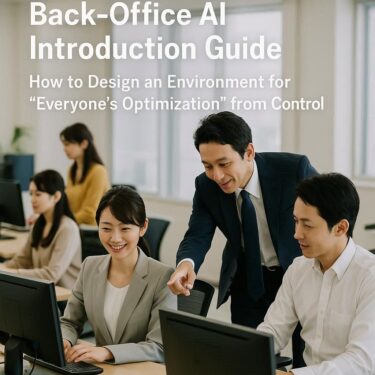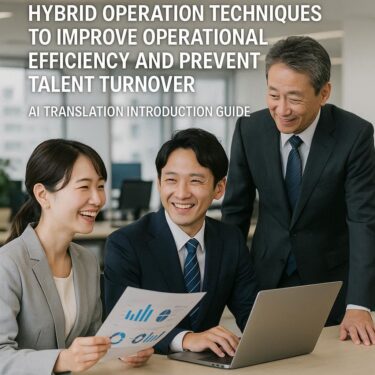「バックオフィスAI導入は“正論”だけでは進まない」――現場の“心の壁”を溶かした裏話
Webで公開しているノウハウ記事には、どうしても書けないことがあります。それは、成功事例の裏側で繰り広げられる、生々しい人間ドラマです。先日公開した『バックオフィスAI導入ガイド』も、フレームワークや導入ステップを綺麗にまとめた、いわば「模範解答」。しかし、実際の現場は、そんな地図通りに進むほど単純ではありません。
バックオフィスAI導入ガイド|統制から「全員最適」の環境を設計する方法 「またこの作業か…」「法改正の対応で手一杯だ…」経理、人事、総務といったバックオフィス部門で働く多くの方が、慢性的な人手不足、繰り返される定型業務、そして繁忙期[…]
今回は、あの記事の元になった、ある中堅メーカーでのAI導入プロジェクトの裏話を少しだけお話ししようと思います。そこには、教科書には載っていない、人の心を動かし、組織を本気で変えるための泥臭いヒントが隠されています。主役は、AI導入に燃える30代の若き担当者と、変化を嫌うベテラン課長。そして、その間で奮闘した私の、ちょっとした苦労話です。
第1章:最初の壁――「便利になります!」が空回りするとき
プロジェクトが発足し、私が初めてその会社のバックオフィス部門に足を踏み入れた時のことを、今でも鮮明に覚えています。担当者に任命された佐藤さん(仮名・30代女性)は、目をキラキラさせながら私に語りかけました。
「すごいですよね、生成AIって! これで、みんなが毎月うんざりしている単純作業から解放されるんです。もっと創造的で、本来やるべき仕事に時間を使えるようになるんですよ!」
彼女の熱意は本物でした。しかし、その熱量とは裏腹に、部署内を流れる空気はひどく冷ややかでした。特に、経理一筋30年、この部署の「主」とも言える鈴木課長(仮名・50代男性)の反応は、その空気を象徴していました。
「んだって、新しいごど覚えんのがまず面倒だべ。今までのやり方で、今まで何も問題ながったんださげ。そだなハイカラなもんで、逆に仕事が増えんのがオチだでの。」
庄内弁の朴訥とした響きとは裏腹に、その言葉には「余計なことをするな」という強い拒絶が込められていました。
これこそ、多くの改革プロジェクトが最初にぶつかる壁です。記事で紹介した「2:6:2の法則」で言えば、佐藤さんは革新層の「2割」。しかし、彼女の正論と熱意は、抵抗層である鈴木課長や、様子見をしている中間層の6割にとっては、「今の平穏を乱す厄介ごと」にしか聞こえないのです。
ここで私が最初にやったことは、「AIの素晴らしさを説く」ことではありませんでした。むしろその逆です。佐藤さんには少し待ってもらい、私は鈴木課長の席の隣に椅子を持っていき、こう切り出しました。
「課長、おっしゃる通りだと思います。そもそも、今のやり方で何十年も会社を支えてこられたわけですから、それを変えるなんて、普通は考えませんよね。長年やってこられた中で、『このやり方だけは変えちゃいけない』っていう“勘所”みたいなものって、どんなところなんですか?」
私は、彼の経験そのものに興味がある、という姿勢を徹底しました。AIの話は一切しません。ただひたすら、彼が築き上げてきた仕事の「こだわり」や「苦労」を聞き出すことに徹したのです。一時間ほど話を聞いた後、私はようやく本題に触れました。
「ありがとうございます。よく分かりました。…もし、課長がこれまで培ってこられた、そのすごいノウハウや判断基準を、そっくりそのままAIに教え込んで、課長の分身みたいなものを作れるとしたら、どうでしょう? 課長が楽をするための、言わば“究極の道具”です。今のやり方を否定するんじゃなくて、課長の経験を会社の財産としてシステムに残す、という考え方です。」
彼の眉が、ほんの少しだけピクリと動きました。人を動かすのは、正論の力ではありません。相手のプライドを尊重し、相手の文脈で物事を語ること。AI導入は「新しいものへの挑戦」ではなく、「あなたの経験を未来に残すための作業」なのだと、意味合いを翻訳してあげることが、最初の扉を開ける鍵だったのです。
第2章:「業務の洗い出し」という名の“宝探し”
次のステップは、記事で言うところの「業務の洗い出し」です。しかし、これもまた一筋縄ではいきませんでした。
佐藤さんが「皆さんの業務効率化のために、日々の作業内容と時間をこのシートに記入してください」と真面目に依頼した結果、提出されたシートはほぼ白紙。現場からは「なんでそんなことまで報告しなきゃいけないの」「サボってないか監視されてるみたいで気分が悪い」という不満が噴出しました。
正論は、時に人を追い詰めます。追い詰められた人は、心を閉ざします。そこで、私はアプローチを180度変えることにしました。
朝礼の場で、私はホワイトボードに大きな宝箱の絵を描きました。
「皆さん、今から“宝探し”を始めたいと思います。この部署には、AI化できる“お宝”がたくさん眠っています。そのお宝とは、皆さんが普段『あー、この作業、本当に面倒くさいな』『なんで毎回同じことやってるんだろう』と感じている、名もなき単純作業のことです。この“面倒くさいお宝”を一番多く見つけてくれたチームには、私から豪華なケーキを差し入れします!」
目的を「業務の可視化(=監視)」から「面倒な作業からの解放(=宝探し)」へと、ゲーム感覚で変換したのです。
さらに、私は“ラスボス”である鈴木課長を巻き込みました。
「課長、この中で、課長が一番『若い子たちに、こんな意味のない仕事で時間を使わせたくない』って思う仕事って、どれですか? 課長の目で見て、一番の“お宝”はどれでしょう。」
ベテランの「矜持」と「部下への思いやり」を、そっと刺激する一言です。鈴木課長は少し腕を組んで唸った後、おもむろに口を開きました。
「そりゃあ…月末に取引先から郵送で届く請求書の束を、一件一件、会計システムさ手で打ち込む作業だべ。あれは目がしょぼしょぼなるし、数字ば間違えらんねぇし、若い子の貴重な時間がもったいなでの。本当はもっと別のこと、考えさせたいんだがな。」
この一言が、プロジェクトの潮目を変えました。一番の抵抗勢力に見えた人が、実は誰よりも現場の課題を深く、そして愛情を持って理解していたのです。彼の言葉は「やらされ仕事」だった業務の洗い出しを、「俺たちの問題を、俺たちで解決するための作戦会議」へと昇華させる力を持っていました。
第3章:「スモールスタート」の罠と“AI調教”という成功体験
鈴木課長の一声で、最初のターゲットは「請求書のデータ入力」に決まりました。早速、AI-OCRツールを試験的に導入し、パイロット運用を開始。…しかし、現実は甘くありませんでした。
AIが読み取ったデータの精度は80%そこそこ。結局、残りの20%は人間が目で確認し、手で修正する必要がありました。現場からは、たちまち不満の声が上がります。
「これ、かえって手間が増えてませんか?」
「AIって、こんなもんなんですか?」
青ざめた顔で私の元へ走ってくる佐藤さん。無理もありません。鳴り物入りで始めた最初の試みが、この結果では、プロジェクトの求心力は一気に失われてしまいます。
ここで犯しがちな過ちは、ツールベンダーに「精度を上げろ」と詰め寄ったり、現場に「慣れれば速くなるから」と我慢を強いたりすることです。私は、佐藤さんにこう言いました。
「佐藤さん、落ち着いて。これは失敗じゃありません。今回のパイロット運用の成功目標は、精度100%を達成することじゃないんです。『このAI-OCRのクセと限界が、データをもって分かったこと』。これこそが、我々が手に入れた大きな成果ですよ。」
私は「失敗の定義」を意図的にずらしました。そして、現場のメンバーを集め、ホワイトボードにこう書きました。
『AI-OCR 調教選手権!』
「このAI、どうやらまだ新人のようです。特定のフォーマットの請求書が苦手だったり、ここに線が入っていると混乱したりするみたいですね。皆さんは、この新人AIを育てる“トレーナー”です。どういう請求書が苦手なのか、どうすれば読み取りやすくなるのか、その“攻略法”を見つけ出すゲームを始めましょう!」
単なる「ツールの利用者」から「AIを育てるトレーナー」へ。この視点の転換が、現場の空気を一変させました。「AIが使えない」という不満は、「どうすればAIが使えるようになるか」という当事者意識へと変わっていったのです。
数日後、鈴木課長がニヤリとしながら私のところにやってきました。
「おい、見てみろ。このAI、取引先のハンコが金額にかぶってっと、数字を読み間違えるみたいだの。まだ赤ん坊みたいなもんだ。俺たちがしっかり教えでやらねばまいね。」
その顔は、面倒な仕事を押し付けられた顔ではなく、手のかかる新人を見守るベテランの顔でした。
最終的に、読み取りやすいフォーマットを取引先にお願いする、といった業務プロセス自体の改善にまで話が及びました。彼らが手にしたのは、「AIで楽になった」という単純な結果だけではありません。「自分たちの工夫で、AIの精度を上げ、仕事を変えた」という、何物にも代えがたい「小さな成功体験」だったのです。
第4章:「ルール作り」は、現場を縛るためでなく、守るために
プロジェクトが軌道に乗り始めると、今度は別の場所から「横やり」が入ります。情報システム部、法務部、内部監査室…。それぞれの立場からの、もっともな懸念です。
「セキュリティは大丈夫なのか?会社の機密情報を外部のAIに入力するなんて、情報漏えいのリスクをどう考えているんだ!」
「AIが生成した内容の著作権はどうなる?誤った情報で会社に損害が出たら、誰が責任を取るんだ?」
各部署から飛んでくる正論の矢面に立たされ、佐藤さんは完全に疲弊していました。これも「改革あるある」です。
私は佐藤さんと一緒に、各部署を説得して回りました。しかし、その時のロジックは「AIは安全です」ではありません。
「ご指摘、ありがとうございます。皆さんが懸念されていることは、我々も全く同じように感じています。そして、もっと恐ろしいのは、私たちが何もしなくても、現場ではすでに個人のスマホで、会社の管理外にある“野良AI”が使われ始めているかもしれない、という現実です。それはリスクが全く管理できていません。」
一呼吸おいて、続けます。
「だからこそ、我々がやりたいのは、会社として公式に安全性を認めたAI環境という『高速道路』を整備することなんです。そして、皆さんと一緒に、『ここから先は危険ですよ』『スピードを落としてください』という標識やガードレールを作りたい。ルールで現場を縛るのではなく、現場の皆さんが安心してアクセルを踏める環境を整えたいんです。ぜひ、そのための知恵を貸してください。」
「評論家」や「監視役」だった他部署を、「安全な道路を一緒に作る仲間」としてプロジェクトに引き込む。ルールは、挑戦の自由を奪うものではなく、安心して挑戦するための土台なのだという共通認識を醸成すること。これが、組織の壁を越えるための重要なコミュニケーションでした。
最後に:地図だけでは、目的地にはたどり着けない
AI導入のフレームワークやステップ論は、確かにゴールへの道筋を示す有効な「地図」です。しかし、その地図を手にしても、一緒に歩く仲間たちが違う方向を向いていては、一歩も前に進むことはできません。
今回のプロジェクトで私が改めて学んだのは、AI導入の成否を本当に分けるのは、最新の技術や精緻な計画書ではない、ということ。
それは、変化を恐れる人の心に寄り添い、長年の経験に敬意を払い、やらされ仕事を「自分ごと」や「楽しみ」に変換していく、地道で、人間臭いコミュニケーションの積み重ねに他なりません。
正論を振りかざす前に、相手の言葉に耳を傾ける。
「できない理由」を嘆くのではなく、「どうすればできるか」を一緒に考える。
そして、時には失敗さえも、次の一歩のための「成功」と定義し直してみる。
もし、あなたが今、組織の壁にぶつかっているのなら。一度立ち止まって、目の前の人の「心の声」に、そっと耳を澄ませてみてください。きっとそこには、どんな高度なAIにも導き出すことのできない、プロジェクトを動かす本当の鍵が隠されているはずですから。